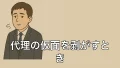謎の遺書が見つかった日
午前九時、いつものように事務所のドアを開けた瞬間、封筒の束が床に落ちた。中のひとつに、見慣れない角印の押された分厚い茶封筒が混じっていた。宛名は達筆で「司法書士 進藤先生」と書かれていた。
その日の午後、地域包括支援センターから一本の電話が入った。「成年後見人の森田さんが、今朝自宅で亡くなられて……遺書が見つかりました」。シンドウの手が止まった。後見人が遺書? 違和感だけが胸をついた。
内容証明に込められた違和感
封筒を開けると、中には一通の内容証明が入っていた。差出人は森田和也、本人の名前だ。だがその筆跡が妙だった。過去の委任状で見慣れている文字とは、微妙に違う。少し震えているのか、それとも誰かが真似たのか。
「偽造、の可能性もあるかもな」ぼそりとつぶやいたシンドウに、サトウさんが目線も寄越さず「それ、警察が先に気づいてますよ」と返す。やれやれ、、、こっちはまだ状況整理も終わっていないのに。
後見制度と秘密の帳簿
森田が後見人を務めていたのは、資産家の独居老人・広瀬静男。後見開始当初は資産管理に熱心だったが、最近は月次報告も雑だった。サトウさんが引っ張り出してきた通帳には、三ヶ月前から見慣れぬ出金履歴が連なっていた。
「この“備品購入”って名目、全部で百二十万ですね。老人ホームでそんなに何を?」とサトウさん。金額の割に、報告書には備品の詳細も添付もない。これは、ルパン三世も驚く空白の帳簿だ。
サトウさんの鋭い一言
「先生、遺書の内容って“私は被後見人の意思を尊重して…”ってありますけど、広瀬さん、失語症ですよね?」 サトウさんのひとことで、空気が止まった。
確かに。昨年の診断書に「高度の言語障害」と明記されていた。尊重すべき“意思”など、明確な形では存在しなかったはずなのに。
やれやれ、、、やっぱりか
森田が死ぬ間際に遺書を書く理由が見つからない。しかも内容は被後見人への財産の譲渡をにおわせるもの。「遺書」というより「誘導された契約文書」と言ったほうがしっくりくる。
「これ、誰かが“森田に書かせた”んじゃないか?」 独り言にサトウさんが、机を拭きながら「あたりでしょうね」と呟いた。やれやれ、、、推理モノならここで大どんでん返しがくるパターンだ。
弁護士からの不自然な連絡
その日の夕方、森田の顧問弁護士を名乗る人物から電話が入った。「先生、遺言の執行について、速やかな対応を…」と妙に急いでいる。遺言の執行とは、つまり被後見人の遺産が絡んでいるということだ。
「ちょっと待ってください。そもそも、それって公正証書遺言ですか?」 すると弁護士は一拍置いて「…自筆です」。公証人の名前が出てこない時点で、シンドウの中の警鐘が鳴り響いた。
記憶に残る面会記録
施設職員からの聞き取りで、新たな情報が浮かんだ。「森田さん、亡くなる前に“本人の希望を形にしたい”って繰り返してました」。 だが、その“希望”を誰が聞き取れたというのか。
広瀬は言葉を失っていた。唯一意思を伝える手段は、首を横に振るか縦に動かすかだけ。そんな彼の「本心」を、森田はどこまで正確に理解していたのだろうか。
印鑑証明と消えた委任状
シンドウが気づいたのは登記の添付書類だった。本来必要な委任状と印鑑証明が提出されていない。申請はされたが、補正がかかった形跡もない。 「これは、誰かが“記録を残さない形”で手続きを進めようとしたな」
だとすると、背後にはより大きな意図がある。財産移転の途中で森田が死んだこと、それ自体が想定外だったのかもしれない。
被後見人の本当の願い
介護記録の片隅に、広瀬が唯一繰り返し示していた行動が書かれていた。「旧宅の写真を眺めると穏やかな表情を見せる」。 それは、広瀬が心の奥に抱えていた“帰りたい”という想いの現れだった。
遺書に書かれていた“生家の修繕費用に充ててほしい”という一節。それは広瀬の想いか、それとも森田の独断だったのか。その答えは、もう誰にもわからない。
真実が語られる法定後見の裏
制度は万能ではない。人が人を管理する限り、必ずどこかに“判断”が入り込む。森田は、後見人でありながら、自らの“解釈”で財産を動かそうとしていた。
そしてそれを監視すべき第三者の目は、形式だけのチェックに終始していた。法定後見制度が抱える、静かな闇がそこにあった。
シンドウが選んだ結末
結局、遺書の効力は限定的と判断され、登記は却下された。遺産は広瀬の甥に相続されることとなり、旧宅も処分される運命にあった。
だが、シンドウは一枚の写真を甥に渡した。古びた家の前で笑う広瀬と森田の写真。 「本人が残した本当の遺志は、たぶん、こっちのほうですよ」 甥は写真を静かに受け取り、涙を流した。
やれやれ、、、正義ってやつは、いつも後味が微妙だ。