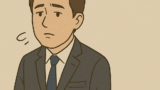静かな朝に届いた一通の封書
夏の暑さがじわりと肌にまとわりつく朝だった。郵便受けにぽつんと差し込まれていた茶封筒は、宛名も震えるような文字で書かれていた。差出人の名は見覚えがなかったが、どこか不穏な気配を帯びていた。
「また厄介な相続かねえ……」と独り言ちつつ、私は事務所のデスクに封を開いた。
依頼人の声はかすかに震えていた
電話口の女性は、どこかで聞いたような名字を名乗った。「父の名義のままの土地がありまして……」と、声は小さく、だが確かに困惑していた。その言葉に、胸の奥で何かがざらついた。
そして私は、知らず息を飲んでいた。かすかな違和感とともに。
相続登記に潜む違和感
遺産分割協議書のコピー、戸籍一式、土地の謄本——書類は一通り揃っていた。だが、どうにも腑に落ちない。亡くなったはずの父の名義が、何度も更新されていないにも関わらず登記が妙に新しいのだ。
「なにかが変だ」と、私はつぶやいた。
間違いだらけの戸籍の謎
戸籍の転記が雑だったのか、除籍されていないはずの人物が途中で記録から消えていた。まるで意図的に記録が削られているように見えた。
「これは……まさか、作為的なミスか?」と、寒気が背を這った。
謄本に記された謎の人物
登記簿の過去の記録を追うと、一度だけ見たことのない名前が現れていた。「山村慎一郎」——それは依頼人の父とは異なる人物。しかも、その名義はほんの数ヶ月だけ存在し、すぐに消えていた。
この土地には、表には見えないもう一つの物語があるようだった。
存在しないはずの前所有者
調べを進めるうちに、その「山村慎一郎」は地元の登記記録には一切出てこなかった。紙の上でだけ存在し、現実にはどこにもいない幽霊のような名義人だった。
「おいおい、サザエさんの花沢不動産でもこんな雑な登記は扱わないぞ」と私は頭を抱えた。
サトウさんの鋭い指摘
「これ、登記識別情報の発行履歴を見たほうがいいです」と、サトウさんは無表情に言った。どうやら私がぐるぐる考えている間に、彼女はすでに一歩も二歩も先を進んでいたようだ。
私は慌てて閲覧請求を出すことにした。
昔の登記規則との食い違い
確認すると、2004年の法改正以前の古い方式で識別情報が発行されていた形跡があった。つまり、最近になって改ざんされた可能性が浮上したのだ。偽造された登記情報で売買が行われたのではないか?
「やれやれ、、、そう簡単には終わらせてくれないらしいな」と、私は椅子にもたれた。
調査の糸口は一通の念書
依頼人の自宅から見つかった一枚の念書。そこには「土地を預かる」と手書きで書かれた文字と、謎のハンコが押されていた。これが偽装登記の証拠になるかもしれない。
手がかりは少ないが、ようやく核心に近づいてきた感触があった。
過去の売買と新たな疑念
念書の日付は10年前。だが登記上では取引が存在しない。つまりこれは登記外で勝手に取引が行われた、いわゆる「仮登記型」の脱法的な処理だった可能性が高い。
それを正式登記にすり替えた誰かがいる。
登記官からの不審な連絡
「あの土地、以前にも質問がありましたよ」と、法務局の職員が言った。しかも、調査記録には残っていない。非公式な照会だったのか、それとも内部の人間が……?
不審は確信に変わりつつあった。
一度抹消された記録の復活
ある日、過去に抹消されたはずの「山村慎一郎」名義の記録がPDFで再表示された。誰かがデータを掘り起こしたのか? それとも削除自体が偽装だったのか?
私はこの瞬間、全体像をつかんだ気がした。
隠されていた旧権利者の死
結論から言えば、「山村慎一郎」は依頼人の祖父だった。かつて資産隠しのために養子に出され、記録から抹消されていたのだ。すべては遺産分割のトリックだった。
その土地は誰のものでもなく、誰のものでもある、曖昧な場所だった。
失踪宣告の裏にあった真相
戸籍上は失踪。実際には数年前に病死していたことが判明した。誰も告げなかっただけだ。その間に名義が空白になり、誰かが利用しようとした。犯罪すれすれの、しかし行政の隙間を縫った手口だった。
その手口を、私は司法書士として暴いたのだ。
やれやれ、、、これは厄介だ
全体像をまとめ、登記の是正申立書を作成した。事件そのものは刑事事件にはならないが、登記手続きは是正され、依頼人の正当な権利が守られる形となった。
「やれやれ、、、やっぱり俺の夏は終わらないな」と、私はため息をついた。
司法書士としての一手
無償で一部の手続きを請け負ったのは、私の勝手な正義感だ。だが、それでいい。サトウさんは「別に褒めませんよ」と言い放ったが、いつも通りの調子に私は少し救われた気がした。
疲れたが、どこか心は軽かった。
法務局での静かな逆転劇
是正登記は受理され、法務局の掲示板にも記録が残った。依頼人は、帰り際に何度も頭を下げた。「これで父も安心できます」と言った表情には、静かな涙が浮かんでいた。
これが、司法書士という職業の報酬なのかもしれない。
一枚の証拠で動き出す歯車
あの念書一枚から、ここまで事実が明らかになるとは思わなかった。だが、それこそが紙と印鑑の魔法だ。文字に刻まれた過去は、いずれ誰かが掘り起こす日が来る。
そしてそれが、今日だったというだけの話だ。
事件の終幕と依頼人の涙
静かな終わり方だった。だが、確かに「真実」は登記簿に書き加えられた。土地も、家族の物語も、ようやく正しい場所に落ち着いたのだ。
「司法書士ってのは探偵より地味だけど、地味なぶんだけ嘘は許されない職業なんだよな」——私はつぶやいた。
登記簿に記された最後の一行
謄本の末尾には、依頼人の名がしっかりと刻まれていた。土地の所有者として、家族の歴史の担い手として。それは、登記簿に眠っていた真実がようやく目を覚ました証だった。
私はそっとその一行に目を落とし、事務所の電気を消した。