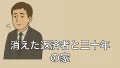朝の来客
司法書士事務所に現れた年配の依頼人
カタカタと鳴る扉の音。朝の書類整理をしていた私の前に、杖をついた年配の男性が立っていた。 しわだらけの手には、黒い布に包まれた小さなケース。それを胸元からゆっくりと取り出す仕草は、まるで時代劇の刀を抜くシーンのようだった。 「これを、正しい持ち主に届けてほしいんだ」 その言葉に、私は少しだけ背筋を伸ばした。
古びたケースの中身
金庫から出されたひとつのバッジ
ケースの中には、どこか見覚えのある金色の円形バッジがひとつ。 中央には秤のマーク、まぎれもない司法書士バッジだ。しかし、その裏には氏名がなかった。 「なぜ名前が削られているんですか?」と尋ねると、老人は目を伏せたまま首を横に振った。
名前の刻まれていない証
バッジには所属も氏名もなかった
バッジの裏はまっさらで、まるで「誰でもない」ことを主張しているかのようだった。 バッジは司法書士にとっての誇りであり、身分の証明。名前がないというのは異常だ。 私はすぐに登録簿の確認に取りかかった。
サトウさんの冷静な観察
見逃されていた刻印の痕跡
「これ、削った跡がありますね」サトウさんが顕微鏡で覗き込みながら呟いた。 確かに、わずかに残る筆記体のようなライン。それは誰かが自分の痕跡を消そうとした証だった。 「これ、まるでルパンが盗んだ宝石に細工するみたいですね」 淡々とした声でそんなことを言う彼女に、私は軽くうなずいた。
不審な依頼の真意
「このバッジを本来の持ち主に返してほしい」
老人は、自分の名を明かそうとしなかった。ただ「託された」とだけ言い残した。 「信じてもらえないかもしれんが……そのバッジは嘘を重ねた男の最後の遺志なんだ」 私は思わず「遺志?」と聞き返した。まさか死者のメッセージを私に託してきたのか。
過去の登録簿を洗い直す
廃業者リストに潜む違和感
過去十年の廃業届を一つひとつ確認していく中で、ある一件に目が留まった。 住所も電話番号も現依頼人のものと一致している。だが氏名はまったく違うものだった。 廃業理由は「病気による長期療養」。本当に病気だったのだろうか。
バッジの行方と失踪届
行方不明になった元司法書士の存在
その人物、北條達也は、十年前に突然消息を絶っていた。 警察には一度だけ相談があり、失踪扱いとなっていたが事件性はないと判断されていた。 「やれやれ、、、またこんな古い話に巻き込まれるとはな」 私は書類を閉じて深いため息をついた。
カフェでの密談
サザエさんの波平のような語り口の老人
喫茶店「なぎさ」の奥の席で、再び老人と対面した。 「私が北條の親友だった」と彼は切り出した。 「彼は最後まで司法書士でありたかった。だから名前を消して、バッジだけを残したんだ」
やれやれと呟く午後
思いがけない人物からの電話
その日の午後、一本の電話が鳴った。名乗ったのは北條の娘を名乗る女性だった。 「父のバッジをそちらで保管されていると聞きました」 その声には、不思議なほどの静けさと誇りがあった。
バッジを巡る嘘と真実
偽名で活動していたもう一人の司法書士
調査の結果、北條は晩年を偽名で過ごしていたことが判明した。 病気で資格を維持できなくなったことを恥じ、社会との接触を絶っていたのだ。 彼の友人は、その思いを私に託したのだった。
サトウさんの推理が冴える
「バッジは人を証明しない」
「結局、名前があってもなくても、人となりは行いで証明されるものです」 サトウさんの一言が、妙に胸に残った。 司法書士バッジは、単なる金属の輪に過ぎないのかもしれない。
静かに終わる告白
遺言の中の名前と正体
数日後、北條の娘から一通の手紙が届いた。そこには父の遺言が記されていた。 「このバッジを、私の名ではなく、私の生き様として誰かに渡してほしい」 それが、沈黙のバッジが最後に語った言葉だった。
胸元の沈黙が語るもの
証を持たぬ者の最期の誇り
私はそのバッジを、北條の娘に手渡した。 彼女は涙をこらえながら、そっと胸にしまった。 誰にも気づかれぬように、でもしっかりと、父の証を受け継ぐように。