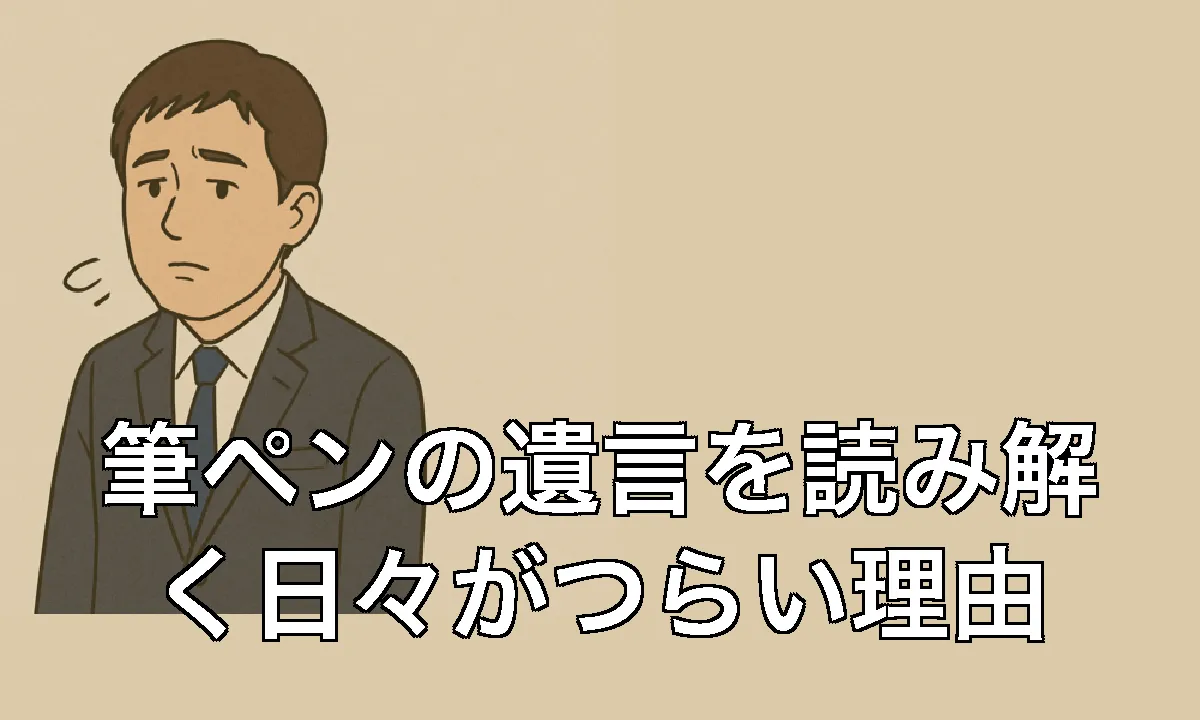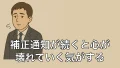誰が読めるんだ筆ペン遺言
自筆証書遺言には「全文を手書きで」という決まりがあります。だから筆ペンだろうがボールペンだろうが理屈の上では構わない。でも現場の司法書士としては、正直言って筆ペンはやめてほしい。太くて、にじんで、文字が潰れて。最初にその遺言を見たとき、「これ読める人いるのか?」と思わず独り言が漏れました。パッと見て名前が判別できないときのあの絶望感、共有できる人はそう多くないはずです。
見た瞬間に脱力したあの日
ある日、60代後半の男性が「父の遺言です」と持ってきたのが、筆ペンで書かれた自筆証書遺言。見開き一面、まるで書道作品のように文字が踊っていました。内容はある程度推測できるものの、肝心の氏名と日付がにじんで判別不能。まるで雨に濡れたまま干された年賀状のようで、「これは…補正対象になるかも」と喉まで出かかった言葉を飲み込みました。
線が太すぎて名前すら曖昧
「田中一郎」が「田中土屋」に見えたことがあります。しかも続柄や相続分を手書きで書いてあるとき、漢字の判別があやふやになると、実質内容が不明瞭になります。しかも依頼者側はそれが当然読めると思っている。だからこちらが「読み取りづらい」と伝えると、なぜかこちらが悪いような空気になる。筆ペンという選択、遺族の優しさではなく、故人のこだわりだったりするんです。
遺言書としての「体裁」の壁
遺言として形式は整っていても、裁判所に出したとき「読み取れない」と判断されれば、無効のリスクすらある。これは裁判所の担当者によって判断がわかれるので、ギャンブルのようなものです。「一応、読める範囲ですよね?」と食い下がる遺族に対して、「この部分は第三者には読めないとされる可能性がある」と伝えるのは精神的にしんどい。特に高齢の依頼者には、丁寧に、でも冷静に説明する必要があります。
補正をお願いするときの気まずさ
補正をお願いする立場というのは、何度やっても慣れません。本人にとっては大切な書類。故人の筆跡そのものですし、遺族の思いも詰まっている。でも、現実には家庭裁判所から「ここを補正して再提出して」と連絡が来る。それを伝えるとき、依頼者の顔色がさっと曇るのを見ると、なんとも言えない後味が残ります。
依頼人のプライドと向き合う
「うちの父は昔教師だったんです。達筆でしょ?」と笑顔で話す依頼人に、「判読困難なんです」とはっきり言うのは難しい。そこには思い出と尊敬と悲しみが混ざっている。でも、法律の世界は情では動かない。説明に感情を挟まないようにしながらも、相手の気持ちを無視しないよう、毎回バランスを取るのにエネルギーを使います。
感情ではなく制度で説明する難しさ
「これはルールなので」と説明すると、時に冷たく映る。それでも、感情を優先して手続きを進めたら後々取り返しがつかなくなることもある。例えば相続人間で争いが起きたとき、この“判読不能な文字”が大きな火種になります。制度で守るのが司法書士の役割。でも、その制度が人の感情とぶつかる場面は、現場に山ほど転がっているのです。
形式の自由さと実務の地獄
自筆証書遺言には定められた形式がありますが、それを満たしていれば基本的には有効です。でもそれって、現場で手続きする人間にとっては恐ろしい話でもあります。文字が極端に崩れていたり、読めなかったり、それでも「本人の手で書いていればOK」となるのは、正直しんどいです。
自筆証書遺言の自由さに泣く
「自分で書けばいい」とネットには書いてあります。でも、それを信じて筆ペンや万年筆で独自ルールのレイアウトで遺言を書く方が本当に多い。結果、現場は「これ、解釈として大丈夫か?」とヒヤヒヤする毎日です。自由に書けるけど、自由すぎるとリスクが跳ね上がる。これ、現実ではほぼ“罠”です。
「自由=何でもOK」じゃない
筆ペンでびっしり書かれた遺言、しかも縦書きで改行もないとなると、読み解くのはほぼパズル。感情抜きで言えば「これは再提出してほしい」となります。でも依頼人の前では、そんな言い方はできないから、なんとももどかしい。自由と実務のすれ違いは、この仕事における“永遠のテーマ”です。
読めなければ無効になる現実
法律上の問題はなくても、誰が見ても読めなければ“無効”とされる可能性がある。しかも、それが最終的に家族間の争いに発展してしまうことも。読めない遺言は争いの火種になりやすいんです。だから、我々は「今のうちに相談しておきましょう」と口を酸っぱくして言うしかないのです。
家庭裁判所からの補正指示が来た日
家庭裁判所の書記官から補正指示が来るたび、正直「やっぱりな」と思います。そしてまた、依頼者へ伝える役目を担うのがこちら。補正してしまえば済む話ではあるのですが、「補正する=不備があった」と思われるため、説明に気を使います。しかも筆ペンだと、修正すること自体が物理的に難しいんですよ。
実はよくあることだったりする
筆ペン遺言で補正が必要になるケース、意外と少なくありません。むしろ「またか」と感じるほど。でも、当事者にとっては人生初の出来事。こちらが慣れていても、向こうにとっては一大事。その温度差がある限り、伝え方には常に神経を使います。「気にしないでくださいね」なんて軽く言えないのがつらいところです。
でも毎回ドキドキするのはなぜか
補正通知が届くたびに、心がざわつくのはなぜでしょう。たぶん、「また伝えるのか」「また気を遣うのか」と思ってしまうからだと思います。一人事務所でやっていると、こうした細かい心労の積み重ねが馬鹿にならないんですよ。独身の身としては、これを誰にも話せないのが一番のダメージだったりします。