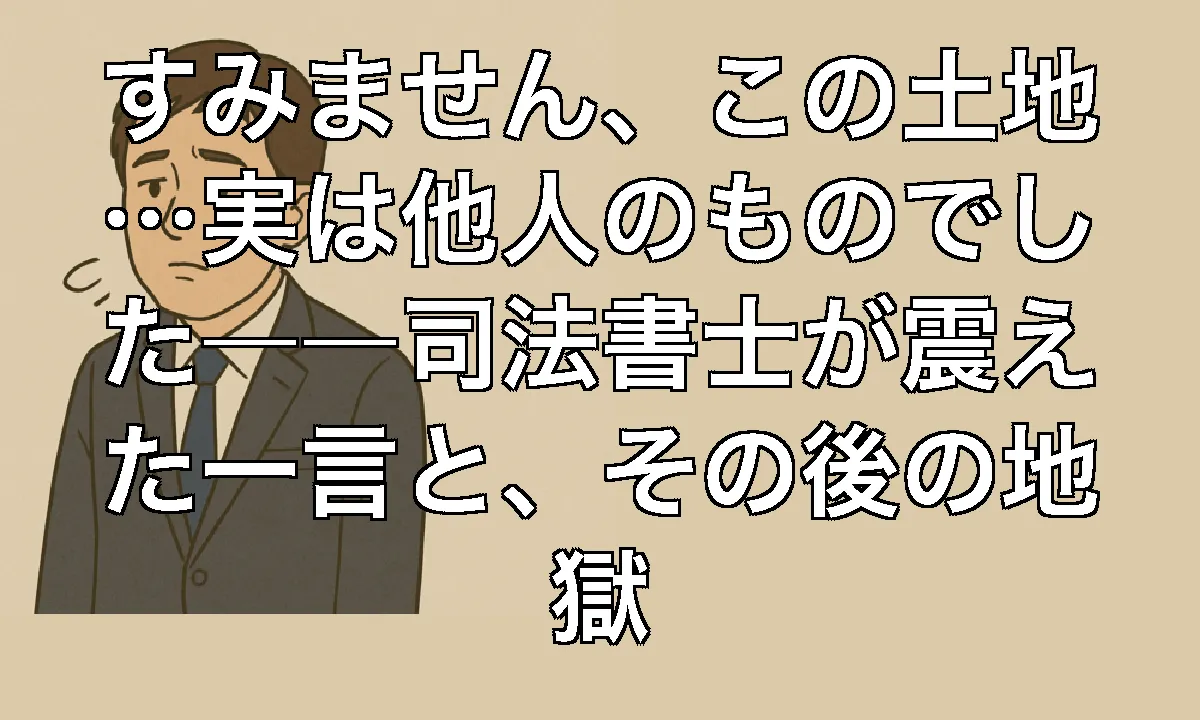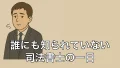あの日、電話口で凍りついた
それはある梅雨のじめっとした午後、事務所にかかってきた一本の電話から始まった。「先生、あの土地なんですが、ちょっと確認したいことが…」。依頼人の口調はどこか遠慮がちだったが、嫌な予感が背中を走った。長年この仕事をしていると、そういう直感だけは当たる。忙しさに追われていた私は、正直「また細かいことか」と思いながら受け答えしたが、電話の内容が進むにつれ、背筋が凍るような感覚に襲われた。登記した土地が、実は依頼人の所有地ではなかったかもしれないというのだ。最初は信じられなかったが、確認のため現地に向かうと、それがただの杞憂ではなかったことに気づかされた。
「ちょっと確認したいんですが…」から始まった違和感
「境界線が違う気がする」と言われたとき、私は頭の中で何度も地番を思い浮かべた。確かに、書類上は間違っていなかったはずだ。しかし、現場の境界杭の位置が微妙に異なる。依頼人の話では、隣地の持ち主が「うちの土地に杭が入ってる」と怒っているらしい。私は慌てて事務所に戻り、登記簿と測量図を再確認した。しかしそこには、どこにも“明確なミス”は見当たらない。じゃあなぜ現場ではこんなズレが?という疑問が残った。まるでパズルのピースが一つだけ別の箱に混じっていたような、そんな奇妙な違和感だった。
登記簿と現地のギャップ――どこで間違えた?
紙の上では完璧なはずの情報が、現地に立つとまるで通用しない――司法書士として何度経験しても慣れない瞬間だ。今回もその例外ではなかった。登記簿上の面積、地番、隣地の情報、すべて整合していた。それでも現場の杭は、まるで違う意志を持っているかのように、こちらの主張を否定していた。周囲の雑草が生い茂る中、私はメジャーを片手にひたすら測り直し、近隣住民に話を聞き、写真を撮った。それでも確証は得られない。登記という“絶対的”なデータが、こんなにも不確かに感じられる瞬間があるとは、数年前には想像もしなかった。
地番の読み違い?まさかの取り違え?
事務所に戻って再確認を重ねる中、ある小さなメモ書きに目が止まった。「地番2-17と2-71、筆界未確定区域」。…まさか、やってしまったのか?その瞬間、胃の中がひっくり返るような気分になった。よく似た番号、隣接する位置、古い資料には筆界未確定のメモ。焦りとともに過去の調査を思い出すが、そこに確信はなかった。私のチェックミスだったのか?いや、そもそも筆界が曖昧なのが問題だったんじゃないか?責任の所在をぐるぐる考えても、苦しいだけだった。
誰のせい?いや、誰のもの?
この仕事で厄介なのは、「誰のせいか」より「誰の土地か」が先に問われるところだ。法的にはどちらの主張も一理あり、第三者が介入しないと埒が明かない。依頼人は私に対し「ちゃんと調べてくれてたと思ってた」と言い、私は「書類上は間違っていなかった」と言いたくなる。でも、それで関係が良くなるわけじゃない。心の中では、「おかしいな、あのとき確かに法務局でも確認したはずなのに」と自分を弁護していた。だけど、依頼人の視線はそんな私の心を見透かすように冷たかった。
境界線の”常識”が通じない現場
書類と現地が食い違っているとき、「常識」で乗り切ろうとすると失敗する。ある農家の方は「ここは祖父の代からうちの畑」と言い切った。資料を見せても納得しない。それもそのはず、正式な測量がされていなかったからだ。人の記憶と感覚、そして曖昧な境界が交錯する田舎の土地では、“うちのもんだ感覚”が法よりも強いことがある。そうなると、登記簿や測量図よりも、村の会話や過去の口約束がモノを言う。合理的ではないが、無視もできないのが現実だ。
「ここはうちの畑だ」と主張する別の家族
現地にいた老夫婦が、「あんた、何勝手に杭を動かしてんだ」と怒鳴ってきたとき、私は一歩下がるしかなかった。こちらの説明をしようとしても「関係ない、ここはうちのもんだ」の一点張り。目の前の光景は、もはや法ではなく感情のぶつかり合いだった。彼らは私を“侵入者”と見ていたのかもしれない。依頼人は私の背後で困った顔をしていたが、私にはもう彼を守れる余裕がなかった。こうなると司法書士としてできることは限られてくる。登記簿を振りかざすより、まずは一緒に頭を下げるしかなかった。
測量図を見せても納得しないときの絶望
法務局で取得した測量図を手に、私は何度も「ここが筆界です」と説明した。しかし、相手は首を横に振るだけだった。「そんなもん、あとから勝手に引いたんじゃろ」と言われたとき、もう何を言っても届かないと悟った。測量士が精度を上げようと苦労してきた成果が、数十年の思い込みの前では「勝手に引いた線」にされてしまう。怒りでも悲しみでもない、虚しさだけが胸に残った。
信頼が音を立てて崩れていく
登記という手続きは、目に見えない信頼の上に成り立っている。その信頼が崩れるときは、音がするわけじゃない。でも、はっきりわかる。「ああ、今、信用失ったな」って。依頼人の表情が曇り、会話が減り、こちらの言葉が届かなくなる。無力感と自己嫌悪のループ。事務所に戻って、誰にも言えずパソコンの前で手が止まる。あの沈黙こそが、何よりもキツかった。
「あんたがプロでしょ?」と詰められる日々
あるとき依頼人に言われた。「こっちは先生に任せたんですから」。その言葉の裏には、「だから失敗はあなたの責任でしょ」という無言の圧がある。私は「全部チェックしてたんですが…」と答えるのが精一杯だった。プロという肩書きは便利だ。でも同時に逃げ場を奪う。「プロなら完璧にやって当然でしょ?」という期待とプレッシャーに、何度押し潰されそうになったか。
謝罪しても埋まらない溝――顧客との信頼関係
誠意を込めて謝っても、関係が元に戻ることはない。謝るほど「そっちが悪いんだ」と思わせてしまうこともある。このときの依頼人もそうだった。表面上は笑っていたが、もう二度と連絡はなかった。仕事だから仕方ない、そう思いたい。でも、やっぱり割り切れない。「ごめんなさい」で帳消しになるミスと、ならないミスがある。今回は後者だった。
それでも、前に進む理由
この仕事、失敗しても翌日はやってくる。嫌でも依頼は入ってくるし、書類も積まれていく。だから立ち止まっていられない。今回の件を経て、私は「チェック体制を強化しよう」と思った。もう二度と同じミスを繰り返さないために。完璧にはできないかもしれない。でも、少しでも精度を上げる。それが、せめてもの償いだと思った。
ミスの中から見えてきた「本当の価値」
登記って、ただの手続きじゃない。人の思いと生活と、時には争いを抱えているものだと改めて感じた。紙の上ではなく、現場で起きている現実。それに向き合えるかどうかが、この仕事の価値を決める。過去のミスが教えてくれたのは、「手続き」より「人」を見る目だった。
逃げずに向き合ったからこそ得た教訓
正直、逃げたかった。でも、逃げずに全部説明して、謝って、最後まで付き合った。結局依頼人とは疎遠になったけど、自分の中ではそれでよかったと思っている。逃げていたら、きっと今も自信を持てなかった。向き合うことでしか、司法書士としての誇りは守れない。そう感じている。
同業者との何気ない会話に救われた
この件のあと、たまたま参加した勉強会で、似たような話をしていた同業者がいた。「うちもあったよ、土地が三角形にズレててさ」って笑ってた。その笑いに、少しだけ救われた。同じように悩み、失敗して、それでもやってる仲間がいる。だから、またがんばろうと思えた。