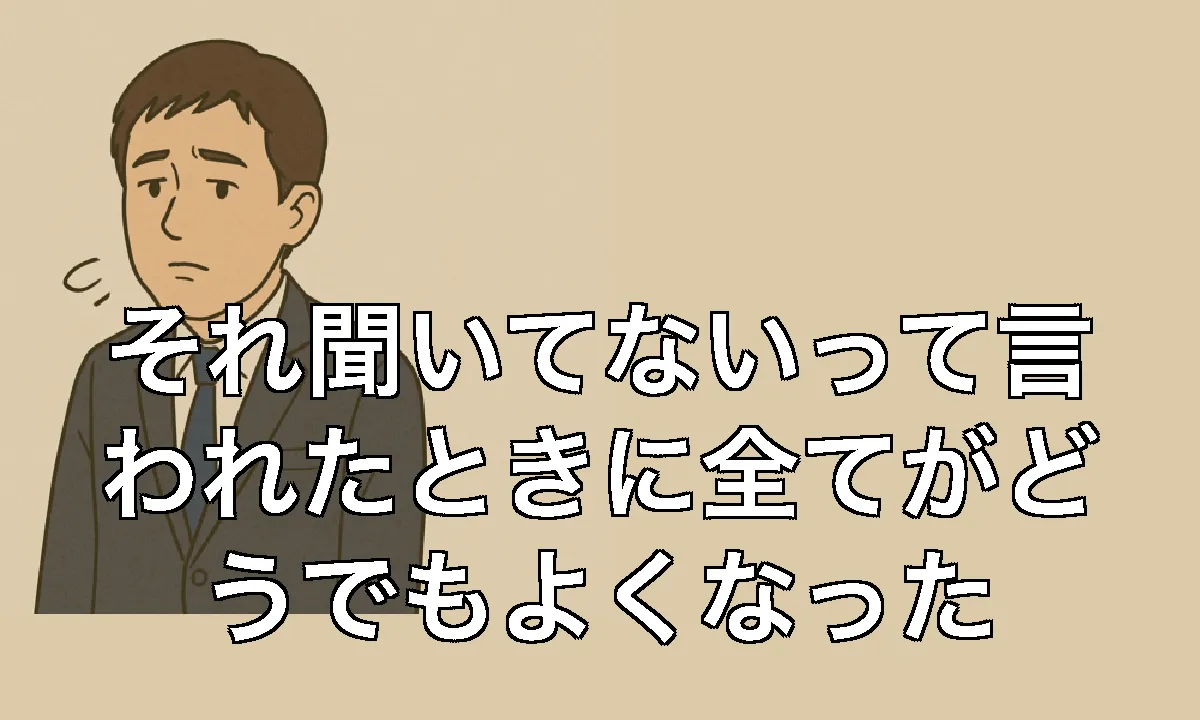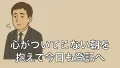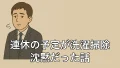全部説明したつもりだったのに
あの瞬間、「え、それ聞いてないんですけど」と言われたとき、僕の中で何かが静かに崩れ落ちた。資料を揃え、スケジュールも確認し、説明も何度もした。事務所の事務員にも伝えた内容だった。それでも、依頼人の口から出たその一言は、こちらの準備や時間、気遣いすら否定されたような感覚に陥った。何がいけなかったのか。何が伝わっていなかったのか。頭の中で何度も巻き戻しては、虚しさが募るばかりだった。
時間をかけた打ち合わせが水の泡
その依頼は、相続登記に絡むもので、被相続人の兄弟姉妹まで関係が広がるややこしい案件だった。依頼人と初めて会った日、僕は1時間以上かけて丁寧に説明したつもりだった。図も描いて、関係図まで作成した。それをもとに段取りを組み、必要書類を依頼した。ところが、1週間後の連絡で「そんなの初耳です」と返され、しばらく声が出なかった。カフェで説明していたあの時間は、何だったのかと。
事務員にも共有したはずの内容
この件については、事務員にも逐一報告しており、共有フォルダにもメモを残していた。メールでのやり取りも残っている。なのに、依頼人には伝わっていなかった。もしかすると、僕の説明が早口すぎたのか。あるいは、相手が聞き流していたのか。原因は一つではないかもしれない。でも、どれだけこちらが努力しても、伝わらなければ意味がない。それがこの仕事の難しさでもある。
依頼人の「知らなかった」の破壊力
「そんなの知りませんよ」と言われると、まるで自分がサボっていたかのような罪悪感に襲われる。こちらとしては誠実に対応したつもりでも、相手にその意図が届いていないのなら、それは“伝えていない”のと同じなのだ。頭ではわかっている。けれど、やるせない気持ちは拭えない。野球で言えば、打ったと思った球がフェンス直撃で戻ってくるような、あの感覚。決して点にはならない。
そもそもなぜ伝わってなかったのか
こうした行き違いは、司法書士の仕事では珍しくない。でも、何度経験しても慣れるものではない。結局のところ「伝える」という行為には、話す側と聞く側の両方の姿勢が問われる。僕は相手の理解を前提にしすぎていたのかもしれないし、相手は聞き逃しても後から確認できると思っていたのかもしれない。だからこそ、記録と確認の重要性を、あらためて痛感する。
口頭の限界と記録の大切さ
口頭での説明には、限界がある。人は忘れる生き物だ。僕自身、昨日の昼ご飯すら思い出せないことがあるのだから、相手に責任を押し付けることはできない。だからこそ、今は話した内容をその場でメモに起こし、後から確認できる形にしている。形式ばっていると思われようが、後で「言った言わない」になるくらいなら、その方がはるかにマシだ。
相手が「聞く耳を持っていない」問題
そもそも相手が、こちらの説明に集中していないこともある。スマホをいじりながらの相談、あくび混じりの反応、何度も時計を見る仕草……。そんなときは、こちらも話しながら心が折れていく。でも仕事だから、説明しなければならない。まるで無人のキャッチボールをしているような虚無感の中、それでも球を投げ続ける日々だ。
絶句したあの日から変わったこと
あの日以来、僕の中で“伝える”という行為の基準が変わった。それまでは丁寧に話せば伝わると信じていたけれど、今は「相手が理解し、記憶し、行動に移せるか」が基準になった。説明の手法を見直し、伝達方法を変えたことで、少しだけ気持ちが楽になった。
確認の取り方を変えた
今は打ち合わせ後に簡単なまとめを書面で渡すようにしている。これがあるだけで、「もらった書類にそう書いてありましたね」と言ってもらえることが増えた。たった数分でできる確認作業が、後々のトラブルを大きく防いでくれる。こんなことならもっと早くやっておけばよかったと後悔している。
メールより紙に残す文化へ
メールは便利だけど、意外と見ていない人が多い。だからこそ、紙で残す。手渡しの瞬間に一言添えるだけでも、印象に残るし、記憶にも定着しやすい。昭和のやり方かもしれないけれど、今のところ一番効果があると感じている。
チェックリストが精神安定剤に
依頼ごとに必要な書類や説明項目をリスト化し、終わったものにチェックを入れていく。これだけで「やり忘れたかも」という不安が減るし、自分自身の頭の中も整理される。精神的にも安定しやすくなったし、仕事のスピードも上がった。
「伝えたつもり」は信用にならない
どんなに誠実に対応しても、「聞いてません」と言われたら終わり。それが司法書士の仕事だと思っている。だから、今は“伝えた”ではなく“伝わった”を目指している。相手が理解したかどうか、そこまで確認するのがプロの仕事。そう思うようになった。
相手の表情をよく見るようになった
話しているときの表情や反応を、以前よりずっと観察するようになった。うなずきが少なかったり、目が泳いでいたりすれば、説明をやり直す。表情には、言葉よりも多くの“伝わっていない”が詰まっていることに気づかされた。
それでもまた起こる「聞いてない」
どれだけ対策をしても、やっぱりまた同じことが起きる。それがこの仕事の現実。完璧な伝達なんて存在しないし、こちらも人間。ミスをゼロにはできない。でも、少しずつ、減らすことはできる。地道だけど、それが僕たち司法書士のリアルな戦いだ。
同じ轍を何度も踏む現実
何度チェックしても、見落とすときはある。事務員にもダブルチェックしてもらっているけれど、それでも抜ける。注意力が続かない日もある。慣れがミスを呼ぶ。忙しさが判断を鈍らせる。そういう積み重ねが、「またやってしまった」につながる。
忙しさが伝達の質を下げる
本当に忙しいときは、どうしても“早く済ませたい”という気持ちが出てしまう。そのせいで説明が雑になったり、確認がおろそかになったりする。後からそれを思い返して自己嫌悪に陥るのも、いつものことだ。
一人事務所の限界
結局、人手が足りないのだ。事務員も頑張ってくれているけれど、すべてを任せるには荷が重い。最終確認はどうしても僕の役目になる。その責任の重さに、押しつぶされそうになる夜もある。
メモすら忘れる日もある
人間だから忘れる。メモをとるべきと思いながら、次の電話、次の来客で後回しになり、結局忘れる。そんな日が続くと、自分が信用できなくなってくる。それでも、明日は来るし、仕事も終わらない。
最後はやっぱり人間関係の話になる
司法書士の仕事は、法的な処理だけでは終わらない。結局は、人と人との関係に尽きる。うまくいくときも、いかないときも、その根っこには「信頼」がある。だからこそ、信頼が崩れたときのダメージは大きい。仕事以上に心が疲弊する。
感情を押し殺す仕事のつらさ
本当は言いたいことが山ほどある。でも、感情を出したら終わり。冷静に、穏やかに、誠実に対応しなければならない。そういう自分を演じるのに、いつも全力を使っている気がする。
謝るのはこっちばかり
「説明不足でした」「確認が足りませんでした」——そうやって謝るのは、たいていこっち側だ。相手の落ち度が明らかでも、それを指摘すると関係がこじれる。だから我慢する。そうしてどんどん疲れていく。
信頼を築くって難しい
信頼は一朝一夕では築けない。日々の小さなやり取り、丁寧な説明、約束を守ること。その積み重ね。でも、たった一つの「聞いてない」で、全部が崩れることもある。それが現実だ。だから、今日もまた、慎重に、丁寧に、でも少し疲れながら、仕事をしている。