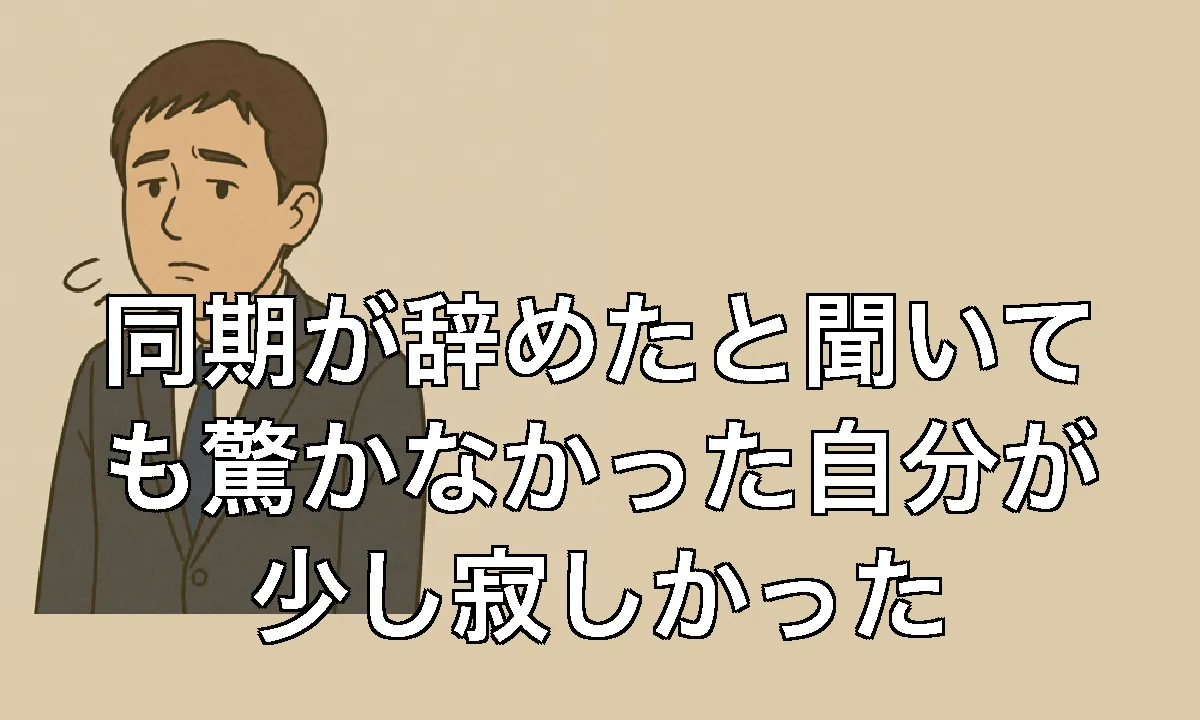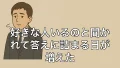気づけばひとりで踏ん張っている日々
この仕事を始めた頃は、まさか自分が45歳になっても独身で、地方の事務所でひとり踏ん張っているとは想像もしていなかった。昔は「いつかは仲間と事務所を大きくして…」なんて夢もあったが、今ではそんなことを口にする気力もなくなってしまった。朝のメールチェック、書類の山、取引先からの電話に追われる日々。となりのデスクにはひとりだけの事務員。彼女も気を遣ってくれているのはわかるが、話しかける隙もない日がある。
誰かと比べてしまう朝のルーティン
朝、歯を磨きながらスマホでSNSを見るのが習慣になっている。そこで目に入るのは、元同期の司法書士たちの充実した日々の投稿。カフェでのミーティング、講師として登壇、家族との笑顔の写真。自分はというと、誰にも見せたくない机の上と、冷蔵庫に放り込んだコンビニ弁当だけ。つい、「俺は何をやってるんだろうな」と呟いてしまう。比べたくなくても、目に入ってくるものは心をざらつかせる。
SNSに映るあいつの笑顔とこっちの現実
特に印象に残っているのは、かつて一緒に研修を受けた同期の一人が、満面の笑みで仲間たちと写真に写っていた投稿だ。都内で立ち上げた事務所がうまくいっているらしい。自分はというと、依頼人のドタキャンで予定が空き、寒空の下で一人自販機のコーヒーを飲んでいた。スマホの画面と紙コップの温もりの対比が、なんだかやけに虚しくて、指先が震えた。
間違ってるのは俺かという疑問
あいつが間違ってるわけじゃない。だけど、じゃあ自分が正しいのかと言われたら、答えに詰まる。ただ仕事を続けてきただけ。逃げなかったことが評価される社会ならいいが、現実はそうじゃない。SNSの中には、「辞めてよかった」「自由になった」と笑う声が溢れている。自分のやってることって、そんなに価値ないのか?そう思うと、眠れなくなる夜もある。
辞めたと聞いても心は静かだった
先日、他の同期から「◯◯、辞めたらしいよ」と言われた。ふーん、としか返せなかった自分がいた。かつては一緒に徹夜で勉強し、酒を飲んで愚痴をこぼしあった仲だったはずなのに。驚きもない自分の感情が、逆に怖かった。心が鈍っているのか、感情を麻痺させているのか。どちらにせよ、あまりいい兆候ではないと思う。
驚きもなければ羨ましさもなかった
正直に言えば、彼の決断が羨ましいとも思わなかった。自由を得たというよりは、重さに耐えきれず手放したように見えたから。自分は、辞めるほどの勇気もなければ、続けることに明確な意義を見出せていない。ただ淡々と、「今日もやるべきことをやる」というスタンスで日々を積み重ねている。それが良いのか悪いのかさえも、最近はわからなくなってきた。
心のどこかでやっぱりなと思っていた
実は、数年前から彼の様子が変わっていたのを感じていた。やたらと講演会やコンサルの話ばかりして、現場の話には乗ってこなくなっていた。きっと彼は彼なりのやり方で「逃げ道」を探していたのだろう。それが悪いわけじゃない。でも、その動きを見て「やっぱりな」と感じた自分もいて、それがまた寂しさを加速させた。
忙しさは誰かを鈍くさせる
朝から晩まで、タスクに追われるような日常が続くと、人は感情に気づかなくなる。いや、気づいていても処理する余裕がなくなるのだろう。特にこの仕事は、感情を排除しないと前に進めない場面も多い。登記一つとっても、冷静で淡々としていないとミスにつながる。だからこそ、感情が抜けていくことにすら慣れてしまう。
電話も来客も重なる昼下がり
「ちょっとだけ休憩を」と思った瞬間に電話が鳴る。お客様が訪ねてきて、予定していた業務が全部ずれ込む。事務員も申し訳なさそうな顔をしているが、責められない。こういうとき、ふと「誰かが代わってくれたら…」と思う。でも、その誰かはもう辞めている。今ここに残っているのは、自分だけ。
いつの間にか感情を置いてきた
ある日、机の引き出しを開けたら、数年前にもらった手紙が出てきた。新人時代、同期からもらった応援の言葉が書かれていた。「あなたなら大丈夫」と。その言葉を見ても、何も感じない自分がいた。あれほど嬉しかったはずなのに。たぶん、もう感情を引き出しの奥にしまい込んだまま、取り出し方を忘れてしまったんだ。
効率だけが正義みたいな毎日
「今日は何件処理できたか」「何分で仕上げたか」そんな数字ばかり追いかけていると、心はどんどん痩せていく。誰かのために頑張る気持ちとか、自分の仕事に誇りを持つ気持ちとか、いつの間にか消えていく。でも、そうじゃないと生き残れない現実もある。効率の向こう側にある「空っぽさ」を、誰も教えてくれなかった。
やめる自由と残る責任
辞めるのも自由、残るのも選択。そのどちらにも正解なんてない。でも、残った側はどうしても「責任」を感じずにはいられない。特に小さな事務所では、一人の退職が業務全体を揺るがす。だからこそ、「続ける選択」が美談になりがちだが、時にそれは苦しさの源にもなる。
残る者が背負うものの重さ
誰かが去るたびに、業務だけでなく「関係」や「記憶」も背負っていく感覚がある。「あの人がいたときはこうだった」と思い出すたび、無性にやるせなくなる。でも、それを誰かに話せるわけでもない。仕事だからと、自分に言い聞かせながら今日も机に向かう。
逃げなかったことが誇りか呪いか
自分は逃げなかった。そう言える。でも、それが誇りになる日もあれば、ただの呪いに感じる日もある。「あの時逃げていたらどうなっていただろう」と、もしもの世界を想像してしまう自分がいる。答えなんて出ないのに、考えてしまうのが人間の弱さかもしれない。
昔の自分ならどう感じていただろう
20代の自分だったら、同期が辞めたと聞いてもっと感情を揺らしていただろう。寂しさとか、悔しさとか、いろんなものが混じって。それが今では、「ふーん」で終わってしまう。変わったのは、自分なのか、環境なのか。それとも、どっちもなのか。
野球部だったころの仲間意識
高校時代の野球部では、誰かが一人辞めるだけでチーム全体が揺れた。涙を流して止めようとしたこともあった。あの頃は、「仲間」の意味を全身で感じていた気がする。今、同じだけの熱量を誰かに向けられるだろうか。正直、自信がない。
信じて頑張ることに意味があったあの頃
「信じてれば報われる」なんて今では笑われるかもしれないが、あの頃は本気でそう思っていた。努力に意味があったし、チームのために走ることが誇りだった。今はどうだろう。誰のために働いているのか、わからなくなる瞬間がある。
今の俺は誰かの背中に何か残せてるのか
辞めていった同期、今も隣にいる事務員、目の前の依頼人。その誰かの心に、自分の働き方が何か少しでも残せているのだろうか。そう思える日はまだ来ていない。でも、いつかそんな日が来ると信じて、もう少しだけ、続けてみようかと思う。