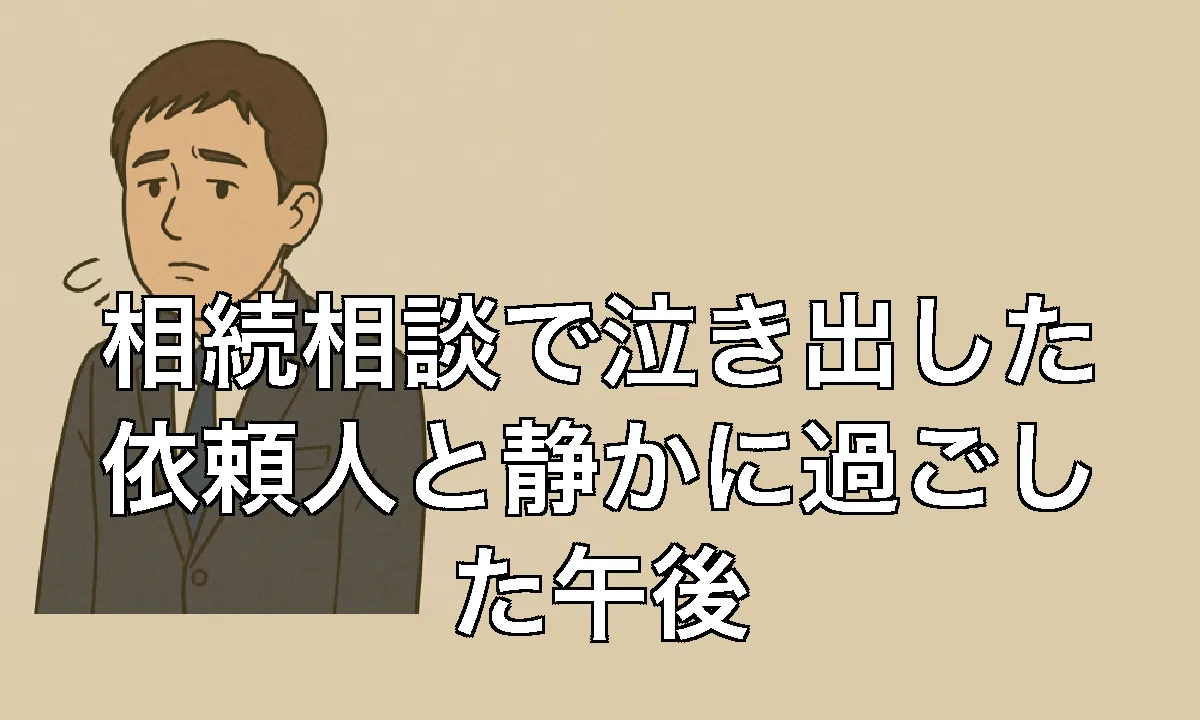静かな午後に始まったひとつの相談
その日は珍しく電話の鳴らない午後だった。事務所の空気も穏やかで、コーヒーを飲みながら書類整理でもするかと思っていた矢先、一本の電話が鳴った。声の主は女性で、相続の件で一度相談したいとのこと。特別な雰囲気を感じたわけでもなかったが、どこか言葉がぎこちなく、ためらいがちだった。予約はすぐに入り、午後三時。僕はその時、これがちょっと特別な午後になるとは思ってもいなかった。
電話の声に違和感を覚えた瞬間
初めての声というのは、意外に記憶に残る。その女性の声は、優しげではあるものの、どこか不安定で、まるで迷子の子どもが大人のふりをして話しているような感じだった。自己紹介のあと、住所を伝えるのにも数秒の沈黙があった。普段なら気にも留めないが、そのときはなぜか胸にひっかかるものがあった。たった数秒の沈黙に、何か大きな葛藤が潜んでいるような、そんな違和感だった。
いつもと違うトーンと沈黙
相談日当日、事務所に現れた女性は、喪服のような黒い服を着ていた。服装のことなど気にしないが、まるで今もなお喪に服しているかのような表情だった。あいさつもそこそこに席についたが、すぐには話が始まらなかった。紙袋の中からぐしゃぐしゃになった戸籍の束を出してきて、ただそれを机に置くだけで、しばらく沈黙が続いた。空気が重たくなっていくのを感じた。
「泣いてもいいですか」と言われたときの戸惑い
沈黙の中、彼女が小さな声で言った。「先生、泣いてもいいですか?」その一言に僕は一瞬、返す言葉を失った。司法書士として数百人と会ってきたが、目の前でこう聞かれたのは初めてだった。泣くことを許される場所が、僕の事務所しかなかったのかと思うと、こちらの胸が締めつけられた。僕はただ「もちろん」とだけ答えたが、それすらも心もとない返事に思えた。
依頼人の涙と向き合う難しさ
彼女の涙は静かだった。嗚咽もなく、ただぽろぽろとこぼれていた。その姿を見て、僕は書類のチェックや法的な説明を一度脇に置くことにした。人として、まず目の前の涙に向き合おうと思った。でも正直、何を言えばいいのかわからなかった。泣く人に対して、専門家としてできることってなんだろうと、答えのない問いが頭を巡った。
言葉を選ぶことの重み
「大丈夫ですよ」とか「つらかったですね」とか、そんな言葉が頭に浮かぶ。でも、どれも安っぽく感じてしまって口にできなかった。テレビドラマならもっと上手に言葉をかけられるのだろうけど、現実は違う。沈黙を埋めるためだけの言葉ほど、無責任なものはない。だから僕は、ただ頷きながら話を聞くことにした。それしかできなかったし、それが精一杯だった。
自分の感情を切り離せない場面
彼女の話を聞いているうちに、僕の中にも何かがこみあげてきた。彼女は母親を亡くし、その後の兄弟間の争いに心をすり減らしていた。僕にも家族とのしがらみはあるし、田舎の兄弟げんかは根が深い。どこかで「他人事じゃない」と思ってしまっていた。司法書士として、感情は持ち込むべきではない。でも人間として、それを完璧に切り離すのは無理だと痛感した。
元野球部の自分が無力に感じた時間
昔はグラウンドで声を張り上げていた自分が、目の前で泣く人にただ黙ってうなずくことしかできない。正直、情けなかった。体育会系らしく「がんばりましょう」とでも言いたかったが、そんな言葉がどれほど無神経かも分かっていた。人の痛みに、声を張る必要はないのだ。静かに、ただそこにいることの難しさと意味を学んだ午後だった。
事務員さんの優しさに救われる
話が終わり、彼女が帰ったあと、事務所には妙な静けさが残っていた。そこへ、奥で仕事をしていた事務員さんがそっとコーヒーを持ってきてくれた。「先生、大変でしたね」とだけ言って、何も聞かずに戻っていった。その一言が妙に沁みた。派手なサポートではないが、そういう優しさがあるだけで、心が救われることがある。
さりげない気遣いに学ぶこと
普段は言葉数も多くない事務員さんだが、ふとした場面で見せる気配りには頭が下がる。あのコーヒーの一杯に、どれだけ助けられたことか。こういう時、感情に流されて疲れてしまう自分と違って、彼女はどこか芯がある。プロってこういうことなのかもしれない、とさえ思った。司法書士である前に、人間としての支え合いが必要なのだと痛感した。
一人ではできない仕事だと改めて思う
書類作成、登記申請、相談業務。表面上は一人で回しているように見えても、結局は事務員さんの力があってこそ成り立っている。あの日のように感情的な出来事があると、なおさらその存在の大きさに気づく。事務所という小さなチームでも、信頼と連携があるからこそやっていける。元野球部らしく言えば「一人じゃ試合はできない」ということだ。
チームプレイという言葉が沁みた日
野球部時代、キャッチャーの一言で投手が救われる場面を何度も見てきた。あの日の事務員さんのひと言も、それと同じだった。表には出ないけれど、縁の下で支えてくれる存在がいるというのは、本当に心強い。個人事業主という立場になってから、つい「自分がやらなきゃ」と背負い込みがちだったけど、やっぱり人に支えられている。それを素直に認められた午後だった。
モテない自分でも誰かの支えにはなれる
これまで、女性にモテることもなかったし、家庭も持っていない。正直、独身生活が長くて虚しいと思うこともある。でも、あの日のように誰かが涙を流せる場所になれるなら、この仕事にもこの人生にも意味がある気がする。モテなくたって、頼られることはできる。そんなふうに、少しだけ自分を肯定できた。
必要とされることのありがたさ
司法書士という仕事は、普段は「淡々」としている。でも、ときにこうして誰かの人生の節目に立ち会うことがある。必要とされることに慣れてはいけないな、と思った。ありがたいことなのだ。この仕事をしていなければ、出会えなかった人、向き合えなかった感情。仕事の意味は、たぶんそういうところにある。
一人の時間があるから寄り添える
独り身だからこそ、こういう時間に向き合えるのかもしれない。家族がいたら、こんなふうに相談者の話に感情移入しすぎることもなかったかもしれない。孤独は苦しいけれど、そのぶん誰かの孤独に敏感になれる。そんなふうに、悪くない面もあると思えた。今日の自分は、ちょっとだけ、誰かの役に立てたのだろう。
今日の午後を明日の力に
夕方になって、ようやく事務所に日常の空気が戻ってきた。書類を片付け、机を拭き、照明を少し暗くしたとき、ふっと疲れが押し寄せてきた。でも、その疲れは悪くなかった。気持ちのこもった疲れというか、「今日という一日」を使い切った感じがした。たまにはこんな午後があってもいい。いや、むしろ、こういう午後こそが、自分を司法書士として育ててくれているのかもしれない。
どんな一日も誰かの人生の一部かもしれない
司法書士の仕事は地味だ。でも、書類の裏には人生がある。あの午後、僕はその一片と向き合った。たった一人の依頼人かもしれない。でも、彼女にとっては大きな一日だったかもしれない。その日に立ち会えたことを、誇りに思っていいのかもしれない。地味な仕事の中に、静かなドラマが潜んでいることを忘れないようにしたい。
疲れていてもまた明日も相談室に灯りを
「また明日も、誰かが来るかもしれない」。そんな気持ちで、僕は毎朝事務所の電気をつける。疲れていても、やる気が出なくても、それだけは続けようと思う。誰かの話を聞く場所があるということは、誰かの救いになることもある。今日の午後のような時間を、また迎えるために。自分のためにも、誰かのためにも。