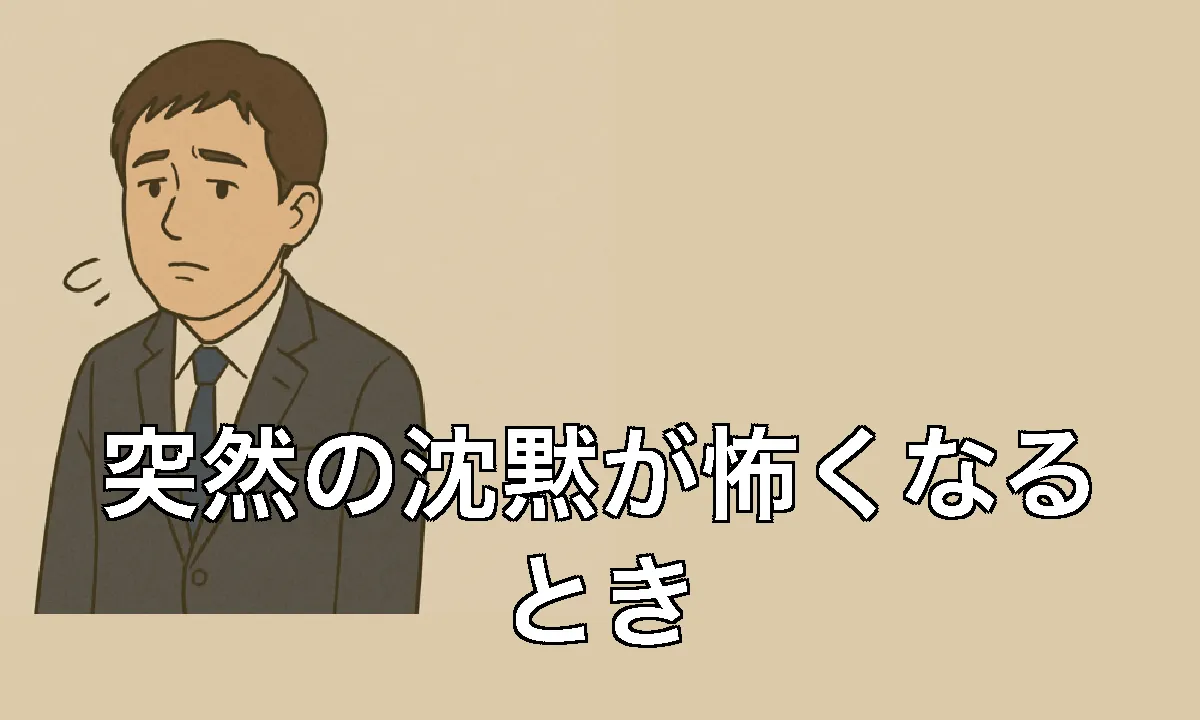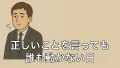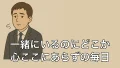静けさに押しつぶされる瞬間
忙しい日々のなか、ふと訪れる「沈黙」。この時間がたまらなく不安になることがあります。例えば、相談中に依頼者が何も言わなくなったとき。その場の空気がスッと冷えていくような、あの沈黙。相手はただ考えているだけなのに、こちらは「怒っているのでは」「話が伝わらなかったのでは」と、余計な心配をしてしまいます。地方の司法書士として、少人数の事務所で働いていると、この種の“空白”に敏感になりがちです。自分で空気をつくるのが当たり前になっている分、何もない時間に取り残されたような気持ちになるのです。
ふとした沈黙が生み出す不安
静寂というのは、時に騒音より心をかき乱します。打ち合わせの最中、ふと会話が途切れた瞬間。たった数秒の沈黙が、まるで数分にも感じられることがあります。「何か言わなきゃ」と焦るあまり、つい余計な一言を口にしてしまい、あとから自己嫌悪に陥る。そんな経験、司法書士であれば一度や二度ではないはずです。言葉を扱う職業だからこそ、言葉のない時間に強く反応してしまうのかもしれません。
会話が途切れたあとの気まずさ
沈黙のあとの空気って、なぜあんなに重たいのでしょうか。特に、初対面や関係が浅い相手との場面では顕著です。「えーと」とか「そうですね」とか、とりあえず何か言って場を繋ごうとする。だけどその繋ぎ言葉すら思い浮かばない時は、沈黙の責任を自分一人で背負っている気になります。それが積もり積もって、「人と話すのが億劫だ」という感情につながるのです。
「何か言わなきゃ」に追い込まれる自分
無理に何か言おうとする癖は、元野球部のころから染みついた「間」を埋める習性かもしれません。試合中に沈黙は命取り、声を出すのが美徳と教え込まれてきた結果、今でも沈黙を「悪」と感じてしまう。だけど仕事では、それが必ずしも正解ではないんですよね。自分の焦りが、相手の思考を妨げてしまうこともある。黙って待つ勇気、それが今の自分には一番足りていないと感じます。
沈黙に強い人と弱い人の違い
沈黙に強い人って、空気に動じないんですよね。どんな間が空いても、落ち着いていて余裕がある。対して私は、ちょっと間が空いただけでソワソワ。頭の中では「今の発言は失礼だったか?」「変な顔してないか?」と自己チェックが止まりません。これは、性格の問題なのか、それとも職業柄のクセなのか。いずれにしても、このギャップはコミュニケーションに大きな影を落とします。
元野球部的な間の取り方は通用しない
野球部時代は、とにかく声出し命。沈黙=怠慢という認識がありました。だから今でも、沈黙を「ミス」と感じてしまう癖があります。だけど、司法書士の仕事では逆。静かに考える時間こそが、大事な判断を生み出す時間。野球で言えば「サイン交換」の時間みたいなものです。でも私はつい、キャッチャーがサイン出す前に投げ始めてしまう。空回りすることも多いんですよね。
相手の反応に過敏になる性格
もともと人の表情や声色に敏感な性格です。だから、ちょっと眉をひそめられただけで「嫌われたかも」と思ってしまう。そんな自分にとって、沈黙は“情報が得られない恐怖”でもあります。相手の反応が読めない。だからこそ、過剰に反応してしまう。しかも独身で、話し相手が限られている日常では、それがさらに深まってしまうんです。
司法書士という職業の性質と沈黙
司法書士の仕事には、独特の「間」があります。依頼者の話をじっくり聞く。法律的な判断を慎重に伝える。すべてのプロセスが、落ち着いた空気の中で行われます。そこに「沈黙」はつきもの。でも、それを怖がっているようでは、この仕事には向いていないのかもしれません。とはいえ、現場に立つとつい焦ってしまうのが人情。私自身、なかなかその境地には達せられずにいます。
相談中の沈黙に耐えられない理由
相談の途中で、依頼者が黙り込む瞬間があります。その時、「不満を感じたのでは」「こちらの説明が分かりづらかったのでは」と、頭の中で反省会が始まってしまうんです。相手がただ考えているだけだと分かっていても、その時間に耐えられない。無理に言葉を繋ごうとして、かえって要点がぼやけてしまうこともある。そんな時、自己嫌悪が強くのしかかってきます。
答えが求められている気がして焦る
相手が沈黙すると、「今すぐ答えを出さなきゃ」という圧を勝手に感じてしまいます。だけど、法律的な問題ってすぐに答えが出るものじゃない。なのに、自分で勝手に“プレッシャー”をつくってしまう。だからこそ、常に肩に力が入っている。余裕がない。結局、それが相手にも伝わってしまうという悪循環。まさに、自爆です。
「信用を失ったのでは」と思い込む癖
特に地方では、口コミや紹介が命。だからこそ、依頼者からの沈黙に対して「不信感を持たれた」と過剰に反応してしまう。実際には何も起きていないのに、最悪のシナリオを想像しては落ち込む。独身で、一人の夜にそのことを思い返すと、ますますネガティブな感情に支配されてしまう。ほんの数秒の沈黙が、心の中では大事件になるのです。
沈黙を受け入れるために必要な考え方
沈黙に対する過敏さを手放すには、「沈黙も会話の一部だ」と認識することが大切です。こちらが話す時間だけが意味あるわけではなく、相手が考えている時間にも大切な意味がある。頭では分かっていても、感情がついてこない。だからこそ、意識して「待つ」姿勢を持つことが求められます。
黙っている時間も「仕事のうち」だと思う
沈黙していると「何もしていない」と思ってしまいがちですが、実際には脳内で思考がぐるぐる動いています。依頼者にとっても同じで、話の内容を理解するための時間が必要なのです。むしろ沈黙している時こそ、大事な判断が生まれている。そう考えると、少し気が楽になります。
相手にも考える時間が必要だと理解する
相手も人間。すぐに答えが出るわけではないし、悩んだ末に出した言葉の方がずっと信頼できます。私自身、他の司法書士さんに相談する時、少し沈黙がある方が「ちゃんと考えてくれてるな」と感じるのです。なのに、自分がそれを許せないのは不思議な話。もっと余裕を持って、相手の時間も尊重したい。そう思えるようになってきました。