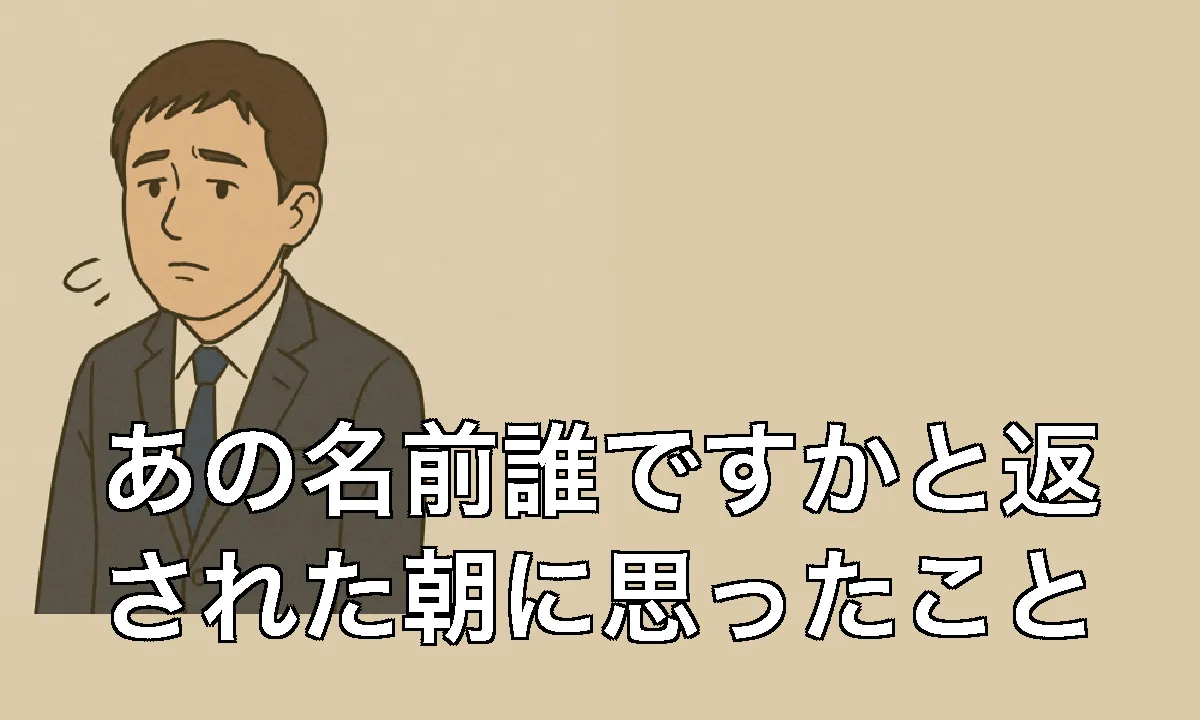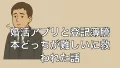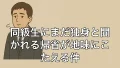メールを送った直後の違和感
朝一番、前日からの懸案だった登記関係の書類を依頼人に送ったあと、いつも通りコーヒーを一口飲んで一息ついた。画面を見ると、すぐに返信が来ていた。「あの名前、誰ですか?」という一文。心臓が軽く跳ねるような、冷や汗の出る感覚だった。何のことだろうと本文を確認すると、依頼人の名前が、別の案件の方のものになっていた。ああ、やってしまった。忙しさで確認を怠った、自分の愚かさが身にしみた。
名前を間違えたことに気づいた瞬間
名前というのは、人の信頼の根幹に関わるものだ。メールの内容に問題はなかった。しかし、冒頭の「〇〇様」という宛名が、全く別の依頼人になっていた。正直、血の気が引いた。これはまずい。単なる入力ミスでは済まされない。別の依頼人の名前が記載されているということは、情報が混ざっている可能性を疑われてもおかしくないからだ。しかも、その名前は少し珍しいもので、より目立ってしまっていた。冷静になろうとしても、動揺は隠せなかった。
自分のミスを認めるということ
一瞬、言い訳をしたくなる自分がいた。「テンプレートが崩れたせい」「事務員が確認していなかったせい」…でも、それはすべて逃げだった。送ったのは自分。最終確認を怠ったのも自分。責任は100パーセント自分にある。そう思うと、なんだか悔しいやら情けないやら。だが、その悔しさをこらえて「」と素直に謝罪文を打った。依頼人の信頼を取り戻す第一歩は、自分のミスを誤魔化さないことだと、改めて思った。
言い訳より先に謝罪する勇気
この歳になっても、「ごめんなさい」と正面から伝えるのは、思っている以上に勇気がいる。つい言い訳をしたくなる。でも、それでは逆効果だと経験上わかっている。だから今回は、言い訳は一切せず、率直に謝罪した。「名前を誤って記載してしまいました。申し訳ございません」それだけの文章が、どれだけ重いか。依頼人からは「気にしてませんよ」と優しい返事がきたが、胸の中はずっとざらざらしていた。この感覚を、忘れてはいけない。
なぜこんな初歩的なミスをしたのか
言ってしまえば、完全に自分の不注意である。でも、そこには日々の業務に追われる中で見落としたものがあった。数分でも落ち着いて確認すれば避けられたミスだったのに、それを怠った。常に時間に追われていると、人は「確認」という当たり前の工程をスキップしがちになる。それがいかに危険かを、今回痛感した。ミスは小さくても、信頼の損失は大きい。
業務の慌ただしさに飲み込まれて
毎日、朝から晩まで依頼の電話、資料のチェック、法務局への提出…気づけば昼も抜いてる日がざらにある。そんな中、メール対応は「すきま時間」にやっていることが多くなる。効率重視でテンプレートを使い回し、確認もそこそこに送信ボタンを押す。便利なはずの仕組みが、今回に限っては落とし穴になった。慌ただしさが日常になると、基本を忘れる。今回のミスは、まさにその象徴だった。
事務員との連携不足が生んだ落とし穴
私の事務所には事務員が一人だけ。とてもよくやってくれているが、どうしても私と一対一のやり取りになると限界が出てくる。今回の件も、事務員が前日夜に作った下書きを私が朝確認して送る、という流れだった。しかし、その確認が甘かった。事務員に責任があるとは思っていない。ただ、今後は「見たつもり」ではなく「ちゃんと確認した」ことを明確にする体制を、二人で作っていかないといけないと感じた。
名前だけ変えればいいという思考停止
最近、効率ばかりを追い求めていた気がする。「名前さえ変えれば大丈夫」と思っていた。でも、それはまさに“思考停止”だった。メール一通にも、その人への配慮や信頼が詰まっている。単に文面を使い回して名前を置き換えるだけでは、いずれどこかで綻びが出る。今回のミスは、その象徴的な出来事だった。効率の中にも丁寧さをどう残すか。そのバランスを、もう一度考え直す時が来たのだと思う。
依頼人との信頼関係が揺らぐ怖さ
司法書士という仕事は、知識よりも信頼が大切だ。どれだけ正確な登記ができても、依頼人との信頼が崩れてしまえば終わりだ。今回のミスでそれを改めて実感した。メール一通の失敗が、長年の信頼関係を壊す可能性だってある。だからこそ、「間違えないこと」以上に、「間違えたときにどう対応するか」が問われているのだと思う。
間違えられた方の気持ちを想像してみた
もし自分が、何かを依頼した士業から、別人の名前でメールを送られてきたら――不安になるし、「本当に自分の情報は守られてるのか?」と疑うはずだ。たとえ文面に情報漏洩がなかったとしても、気持ちが引っかかる。依頼人にとっては、自分の人生の大事な節目を託しているわけで、そのやり取りの中で「他人の名前」が出てくるのは不快極まりない。自分がその立場だったら、どう感じるか。そう考えれば、軽視なんてできない。
名前を間違えることの重大さ
名前はその人そのもの。司法書士の仕事は、登記簿に名前を正しく記すことでもある。だからこそ、書類や会話、そしてメールでの名前の扱いには最大限の注意を払わなければならない。誤って記載すれば、その人の人生や財産に影響が出る可能性がある。それと同じくらい、コミュニケーション上でも名前の扱いは繊細であるべきだ。どれだけ小さなやり取りでも、名前を丁寧に扱う意識が必要なのだ。
信頼を回復するためにできたこと
今回の件で学んだのは、信頼は失ったときこそ取り戻すチャンスがあるということだった。謝罪のあと、すぐに電話でも連絡を入れ、再確認とお詫びを伝えた。すると依頼人から「ちゃんと対応してくれてありがとう」と言ってもらえた。信頼は、完璧さよりも「真摯な対応」で築かれる。同じ失敗を繰り返さないのが前提だが、誠意をもって向き合うことの大切さを、改めて胸に刻んだ。
今後の対応と自戒
メールのミス一つでここまで落ち込むのは、自分がこの仕事に誇りを持っているからだと思いたい。今後は「確認」を形式ではなく習慣にし、「忙しいから仕方ない」という言葉を言い訳にしない。司法書士という職業は信頼を売る仕事。その重みを、あの返信メールからもう一度教えてもらった気がする。明日から、いや、今からでも変えようと思う。
メール送信前にできるたった一つの確認
結局のところ、送信ボタンを押す前の“たった5秒の確認”ができていれば、このミスは防げた。宛名、本文、署名。最低限この3つだけでも、声に出して読むなり、ひと呼吸置いて目を通すだけで違っていた。日々の忙しさの中でこのワンアクションを忘れずにいられるかどうか、それがプロとしての意識の差になる。習慣化の鍵は、「面倒だからこそやる」に尽きる。
忙しい中でも丁寧さを忘れない仕組み作り
もう一人の事務員がいれば…と何度思ったかわからない。でも現実には、いまの人数でやるしかない。その中で、確認をルーチンにする仕組みを作ることが必要だと感じている。例えば、メール下書きのチェックリスト化、名前の自動補完機能の見直し、声に出して読む時間を5分確保するなど、できることはある。少しの工夫で、再発防止に大きくつながる。手間ではなく、自分を守る手段として考えていきたい。
同じ失敗を繰り返さないための小さな習慣
今日のようなミスを、来週、来月も繰り返していたら、それはもう「ミス」ではなく「無責任」だ。自分の名刺にある「司法書士」の文字に恥じないよう、小さな習慣をコツコツ積み重ねていくしかない。メールだけでなく、書類、説明、報告、すべてにおいて「名前」を意識すること。それが結局、依頼人への敬意となり、自分自身の誇りになるのだと思う。