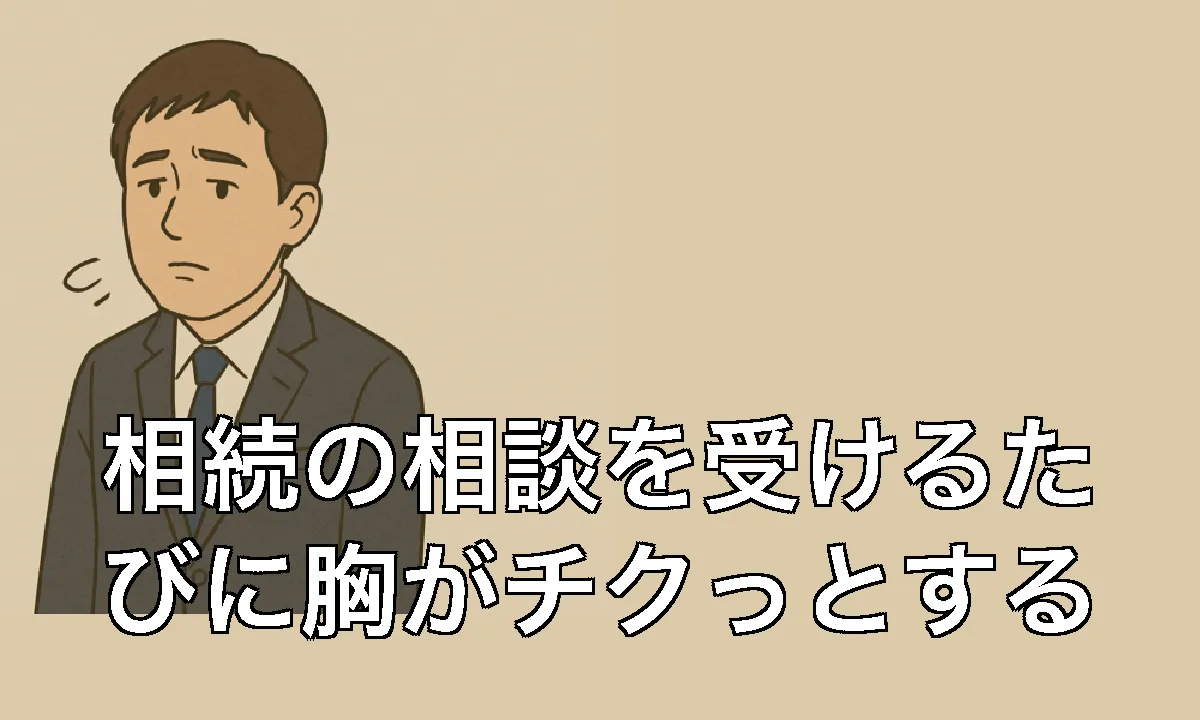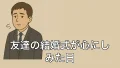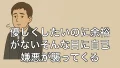自分とは無縁だと思っていた相続の現場で
司法書士という職業柄、「相続」の相談はよくある業務の一つです。最初のうちは、淡々と書類を作り、必要な登記を済ませていく毎日でした。でも、ふとした瞬間にその「相続」という言葉が、自分自身にグサリと刺さることがあるんです。人の家族の問題を扱っているはずが、気がつけば、自分には家族がいないという現実に向き合わされてしまう。遺言や遺産分割協議の書類を見つめながら、自分の名前がどこにも書かれない未来を想像してしまう。そんなとき、胸がチクっとするんですよね。
遺産分割協議書を見てふと立ち止まる
ある日、60代の女性が訪ねてきました。ご主人を亡くされ、相続手続きをしたいとのこと。遺産分割協議書を作成する中で、彼女が「うちの子たち仲が良くて助かります」と笑って言ったんです。その瞬間、頭の中が真っ白になりました。自分には分けるべき財産も、相手もいない。紙に並んだ家族の名前がまぶしくて、パソコンの画面を見つめる手が止まったんです。「この仕事、慣れたはずだったのに」と、自分の動揺に驚きました。
そこに家族の名前があるという当たり前
協議書に兄弟や子どもたちの名前が並ぶのを見て、「これが普通なんだ」と感じました。私の家族は高齢の母一人だけ。兄弟もいないので、いずれ私がいなくなったとき、書類に名前を書く人間すらいないかもしれない。そんな不安が頭をもたげてきます。クライアントの家族構成が豊かであるほど、逆にこちらの孤独が浮かび上がるのです。「普通」に家族がいて、「普通」に相続する世界に、自分は入れていないような気がしてしまいます。
誰のために残すのかという問い
最近、自分自身の遺言書を書いてみようと思ったことがあります。でも、書く手が止まってしまいました。誰に何を残すのか。そもそも残すほどのものがあるのか。そんなことを考え出したら、むなしくなってしまった。相談者の多くは、「家族のために」「迷惑をかけたくないから」と口をそろえます。でも私には、そんな誰かがいない。果たして自分の人生は、誰かのために何かを残せるものなのだろうか。問いだけが胸に残りました。
司法書士という役割に徹しきれない瞬間
「プロなんだから、感情を持ち込むな」そう言われればそれまでです。けれど人間ですから、目の前の依頼者とその人生に触れると、どこか心が揺れてしまいます。たとえば、遺言執行を頼まれたとき。家族写真が一枚、遺品として手渡されたことがありました。そのときのことは、今でも思い出します。誰かに託された人生の一部。それを整理するという責任の重さ。そして、託す相手すらいない自分との落差に、どうしようもなく胸が痛みました。
他人の人生に向き合う重みと自分の影
他人の人生に触れることが多い職業です。だからこそ、他人の「幸せの形」に敏感になる。ある意味でそれは、鏡を見ているようなものです。「この人には支える家族がいる」「この人には守るべき子どもがいる」。そんな情報が、書類の中にたくさん詰まっている。そしてそれを見るたびに、自分の影のようなものが、心のどこかに残り続けるんです。「誰にも触れない自分の人生は、誰に照らされているんだろうか」と。
書類の山の向こうにあるもの
業務としての相続手続きは、淡々と進んでいきます。けれど、その一件一件に、人生の終わりと家族のつながりが込められていることも事実です。そうした書類を日々処理していると、「自分は何をやっているんだろう」と立ち止まることがあります。作業の山に追われながら、その向こうにある“誰かの想い”を見過ごしてはいけないと思う一方で、自分の想いはどこに行けばいいのか、その答えだけはいつまでも見つかりません。
独身という立場がじわじわ効いてくる
結婚しないまま歳を重ねると、「独身である」という事実の輪郭がどんどんはっきりしてきます。若いうちはまだ「そのうち」とか「今は仕事優先」とか、いろんな言い訳ができました。でも45歳にもなって、母親もだんだん年老いてくると、将来のビジョンが見えなくなります。相続の手続きをしているときほど、「家族のかたちは力になるんだな」と実感します。そして、その力を持たない自分が、とても小さく感じてしまうことがあるのです。
ご家族はいらっしゃいますかと聞かれたとき
たまに、依頼者から「先生はご家族いらっしゃるんですか?」と聞かれることがあります。悪気のない雑談のつもりなんでしょうが、そのたびに笑ってごまかしています。「母が元気で」とか、「一人で気楽にやってます」とか。でも内心では、答えたくない気持ちと、答えられない現実に挟まれて複雑な気持ちです。質問されたときのあの空気、説明しにくいんですよね。なんとなく、自分だけが“違う人生”を生きてる気がして。
想定されていない選択肢に気づく
世の中の制度も手続きも、基本的には「家族がいる」ことを前提にできています。相続もその一つ。相続人がいない場合の手続きは複雑で、そもそも誰も気にしてくれないことも多い。書類を作る側として、それは知識として理解しているけれど、「自分がその対象になる」とは考えてなかった。でもふと、「自分が死んだらこの事務所は誰が畳むんだ?」なんてことを考えると、急に足元が崩れるような不安に襲われるんです。
一人暮らしが当たり前になる感覚
帰宅して、冷蔵庫を開けて、何も入っていないことに気づく。その瞬間に、「ああ、今日も誰とも話してないな」と思うことがあります。一人で暮らすことに慣れすぎると、誰かに頼ることを忘れます。そうなると、逆に誰かと暮らす自分の姿が想像できなくなっていく。そうやって気がついたときには、もう誰かと一緒に生きるという選択肢が現実味を帯びなくなっているんです。独身が楽なようで、実は怖いのはそこかもしれません。
自分の相続を想像してみたけれど
夜中にふと、「もし自分が明日死んだら」と想像することがあります。仕事の書類は事務員が整理してくれるかもしれない。でも、誰が通知を出してくれる?銀行口座は?スマホのロックは?そう考え始めると、ぞっとします。司法書士という職業なのに、自分の人生の“終い方”についてはほとんど何も準備していない。なんとなく「まだ先の話」と思っていたことが、急に目の前に迫ってくる。そういうときに限って、不安で眠れなくなります。
誰に何を残すのかがわからない
仮に財産があったとして、それを誰に残すべきか。甥や姪もいない、親族づきあいもほとんどない。残すべき人がいないというのは、想像以上に心を不安定にさせるものです。何のために働いて、何のために築いたのか。その答えを見失ってしまうと、毎日の仕事すら空虚に感じてくるんです。依頼者には「将来を見据えて備えましょう」と伝えながら、自分にはその将来がまるでぼんやりとしていて、見えなくなってきているのです。
生前整理の話に妙に共感してしまう
最近、生前整理をテーマにした本を読んだとき、やけに心に刺さりました。モノを減らしていく過程の中で、「残された人が困らないように」という前提がある。でも、自分には残される人がいない。じゃあ何のために整理するのか。そんなことを考えながら、本棚を一つ空にした日。どこかで「これで少し楽になるかもしれない」と思ってしまった自分がいて、怖くなりました。生前整理が自分にとって“終活”じゃなく“今の生き方”になっている気がしたのです。