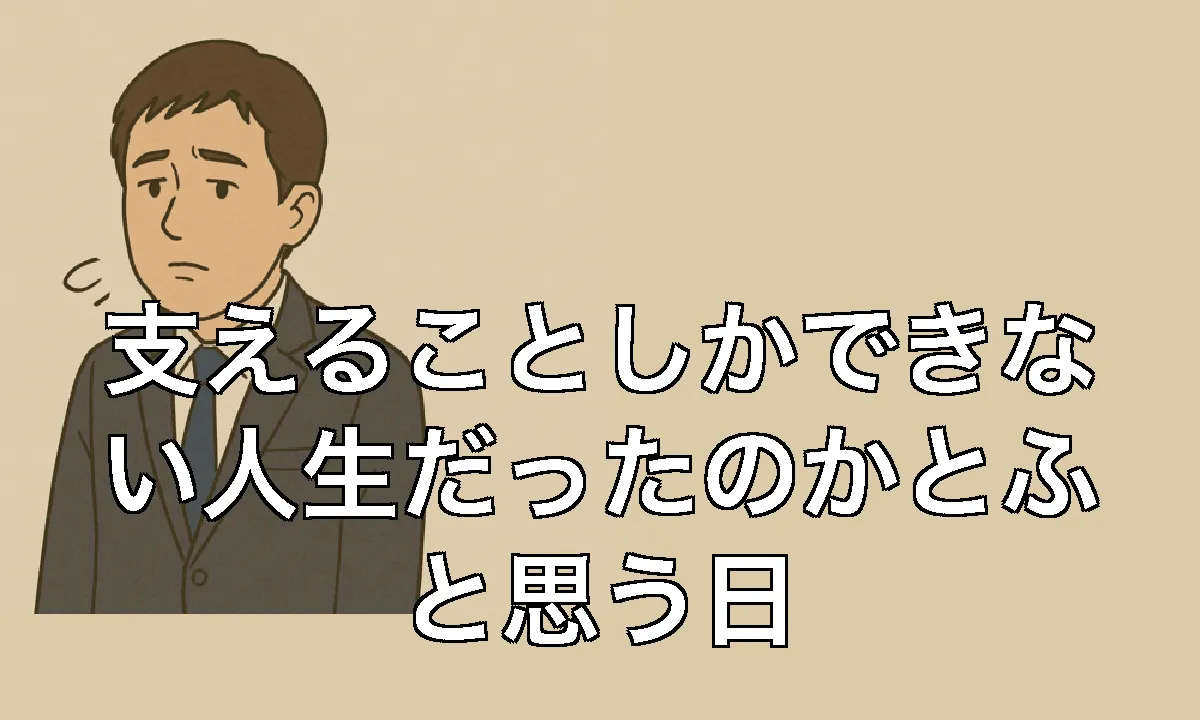支える立場に慣れすぎた自分に気づく瞬間
ふと気づくと、僕の人生は「支える側」に徹してきた。司法書士という仕事もそうだし、元野球部の頃からポジションもキャプテンではなく控えめなポジションばかり。表舞台に立つ人をサポートするのが当たり前になっていた。でも、心のどこかでずっと、「いつかは自分も主役に」という気持ちが消えたわけじゃなかった。最近では、その思いが浮かんでは消え、浮かんでは沈んでいく。
主役ではなく脇役のまま進んできた道
振り返れば、野球部時代もそうだった。誰よりも球拾いがうまく、バットを磨くのは得意だった。監督にも「お前がいると助かる」とは言われたけど、試合に出る機会は少なかった。大学も、就職も、そして司法書士としての今も、誰かの背中を見ながら、その後ろを支えるように進んできた。気づけば「自分が主役になる人生」を選ぶ勇気を、どこかで置いてきてしまったような気がする。
司法書士という職業の立ち位置
司法書士の仕事は、基本的には裏方だ。登記の現場に立ち会っても、主役は不動産業者だったり、クライアントだったりする。僕たちは手続きを滞りなく進め、法的なトラブルが起きないように陰で調整する。その重要性は理解されにくいし、感謝されることも多くはない。でも、誰かの大事な節目を静かに支えているという誇りは、確かにある。
主役になれなかった人生の選択
司法書士になったのは、「弁護士じゃなくても法に関わる仕事ができる」という理由だった。どこかで「目立ちたくない」という気持ちもあったと思う。でも、それは裏返せば「目立つのが怖かった」だけかもしれない。自分に自信がなくて、責任を持つことに怯えていた。支える人生を選んだのではなく、主役になることから逃げた人生だったのかもしれない。
誰かのために動いてばかりいた日々
気づくと、毎日誰かのスケジュールに合わせ、誰かの手続きを進めている。自分のペースで動ける日はほとんどない。事務員が風邪を引けば一人で電話もFAXもこなす。急な依頼があれば休日返上。そうして誰かのために動いている自分に、時々「これって、自分の人生なのか?」と問いかけてしまうことがある。
クライアントの「ありがとう」に救われる瞬間
すべてが報われないわけじゃない。たまに、「先生がいてくれて本当に助かりました」と言われることがある。そんな一言で、疲れた心が一瞬だけ和らぐ。でも、正直言って、それは数十件に一件くらいのレアケースだ。報酬よりも、感謝の一言が、どれだけ心の支えになっていることか。けれど、期待している自分が情けなくもある。
感謝されないことの方が多いという現実
むしろ、文句を言われることの方が多い。「なんでこんなに時間かかるの?」「前の先生はもっと安かった」そんな言葉を浴びながら、それでも自分を抑えて笑顔で対応する。支える側というのは、言い返すことができない立場でもある。言い返したら仕事が切られる。そんな緊張感の中で、自分の感情にフタをして働いている人は少なくないと思う。
「裏方でいい」と思ったのは強がりだったかもしれない
「目立つのは向いてない」「自分は脇役でいい」と言い聞かせてきたけれど、それはただの強がりだったかもしれない。ふとした瞬間に、「自分も拍手されたい」「名前を覚えられたい」と思ってしまうのは、人として自然なことじゃないか。司法書士という職業は、名もなき支援者であることが美徳のように扱われる。でも、そんな自分を誇れない夜もある。
見えない不満と諦めの積み重ね
「しょうがない」「そういう仕事だから」と納得することで、なんとか心の安定を保っている。でも、積もり積もった不満は、どこかで顔を出す。たとえば、誰かに「司法書士って地味だよね」と言われたとき。たとえば、異性との会話で職業を説明しても反応が薄いとき。ああ、自分の人生って誰の記憶にも残らないのかもしれない、とふと思ってしまう。
選ばれない自分への納得と葛藤
高校の頃からモテた記憶はないし、今も独身だ。年齢的にも、もう人を好きになる感情をどこかに置いてきた気がする。でも、そのことと仕事の充実感は別の話だ。人として「誰かに選ばれる経験」がないまま生きていると、自己肯定感がどうしても弱くなる。だからこそ、「仕事だけは役に立ちたい」と必死になってしまうのかもしれない。
誰かの成功の影にいる居心地の悪さ
不動産業者や士業同士の連携の中でも、やはり司法書士は裏方だ。花形の職業ではないし、表彰されることもまずない。「あの先生のおかげで」と言われることも、あまりない。でも、いないと困る存在ではある。矛盾しているようだけど、その「必要なのに目立たない」という立場が、一番モヤモヤを生む。誇りと孤独は紙一重だと思う。
たまに湧いてくる「主役願望」
テレビで誰かがスポットライトを浴びているのを見て、心の奥で少しだけ「羨ましい」と思う自分がいる。野球部時代の仲間が地元でコーチをしていて、子どもたちから「監督!」と呼ばれている姿を見て、ちょっと胸が締めつけられた。「自分は何を残せているだろう」と問いかける夜がある。誰かに誇れる何かを、持っていない気がしてならない。
周囲に言えない虚しさとの向き合い方
こうした感情は、同業者にもなかなか打ち明けづらい。相談会や勉強会では、みんな「順調そう」な顔をしている。でも、本音はどうなんだろう。僕のように「もうちょっと人に認められたい」と思いながら、それでも黙々と登記簿を整えている人は、意外と多いんじゃないだろうか。表に出ない思いほど、実は根深い。
一瞬だけ光が当たる瞬間の重み
たまに、同業の仲間から「この案件、先生じゃないと無理だと思って」と言われることがある。その瞬間だけ、自分が必要とされている実感がある。きっとそれがあるから、続けていられるのだと思う。でも、本当はもっと、日常の中でも自分に光が当たるような場面が欲しい。そう思うことが、甘えなのかどうか、自分でもわからない。
司法書士という仕事がくれた誇りと限界
司法書士としてやってきた20年近くの時間に、後悔はない。だけど「このままでいいのか?」という問いは、年々重くなってきている。支えることに意味はある。でも、自分を支えてくれる人がいない現実に、時々苦しくなる。この仕事を誇れるようになるには、自分自身をもっと大切にする必要があるのかもしれない。
支える人生にも意味があると思える時
元野球部の感覚で言えば、キャッチャーやマネージャーのような立場もチームには必要だ。目立たなくても、その人がいることで全体が機能する。司法書士も、そんな存在だ。もし僕がいなければ、誰かの人生の大切な局面がうまく進まないかもしれない。そう思えば、少しはこの仕事に誇りを持ってもいい気がする。
元野球部としての「チームを支える」精神
野球では、ベンチにいる人間もチームを盛り上げる役割がある。声を出し続けたり、スコアを取ったり。僕はその「縁の下の力持ち」だった。でも、そのポジションがなければ、チームは崩れていたかもしれない。司法書士という裏方の職業も、そんな存在だと思いたい。そうでもしなきゃ、報われない気がしてしまう。
影の役割だからこそできることもある
影であるからこそ、見えることもある。主役の人たちが気づかない問題や、不安を先に感じ取り、サポートできるのが僕たちの強みだ。控えめだけど確かな役割が、ここにはある。だから今日もまた、誰かの後ろで静かに仕事をしている。そんな自分を、少しだけ好きになれたらと思う。
だけどやっぱり一人はしんどい
いくら仕事に誇りを持てても、家に帰って電気をつけたときの静けさには勝てない。仕事が忙しいふりをしてごまかしてきたけれど、心の中にはいつもぽっかりとした穴がある。誰かの人生を支えるだけでは、どうにも埋まらないものがある。
誰かと一緒にいる意味を考える
一緒にご飯を食べてくれる人がいたら。一緒に「今日も疲れたね」と言って笑い合える人がいたら。そういう小さな幸せを、今さらながら求めてしまう自分がいる。誰かを支えるだけでなく、誰かに支えられることも、大事なのだと最近になって思う。
独身の夜にふと考える「この先」
もう若くはない。でもまだ終わりじゃない。支えることしかしてこなかったけれど、自分の人生を取り戻すことだって、できるかもしれない。これからは、誰かの影だけでなく、自分の光も少しは探してみようと思う夜が、増えてきた。