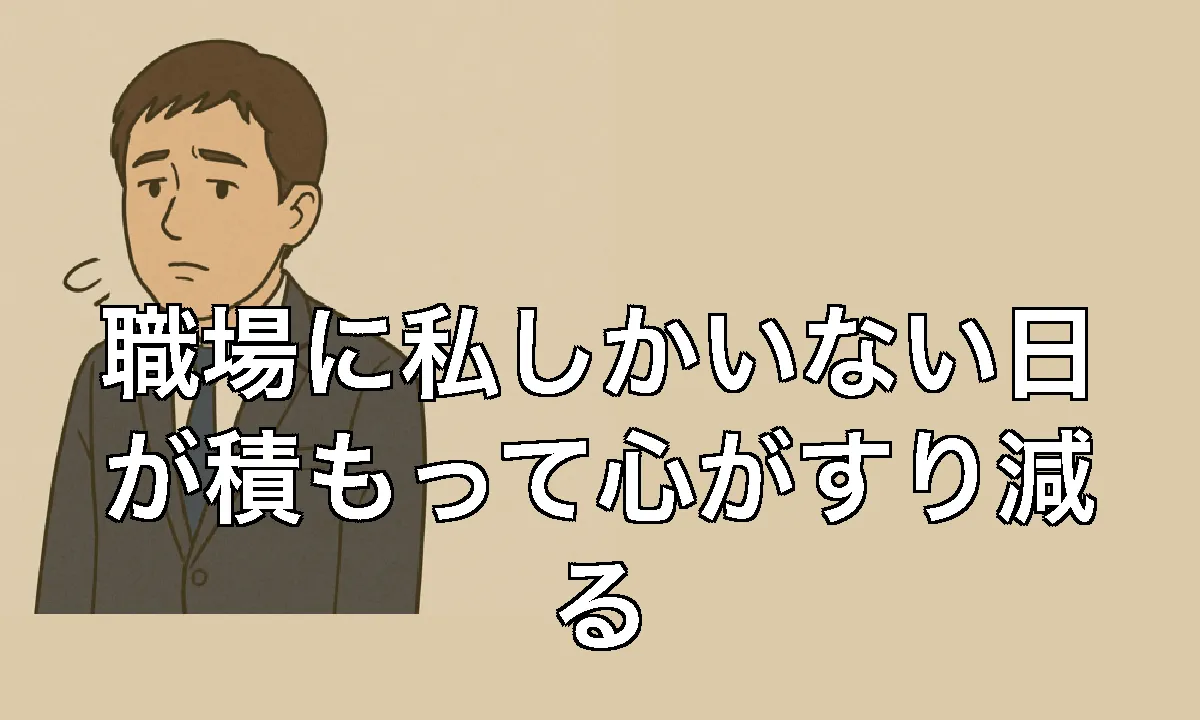朝出勤して鍵を開けるのはいつも自分だけ
今日もまた、事務所のシャッターを上げて、重い引き戸の鍵を開ける。誰かがいる気配のない朝は、もう慣れたとはいえどこか物悲しい。静まり返った空間に「おはようございます」と小さくつぶやいてみるが、返事はもちろんない。野球部時代は声を張るのが当たり前だった自分が、こんなに静かな世界にいるとは思わなかった。最初の頃は「一人のほうが気楽でいい」と思っていたが、その気楽さの中には不安や孤独がじわじわと忍び寄ってきていた。
静かなオフィスに差し込む朝日がむしろ切ない
朝一番に窓のブラインドを開けると、差し込む朝日が部屋を照らす。その光すら、時にはまぶしく感じるのだから、きっと自分の心がくたびれているのだと思う。以前はこの光が一日の始まりを前向きにしてくれていた。でも今は違う。あの頃一緒に働いていた補助者が辞めてから、静寂だけがずっと続いている。事務員の小さな雑談がこんなにもありがたかったとは、失ってみて初めて気づいた。孤独な朝に、人の声は最高のスイッチだった。
自分の足音しか聞こえない空間で不安が育つ
一歩歩くたびにコツン、コツンと床に響くのは自分の足音だけ。電話も鳴らない、コピー機の音もしない、何も動かない空間は、まるで時が止まったようだ。そんな中で仕事を始めても、ふとした瞬間に「これで大丈夫か?」という不安が胸をよぎる。確認できる相手もいない、声をかけられる仲間もいない。司法書士という仕事は責任が重いだけに、一人きりという状況が、どんどん自信を奪っていくように感じる。
今日も一人かと思うその瞬間から疲れている
事務所のドアを開けて、誰もいないことを確認するたびに、ほんの少し肩が落ちる。朝の時点で「今日も一人か…」と心がつぶやいている時点で、もうその日は半分疲れている。仕事は好きだし、誇りもある。でも、それを誰かと共有できない状況が続くと、ただの作業に感じてしまう。孤独は疲労よりも厄介で、やる気を静かに奪っていく。コーヒーを入れても、誰かと飲むわけではないのだ。
何かあったとき誰も助けてくれない現実
一人勤務の日に限ってトラブルが起きる。そんなジンクスでもあるかのように、書類の間違いや急な来客、電話の嵐が重なる。しかも、誰にも相談できない。ちょっとした確認をしたいだけなのに、それができないことで大きな不安に変わっていく。司法書士としての責任感はある。でも、人間だから不安にもなるし、誰かと一緒に背負いたいと思うこともある。そんな時、孤独という事実が重たくのしかかる。
ミスもトラブルも全部自分で受け止める日々
書類の数字が一桁ずれていた、印鑑の押し間違いがあった。そんな小さなミスも、自分しかいない職場ではすべて自分の責任になる。たとえ原因が他にあっても、気づかなかった自分が悪いとされるのがこの世界。事務員と二人三脚でやっていた頃は、お互いの目でチェックできていた。でも今は、その目がない。だから確認作業に倍の時間がかかる。焦れば焦るほどミスが増える悪循環。誰かがいてくれたら、どれだけ心強いだろう。
相談できる誰かがいないと判断も心細い
「これで大丈夫か?」「この表現で通じるか?」と迷ったとき、以前ならすぐに隣の事務員に声をかけられた。今はそれができない。法律の判断に関することは最終的に自分で決めるしかないが、それでも「ちょっと意見を聞かせて」と言える相手がいるだけで、ずいぶん精神的に違っていた。今はその確認作業すらひとり。自信がないときの判断ほど怖いものはない。そしてその怖さが、自分をどんどん内向きにさせていく。
結局最後は責任という名の重しがのしかかる
すべてを自分で決め、自分で行い、自分で確認し、自分で反省する。それが一人職場の現実だ。うまくいけば誰にも褒められないし、ミスがあれば全部自分の責任。誰かに八つ当たりできる環境ですらない。一人で淡々と責任を背負う毎日は、思っている以上に消耗が激しい。責任感が強いほど、それが心の中で爆発する前に、じわじわとすり減っていくのだ。