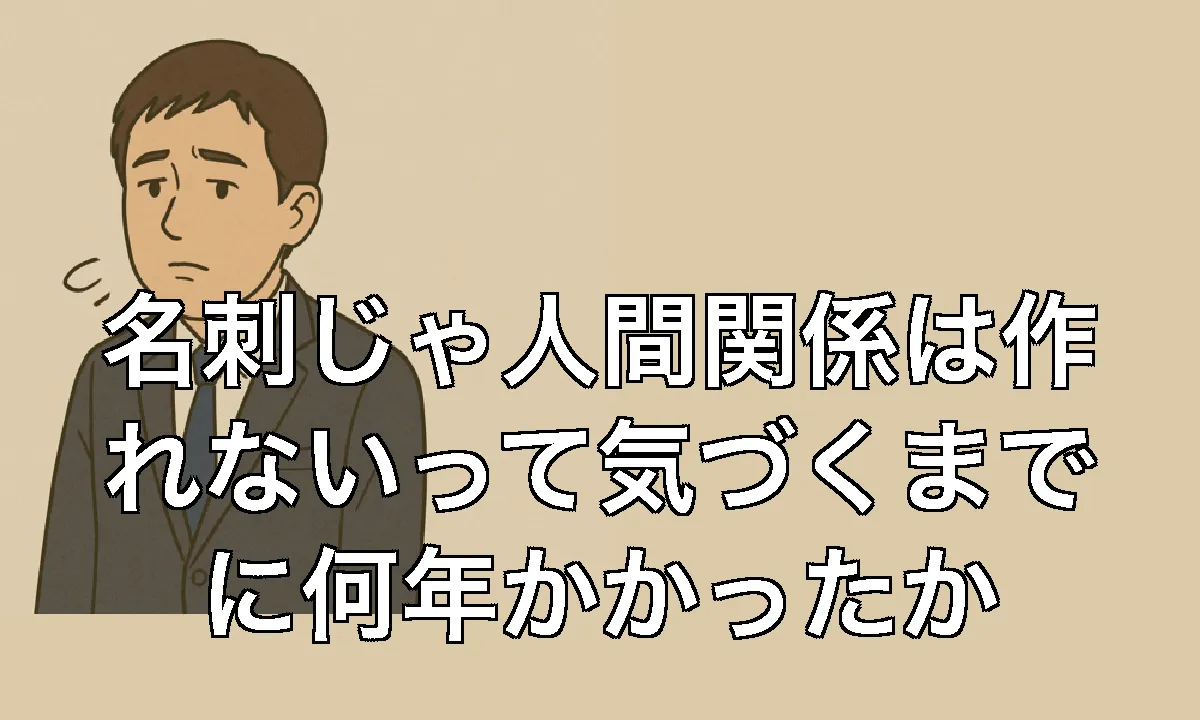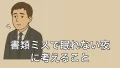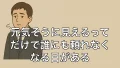名刺は持っていて当たり前の世界で
司法書士という職業をやっていると、名刺交換の機会は多い。銀行、不動産、税理士、弁護士、役所関係……出入り先のあちこちで「名刺をください」と言われる。最初のうちは、自分の名前が刷られた名刺を渡すのがちょっと誇らしかった。ああ、ようやくプロになったんだなと。でも、それも束の間。気づけばただの紙切れになっていた。相手の顔も覚えていない、もちろん向こうもこちらを覚えていない。そんな“交換”が仕事だと思い込んで、何年も過ごしてしまった。
初対面の挨拶はいつもどこか嘘っぽい
「はじめまして、◯◯司法書士事務所の稲垣です」——もう何百回と繰り返してきたこのセリフ。でも、口にするたび、どこか虚しさがある。たいてい相手もマニュアル的な受け答えで、目線は名刺かスマホの通知の方に向いていることが多い。誰もこちらの“人間”を見ていない。ただの立場や職業で判断されるだけだ。まるで、会話というよりシステムの一部を演じているような感覚になる。
肩書きで判断される虚しさ
司法書士という肩書きには、それなりに信頼が伴う。けれど、そこに“自分”が存在していないとき、その信頼は表面的なものだ。たとえば、先日依頼された会社設立登記の案件。紹介で来たお客さんは、僕のことを一度も見ず、ずっと税理士さんとばかり喋っていた。名刺は渡したけれど、僕はまるで透明人間だった。名刺があるから信頼されるわけじゃない。むしろ、信頼があってこそ名刺に意味が生まれるんだと痛感した。
「先生って呼ばれても中身がない」
正直、“先生”って呼ばれるのも、もう飽きた。最初は照れながらも悪くない響きだと思っていたけど、今は逆に距離を感じる言葉になった。「先生」と呼べばいいという安心感だけが先行して、こちらの話をまともに聞こうとしない人も多い。そんなとき、自分の存在意義がどこにあるのか見失いそうになる。名刺に刷られた「司法書士」という文字より、僕がどんな人間なのか、それを知ってもらう方がずっと大事だったと、ようやく思えるようになった。
名刺交換のたびに生まれる距離感
渡すたびに、自分が空っぽになっていく気がした。確かに仕事は取れる。でも、それは本当に「関係」なんだろうか? 一度会ったきりで音沙汰なし、話した内容も覚えていない。そんな名刺の山が引き出しの奥に積もっていく。あれが自分の“営業成績”だとしたら、どれだけ中身のない数字を積み上げてきたんだろうか。
名前は覚えられても、顔は思い出されない
何かの集まりで久しぶりに再会した相手に、「あ、名刺いただきましたよね?」と言われたときの、あの微妙な空気。こちらは相手の名前も顔もピンとこない。向こうもたぶん同じ。名刺という形があるからこそ、「会ったことある人」扱いにはなるけれど、そこに心の通った記憶なんてない。むしろ、形式的なつながりがかえって人との距離を広げているような気さえする。
誰かの「ついで」に扱われた日
一番しんどかったのは、税理士さんとの打ち合わせの場で「この人は書類の登記の人です」とだけ紹介されたときだ。名前も呼ばれず、ただの“処理係”。名刺を渡す機会すらなかった。もちろん仕事はもらえたし、やったけど、そこにあるのはただの事務作業の委託。僕という人間じゃなく、職能だけを見られている。そう感じるたび、自分が機械になったような気がして、事務所に戻って一人で落ち込む。
たくさん配っても、誰とも繋がれない
独立して最初の数年は、とにかく名刺を配った。名刺交換会にも出た。ひたすら名刺を差し出して、笑顔をつくって、気の利いたひと言を添えるようにしていた。でも、誰も本当の意味で覚えてくれていないし、僕自身も誰にも興味を持てなかった。表面的なやりとりだけが残って、ただ名刺の在庫が減っていくだけ。数はあっても、そこに“人間関係”なんて一つもなかった。
それでも渡さなきゃ仕事にならない
名刺がないと話が進まないのも事実。だからこそ余計に、その紙切れ一枚に自分の存在を委ねるしかないのが辛い。司法書士という職業は信頼が命だけど、その信頼を最初に示す手段が名刺だけって、何とも皮肉な話だ。渡したからといって信用されるわけじゃない。でも、渡さなければ“プロ”として認められない。
儀式のような「交換」だけが続いていく
毎回の挨拶が形式的になっていくのがわかる。「よろしくお願いします」の言葉に感情がこもらない日がある。もう、作業なんだ。お互いにスーツを着て、名刺を出して、お辞儀をして、それで終わり。そんな出会いを積み重ねても、本音を話せる関係にはならない。むしろ、相手にとって「交換済みの誰か」になって、記憶からも感情からも遠ざかっていく気がする。
本音で話せた相手は何人いただろう
思い返してみると、本音を話せた相手なんてほんの数人。長年付き合いのある司法書士仲間とか、地元の不動産会社の社長とか、数えるほどしかいない。そういう人たちとは、名刺を交換した瞬間よりも、そのあと何度も顔を合わせて、雑談をして、仕事以外の話をした時間の方が長い。関係って、名刺じゃなくて“経験”でできていくものなんだよな。
信頼は、名刺じゃなくて時間でできる
結局のところ、人とのつながりは、肩書きや名刺に頼らない方がうまくいく。時間をかけて、少しずつ相手と関わっていく中で、ようやく築けるものだって、やっと気づいた。遅いけど、それでも無駄じゃなかった。何百枚と配った名刺があったからこそ、たった一枚の“意味ある関係”の重みも知れた気がする。
何度もやり取りして、ようやく心が見える
一度じゃわからない。二度目もまだ表面。それでも三度、四度とやり取りを重ねていくうちに、少しずつ相手の考えや価値観が見えてくる。こちらのことも、ようやく相手が知ろうとしてくれる。時間がかかる。でも、その時間こそが信頼なんだと思うようになった。焦らず、でも丁寧に関係を築いていく。それが、名刺以上に大事な“武器”なんじゃないか。
地味な積み重ねしか道はない
若い頃は、「印象に残る名刺のデザイン」とか「覚えてもらえるキャッチコピー」に躍起になった。でも、そんなの全部一瞬で忘れられるってことを、現場で学んだ。やっぱり大事なのは、日々の仕事ぶりと、ちょっとした気遣い。地味だけど、丁寧に向き合うこと。それを続けていれば、名刺なんてなくても覚えてもらえるようになる。
それをわかってくれる人は少ないけど
正直、ここまで書いてきたような思いを共有できる相手は少ない。世の中は効率を求めるし、肩書きで判断される場面もまだまだ多い。でも、それでもあきらめず、少しずつでも人とちゃんと向き合う努力は続けたい。名刺を渡すのではなく、自分を伝える。そうやって繋がった関係の方が、何倍も仕事がしやすいし、何より疲れない。名刺を配るより、心を配りたい。そう思えるようになったのは、無駄に名刺を配り続けたあの数年のおかげかもしれない。