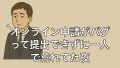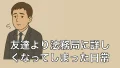書類が戻ってきた日の絶望
朝、事務所のポストを開けた瞬間、嫌な予感がした。見覚えのあるレターパックが、無惨に折れ曲がって詰まっていたからだ。嫌な予感は的中した。中には、先週出したはずの登記申請書類が返送されていて、「書類が折れており受理できません」との赤いハンコ。いやいや、ちゃんと送ったじゃないか。追跡番号だって記録されている。なのに「届いたのに届いてない」と言われる理不尽さ。司法書士をやっていると、こんなちょっとしたことで心が折れることがある。
ポストを開けた瞬間の違和感
いつも通り事務所に来て、机に座る前にまずポストを確認するのが日課だ。その日は妙にポストが詰まっていた。何かが中で引っかかっている感触があった。無理やり引き出してみると、そこにあったのは自分が送ったレターパック。しかも角が思い切り折れて、紙が曲がって変形している。「まさか」と思って中を見た瞬間、頭の中が真っ白になった。あの書類は、急ぎの登記案件のものだったのだ。
角が折れたまま戻ってきた書類
書類自体は破れてはいない。だけど折れ目が付いてしまった申請書類というのは、それだけで法務局からは「形式不備」とみなされることがある。特に今回は、申請書の右上に押された実印の一部が折れでかすれており、それが問題視されたらしい。そういう細かいチェックがあることは知っていたし、自分も他人には「丁寧に梱包して」と言っている。けれど、まさか自分がそんなことで足をすくわれるとは思っていなかった。
「受理できません」との冷たいメモ
法務局からの返送には、よくある定型文の「不備通知」が添えられていた。「書類が破損していたため受理不可。再送付のこと。」と、まるで事務的な通知。こちらの苦労や気持ちは一切考慮されていない。「いや、それは郵便事故でしょうが」と叫びたくなったが、誰に言えばいいのか分からない。結局、急いで再印刷して、印鑑を押し直して、封筒を新しくして……予定していた段取りはすべて崩れてしまった。
誰のせいでもないが誰かのせいにしたくなる
こんなとき、本当は誰の責任でもないと頭では分かっている。郵便局も悪くない、法務局もルールに従っているだけ、もちろん自分も可能な限り丁寧に対応したつもりだ。でも、どこにもぶつけようのない怒りややるせなさが溜まっていく。言ってしまえば、運が悪かった。それだけのことかもしれない。でも、こっちは仕事でやってるんだ。予定が狂えば、お客さんに謝り、次の案件にも影響が出る。
郵便事故か配達ミスかただの運か
今回のケースは、明らかに「折れ曲がっていた」ことが問題だったが、それが配達中のことなのか、法務局での受領時なのか、もうわからない。責任の所在を追求しても、誰も得をしない。でも、もしこれがもっと重大な案件だったら? もし依頼者が高圧的な人だったら? そんな想像がどんどん膨らむ。そしてふと、「なんでこんなことまで考えないといけないんだ」と、自分が情けなくなってくる。
相談者に説明する気まずさ
一番つらいのは、依頼者に説明するときだ。「すみません、郵送中に書類が折れてしまいまして…」という話は、こちらの落ち度でないのに、まるで言い訳のように聞こえる。しかも、相手はそんな事情より「登記が遅れること」にしか関心がない。冷静な人なら理解してくれるが、少しでも感情的なタイプだと「プロなんだから、そういうのも防いでよ」と言われかねない。実際にそう言われて、胃が痛くなった。
忙しい日々の中でのちょっとしたトラブル
普段から業務はパンパンに詰まっていて、昼飯を座って食べられたらラッキーなほう。そんな中で今回のような「想定外」は、心の余裕を一気に削り取る。再送対応、予定の見直し、そして次の案件の処理。全部がズレて、全部が重なって、疲労感が倍になる。小さなトラブルだけど、忙しい人間にとっては致命的だ。誰かが代わってくれるわけでもないし、ただ淡々と自分が処理するしかない。
予定が一つ狂うと全部がズレる
たとえば、午前中にその案件を処理する予定だったのが、午後に回る。午後は別件の相談があるから、それも後ろ倒し。結局、事務員の子も帰れず、なんだか申し訳なくなる。うちは少人数だから、こうしたズレがダイレクトに効いてくる。しかも、電話が一本でも鳴れば、リズムはまた崩れる。「なんで今日はこんなに噛み合わないんだろう」と思っていたら、そもそも最初から崩れていたんだと気づく。
事務員さんも気まずそうな顔
うちの事務員さんは真面目でよく気が利く。でも、今回の返送を見て「すみません、私の梱包が甘かったのかも」と気を遣ってくれた。その一言で、ちょっと泣きそうになった。いや、悪いのはたぶん誰でもない。でも、こうしてお互いに気を使ってしまうような空気が、またしんどい。仕事って、本当に人間関係の積み重ねだなと痛感する。
書類の扱いにも気を配らなきゃいけない職業
司法書士の仕事は、とにかく「正確さ」が求められる。形式が少しでも崩れていればダメ。内容が正しくても、紙がヨレていれば再提出。どこか理不尽に思えるけれど、それがこの世界のルールであり、信頼を担保するための仕組みだ。わかってはいるけれど、「そこまで?」と思うことはしょっちゅうある。今回の件も、まさにその象徴だった。
折れただけでやり直しになる世界
現場を知らない人にとっては、「紙がちょっと折れたくらいで何が問題?」と思うかもしれない。でも、その「ちょっと」の差が、大きな信用問題につながることもある。申請は法務局の担当者の目でチェックされる。その人の感覚ひとつで、通るかどうかが変わることすらある。そういう曖昧で厳格な世界にいると、神経がすり減っていく。
「ちょっとくらい大丈夫だろ」が通じない
たとえば、かつて銀行員時代の友人が「そっちはまだ紙文化なんだな」と笑っていたが、まさにそう。デジタル申請が増えても、まだまだ紙の世界。だから、折れ曲がりひとつでアウトになるのだ。自分の中の「常識」が通じない、ということが、こんなにもストレスになるとは、司法書士になってから初めて実感した。
それでもやるしかないからやっている
結局、誰に泣きついてもどうにもならない。書類を直して、封筒を変えて、もう一度投函する。それがこの仕事だ。愚痴もこぼしたくなるが、同時に「自分しかいない」とも思ってしまう。元野球部だった頃、「最後まで諦めないのが役割だろ」と言われていたが、今もそれに近い気持ちで仕事をしている。
ひとり事務所のリアルな現場
都会の事務所のように、チームで支える余裕はない。自分と事務員さんの二人三脚。だけど、こうした一つ一つの経験が、自分たちを強くしてくれる気もする。苦労ばかりだけど、たまに「ありがとう」の一言で救われる。折れた書類一つで一日が潰れても、また明日、同じように机に向かう。それが、司法書士という仕事なのかもしれない。