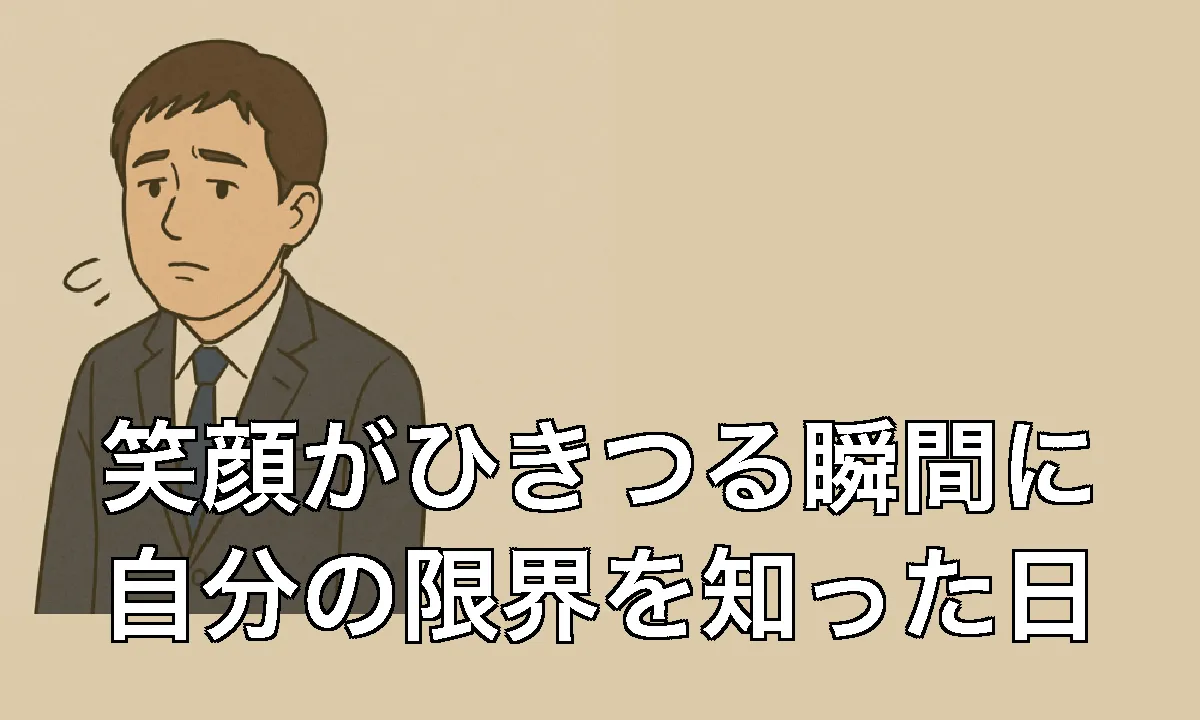自分でも気づかなかった笑顔の異変
ある日、ふと鏡を見たとき、そこに映っていたのは自分ではないような、何とも言えない表情の男だった。口元は笑っているつもりなのに、目が笑っていない。自分が思っている「笑顔」が、他人から見ればどんな風に映っているのかなんて、普段は気にも留めていなかった。けれど、その時は違った。いつものように依頼人を迎える前の準備のはずが、なぜか違和感が胸をざわつかせた。「これが俺の限界サインなのか」と、どこかで思っていたのかもしれない。
鏡の中の自分が誰か分からなくなる朝
朝起きて、洗面所で顔を洗いながらふと目が合った鏡の中の自分。そこにいたのは、数年前の自分とはまったく別人のような表情の男だった。くたびれた目の下のクマ、歪んだ笑顔、そして乾いた口元。それなのに、口角だけはなんとか上げようとしている。そうして自分を「笑顔だ」と思い込ませて仕事に向かおうとしていた。昔の野球部時代、どんなに疲れても「気合いだ」と自分に言い聞かせていた習慣が今も染みついているのかもしれない。けれど、司法書士という仕事は気合いだけじゃ乗り越えられない瞬間が多すぎる。
身だしなみよりも表情が気になった
これまでは朝の準備といえば、スーツのしわ、ネクタイの締まり具合、髪の寝癖など、見た目ばかりを気にしていた。だが、その日は違った。どうしても顔が気になって仕方なかったのだ。「この顔で依頼人に会って大丈夫だろうか」そんな不安が胸の奥からこみ上げてくる。決して大げさではなく、笑顔が「演技」にしか感じられなくなっていた。そんな状態で、信頼を預かる立場に立っていいのかと、自問自答しながらネクタイを直した。
「笑ってるつもり」が「引きつって見える」違和感
自分では笑っている「つもり」なのに、それが相手にどう伝わっているかまでは想像できていなかった。だが、実際にその笑顔を見た事務員が「先生、顔がちょっと…」と口ごもる姿を見て、初めてそれが伝わってしまっている現実を突きつけられた。心の疲れは、無意識のうちに表情にも出るものだ。プロとして、人前に立つ者として、それを隠せていないことが恥ずかしくもあり、情けなくもあった。いや、そもそも「隠す」という感覚すら薄れていたのかもしれない。
仕事の山に押し潰される予感
司法書士の仕事は、やろうと思えばいくらでも仕事が積み上がる。登記手続き、裁判所関係、後見業務…。自分で制御しない限り、仕事は止まってはくれない。それなのに「これだけ終わらせれば今日は楽になる」と思って次々と抱え込んでしまう。結果、休みも気分転換もなくなり、疲労だけが溜まっていく。そしてある日、ふと手が止まった。「もう無理だな」と、心がささやいていた。
やることは無限、気力は有限
自分のキャパシティを見誤るのは、真面目な人ほど陥りやすい罠だと思う。自分もそうだった。「あの人も困っている」「この人の案件は急ぎだ」そんな風に、つい引き受けてしまう。相手に断られる辛さを味わわせたくないという思いやりが、いつの間にか自分を苦しめていた。それでも、「休んだら後が怖い」と自分に言い訳をして、気力でカバーしようとしていた。気力って、本当に有限なんだと身をもって知るまで時間はかからなかった。
一人で背負い込む悪いクセがまた顔を出す
何かあると「自分でやったほうが早い」と思ってしまう癖がある。事務員に頼めばいいのに、細かい手続きや書類確認まで全部自分で抱える。「責任感が強い」と言えば聞こえはいいが、実態は単なる不器用さだ。そうやって一人でどんどん仕事を背負い込み、結果的に精神的に追い詰められていく。気がつけば、笑顔を作る余裕すら奪われていたのだ。
相談を受けるたびに削れていくもの
相談者の前に立つとき、自分の感情は脇に置いておかねばならない。「頼ってくれる人の前では、安心感を与えるべきだ」そう信じて、これまでやってきた。でも、その姿勢が自分の心をすり減らしていくとは、当時は思ってもみなかった。笑顔は安心の象徴でありながら、自分にとっては仮面にもなっていた。長年かけて作り上げてきた「理想の司法書士像」に、自分が追い詰められていた。
依頼人の前では笑顔を保たねばならない
依頼人は不安を抱えてやってくる。その不安に寄り添うためには、こちらがまず落ち着いた表情をしていなければならない。だから、どんなに疲れていても、無理にでも笑顔を作る。しかしその笑顔が、「どこか怖い」と言われたことがある。その瞬間、胸の奥がズシンと重くなった。信頼してもらおうと頑張ってきたはずの笑顔が、かえって相手に警戒感を与えてしまった。その事実に、心が折れそうになった。
でも、感情がついてこない
無理に笑顔を作っても、心が疲れていれば表情は追いついてこない。思考が鈍っていると、言葉の選び方にも影響が出る。依頼人との会話で噛み合わないことが増えてきたと感じたとき、「自分、大丈夫か?」と心の中で問いかけた。昔のように、冗談を交えながら会話を和ませる余裕もない。もはや、感情のスイッチの入れ方を忘れてしまったかのようだった。
「大丈夫ですか?」と逆に心配される日も
ある日、依頼人に「先生、お疲れじゃないですか?」と心配されたことがある。その一言に、言葉を失った。「こちらが不安を取り除いてあげる側なのに、逆に気を使わせてしまっている」その現実にショックを受けた。立場の逆転を感じる瞬間というのは、想像以上に堪えるものだ。自分の弱さを人に見せたくないというプライドと、どうにもならない現実との間で、どうしていいか分からなくなっていた。