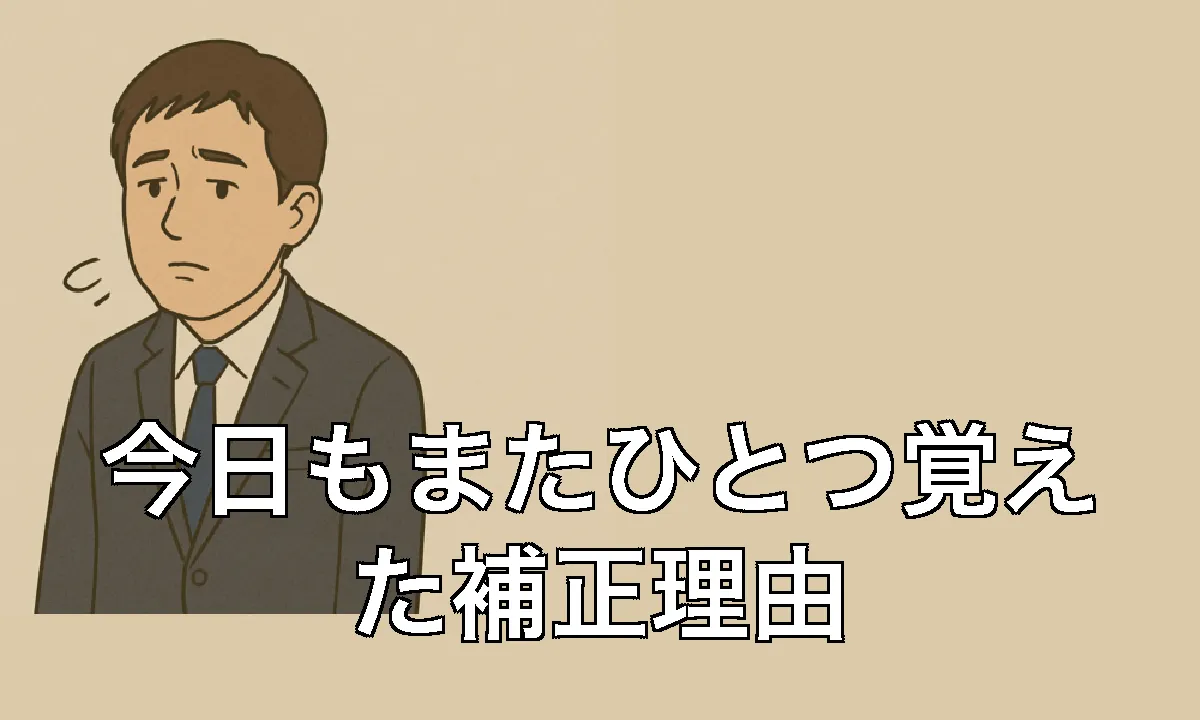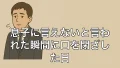今日もまたひとつ覚えた補正理由
司法書士をやっていると、いつの間にか補正通知が日常の一部になる。ないに越したことはない。でも、現実はそう甘くない。朝一番でメールチェックして、「ああ、やっぱり来てたか」とため息交じりにPDFを開く。今日はどんな理由か…確認した瞬間、思わず「またそれかよ」と独り言。ひとつひとつが大したミスじゃない。でも、それでもやっぱり自分の不注意や甘さに腹が立つ。補正理由、それはまるで今日の自分の通知表だ。
なんで毎回こうなるんだろうと机を見つめる朝
デスクに座り、書類を開くたびに思う。「昨日の俺、なんでこれでOK出した?」と。補正の内容は決して難解なことじゃない。たとえば住民票の写しの記載事項が不足していたり、登記原因証明情報に日付のズレがあったり。「そんな初歩的な…」と自分で自分に呆れるのも、もはや日課だ。外は朝日がまぶしいのに、こちらの心はどんより曇天。そんな朝が、週に何回あるだろう。
昨日の自分にツッコミを入れながら書類を開く
補正通知を見ながら、つい声が漏れる。「おい、昨日の俺、これ見落とすか?」自問自答というよりは、自責の独り芝居。昨日は疲れていた?いや、そんな言い訳は通じない。司法書士という仕事は、常に冷静で正確であることが求められる。とはいえ人間だから、ミスもする。でもその「人間らしさ」が業務に出たとき、許されないのがこの仕事だ。まるで自分の野球部時代のノーサイン暴走を思い出す。「走るなって言っただろ!」って、あの監督の声が今でも耳に残っている。
修正理由が「なるほど」よりも「またか」で始まる
補正理由を読むとき、最近「なるほど」という感想は減った。その代わりに増えたのが「またか」。補正通知が来ると、だいたい見当がつくようになってきたのは、ある意味スキルなのかもしれない。でもそれは、つまり同じようなミスを繰り返しているってことだ。進歩してないのか?いや、してるはず。でもその実感よりも、「またこのパターンか…」という絶望感が先に来る。毎回違う書類で、毎回同じ気持ちになる。それが地味に堪える。
補正通知との付き合い方が変わってきた
補正通知が届くたびに心を乱されていた新人時代。あの頃は、「自分はこの仕事に向いてないんじゃないか」と本気で悩んだ。でも今はちょっと違う。補正が来ること自体に動揺はしなくなった。正直、慣れたとも言える。でも、それは成長ではなく、鈍感になっただけかもしれない。問題は、反省と自己嫌悪のバランスをどう保つかだ。感情の起伏が落ち着いてきた分、逆に無力感が濃くなった気もする。
最初はビクビクしてたけど最近はもはや日常
初めて補正通知を受け取った日のことは今でも覚えている。あの時は、手が震えていた。「これって、自分の責任じゃん…」って頭が真っ白になった。でも今は違う。ビクビクはしない。ただ、「はいはい、また来ましたね」といった感じ。慣れとは怖いもので、通知を見るたびに心拍数が上がることもなくなった。それが良いことなのか、悪いことなのか、正直わからない。でも、この“慣れ”がなければ精神が持たないのも事実だ。
それでも心のどこかでまだショックを受ける
慣れたとはいえ、ゼロにはならない。やっぱり、胸の奥では少し痛い。「また確認不足か」「また凡ミスか」——そんな自分へのがっかり感が、じんわりと染みてくる。事務員さんがさりげなく補正対応のチェックリストを机に置いてくれるとき、「ああ、俺がまた手間かけてるんだな」と思って申し訳なくなる。その無言のやさしさが、逆にきつい。自分が甘えてることに気づいてしまう瞬間でもある。
事務員さんの静かなため息が刺さる
事務所は基本的に静かだ。電話が鳴っていないときは、ほとんどキーボードの音しか聞こえない。でも、ふとした瞬間に聞こえる「ふぅ…」という事務員さんのため息。それが妙に耳に残る。彼女は文句を言わないし、責めもしない。でも、その沈黙が逆に責任を突きつけてくる。補正通知が来た日、彼女の動きが少しだけ早くなったり、無言が続いたりすると、「ああ、気を遣わせてる」と察してしまう。
「またですか」って言葉は聞こえないけど聞こえる
彼女は一度も直接「またミスですか?」とは言わない。そんなこと言うような人じゃない。でも、その優しさの中にある“諦め”のような雰囲気は、なんとなく伝わってくる。たぶん、僕自身がそう思われていると感じてしまっているだけかもしれない。でも、人の気配って、案外ごまかせない。自分が誰かの時間を使わせていることに気づいたとき、一番ダメージを受けるのは、やっぱり自分だ。
間違えたのは俺だけど、処理するのは彼女
補正通知が来て、訂正の手続きを進めるのはたいてい僕だ。でも、そこに付随する事務的な作業、通知の整理や顧客対応、再提出の段取りは、ほぼ事務員さんに頼っている。僕の一つのミスが、彼女の手間を倍にする。そんなことはわかっている。でも、だからといってすぐに完璧になれるわけでもない。自分の無力さを突きつけられながら、それでもまた明日も仕事は続く。
補正理由って結局どこまで理解してるんだろう
何年この仕事をしていても、「完璧に理解してる」と胸を張って言える補正理由は少ない。書面上の言葉は理解できても、実務の流れや書類の背景にある“意図”まできちんと読み取れているのかと言われると、正直心もとない。機械的に処理してしまっている部分もあるし、深掘りを避けてしまっている自覚もある。仕事に慣れるほど、油断も増える。毎回自分の勉強不足を突きつけられているようだ。
知識じゃなくて注意力の問題だと気づく
補正理由の多くは、知識不足よりも注意力不足に起因する。たとえば日付のミス、地番の誤記、書類の添付漏れ。どれも一度は学んだはずのこと。なのに、実際の現場では抜けてしまう。それは集中力が落ちているときだったり、他の業務と並行して焦っていたりするタイミングだ。知識でどうこうなる問題じゃない。まさに「疲れ」が犯人。だからといって言い訳にはならない。わかってる。でも、しんどい。
毎回違うのに、毎回「またやった」と思う不思議
補正の内容は毎回微妙に違う。でも、気持ちは毎回同じ。「ああ、またやった…」。一度として同じミスをしてないのに、同じ反省を繰り返している気がする。まるで形を変えたデジャヴ。改善したつもりでも、別の角度から突っ込まれる。それがこの仕事の難しさだと思う。法律も制度も変わる。申請様式も細かく修正される。その変化に、毎回「またか」と思いながら、なんとか食らいついていく。
学びと反省の間にある疲労感
補正通知を通じて、毎回なにかを学んでいるはずだ。そう思いたい。実際、「次は気をつけよう」と思うし、チェック項目も増やしている。でも、学びの先にあるのは「もう間違えたくない」というプレッシャーだけで、心が軽くなることは少ない。反省して学んで、また反省する。そのサイクルが続くと、どうしても疲れてくる。前向きな努力が、いつの間にか消耗に変わる瞬間がある。
成長してる気はするけど報われてる気はしない
少しずつ成長はしている。あきらかに昔より補正は減っている。でも、その実感がモチベーションに変わることは少ない。「今回たまたま補正が来なかっただけかも」と疑ってしまう自分がいる。褒められることも、評価されることもほとんどない。自分の成長を信じられないまま、今日も仕事をこなす。そんな日々が続くと、「この努力、意味あるのか?」という気持ちが顔を出す。
「ありがとう」より先に「すみません」が出る日々
事務員さんに対して、つい先に出てしまう言葉は「ありがとう」ではなく「すみません」。本当は「いつも助かってます」と感謝を伝えたい。でも、先に謝罪の言葉が出る。それだけ負い目を感じているのかもしれない。「すみません」が積み重なると、だんだんと自己肯定感もすり減っていく。でも、それでもやるしかない。司法書士としての仕事は、そういう積み重ねの上に成り立っているのだと思う。