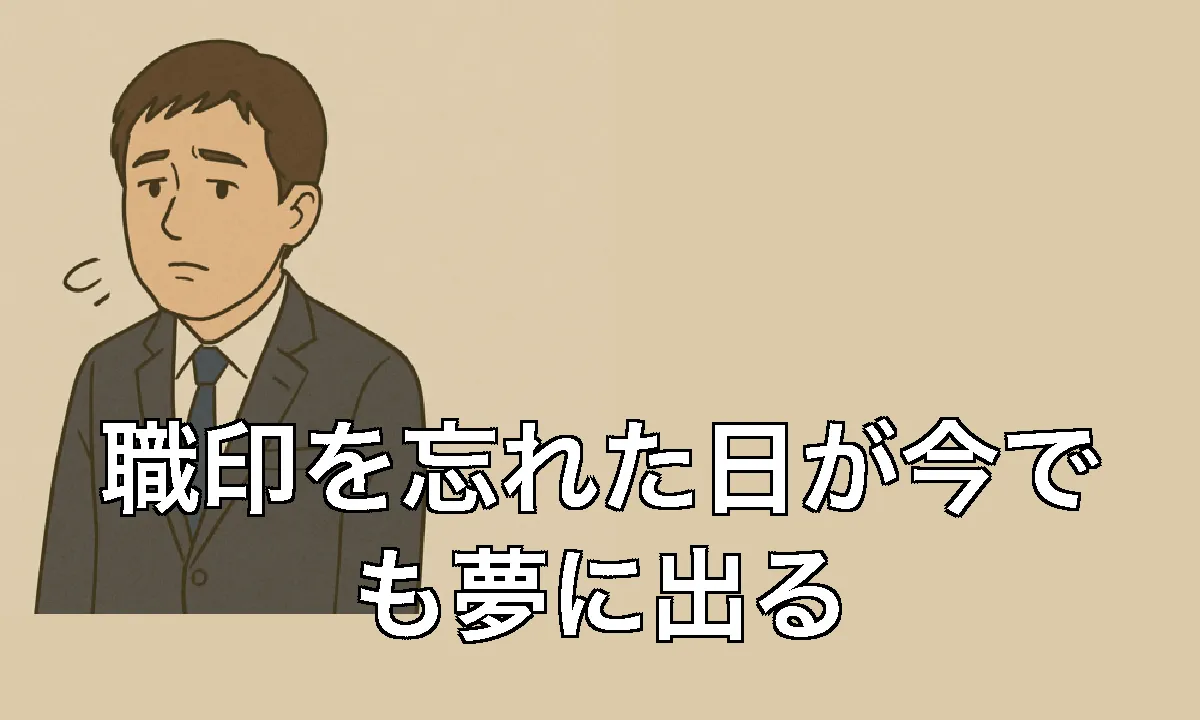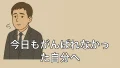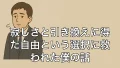朝からなんだか嫌な予感がしていた
その日は特に朝からバタついていた。いつもより寝坊したわけでもないし、朝食も普通に食べた。けれど、なぜか気持ちが落ち着かず、どこか胸がザワザワしていた。元野球部時代、試合でエラーする日も大抵こんな感じだった。イヤな予感というのは、だいたい当たる。そういう経験則を無視して慌ただしく家を出たのが、すべての始まりだった。
忙しすぎて確認すらしないまま家を出た
朝一番の案件が急ぎで、事務所に着いたらすぐに申請書をチェックして、提出しないといけない。そんな焦りからか、毎朝欠かさずやっている鞄の中身チェックをこの日に限って省略した。職印は、私たち司法書士にとって“バット”のようなもの。これがなければ試合にならない。にもかかわらず、その“バット”が鞄に入っているかどうか、確認を怠ったのだった。
事務所についた瞬間の違和感と焦り
出勤してデスクに座り、資料を並べていたときにふと違和感を覚えた。鞄の中に、あの手触りがない。いつもならファスナー越しに少しだけ硬さを感じる職印のケースが、そこにない。慌てて手を突っ込んだが、空振り。胸がぎゅっと締めつけられるような、冷や汗が背中を伝うような、あの瞬間。忘れようにも忘れられない。
職印がないとどうにもならない仕事の現実
職印を忘れると、仕事にならない。それは大げさでもなんでもない。職印がなければ、登記申請もできない。依頼人からすれば、こちらの都合など関係ない。ただ「予定通り申請されたかどうか」だけが問題なのだ。そう考えると、手の震えが止まらなかった。
登記申請書を前にして手が止まる
パソコンの画面には、提出直前の登記申請書。何度もチェックを重ね、事務員も一緒に目を通してくれた。あとは押印して、提出するだけ。なのに、職印がないだけで、すべてが止まる。まるでエンジンが壊れて発進できない車に乗っている気分だった。何もできない無力感に、ただただ呆然とするしかなかった。
何度確認しても鞄の中にはない
机の上で再度鞄をひっくり返し、ファスナーの奥まで覗き込んだ。まるで魔法のように現れてくれないかと願ったが、現実は非情だ。職印のケースはやはりどこにも見当たらない。絶望とともに、背中に汗が滲み、頭が真っ白になる。こういう時ほど、時間がやたら早く進む気がするのはなぜだろうか。
代用できるものなんてこの世にない
もしかして認印で…などと一瞬でも考えた自分が恥ずかしい。そんなことが許されるわけがない。職印は司法書士としての「信頼」を象徴するものだ。それを忘れたというのは、野球で言えばグローブを家に置いてきたようなもの。仕事としては完全に“アウト”だ。
事務員に伝えるときの気まずさと情けなさ
「…ごめん、職印忘れた」その一言を伝えるまでに、数秒の沈黙があった。事務員の彼女は驚いた顔をしたあと、苦笑いを浮かべた。責めるでもなく、呆れるでもなく。「取りに戻りますか?」と淡々と聞かれたのが、逆に胸に刺さる。やってしまった感と、情けなさが混ざって、床に沈み込みたくなった。
急いで家に取りに帰るという選択肢
こうなれば、もはや選択肢は一つしかない。片道30分、往復で1時間。車を飛ばして家に戻り、職印を手にし、また戻ってくる。時間のロスがすべての予定に影響を及ぼす。だが、それでもやるしかない。失った信用は、行動で取り返すしかない。
往復1時間のロスが予定をすべて崩壊させる
車内ではずっと時計を睨みつけていた。朝の渋滞に引っかかりながら、時間だけが無慈悲に過ぎていく。頭の中ではその後の予定がどんどん崩れていくのがわかる。午後の相談予約、電話対応、書類チェック…。すべてが狂う。職印一つで、ここまで崩壊するとは。
クライアントからの電話が心に刺さる
その日の午後、申請を急いでいた依頼人から電話が入った。「あの件、提出されましたか?」というシンプルな質問に、「はい」と即答できない自分がいた。「すみません、少しトラブルがありまして」と苦し紛れに言い訳を並べるしかなかった。罪悪感と自己嫌悪がぐるぐる回る。
信用という言葉の重さを実感する瞬間
司法書士にとって一番大事なのは「信用」だ。知識でもスピードでもなく、信用。それを損なうのは一瞬でできる。その一瞬が、まさに「職印を忘れた」という凡ミスだった。一歩間違えれば依頼人からの信頼を完全に失っていたかもしれないと思うと、今でも背筋が冷える。
忘れ物ひとつで自分の無力さを突きつけられる
この仕事は、ひとつの道具を忘れるだけで、何もできなくなる。どれだけ準備しても、最後の仕上げをする「職印」がなければ意味がない。自分の脆さや限界を突きつけられたあの日は、忘れようにも忘れられない。
独立した責任の重さを改めて痛感した日
会社勤めの頃なら、誰かがカバーしてくれたかもしれない。でも今は一人で背負っている。事務員がいても、責任を取るのは代表である自分。独立してからずっと感じてはいたが、この出来事でその重みが骨の髄まで染みた。責任って、見えないけれど、重たい。
誰も助けてくれない世界で生きるということ
結局、自分のミスは自分でなんとかするしかない。誰も助けてはくれないし、責任も取ってはくれない。そういう世界で生きるのが、この仕事なんだと改めて痛感した。独身でひとり暮らしの自分には、家庭で気持ちを切り替える場所もない。ただ、一人で立ち向かうだけだ。
昔の同僚の顔がふと浮かぶ理由
その日の帰り道、ふと昔の同僚の顔が浮かんだ。あいつなら「やっちまったな〜」と笑ってくれたかもしれない。もう連絡も取っていないけれど、こんな時だけ、妙に懐かしくなる。誰かに話を聞いてもらいたい、でもそんな相手がいない。それが今の自分の現実だ。
ミスを繰り返さないためのささやかな習慣
この経験を境に、日々の習慣を見直すようになった。小さな見直しが、大きな安心につながることを学んだからだ。ミスをゼロにはできなくても、限りなく少なくする努力ならできる。そう自分に言い聞かせている。
職印の保管場所を変えた話
まず職印の保管場所を変えた。以前は机の引き出しに入れていたが、今は毎朝必ず目にする玄関の小物棚に置いている。出かけるときに絶対に目に入る位置。これだけで忘れるリスクが大幅に減った。習慣を変えることの大切さを、あらためて実感している。
朝のチェックリストが習慣になった経緯
さらに、毎朝出勤前に確認する「チェックリスト」を手帳の表紙に貼った。スマホのリマインダーでもいいのだが、アナログな自分には紙のほうが合っている。鞄の中身、鍵、職印、申請書類…。それを一つひとつ確認することで、あの日のような取り返しのつかない失敗を防いでいる。
職印を忘れたことで得られたもの
できることなら忘れたくなかった。でも、あの失敗があったからこそ、今の自分があるのも事実だ。ミスを経験した人間にしか語れない言葉があると信じている。そして、それを発信することで、誰かが同じ思いをしないで済むなら、それもまた意味のある失敗だったのかもしれない。
ちょっとした凡ミスも誰かの役に立つかもしれない
このコラムを書こうと思ったのも、自分の凡ミスが誰かの気づきになればという思いからだ。どんなに小さな失敗でも、それが共感や防止につながるなら、決して無駄ではない。人は完璧じゃない。だからこそ、共有し、学び合えるのだと信じている。
他人のミスに優しくなれた自分がいた
あの事件以来、他人のミスに対して以前よりも寛容になった気がする。以前なら「なんでそんなこともできないの」と思っていたような場面でも、「まあ、人間だしな」と思えるようになった。それは自分が失敗して、心の底から「情けない」と思ったからこそ芽生えた感情かもしれない。
経験が言葉になるとき孤独は減る
この仕事は、ときにものすごく孤独だ。だからこそ、こうやって自分の失敗談を言葉にすることで、誰かの孤独を少しでも減らせたらと思う。自分の恥をさらすことに意味があるなら、それも悪くない。失敗を語れる人は、強い。そう自分に言い聞かせながら、この文章を締めくくる。