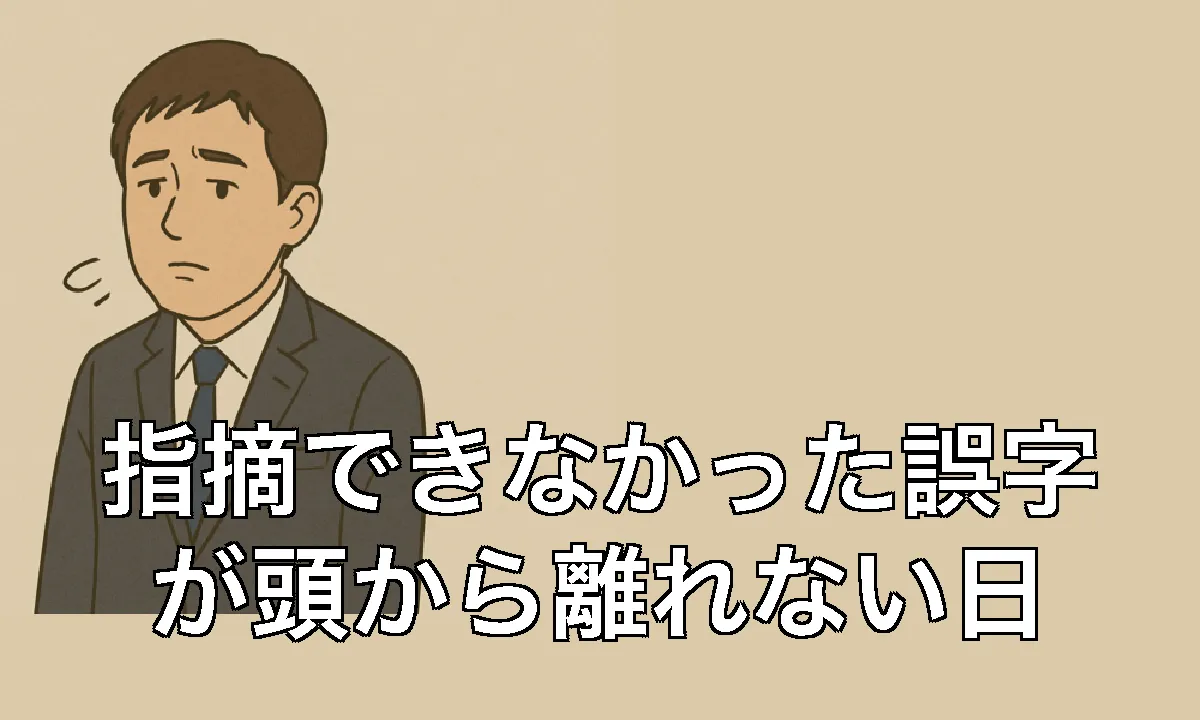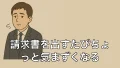公証役場での静かな違和感
先日、公証役場で定款認証の立会いをしたときのことだ。お客さんとの打ち合わせも順調に進み、あとは署名押印を残すだけという段階で、ふと目に入った一文字に違和感を覚えた。確信はなかったが、明らかに誤字だと思える箇所。しかしその場で「ここ違ってませんか?」と言い出せなかった。周囲はみな淡々と進めている中で、私ひとりだけが時間を止めるような行動をする勇気がなかったのだ。
文字の違いに気づいた瞬間
「株式会社」の「社」の字が、旧字体のまま使われていた。それだけなら大したことではないと思われるかもしれないが、相手は行政書士、相手先は上場を目指す企業。書類の一点ミスが全体の印象を損なう可能性はある。私の中で警鐘が鳴ったが、なぜかその警鐘を無視してしまった。きっと「空気を壊したくない」という気持ちが勝ったのだ。冷静になれば、「ここ、念のためご確認を」と軽く言えば済む話だったのに。
それでも声が出なかった理由
私は昔からそういうところがある。中学の野球部でも、明らかに監督がサインを見逃していた場面があっても、誰も指摘できずに見送った。あのときの試合も、モヤモヤしたまま終わった。おそらく私の中には「波風を立てたくない」「相手に恥をかかせたくない」という感情が強すぎるのだろう。だがそれが結果的に、誰かを困らせたり損をさせている可能性があると思うと、胸が苦しくなる。
緊張と遠慮が入り混じる時間
あの場には、公証人の先生も、顧客の担当者も、全員がプロとして振る舞っていた。その空気感の中で、「一介の司法書士」が割り込むことへの抵抗感があった。しかも、もし私の指摘が誤っていたら…という不安もあった。たった一文字が、私の中でどれほどの葛藤を生んでいたか、今でも思い出すとため息が出る。その時間はわずか数十秒だったが、心の中では何時間も格闘していたような気分だった。
誤記を放置した代償
結局、誰も気づかぬまま手続きは終わった。そして数日後、その会社から「訂正が必要になりました」と連絡が入った。胸がズキンと痛んだ。あのとき私が一言でも声を出していれば、誰かが救われていたかもしれない。もちろん私一人の責任ではない。でも、あの瞬間に気づいていた人間が他にいたかと言えば、おそらく私だけだった。だからこそ、責任の重さがのしかかる。
相談者の信頼を裏切ったような気がして
お客さんからの言葉はやさしかった。「ミスは仕方ないですから」と。でもそのやさしさがまた苦しい。自分が「大丈夫です」と背中を押したはずなのに、実は落とし穴があったわけで、それを見て見ぬふりしていた自分が情けない。信頼とは、見えないところで守るものだと、改めて実感した。私がもし相談者の立場だったら、きっと「なんで言ってくれなかったんですか?」と心の中で叫んでいただろう。
修正依頼ができない書類の重み
公証人が認証した定款は、簡単にはやり直せない。内容によっては全ての手続きが一からになってしまう場合もある。それだけに、一発勝負のような緊張感がある。だからこそ、確認の一瞬がどれほど重要か、身に染みてわかった。しかも、その確認作業は司法書士である自分の目にかかっているという責任の重み。誤記を見逃すということは、目を閉じてサインしているのと変わらないのだ。
自分を責める夜の独り言
その夜、自宅に戻ってから何度もため息をついた。テレビの音も入ってこない。ビールを飲んでも、心のモヤモヤは晴れない。誰かに話せる話でもないし、話したところで「言えばよかったのに」で終わるだろう。わかっている。でも、それができなかったから苦しんでいるんだよ。そんなことを自問自答しながら、結局、深夜まで眠れなかった。
誰にも言えずにくすぶる後悔
この仕事は孤独だ。誰かに「ねえ、これってどう思う?」と気軽に聞けるわけでもないし、ましてや事務員にこんな愚痴をこぼすわけにもいかない。周囲から見れば、小さなミスかもしれない。でも自分にとっては、「声を上げる勇気」が試された重要な場面だった。あのときの沈黙は、単なる怠慢ではなく、怖さと遠慮と自信のなさの集まりだった。それがいまだに胸の奥で燻っている。
頭の中で繰り返されるあのとき言えば
人間の記憶というのは本当に厄介だ。なぜか、言わなかった瞬間だけがやけに鮮明に残る。「あの一言さえ言っていれば」という後悔は、何度もリピート再生される。しかも深夜に限って。時計の針が2時を回る頃、決まってその場面が頭に浮かぶ。どこかの書類棚を開けたとき、似たような漢字を見るだけで、ふと心臓がドクンと鳴る。これはもう、一種のトラウマかもしれない。
酒を飲んでも消えない自責の念
昔は落ち込んだら飲んで忘れるタイプだった。でもこの仕事を始めてからというもの、酒は「忘れるため」じゃなく「ごまかすため」にしかならなくなった。自分をごまかしても、次の日の朝には必ず現実が待っている。頭痛と一緒に。「司法書士」という肩書きが、軽くなることはない。むしろ年々、重さが増している気がする。その重さに潰されそうな夜も、正直、一度や二度ではない。
司法書士という肩書の責任
「司法書士って何する人?」と聞かれたとき、最近は言葉に詰まることがある。登記の専門家、法律の手続きの橋渡し…そんな定義はある。でも本質は「見えない責任を背負う仕事」だと思う。誰にも気づかれないような小さなところに目を配り、誰にも文句を言われないように手続きを完了させる。ミスをしてはいけないのはミスを見逃してもいけない。それがどれだけ神経を使うことか。
一文字の見逃しが仕事の信用を削る
誤字ひとつで司法書士の信用がガタ落ちすることもある。実際、今回の一件で「次もこの人に頼もう」と思ってもらえたかどうか、自信がない。逆に「やっぱり司法書士って…」という不信感を与えたかもしれない。だからこそ、たった一文字でも見逃してはいけなかった。文字の裏には意味があるし、誤記の影には失望がある。プロとして、それを防げなかった自分を恥じるしかない。
信用は積み上げよりも崩れやすい
信用というのは、積み上げるのに時間がかかるくせに、崩れるのは一瞬だ。何年もかけて築いてきた信頼関係も、たった一度の「見逃し」で崩壊しかねない。それがこの仕事の怖さでもある。でも怖がってばかりでは務まらない。だからこそ、日々の緊張感は切らしてはいけない。自分の心に油断の隙間を作らないように、常に自戒しなければならないのだ。
プロとしての矜持とは何か
私は司法書士である前に、一人の人間だ。完璧ではない。でも、それでもなお「ミスを減らす努力」「声を出す勇気」を持たなければならないと思う。それがプロの矜持というものではないか。間違っていたら謝ればいい。でも、何も言わずに見逃すことだけは、もう二度としたくない。あの一文字が、私にそう教えてくれた。だから今日もまた、目を凝らして書類に向かっている。