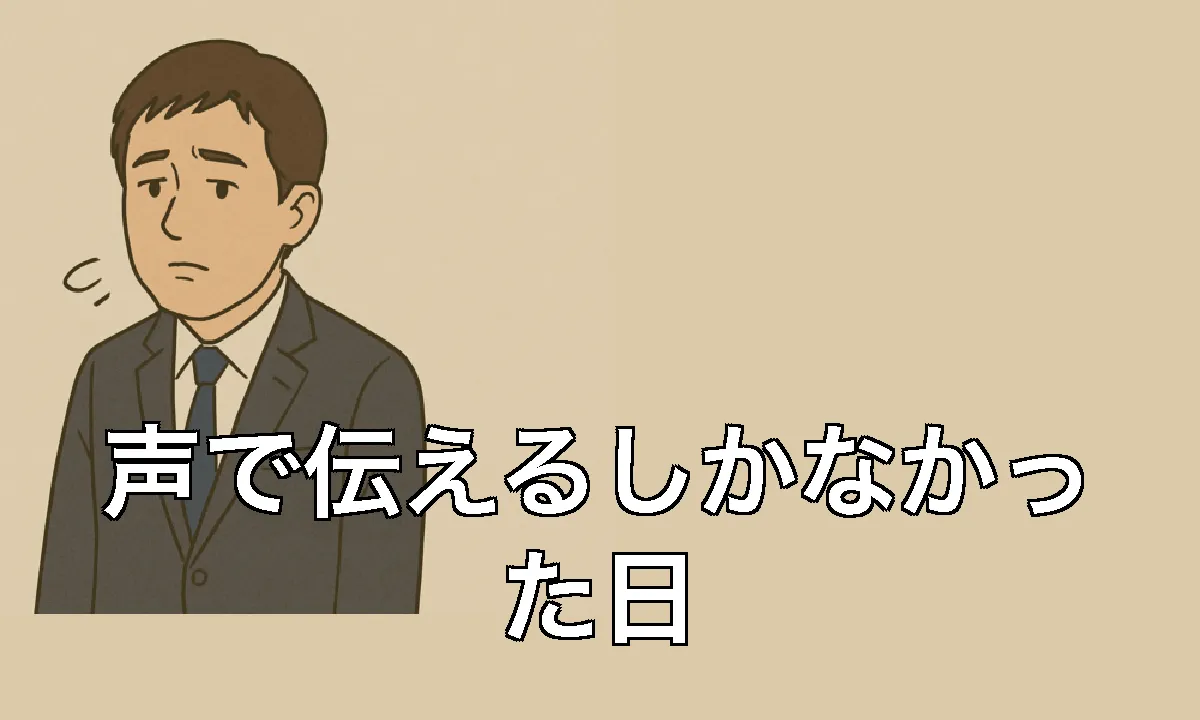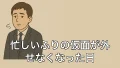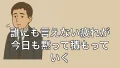言葉ではなく声で伝わることもある
司法書士という職業は、基本的に書面や契約書、登記簿といった「文字」で仕事が進んでいく。だが、実際のところ、依頼者とのやりとりの中では、書類では伝えきれない思いや空気が存在している。そんな時、最後に頼れるのは自分の「声」だと感じることがある。特に、相手が不安や悲しみを抱えている場面では、たった一言のトーンが信頼にも不信にも変わりうる。私自身、その境界線を何度も踏み越えてきた経験がある。
書類では足りない温度
ある日、遺産分割協議のために訪れた年配の女性がいた。彼女は兄弟との関係が複雑で、話の途中で何度も言葉に詰まっていた。私は必要事項を淡々と説明していたが、ふとした瞬間、彼女が涙をこぼした。その時、「大丈夫ですよ」と私が声をかけたのだが、それは台本のような言葉ではなかった。声のトーンに込めた共感と気遣いが、彼女の表情を少しだけ和らげたのを感じた。書面では到底届かない、そんな場面だった。
登記簿謄本には載らない思い
登記手続きは、感情を排した正確さが求められる。だがその裏には、家族の歴史や葛藤、そして時には怒りや悲しみがある。ある依頼者は、相続手続きのために訪れたが、明らかに話したくない事情を抱えていた。形式的な説明をしても心は開かれない。だからこそ、声に少し柔らかさを加え、「無理にお話いただかなくても大丈夫ですよ」と伝えることで、相手が少しだけ安心したように見えた。声の持つ力を再認識した瞬間だった。
依頼者の沈黙に返す一言の重さ
沈黙が流れる場面は少なくない。特に相談者が何かを決断しようとしている時、その沈黙は重く、苦しい。私は焦って言葉を挟みそうになるのだが、昔、ある先輩に「その沈黙に耐えることも、仕事のうちだ」と言われた。沈黙に耐え、相手の呼吸を感じて、やっと「よく考えられましたね」と声をかけたとき、依頼者は少しだけうなずいた。言葉ではなく、声のトーンに込めた理解が、確かに伝わった瞬間だった。
説明だけでは伝わらない葛藤
契約や登記は、事実を積み上げていく作業だが、その過程にある感情や迷いまでは、説明だけでは届かない。とくに初対面の依頼者との距離感は難しく、「これは業務として」「これは人として」の切り分けが問われる。その分、水面下で伝えようとする「声」の役割は大きくなる。うまくいけば信頼に、失敗すれば拒絶に。私は何度もその瀬戸際に立たされてきた。
「大丈夫ですよ」に込めた本音と建前
軽々しく「大丈夫ですよ」と言うことが怖い時がある。特に、自分の中でまだ処理しきれていない案件や、想定外のトラブルに直面しているとき。ある依頼者が不安そうに書類を見つめていたとき、私が「大丈夫ですよ」と言った。その声が自分の耳にも頼りなく響いた。結局その案件は無事終わったが、自分の声に責任を持てるかどうか、ずっと胸に残った。声のトーンは、そのときの自分の覚悟の表れでもある。
丁寧すぎる声がかえって傷をえぐることもある
丁寧に話そうとして、かえって距離を感じさせてしまうことがある。とある依頼者が、離婚後の財産分与の件で相談に来た。私なりに誠意を込めたつもりで話していたが、途中で相手が「もっと普通に話してくれていいです」と言った。そのとき、自分の声が“よそよそしく聞こえていた”と気づいた。言葉選びやマナーだけではなく、自分の人間味が声に表れていたか。あの一言は今でも忘れられない。
電話越しに伝えられる限界
顔が見えない電話では、声のトーンがすべてを決める。特に説明内容が複雑なときや、相手が高齢の方だったりすると、こちらの声が頼りになる唯一の情報になる。そんな場面で、無意識に声を張ってしまい、逆に相手を萎縮させてしまったこともある。声が武器であると同時に、刃にもなりうる。そこをコントロールするのは簡単じゃない。
顔が見えないからこその声の工夫
電話では、相手の表情も身振りもわからない。だからこそ、言葉を選ぶ以上に、声のトーンやテンポを意識する必要がある。私は電話を取るとき、あえて一呼吸おいてから名乗るようにしている。相手の第一印象を決めるのは、その最初の声だと考えているからだ。昔、電話口で「声が落ち着いていて安心した」と言われたことがある。それが励みになって、今もその癖は続いている。
自分の不機嫌を隠す術としての声
忙しい日や、トラブル続きのとき、声にその苛立ちが滲んでしまうことがある。だがそれを表に出すわけにはいかない。私はそんな時、意識して低めのトーンでゆっくり話すようにしている。心は荒れていても、声だけでも穏やかでいようとするのだ。ある時、そんなふうに電話を終えたあと、事務員に「先生、今日はちょっと優しすぎて気持ち悪かったです」と言われた。バレてるじゃないかと思いつつも、ちょっと救われた気がした。
相手の心を読み取るヒントは間にある
声と声の間、つまり“間”こそが、相手の気持ちを知る大きな手がかりだと思っている。ある依頼者が、登記の相談をしていたが、話の途中で微妙な間が続いた。私は焦って説明を進めようとしたが、その間に含まれた「迷い」や「不安」に気づけなかった。後日、別件で同じ方から連絡があったとき、「前より話しやすくなった」と言われた。前回の“間”を反省し、今回はあえて沈黙を受け止めた結果だった。学びは、いつも失敗のあとにやってくる。
怒りを沈める声 落ち込む声
怒鳴られる電話もある。理不尽なクレームもある。そんなとき、つい売り言葉に買い言葉で応じたくなるが、それでは余計にこじれるだけ。そんなこと、わかっている。でもこっちだって人間だ。とはいえ、声のトーンを抑えることでしか、事態を収める術はない。
お叱りの電話対応に必要な防御力
相手の怒りに真正面からぶつかっても、こちらが傷つくだけだ。私は自分の中で「相手は怒っているのではなく、困っている」と言い聞かせて声を発するようにしている。「ご指摘ありがとうございます」と言う声の中に、なるべく平常心を込める。でも、やっぱり後から一人になったとき、ふっと落ち込むこともある。声で守れるのは、相手だけじゃなく、時に自分自身でもあるのだ。
一呼吸で雰囲気が変わることがある
ある電話で、最初は険悪なムードだったが、こちらが一拍おいて「すみません、確認しますね」と落ち着いた声で返した瞬間、相手の声も少しトーンが和らいだ。言葉の内容は変わらなくても、声の出し方ひとつで空気は変わる。これは魔法ではない。けれど、長年やってきた経験の中で、ようやく身についた“呼吸の技術”かもしれない。若いころの自分では到底できなかったことだ。
事務所の中の声 外の声
外に向ける声と、事務所の中での声は、実は違う。依頼者対応では張りつめていた声が、事務員との会話では気が抜けたように出る。それはたぶん、私が独身で、誰にも甘えられない分、仕事場で少し気を緩めている証なのかもしれない。
事務員との会話が救いになった日
朝からトラブル続きで、怒鳴られ、書類の不備に焦り、正直、もう帰りたいと思っていた日。ふとしたタイミングで事務員が「先生、お昼まだですよね?」と声をかけてくれた。その声が優しくて、それだけで涙が出そうになった。人間、声だけで救われることもあるのだ。
愚痴を聞いてくれるだけで違う
「また怒鳴られたよ」とぼやくと、「でも先生、だいぶ声落ち着いてましたよ」と返してくれる。そんな事務員の一言が、どれほどの慰めになるか。うちは小さな事務所で、彼女一人しかいない。でも、彼女の声があるから、なんとか今日もやれている。
ちょっとした「おつかれさま」の力
夕方、事務所の電気を消す前に聞こえる「先生、おつかれさまでした」の声。それが、今日の終わりを教えてくれる。疲れてても、報われたような気になる。声には、区切りをつけてくれる力もあると感じる。
元野球部としての声の張りと空回り
若いころ、声を張ることが美徳だと思っていた。挨拶は大きく、返事は力強く。元野球部の習性が抜けない。でも、司法書士になってからは、それが時に空回りすることも多い。声の大きさと、相手の安心は必ずしも一致しない。
元気さが通じないことへの虚しさ
ある依頼者に、いつものように明るく挨拶したら「そんな元気出されても困ります」と言われたことがある。まさかの反応に、言葉を失った。その時、声のボリュームではなく“調子”や“空気”を読む力が大事なんだと、痛感した。
「声が大きいだけ」と言われたことの傷
昔、別の士業の先生に言われた。「稲垣さんは声が大きいだけで、内容が入ってこないよ」。ショックだった。でもその言葉が、声に気を配るようになったきっかけでもある。今でも時々思い出して、声の出し方を反省する。