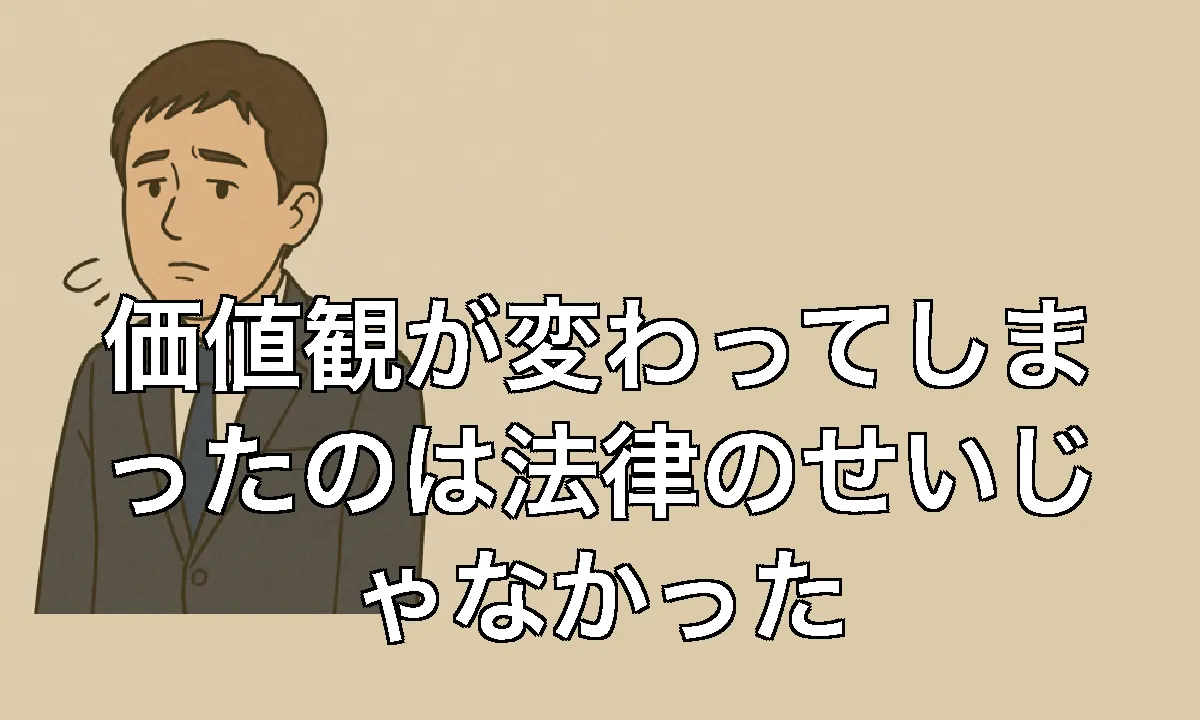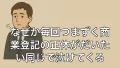価値観が変わってしまったのは法律のせいじゃなかった
あの法改正を聞いても心が動かなかった自分に驚いた
「また変わったのか」――そんなふうに、事務所で法改正のニュースを見たとき、思わず心の中でつぶやいた。昔なら、どこがどう変わったのか、どの依頼に影響が出そうか、すぐに資料をあたって動いていた。でも今回は違った。関係ある分野だとわかっているのに、手が止まらなかった。これは、仕事に慣れたとかそういう話じゃない。自分の中で何かが変わってしまっていた。
昔ならもっと反応していたはずなのに
開業して十数年、法改正のたびに「これはチャンスだ」と前向きに捉えていた時期があった。何より早く情報を仕入れて、事務員に説明して、依頼者にも先回りしてアドバイスする。それが当たり前だったし、誇りでもあった。でも、今はその熱がない。年齢のせいか、心がついてこないのか。昔の自分が今の自分を見たら、情けないと思うかもしれない。でも、それが正直な今の姿だ。
法改正を追うのが当たり前だったあの頃
開業当初は、法改正のたびに専門誌を買い漁り、セミナーにも足繁く通った。地方にいる自分にとっては、情報格差が致命的にならないように、必死だった。だからこそ、ちょっとした改正でも「これはこう使える」「この分野を打ち出そう」と目を輝かせていた。でも今は、その原動力がどこかへ行ってしまった。自分でもそれが寂しいと感じる。
今は改正を前にしてもどこか他人事のよう
今回の法改正も、もちろん把握はした。でも、どこか遠くのことのようだった。まるで、自分には関係のない国のニュースを見ているような感覚。一応チェックはしたし、事務員にも話はしたけれど、かつてのような「動かなきゃ」という焦りはなかった。その冷めた自分が、逆に怖かった。司法書士としての感覚が鈍っているのか、それとも価値観そのものが変わってしまったのか。
実は少しずつ価値観が変わってきたことに気づいていた
よくよく思い返してみれば、自分の中で変化は少しずつ始まっていた。何かきっかけがあったわけではない。ただ、日々の業務や人との関わり、依頼者とのやりとりの中で、少しずつ、自分の考え方がズレてきた。昔の自分が正しいと思っていたことに、今は違和感を感じる。変わったのは社会じゃなくて、自分だったのかもしれない。
法の動きよりも大きかった身の回りの変化
この数年、地方の司法書士としての役割も少しずつ変わってきた。昔は「先生」と呼ばれたが、今はむしろ「サービス業」としての側面が強くなっている。相談者もネットで調べてから来るし、感情的なケアが求められる場面も多い。そんな中で、自分の対応も徐々に変わってきた。法律だけを武器にしていた頃とは違い、人との距離の取り方や、気持ちの扱い方に重きを置くようになっていた。
若手の感覚に引っ張られているのかもしれない
最近よく思うのは、若い世代の司法書士や、うちの事務員の感覚の柔らかさに感化されている自分がいるということだ。SNSで軽やかに発信している若手や、「それって今どきじゃないですよ」と指摘してくれる事務員の言葉に、内心グサッとくることが増えた。頑固だった自分が、少しずつ「まあ、そういう考えもあるよな」と受け入れるようになったのは、年齢のせいだけではない気がしている。
事務員との何気ない会話が刺さった日
ある日、事務員に「先生って、もっと人の話聞くタイプだと思ってました」と言われた。たぶん本人は何気なく言ったのだろうが、グサッときた。忙しさにかまけて、相談者の話をさばくようになっていた自分に気づいた。それ以来、依頼内容よりも相手の表情を見るようになった。効率よりも「ちゃんと話すこと」に重点を置くようになった。それもまた、価値観の変化だった。
地方で司法書士を続ける中でこぼれ落ちたもの
この土地で開業してもう長い。地元の人たちとも顔見知りになった。でもその分、依頼者が「先生ならわかってくれる」と過度に期待してくることもある。仕事としてはありがたいが、人としては正直しんどい。そういう中で、ふと「自分って何のためにやってるんだっけ」と立ち止まることが増えてきた。法律よりも、自分自身の感情が揺れることの方が多くなった気がする。
理想と現実のすれ違いが積もってきた
独立したときは、もっと自由で、自分の理想を貫ける仕事だと思っていた。でも現実は、手続きに追われ、急ぎの案件がどんどん入ってきて、気づけば“処理する人”になっていた。理想の「寄り添う司法書士像」はどこかへ行ってしまった。そうした積み重ねが、自分の価値観をじわじわと変えていったのかもしれない。
独身でいることの気楽さと寂しさの交差点
誰にも気を遣わずに好きなように働ける。それが独身の強みかもしれない。でも、夜遅く事務所の灯りをひとりで消すとき、ふと「これでいいのか?」という感情がわいてくる。誰かと価値観を共有できる相手がいないから、自分の中で抱え込んでしまう。そういう生活が、仕事への感じ方も変えていった気がする。
変わったのは価値観じゃなくて感情の使い方かもしれない
本当は、価値観そのものが変わったわけではないのかもしれない。ただ、どう感情を使うか、どこに重きを置くかが変わってきたのだと思う。昔は「正しいこと」が第一だった。でも今は、「それをどう伝えるか」「どう受け取ってもらうか」の方が大事になっている。それを年齢のせいと言ってしまえば簡単だが、もっと複雑な感情が絡み合っている。
誰かの正義よりも自分の感情を優先するようになった
若いころは、「司法書士としてのあるべき姿」にとらわれていた。でも今は、無理をしてまで“正義”を貫くことに意味を感じなくなった。自分が無理してやることで誰かを傷つけたり、自分が疲れきってしまうなら、それは本当に正しいことなのか?と疑問に思うようになった。感情を押し殺して仕事をするのではなく、自分の感覚を大切にしていきたい、そんなふうに思っている。
共感されなくてもいいと思い始めた理由
以前は、同業者からの評価や、依頼者の反応をとても気にしていた。でも、最近は「別に理解されなくてもいい」と思えるようになってきた。それは諦めではなく、自分を守る手段のひとつ。価値観が合う人もいれば、合わない人もいる。それでも、自分のやり方でやっていく。それが、今の自分の流儀になっている。
それでもまだ現場で続けている理由
こんなふうに変化を感じながらも、今も司法書士としてこの場所にいる。それはきっと、どこかで「まだやれる」「やる意味がある」と信じているからだ。理想と違っても、失望しても、それでも誰かの役に立てる場面がある限り、自分の足は止まらない。そういう小さな原動力が、毎日を支えている。
誰かに必要とされてる気がするときがある
全ての依頼が報われるわけじゃない。むしろ、理不尽なことも多い。でも、たまに「先生にお願いしてよかった」と言われると、それだけで救われたような気持ちになる。その瞬間だけは、自分の価値観も苦労も報われるように感じる。その一言があるから、続けられているのかもしれない。
変わった価値観とこれからの選択
これからもまた、自分の考えは少しずつ変わっていくのだろう。今の価値観が、数年後にはまた違う形になっているかもしれない。それでも、自分自身を見失わずにやっていけたら、それで十分だと思っている。完璧じゃなくていい。ぶつかりながらも、続けていければいい。そう思えるようになったのは、歳を重ねたおかげかもしれない。
野球部で培った我慢がまた顔を出す
学生時代、補欠だった自分は、ベンチで腐らず声を出し続けた。あのときの「我慢」が、いま仕事のどこかに生きている気がする。つらくても、自分の出番を信じて、黙々と準備する。司法書士としての今も、似たようなものだ。報われない時間もあるけれど、きっといつかまた自分の感覚が誰かの役に立つ。そんなふうに信じている。