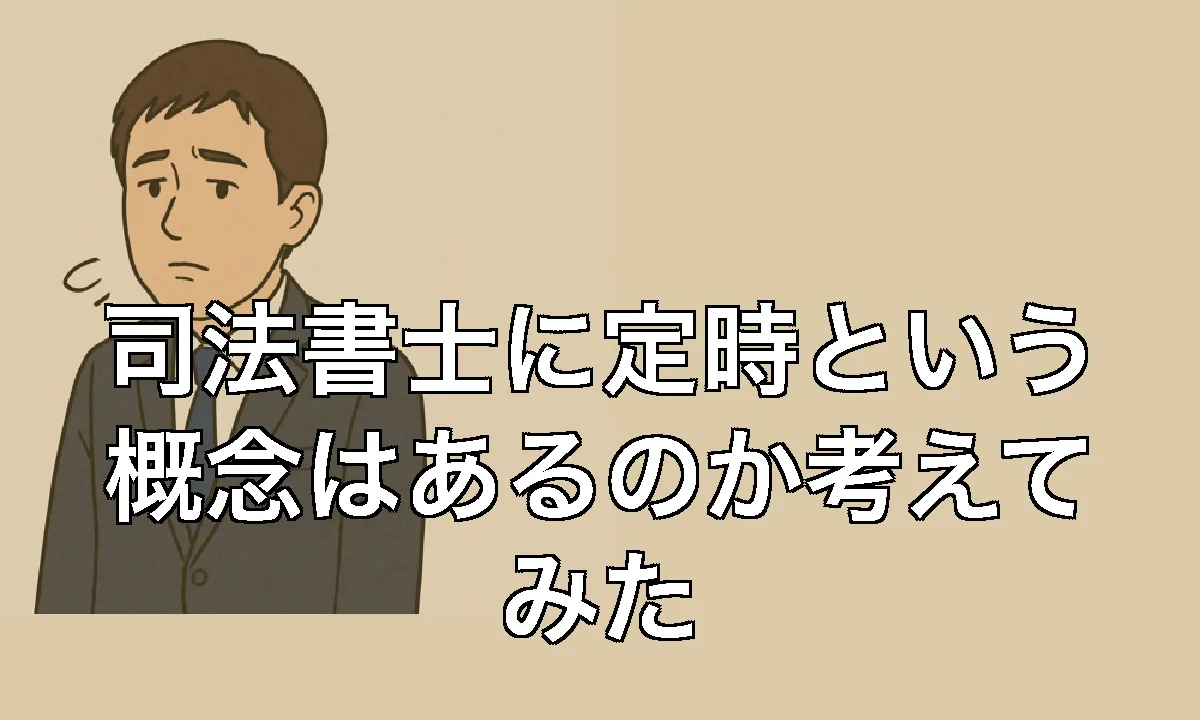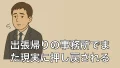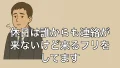定時ってそもそも何なのか
「定時」という言葉を見聞きすると、正直、別の世界の話に思えてしまう。公務員時代の友人に「今日はサクッと定時退社」とLINEで送られてきた画面を見たとき、なんだか遠い星の出来事のようだった。司法書士という仕事は、お客さんの都合と書類の流れに左右されることが多く、自分で時間を決めて仕事を切り上げるという発想がなかなか持てない。そもそも「定時」の定義すら曖昧で、朝決めた予定通りに進むことのほうが稀だ。
時計の針は見ているけど意味はない
夕方になると、一応「何時だ」とは思う。でも、それが「帰れる時間」ではないことは体がよく知っている。18時に「帰ろう」と思ったことはある。でも机の上には残っている登記簿の束、隣のプリンタがうなりを上げる。電話も18時過ぎに鳴ることが多い。そんな日常を繰り返していると、時計の針は「帰るための目安」ではなく、「終わらない業務の延長線上の飾り」にしか思えなくなるのだ。
気づけばいつも帰るのは夜
一番多いのが「今日は早く帰るつもりだったのに」というやつ。朝は「今日は定時に帰るぞ」と決意して出勤する。午前中までは順調なのだが、昼過ぎから電話が立て続けに入り、午後4時には予定がグチャグチャになっている。気づけば外は真っ暗、時計は20時半。夕飯はコンビニ弁当、誰とも話さず独りで食べる日がまた増えていく。
事務員にだけは早く帰ってもらいたい気持ち
事務員にはせめてもの気遣いとして、「今日はもう帰っていいよ」と声をかけるようにしている。でも本音を言えば、一緒に残ってほしい日もある。寂しいし、誰かと一緒に残業しているだけで救われる日もある。でも、そんなこと言えないから「先に帰っていいよ」と言って、自分は黙って机に向かう。たまに「先生、今日は遅いですね」と言ってくれるが、内心では「いつもだよ」とつぶやいている。
司法書士という仕事の性質上の限界
この仕事には「人の都合に合わせる」という宿命がつきまとう。登記の締切は急に決まるし、依頼人は「できれば早く」と言う。全部の要望に応えることは無理だが、断ったことで信頼を失うこともある。だから、多少の無理をしてでも応えようとする。これが続くと、定時なんて言葉はどこかへ吹き飛んでしまう。
書類は待ってくれない登記は止められない
登記というのは一度走り出すと止められない列車のようなものだ。書類が揃えば即座に対応しなければならず、法務局への提出期限も迫っている。特に不動産売買や相続案件では、関係者が多く、誰か一人が「今日しか無理」と言えば、それに合わせるしかない。だからこそ、夕方以降に動くことも多くなってしまう。
お客さんのスケジュールがすべての基準
たとえば会社勤めの方が「19時以降しか会えません」と言えば、それに合わせて事務所に残る。「先生が夜も対応してくれて助かります」と言われると、悪い気はしない。むしろ嬉しい。でもその積み重ねが、自分の生活リズムを壊していると気づくのは、深夜になってからだ。
急ぎの案件はなぜか夕方にやってくる
不思議なことに「急ぎなんですけど」と言われる電話は、なぜか午後5時を過ぎてから鳴る。きっと依頼人も一日仕事を終えて、やっと登記のことを思い出すのだろう。こっちは終わらせたいのに、むしろそこから始まる。そういう日は、夕方からが本番。気づけば21時。いつからこの仕事は夜型になったんだろう。
それでもやめられない理由
正直、何度も「もうやめたい」と思ったことがある。でも、ふとした瞬間に救われることがある。たとえば、書類を届けたあとに「本当に助かりました」と深々と頭を下げられたとき。そんな場面に出会うと、「ああ、この仕事やっててよかったな」と思ってしまう。そしてまた、机に戻るのだ。
たまに届くありがとうの重み
先日、あるお年寄りの方の遺産整理を手伝ったときのこと。何度も通って話を聞いて、やっと手続きが終わったとき、その方が涙ぐみながら「あなたがいてくれて本当によかった」と言ってくれた。心がじんわり温かくなった。そういう一言のために、遅くまで働いてしまうのかもしれない。
人に必要とされる感覚が唯一の救い
「誰かの役に立っている」という感覚は、何にも代えがたい。でもそれが、生活を犠牲にしてまで必要かと言われると、答えに困る。自分のことを後回しにし続けて、何年経っただろう。独りでいる夜、自分の人生についてふと考える瞬間がある。
おわりに 定時のある未来は来るのか
司法書士にとって「定時」は夢のような言葉かもしれない。でも、それを完全に諦めるのも違う気がしている。働き方改革という言葉が世の中を少しずつ変えているように、いつかこの業界にも光が差す日が来るのではと、わずかな期待を抱いている。今日もまた遅くなるけど、明日は少しだけ早く帰れることを祈って、机に向かう。