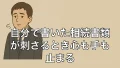気づけば20年独り身と司法書士
一人暮らしを始めたのは司法書士になる前、まだ補助者として事務所勤めをしていた頃だった。最初は「自由でいいじゃないか」と思っていたが、気づけばもう20年。独身で、地方の片隅で事務所をひとつ構え、事務員さんと二人三脚。仕事があるのはありがたいけれど、日常に誰かのぬくもりがないというのは、年々ずしりとくる。独り身と司法書士、どちらが先だったかもわからないくらいに、自分にとっては当たり前になってしまった。これが「慣れ」というやつかもしれないが、正直なところ、寂しさと紙一重だ。
最初は「気楽」だったひとり暮らし
20代の頃、アパートに引っ越して最初に感じたのは「誰にも干渉されない自由」だった。食事は好きなものを、掃除も自分の気が向いたときだけでいい。誰かに「早く寝ろ」と言われることもなければ、夜中にラジオを聴いていても文句を言われない。最初はそれが快適で、これが大人の暮らしだと浮かれていた。でも、そんな自由は、数年経つと「孤独」と紙一重だと気づく。夕飯を作るのが面倒で、コンビニ弁当を食べながら、テレビを眺めている自分。あれ?ってふと思う瞬間が、積もり積もって、今がある。
事務所開業が孤独感を押し上げた
自分の事務所を構えたのは、ひとり暮らしを始めて5年目くらいだった。地域の人との関わりも増えたし、ありがたいことに仕事はあった。ただ、仕事が終わって帰っても、迎えてくれる人はいない。事務所という小さな「社会」を手に入れた代わりに、私生活の人間関係はどんどん狭くなったように思う。責任も増え、時間もなくなり、「婚活」なんて言葉は遠い世界の話になっていた。いつのまにか、仕事を言い訳に、孤独を正当化している自分がいた。
元野球部だった自分が机に向かう毎日
高校時代はバリバリの野球部。土にまみれて、声を張り上げて、仲間と汗を流していた。グラウンドでは、誰かが常にそばにいて、自分の存在を認識してくれていた。あの頃の自分が、いま机に向かって、静まり返った部屋で書類とにらめっこしている姿を見たら、どう思うだろうか。あの頃の喧騒が、今ではたまに恋しくなる。たぶん、自分はあの「音」の中に安心していたんだと思う。今はその「音」が、ほとんどない。
グラウンドの喧騒と比べてしまう日々
事務所では、パソコンのタイピング音とプリンターの駆動音だけが鳴る。電話のベルすら、最近は少なくなった。ふと、昔のグラウンドを思い出す。声が飛び交い、ボールがミットに収まる音、バットが風を切る音。あの音たちは、自分に「ここにいていい」と言ってくれていた気がする。今、自分の居場所は間違いなくこの事務所なんだけど、「誰かと作っている場所」ではなく、「自分が守る場所」になってしまっている。責任の重さだけが積もっていく。
「誰とも話さない日」が普通になった
忙しい日々の中、気づけば「今日は誰とも話していないな」という日が珍しくなくなった。特に事務員さんが休みの日などは、朝から晩まで一言も声を発しないこともある。電話も来客もない日は、本当に無音の世界で一日が過ぎていく。声を出すのは、家で独り言をつぶやくときくらい。それが妙に悲しい。人間って、こんなにも「音」に救われていたんだなと実感する。
事務員さんが休みの日の静寂の重み
普段は無口な事務員さんだけれど、いてくれるだけで全然違う。書類の受け渡し、ちょっとした確認の声掛け、電話応対の返事。そんなささやかな「音」があるだけで、孤独感はずいぶん和らぐ。けれど、その人が休みだと、事務所はまるで倉庫のように静まり返る。ラジオをつけても虚しくて、かえって無音に戻してしまう自分がいる。その静けさが、ひとりでいることの現実を突きつけてくる。
コンビニの「温めますか」が唯一の会話
ある日、ふと気づいた。「今日、声をかけてくれたのは、コンビニの店員さんだけだ」と。レジでお弁当を出したときの「温めますか?」の一言が、その日いちばん人間味を感じた瞬間だった。人と接する機会があまりにも少ないと、こんなやり取りにさえ感謝したくなる。だからこそ、あいさつや返事をきちんとするようになった。誰かに優しくされると、それが何倍にも心に染みるのが、一人暮らしという生活だ。
女性にモテないという現実
「士業ってモテるんでしょ?」と何度か言われたことがある。でも、現実は違う。特に地方の司法書士、しかも40代半ばで独身で、という条件がそろうと、もう“結婚対象”には見られない気がしている。若い頃ならまだしも、今は仕事が優先されがちで、出会いの場に行く気力もない。結局、「モテなかった」というより「出会いに向き合わなかった」結果なのかもしれないけれど、それを言い訳にしている自分が一番わかっている。
士業ってそんなに魅力ありますか
確かに、司法書士という肩書きには一瞬「へぇ」と反応されることもある。でもそこまで。お金持ちそうとか、頭よさそうとか、そんなイメージが先行しても、実際の生活は「地味で孤独」。仕事が終わって、疲れ果てた顔で帰る中年男性に、誰がときめくだろうか。魅力って、肩書きではなくて“生き方”に出るものだと思う。そういう意味では、自分にはまだまだ伸びしろがある…と自分に言い聞かせて、今日も仕事に向かう。
「安心して任せられる」と「恋愛対象外」の境界線
依頼者の女性に「先生みたいな人、安心できます」と言われたことがある。その時、ありがたい反面、どこかで「それ、恋愛対象にはなれないってことだよな」と思ってしまった。真面目で優しい、でも恋愛には発展しない…そんな立ち位置に、自分はいるのかもしれない。責任感と誠実さを武器にしてきた結果、恋愛という戦場では丸腰だった、そんな気がする。悲しいけれど、それも自分の選んだ道なんだ。
「愚痴れる場所」がなくてここに書いてます
気を抜いたらため息しか出てこないような日もある。でも、誰かに弱音を吐くわけにもいかず、ましてや家に帰っても聞いてくれる人はいない。だからこうして、コラムとして愚痴を書いている。誰かの役に立つかもしれないし、少なくとも「わかる」と思ってくれる人がいれば、自分も少し救われる。独り言のような文章かもしれないが、同じような日々を送っている誰かと、どこかでつながっていればいいなと願っている。