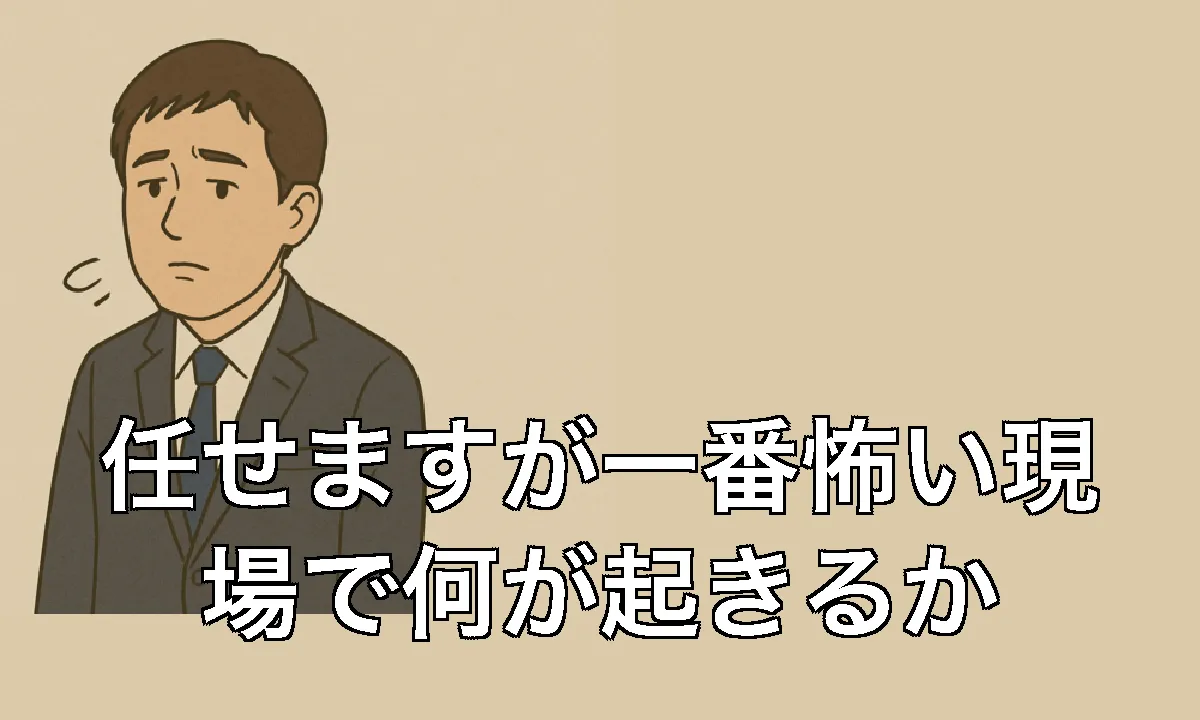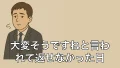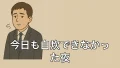なぜ「任せます」が怖いのか
「任せます」という一言には、信頼の意味があると同時に、無関心や責任放棄の裏返しであることも少なくありません。司法書士として長年やってきて思うのは、この言葉の裏にある曖昧さが、後々のトラブルの火種になりやすいということです。特に、登記業務のように細かい内容確認が必要な仕事において、「全部任せる」という態度は、むしろ恐怖すら感じます。人が関与する限り、完全な任せっぱなしで完璧な成果などあり得ないのです。
言葉の裏にある無関心と責任放棄
「任せます」と言う人の中には、プロを信頼してくれているから、という好意的なケースももちろんあります。でも実際のところ、関心がない、面倒くさい、あるいは自分の責任にしたくない、という動機が見え隠れすることが多いのも事実です。あるとき、相続登記の相談で「全部任せるから」とだけ言って帰った依頼者がいました。ところが、登記完了後に「こんな内容だとは思わなかった」とクレームが入り、結局、手戻り作業で事務所も私も大混乱。任せると言ったんだから、最後まで任せてほしい。そういう気持ちになります。
任された側の見えないプレッシャー
「任せます」と言われると、一見すると信頼されているようで、実は強烈なプレッシャーも伴います。特に司法書士は、依頼者との信頼関係のうえで成り立つ仕事ですから、期待を裏切れないという気持ちが常にあります。でもその一方で、具体的な希望や条件を聞き出さなければ、地雷を踏むリスクが常にあるのです。まるで、サインのない契約書に実印を押せと言われているようなもの。責任だけがのしかかり、判断に迷うたびに胃がキリキリ痛みます。
実際にあった怖い「任せます」事件簿
私の事務所でも、「任せます」から始まったトラブルは一度や二度ではありません。言った本人は軽く言ったつもりでも、こちらとしては命綱を渡されたようなもの。言葉は軽くても、責任は重くのしかかってくるのです。特に、登記や遺産分割に関わる案件では、一言の重さが結果に大きく影響します。ここでは、実際にあった事例を2つご紹介します。
登記内容を一切確認しない依頼人
あるとき、土地の名義変更で来た依頼人がいました。高齢の方で「もうよく分からんから任せる」とおっしゃって、詳細を一切確認せずに印鑑だけ預けていかれたのです。そのときはスムーズに終わったと思っていたのですが、後日、家族から「なぜ父の名義だけにしたのか」と怒りの電話が。こちらとしては言われた通りに手続きをしただけ。しかし、家族内での合意ができていなかったようで、板挟みになってしまいました。確認の手間を省かず、粘ってでも状況を聞き出すべきだったと反省しました。
「プロに任せます」からのクレーム地獄
もう一つは、会社設立の登記依頼を受けたときの話。「おたくが専門でしょ?全部任せるよ」と言われ、最低限の質問に答えてもらっただけで進めたのですが、登記が完了してから「役員報酬がゼロってどういうこと?」「会社の目的が違う!」と怒鳴り込まれました。正直なところ、書式上の確認書を出したり、電話で説明したりはしていたのですが、「全部任せたのに」という言葉で一蹴。その後の修正手続きは当然無償対応です。プロという言葉の裏に潜む責任の重みを痛感しました。
事務員に丸投げしてミスが発覚
少人数の事務所では、事務員との連携も生命線です。以前、登記簿の写し取得を依頼された案件で、忙しかった私は「そのへん、○○さん(事務員)に任せておいて」と軽く言ってしまいました。結果、申請書に一部ミスがあり、補正通知が届く事態に。もちろん最終的なチェックは私の責任ですが、「任せる」の一言が、油断や確認漏れを生みました。事務員を責めるわけにもいかず、内心では自己嫌悪の嵐でした。
元野球部でもカバーできない連携ミス
学生時代は野球部で、サインプレーや声掛けで勝負を決めてきました。そんな経験からか、チームワークには人一倍気を使っているつもりでした。しかし、現実は違いました。事務仕事は、野球のような感覚では通じない細かさと集中力が求められます。「ちょっと任せた」は、「ミスっても仕方ないよね」という空気を生んでしまう。今でもあの補正通知を見ると、キャッチャーのサインを無視して三振したような、後悔がよみがえります。
小さな“任せます”が招く大きなトラブル
「任せます」は一見、仕事がやりやすくなる魔法の言葉のように見えますが、その実、判断の逃げ道を奪う危険な言葉でもあります。小さな確認不足や意思疎通のすれ違いが、積み重なって大きなトラブルになることも。あのとき一言聞いておけば、と思うことが後を絶ちません。
関係者全員が責任を取らなくなる
「任せた」と言われた側は「言われた通りにやった」と言い、言った側は「説明がなかった」と言う。そんなやりとりが続くうちに、誰も本当の意味で責任を取らなくなる空気が生まれます。書類にサインするだけの仕事ではないはずなのに、まるで誰かの“作業代行”のような立場に追いやられる。司法書士の仕事の本質が、そこではどんどん薄れていってしまう気がします。
書士会の調整役も地味につらい
こうしたトラブルが表面化すると、書士会からも「きちんと説明したか?」と確認されることがあります。説明したつもりでも、相手に伝わっていなければ意味がない。説明不足だとされれば、注意や指導対象になることも。現場の苦労や事情は、なかなか汲んでもらえません。調整役として謝罪したこともありますが、内心は「任せるって言ったじゃないか…」と、やりきれなさでいっぱいでした。
任される側の本音と限界
「信頼してるから任せます」なんて言われると、こっちは悪い気はしません。でもその信頼の裏に、責任の重圧や、プレッシャーが付きまとう。特に一人で多くの案件を抱えていると、判断のたびに「これでいいのか」と自問する日々が続きます。頼られるのはありがたいけれど、頼られすぎるのも辛いというのが正直な本音です。
「プロなんだから当たり前」の一言に疲れる
「それがプロでしょ」「お金払ってるんだから当然」——そんな言葉をさらっと言われることもあります。でも、プロだって人間です。判断材料が足りない状態で進めることはリスクが高すぎます。それでも結果を出さなきゃいけないというのは、まるでブラインドで打席に立たされているような感覚。野球なら三振すれば済みますが、司法書士のミスは依頼者の人生に関わることもある。だからこそ、気軽な「任せます」は、こちらの心をすり減らすのです。
無言の圧と“察して”の空気
地方の事務所では、あえて細かく言わない“察して文化”も根強く残っています。「言わなくてもわかるでしょ」「そっちで判断して」みたいな空気が漂うこともあり、その読み合いに疲弊することもあります。かといって強く主張すれば「融通が利かない」と言われる。結局、板挟みの中でひとり気を張り続ける日々が続き、時々ふと「何やってるんだろう」と思う瞬間があるのです。
どうすれば“怖い任せます”を避けられるか
「任せます」の一言を減らすことはできなくても、それを怖い言葉にしない工夫はできます。大切なのは、依頼者との対話を諦めないこと。そして、事務所の中でも同じ意識で動けるようにすること。私自身、何度も失敗を繰り返しながら、少しずつですが、任され方を工夫するようになりました。
最低限の確認事項を共有する習慣
依頼者には、最初に必ず「確認してほしいことリスト」を渡すようにしています。「任せる」と言われても、最低限の意思表示はしてもらう。そのひと手間があるだけで、後々のトラブルがかなり減ります。書類の内容に印をつけてもらったり、口頭で希望を聞いてメモを残すなど、やり方次第で誤解は防げると実感しています。
相談の形を取った意思表示を促す
「全部任せます」ではなく、「どうすればいいと思いますか?」といった相談ベースの会話に持っていく工夫もしています。そうすると、相手も考えを口にするきっかけができ、こちらも提案がしやすくなります。一方的な依頼で終わらせず、会話のキャッチボールにすることで、責任の共有感も生まれます。
事務所内でも「聞く勇気」を大切に
事務員に対しても、「任せる」とは言わず、「ここは確認してもらっていい?」というような依頼の仕方に変えました。忙しいとつい、投げるように指示してしまいますが、それがミスのもとになりやすい。わからないことを聞くのは恥ずかしいことではないと、お互いに言い合える空気が、やっぱり大事だと思います。
一人事務所で孤独を感じない工夫
一人で抱え込んでしまいそうなときほど、誰かと話す時間を意識して作るようにしています。愚痴でもいい、笑い話でもいい、ただ「わかるよ」と言ってもらえるだけで、ずいぶん救われる。私も司法書士として、誰かの「任せます」が怖くならないよう、今日もまた、話し合いから始めようと思っています。