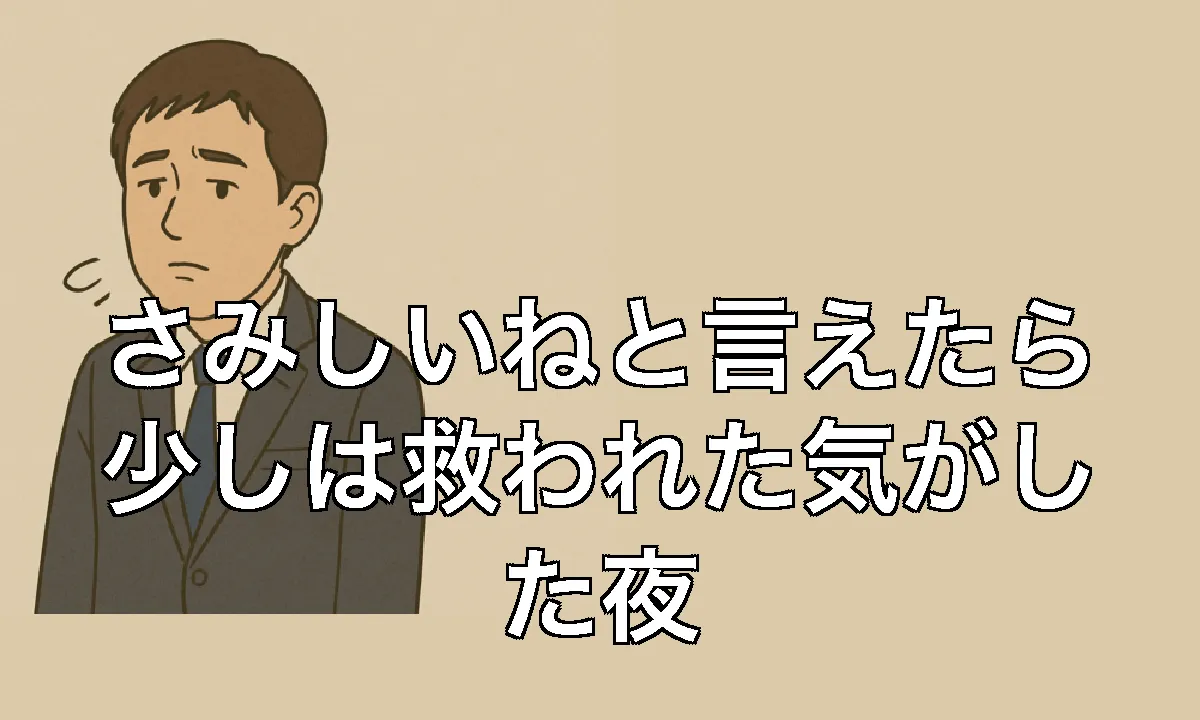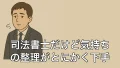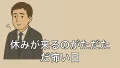誰かと過ごしていてもふと訪れるさみしさ
忙しい日々の中、人と関わっているはずなのに、ふとした瞬間に心の中にぽっかりと空洞ができたような気持ちになることがある。誰かと話していても、食事をしていても、なんとなくその場に「自分がいない」ような感覚。笑っているのに、心の奥では別の自分が冷めた目でそれを見ているような、あの不思議な孤独感。これは仕事柄、人と接することが多い司法書士としても感じることで、むしろ誰かと一緒にいるときほど浮かび上がってくることがある。
笑っていても心は晴れない瞬間
例えば、相談者の前で笑顔を絶やさずに対応しているとき。相手の緊張を和らげるため、丁寧に言葉を選び、雰囲気を和ませようと努める。だけど、自分の心はまるで誰かに貸しているみたいで、終わったあとはどっと疲れる。打ち合わせが終わってひと息ついた時、静かな事務所に戻ると、まるで自分が「いなかった」かのような感覚に襲われるのだ。笑顔を作れば作るほど、自分が遠のいていく。そんな虚しさを抱えて帰る夜は少なくない。
仕事が忙しいほど孤独は深くなる
司法書士の仕事は、想像以上に「一人で考える」時間が多い。登記、相続、契約書…。そのひとつひとつに集中しなければならないし、責任も重い。相談者の人生の大切な局面に関わる分、プレッシャーもある。だからこそ、気を張っているうちはいい。でも、仕事がひと段落した時、ふとした隙間に「誰にも頼れない自分」が顔を出してくる。忙しさでごまかしていた孤独が、静けさの中で膨らんでいく。それが夜になると一層強くなる。
事務員との距離感が余計にしんどい
ありがたいことに、事務員さんはよく働いてくれる。ミスも少なく、気も利く。ただ、それだけに余計な話がしづらい。「さみしい」とか「しんどい」なんて、冗談でも言えない。変に気を遣わせたくないし、職場の空気も悪くしたくない。でも、本当はちょっと話したい日もある。何でもない会話でよかった。ただ、それができない。この適度な距離感が、逆にこちらの孤独を際立たせてしまう。仕事場にいても、どこかひとりきりのような気分になる。
さみしいと言えない自分を責めてしまう
「さみしいね」と一言、誰かにこぼせたら、もう少し気持ちが軽くなるのかもしれない。でも、その言葉がどうしても喉を越えない。そういう自分を「弱い」と思ってしまう癖がある。「男なんだから」とか、「経営者なんだから」とか、昔から刷り込まれてきた価値観がブレーキをかけてくる。感情を抑え込みすぎて、自分でも自分がよくわからなくなる時がある。そして、言えない自分を、また責めるのだ。
弱音を吐くことへの罪悪感
学生時代からそうだった。野球部ではとにかく根性論。弱音を吐くと「逃げ」だと見なされた。あの頃から、自分の感情を外に出すことが怖くなっていたのかもしれない。社会に出てからも、相談される立場にいる以上、自分が相談する側にはなれないと勝手に思い込んでいた。「そんなことくらいでさみしいとか言うなよ」って、自分で自分を否定してしまう。結果、誰にも言えず、ただ心の中に重たいものがたまっていく。
元野球部の我慢は美徳が染みついて
「歯を食いしばって乗り越えるのが男だ」そんな価値観が、いまだに体の奥に残っている気がする。熱中症寸前でも水を我慢していた高校時代。それが当たり前だった。今では笑い話にしているけれど、本当は笑えない。大人になってからも、その延長で「つらい」や「さみしい」が言えなくなった。弱音=甘え、という等式が抜けない。だからこそ、自分の中の「感情」が行き場をなくしてしまうのだ。
強い人ですねと言われるほど苦しくなる
相談者から「先生って強いですね」と言われることがある。たぶん、表面だけを見れば、そう見えるのかもしれない。でも、そんなときほど苦しくなる。「強くあらねば」と背伸びしているだけで、本当はボロボロ。誰かに頼りたいけど頼れない。だから、誰かに強いと言われるたび、「ああ、自分はまた本音を隠しているな」と気づく。強さを演じ続けることが、どれだけ孤独を深めているか。気づいても、なかなかやめられない。
言えない言葉ほど溜まっていく
「さみしいね」と言えないまま日々が過ぎると、その言葉は心の中で濁っていく。ちょっとしたことでイライラしたり、妙に感傷的になったり。要するに、未消化の感情が溜まっているのだ。誰かとケンカしたわけでもない、仕事で大失敗したわけでもない。ただ、なんとなく心が重い。それは、きっと「言葉にできなかった気持ち」がうずくまっているからだ。
夜中のコンビニで買う無駄なアイス
そんな気持ちの夜は、なぜかコンビニに足が向かう。別にお腹が空いているわけでもないのに、アイスや甘いものを買ってしまう。「頑張ったご褒美」とか言い訳しながら、本当はただ何かを満たしたいだけ。でも、食べ終わったあとに残るのは、満腹ではなく、むしろ虚しさだったりする。誰かと「一緒に食べた」記憶があれば、それだけで違うんだろうな、と思いながら帰る夜道は、妙に寒い。
さみしさをごまかすための習慣
YouTubeを見ながら寝落ちしたり、意味もなくSNSを眺めたり。どれも、心のどこかを埋めるための「代替行動」なのだと気づいている。でも、それが習慣になると、逆にさみしさを強化してしまう。誰ともつながらない夜に、誰かの幸せそうな投稿ばかり目にすると、余計に孤独感が増してしまう。そんな自分に「何やってるんだ」とツッコミを入れながらも、やめられない。もはやそれが、自分の中の逃げ道になっている。
それでも心は満たされない
いくらアイスを食べても、いくら動画を見ても、心の空洞は埋まらない。「さみしいね」のひと言を誰かに伝えるほうが、きっとよほど効果的なのだと思う。でも、その一言が言えない。言えたら少しは救われたかもしれないのに、と思う夜が何度あっただろう。結局、最後は一人で布団に入って、自分の呼吸だけが聞こえる暗闇の中で、そっとつぶやく。「さみしいね」って。それだけで、少しだけ、気持ちがほどけるような気もする。
言葉にして初めて見える風景がある
先日、昔の友人と久しぶりに飲みに行ったとき、不意に「最近さみしいなあ」と口にしてしまった。すると相手も「ああ、俺もだよ」と笑った。その瞬間、不思議な安堵感が広がった。言ってよかった、と思えた。大げさなことじゃない。ただ、同じ温度の言葉を共有するだけで、こんなにも心が軽くなるのかと驚いた。あの夜から、「言ってもいいんだ」と少しだけ思えるようになった気がする。
さみしいねと言えた日のこと
その日、空は雨が降りそうな曇り空で、気分も沈んでいた。だけど、友人と会って、「最近どう?」の何気ないやりとりの中で、ぽろっと出た「さみしい」という言葉。相手がすぐに「俺もそうだよ」と返してくれたから救われた。共感してもらうというより、否定されなかったことで、気持ちがふっと軽くなったのだ。あの一言がなければ、今もまだ、同じところで足踏みしていたかもしれない。
相手の反応がどうでもよくなった瞬間
最初は「変に思われないか」とか「重くないか」とか気にしていた。でも、言ってみたら、意外と大丈夫だった。というか、相手の反応なんて、そこまで重要じゃなかったのかもしれない。「さみしい」と言えた時点で、自分の中の重石がひとつ取れた気がした。それが誰に対してであれ、自分が自分に許可を出した瞬間だったんだと思う。
共感よりもまずは自分への許し
「さみしい」と言ってもいい。「つらい」と感じてもいい。そうやって、自分の気持ちにフタをしないこと。それが大人になって一番難しいことのひとつかもしれない。でも、自分で自分を認めてあげない限り、誰といてもきっと孤独は消えない。共感してもらえなくてもいい。まずは、自分で自分に「さみしいよな」と声をかけてあげること。たったそれだけで、救われる夜があるのだから。