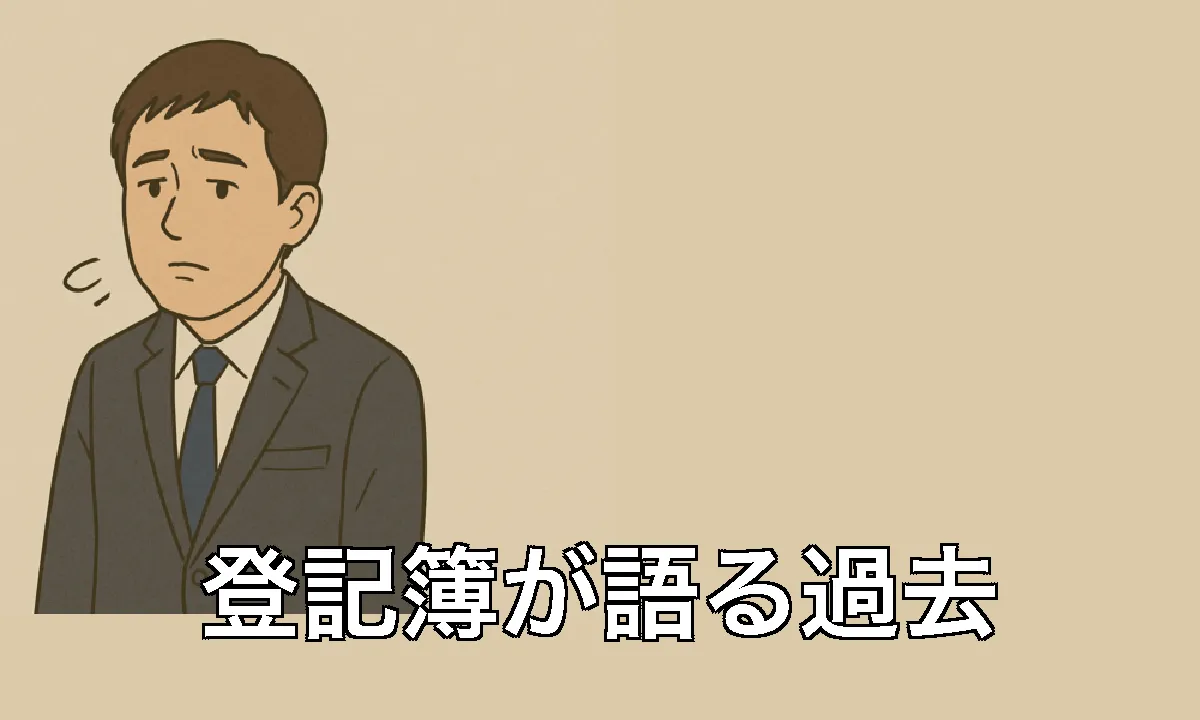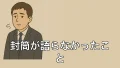朝一番の依頼人
事務所のドアが開いたのは、まだ珈琲も飲み終えていない朝九時。無言で入ってきた初老の女性は、カバンから一枚の登記簿謄本を差し出した。目元は固く、なにかを押し殺すような表情をしていた。
「この土地……どうして私の名前になっているのか、調べていただけますか」
依頼の内容は単純そうに見えて、なぜか胸騒ぎがした。土地の名義を見た瞬間、見覚えのある住所に一瞬、目が止まった。
無言で差し出された一枚の登記簿
登記簿を確認すると、名義人が変わったのは昭和49年。原因は「相続」と記されている。しかし、戸籍を確認すれば本来この依頼人の兄が相続人となるはずの順番だった。
「ずっと母の名義だったはずなんです。兄が亡くなったとき、こんなことは何も…」
司法書士としての直感が、これはただの手続きミスではないと囁いていた。
サトウさんの鋭い一言
「この地番、土地の形がいびつです。昔の分筆跡、地図で見たことあります」
サトウさんがパソコン画面に表示された地図を指さす。彼女の言う通り、その土地は元々隣地と一体だったものが、無理やり切り離されたような痕跡を残していた。
私は頭をかきながら唸った。「やれやれ、、、また複雑なやつか」
相続登記の裏側
昭和の登記簿はクセが強い。タイプライターで打ったような文字が並ぶ紙のコピー。そこには“誤記訂正”というハンコが押され、名前の一部が修正されていた。
だがその訂正がまたおかしい。訂正されたのは「山田一郎」が「山田二郎」になったという、まるで兄弟をすり替えたかのような変更だった。
「誤記っていうには、ちょっと大胆すぎますね」とサトウさん。
名前のない相続人
古い戸籍を調べると、確かに山田家には三人兄弟がいた。しかし三男の名前が登記簿に一切出てこない。まるで最初から存在しなかったように。
戸籍の附票も住民票もすでに除籍・廃棄されていたが、かろうじて学校の卒業名簿にその名が見つかった。三男は養子に出されていた可能性があった。
こういう時、法定相続人の判断が一気にややこしくなる。
土地に残された謎の地番
さらに気になるのは、対象の土地がかつて山田家の隣人だった「高木家」の土地とつながっていたことだった。昭和49年の法務局の資料に、地番の分筆登記があった。
「これ……兄の死後に分筆してるって、かなりおかしいですよ」
登記原因が“相続”であるにも関わらず、名義変更が終わっていない状態で分筆されていた。サトウさんの眉間にシワが寄る。
旧家の秘密
依頼人と一緒に、問題の土地に行ってみることにした。そこは今、誰も住んでおらず、蔦に覆われた古びた木造住宅がぽつんと建っていた。
鍵のかかった母屋の裏手に、ひとつだけ開いていた蔵の扉があった。埃まみれの中から出てきたのは、赤茶けた封筒と古びたアルバム。
封筒の中には、昭和47年の日付が入った遺言書の写しがあった。
閉ざされた母屋と封印された部屋
遺言書には「三男に土地を相続させる」と記されていた。しかし、この遺言書は登記に使われた形跡がない。それどころか、三男の存在自体が消されていた。
「遺言が無効になったか、隠されたか…ですね」サトウさんは蔵の中をライトで照らしながら言った。
そのとき、床下からコツンと何かが転がる音がした。
近所の証言と古写真
近所の古株の住民に話を聞くと、皆一様に渋い顔をした。「あそこはなぁ…昔から揉めてたよ。三男坊は気の毒だった」
「父親の死後、家を出てったって話だったけどね…ほんとは追い出されたんじゃないかって噂だよ」
まるでサザエさんに出てくる伊佐坂先生のご近所会話のように、噂話は断片的ながらも核心を突いていた。
サザエさんのようなご近所ネットワーク
「町内会長の奥さんが、昔その家でお手伝いしてたらしいですよ」とサトウさん。紹介してもらったその女性は、驚くほど記憶が正確だった。
「三男さんはね、ほんとは一番家を大事にしてたの。でも兄たちが全部持ってっちゃったのよ」
彼女の話から、登記簿に残されなかった真実が浮かび上がってきた。
登記簿が語る過去
昭和49年の相続登記の際、遺言書の存在が伏せられ、兄が土地を相続したように偽装された。三男は文句も言わず、街を離れてそのまま帰ってこなかった。
つまり、この名義変更は「虚偽の登記」だった可能性がある。そして依頼人に名義が移ったのは、その兄の死後、さらに第三者を介した相続によってだった。
法務局に申請された登記簿は語らない。しかし、すべてを知っている。
昭和四十年代の名義変更の痕跡
古い登記簿の“訂正印”が、不自然なほど何度も押されていた。あれはミスではなく、意図的な操作だったのだろう。
「こういうの、昭和あるあるってやつですよね」サトウさんがため息をつく。
「……いや、これは犯罪だよ」と私はぼそりとつぶやいた。
転籍と失踪と養子縁組
追い出された三男は、他家の養子となり、名前も戸籍も変わっていた。現在は関東で暮らしているらしいが、相続の権利は法的にはまだ存在していた。
依頼人は混乱しながらも、「それでも、本当のことが知れてよかったです」と微笑んだ。
やれやれ、、、また複雑な相続と因縁の物語だったなと、私は心の中で呟いた。
すべてのつじつまが合うとき
事件とは呼べない小さな嘘と沈黙が、家族を分断し、土地を歪め、時間を止めていた。それを一つずつ紐解くのが、司法書士の仕事である。
この土地も、ようやく“正しい持ち主”の元へと向かう準備が整った。
遠くから蝉の声が聞こえる夏の昼下がり。私は静かに登記申請書に印を押した。