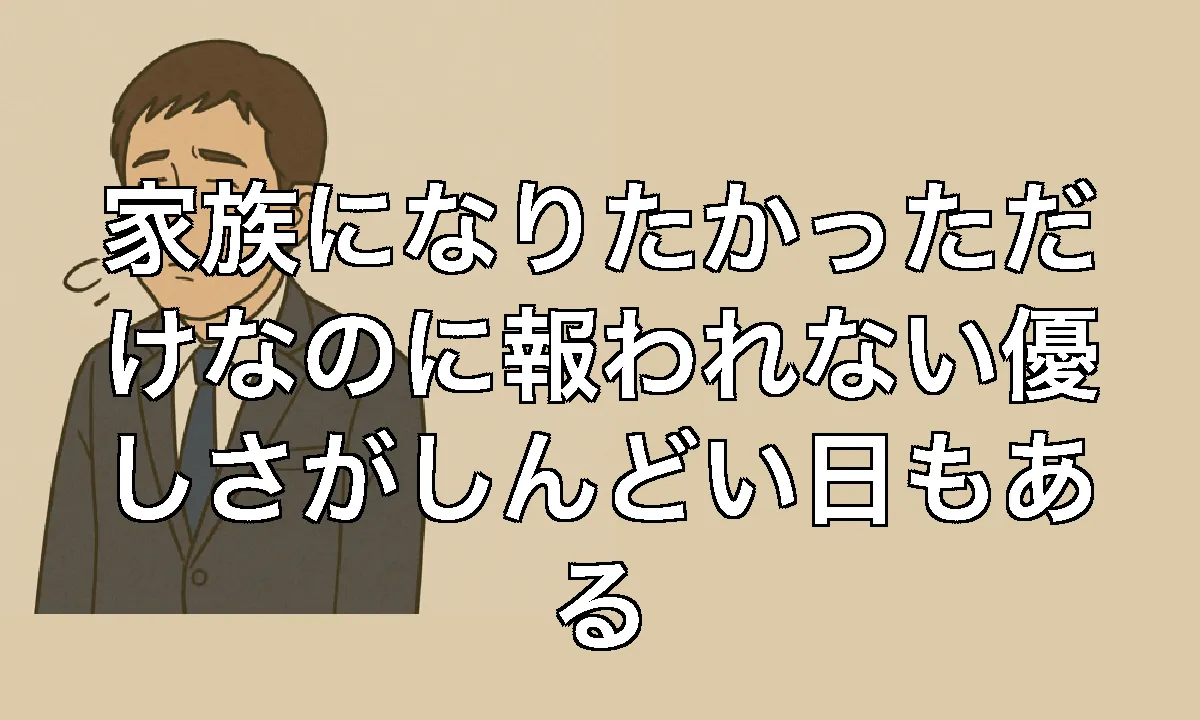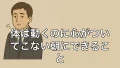家族という言葉にすがりたかった夜があった
司法書士という職業柄、人の戸籍や相続に触れる機会が多い。赤の他人の家族の話に深く関わるのに、自分はその輪の外。そんな矛盾に、ふとした瞬間に胸が締めつけられる。帰り道にコンビニで買った弁当を片手に、一人暮らしの家の玄関を開ける。明かりのない部屋、誰の気配もしない空間。それでも自分の人生をここまで進めてきた。その裏にあるのは、「誰かの家族になりたかった」という、叶わなかった願いだった。
仕事帰りのコンビニ弁当と空っぽの部屋
夕方になると、駅前のコンビニが混み始める。仕事終わりにスーツ姿の人々が列をなすなか、弁当と缶ビール、菓子パンを手にした自分が映る。家に帰れば、声をかけてくれる人も、晩ごはんを一緒に食べる人もいない。事務員の子には「先生っていつも同じ弁当ですね」と笑われるが、実はそれがちょっとした会話の支えになっている。ふと、誰かに「今日もお疲れさま」って言ってもらえたら、それだけで救われる気がする。
孤独と向き合う音は電子レンジの「チン」
帰宅して弁当の包装を外し、電子レンジに入れる。部屋はしんと静まりかえっていて、動いているのは電子レンジだけ。チン、という音が鳴るその瞬間だけ、なぜか胸にぽっかり穴が開く。野球部時代は帰宅すれば母が夕飯を用意してくれていた。あの頃は当たり前だった生活が、今ではどれほど贅沢だったか。たった一人で「おかえり」と言う声を待っている自分に、気づかないふりをするのが精一杯だった。
それでも明日は依頼者の前で笑う
どれだけ疲れていても、依頼者の前では笑顔でいなければならない。戸籍の相談、相続のトラブル、登記の確認。人の家族の「これから」を支えるのが司法書士の仕事だ。だけど、心のどこかで思ってしまう。「自分にも、誰かがいたら」と。そんな自分勝手な感情に負けそうになる夜もあるが、だからこそ依頼者の人生に敬意をもって接するようにしている。誰かの家族にはなれなくても、少しの安心を届ける存在ではいたい。
優しさが過剰になるときの自分が嫌い
「先生って、優しすぎるんですよね」と言われたことがある。事務員や依頼者に対して、つい何でも引き受けてしまう自分。それが時に自分自身を追い詰めていると分かっていても、つい「いいですよ」と言ってしまうのだ。優しさが自分を苦しめるとは思ってもいなかった。誰かと深くつながりたい、という思いが、変な形で仕事にもにじみ出ているのかもしれない。
頼られると断れない性分とその代償
ある日、事務所に飛び込みの相談者が来た。相続放棄の期限が明日に迫っているという、緊急案件だった。本来なら予約制だが、「困ってるなら放っておけない」と思ってしまった。結局その日、予定していた書類作成は深夜に持ち越し。翌朝までに仕上げ、眠い目をこすりながら出勤した。誰かに頼られるのは嬉しい。でも、その分自分の時間や健康が削られていくことを、もっと真剣に考えるべきだったと後悔する夜もある。
「いい人」止まりの人生に意味はあるのか
相談者に感謝されることはある。けれど、それが報われている実感に結びつくことは少ない。いい人、真面目な先生、仕事が丁寧。それは褒め言葉なのかもしれないが、どこか虚しい。「家族になりたい」と願ったあの気持ちは、こんなふうに仕事にすり替えられてしまったのだろうか。自分をすり減らしながら「誰かの役に立ちたい」と願う優しさが、どこかむなしく響く。
感謝されても残らないものがある
「ありがとう」の言葉は確かに嬉しい。でも、家に帰ればその言葉はもう聞こえない。冷めた風呂、脱ぎっぱなしの服、静まり返った部屋。その現実に直面したとき、感謝の言葉だけでは足りないのだと気づく。心の隙間に入ってきてくれる誰かがいなければ、どれだけ感謝されても、どこか空虚なままだ。そんな夜に、自分の優しさが報われる場所はどこなんだろうと考えてしまう。
仕事では信頼されるのに家では誰にも待たれていない
事務所ではたしかに頼りにされている。書類を整え、トラブルを未然に防ぎ、必要な説明をていねいにする。それはプロとして当然のことだ。でも、仕事が終わって帰る場所では、自分を待ってくれている人はいない。その事実が、たまにどうしようもなく寂しい。
電話が鳴るたび少し嬉しいと思ってしまう
スマホが鳴るたび、「誰だろう」と一瞬ときめいてしまう自分がいる。実際は取引先か、依頼者か、行政からの連絡だと分かっていても、つい期待してしまう。誰か個人的に自分を思い出してくれる人がいるのではないかと。でも、それはたいてい期待外れで終わる。そんな些細なことに一喜一憂している自分が、少し情けなく思えるときもある。
声が出る相手がいるだけでありがたい
人と話す時間がない日もある。事務員が休みの日や、依頼者と会わない日には、誰とも口をきかないまま一日が終わることもある。だから、スーパーのレジで「袋は要りますか?」と聞かれることすらありがたいと思う。声を出せる相手がいる。それだけで「社会とつながってる」と思えるなんて、ずいぶん寂しい話だ。
報酬よりも言葉が欲しかった瞬間
大きな案件が無事に終わった日、銀行に入金された報酬を確認したとき、なぜか心が動かなかった。嬉しいはずなのに、どこか冷めている。欲しかったのはお金ではなく、「先生、助かりました」「頼りにしています」といった、温かい言葉だったのだと思う。そう気づいた瞬間、自分がどれだけ人とのつながりに飢えているのか、痛感した。
独身司法書士が家族という言葉を手放すまで
たぶんもう、誰かの家族になることはないのかもしれない。そう思ったら、少し気が楽になった。執着せず、今ある縁に丁寧に向き合う。それだけでも、十分に意味のある生き方なのかもしれない。結婚だけが幸せじゃない。そう思えるようになるまで、ずいぶん時間がかかった。
期待をやめたら少し楽になるって本当か
誰かに期待することをやめたら、心が軽くなった気がする。誰にも頼られなくても、誰かの家族になれなくても、自分の存在には意味がある。司法書士として、人の人生の分岐点に関わる責任ある仕事ができるだけでも、ありがたいことなのかもしれない。とはいえ、時折ふと心が冷える夜もある。でもそれも、自分の人生の一部として、受け入れていくしかない。