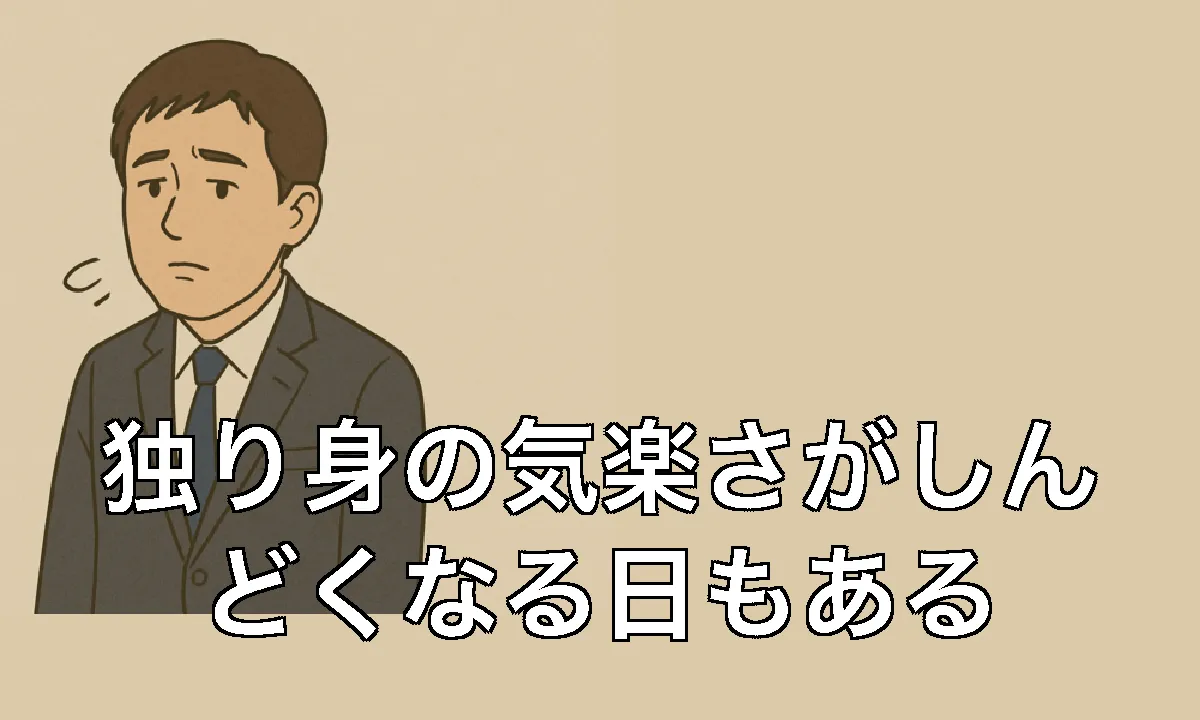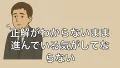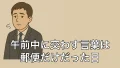誰にも干渉されない自由は本当に自由なのか
誰にも文句を言われない。何時に寝ようが、何を食べようが、どんな生活リズムであろうが、全部が自由。それが独り身の醍醐味だと思っていた。実際、誰かと暮らしていたら今のように仕事に打ち込むことはできなかっただろうし、夜中まで書類を広げていても怒られることもない。ただ、ふとした瞬間、その「自由」が重たく感じる時がある。誰にも見られていないからこそ、何をしても「自分次第」で、その結果が全部自分に返ってくる。自由という名のプレッシャーに、独りで耐え続ける日々があるのだ。
独りの生活リズムは誰にも邪魔されない
朝起きる時間も、夜ご飯の時間も、全部が自分の裁量だ。好きなタイミングで仕事に入って、好きなタイミングでコーヒーを淹れて、誰に遠慮もせずに風呂に入れる。こんな生活、結婚していたらなかなか難しいだろう。特に司法書士という仕事は急な対応も多いから、「ご飯できてるよ」と言われても「今無理」と返してしまう自分が容易に想像できる。だから独りの方が楽だと思っていた。でも、それって本当に“楽”なんだろうかと最近思う。誰にも邪魔されないって、つまり、誰も気にしてないってことでもある。
気楽さの裏にある自己責任の重圧
独り身である以上、全ての生活の責任は自分一人にある。食べなきゃ痩せるし、片付けなければ部屋は荒れる。洗濯を溜めれば着る服がなくなる。健康管理だって、誰も「病院行ったら?」なんて言ってくれない。気楽なようで、その実、全部が「自己管理」だ。特に忙しい時期なんかは、生活が崩れるスピードも早い。仕事に集中しているうちに部屋はカオス、冷蔵庫は空っぽ、そして疲れが溜まり体調を崩す。でも誰も責めてくれないから、なおさらしんどい。
何でも自分でやる生活は地味に消耗する
たとえば、夜遅くまで登記の書類を作成して、ようやく終わって時計を見たら午前1時。そこから夕飯の後片付けをして、風呂に入り、洗濯物を取り込んで…となると、もう完全に体力は底をつく。こういう日々が積み重なると、「誰かやってくれたらな」とふと思う。でもそれは贅沢だと自分を戒めてまた一人でやる。頼る人がいないというのは、心の面だけでなく、現実的な疲れを抱えるという意味でも厳しい。それを気楽だと思い込んでいたのは、若さゆえだったのかもしれない。
ふとした瞬間に押し寄せる孤独感
忙しく働いているときは気にならない。でも、仕事が一区切りついて、ふと家に帰ったときの静寂に包まれた部屋に、心が沈むことがある。音がしない。明かりもついてない。ただ自分だけがそこにいる。その空間に、なんともいえない寒さのようなものを感じる。誰かと会話をして笑っていた数時間前が、遠い過去のようにも感じてしまう。独りでいることに慣れすぎると、感情が鈍くなるような感覚もあるのだ。
仕事が終わった後の無音の部屋
「今日もよく働いたな」と事務所の灯りを消して帰宅する。真っ暗な部屋に入って、照明をつけ、スーツを脱いで、ため息ひとつ。テレビをつけても、誰かの声があるだけで心が落ち着く。でも結局、自分の声はどこにもない。そんなとき、「話し相手がいたらなぁ」と思うこともある。仕事では人と話していても、プライベートでの会話がほとんどないというのは、思っていた以上に堪えるものだ。
愚痴をこぼす相手がいない寂しさ
仕事が立て込んでいたり、理不尽なクレームを受けたりしたとき、本音を吐ける相手がいるかいないかで、心の負担は全く違う。昔なら同僚や恋人に「ちょっと聞いてよ」と言えた。でも今は、自分の中に溜め込むしかない。それがだんだん蓄積していくと、ある日どうしようもなくなって、意味もなく落ち込んだり、寝付きが悪くなったりする。誰にも見せられない愚痴が増えていくと、自分自身に嫌気がさす瞬間もある。
電話一本すら面倒になる自分が怖い
誰かと話したい気持ちはあるのに、いざスマホを手に取ると「今さら何話せばいいんだろう」と考えてしまい、結局やめる。そういう日が増えた。電話一本、LINE一通でつながれるはずなのに、心の壁がどんどん高くなっていく。自分で選んだ独りの道だけど、そこに閉じ込められてしまっているような気分になる瞬間がある。誰かを頼るのが下手になってきたことに、自分でも戸惑っている。
「気楽そうでいいですね」と言われるもやもや
「独身って気楽でいいですね」「自分の時間持ててうらやましい」…そう言われることは少なくない。でも、その言葉の裏には「責任がない人」という見られ方も混じっているように感じる。自由と引き換えにしているものが、意外と大きいことに気づいていない人も多い。独り身で生きるには、それなりの覚悟が必要だということを、誰も教えてくれなかった。
独り身イコール自由という見られ方のズレ
確かに、既婚者に比べて予定は立てやすいし、急な仕事にも対応しやすい。でもそれは、誰にも予定を合わせる必要がないからであって、自由というより「合わせる相手がいない」という状況なのだ。特に法務の世界では、休日も平日も曖昧な中での仕事が続く。それを「自由でいいですね」と言われるたび、どこか虚しくなる。「自由」と「孤立」は紙一重だ。
誰にも頼られない日々は誇りか不安か
独りでなんでもできる。それは一つの強みでもあるし、誇りにもなっている。だけど同時に、「もし自分が倒れたら?」という不安が常につきまとう。何かあったときに頼れる人がいない現実は、意外と怖い。責任のある仕事を任されている身だからこそ、ふとしたときに「誰かがいてくれたら」と思ってしまうのだ。強さと弱さが、常に背中合わせにある。
それでも前を向こうと思える瞬間
こんなふうに弱音を吐きながらも、それでもこの仕事を続けていける理由はある。たとえば、お客さんに「先生にお願いしてよかった」と言われたとき。誰かの役に立てているという実感が、日々の孤独や疲れをふっと軽くしてくれることがある。人と人とのつながりの中で、自分の存在価値を見いだせる。独りでいても、独りじゃないと思える瞬間が、確かにある。
相談者とのやり取りで救われること
普段は淡々とした仕事のやりとりが続くけれど、ときには人生相談のような場面になることもある。遺産の問題、相続の悩み、夫婦のこと…そんな話を真剣に話してくれる相談者を前に、自分もまた真剣になる。話が終わったあと「先生、なんかホッとしました」と言われると、自分の存在にも意味があるんだと思えてくる。そんな瞬間があるから、今日も仕事を続けられる。
たまに届く「ありがとう」が染みる
郵便で届いた手書きのハガキ。「このたびはお世話になりました」という丁寧な文字を見たとき、胸が熱くなった。顔も覚えていない依頼者だったけど、その感謝の言葉だけで疲れが吹き飛ぶようだった。大仰なことは求めていない。たった一言の「ありがとう」が、心の支えになる。だからこそ、今日もまた机に向かうことができる。
独りでも誰かとつながれる感覚を信じて
独りで生きていくのは簡単ではない。気楽に見えるけれど、実際には不安や孤独が常にそばにある。それでも、自分の仕事が誰かの助けになっていると実感できるとき、人とのつながりを感じることができる。直接的ではなくても、心のどこかで誰かと結ばれている。そんな小さな手応えが、独り身の生活を少しずつ照らしてくれるのだと思う。