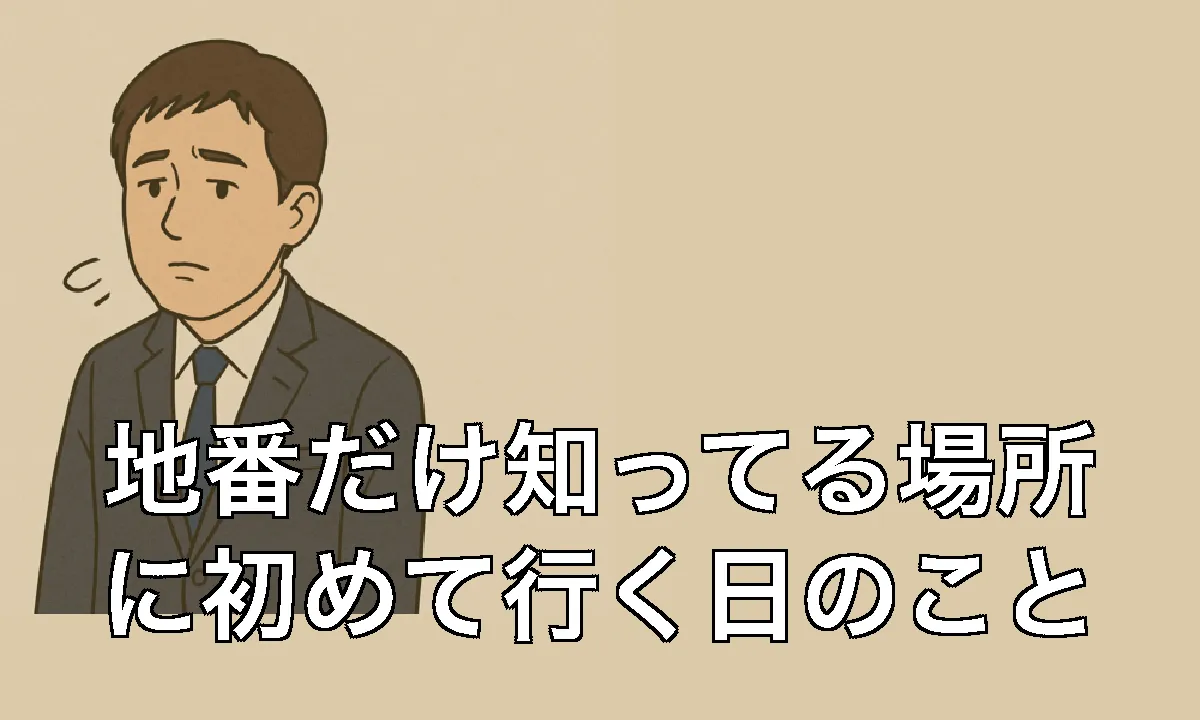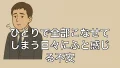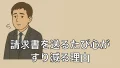地番だけ握りしめて出発する朝の不安
朝のコーヒーを飲みながら、今日の予定を確認する。ふと一件の地番調査があることに気づき、プリントアウトされた登記簿謄本を見つめる。そこには見慣れない地番の数字だけが記されている。住所ではない、目印もない、写真もない。スマホの地図で検索しても「その地番は見つかりません」と冷たい表示。車に乗り込みながら、「たぶんこの辺だろう」と思い込むことにして、見知らぬ場所へとアクセルを踏む。経験を重ねても、初めて行く場所はやっぱり緊張するのだ。
スマホ地図では出てこない現実とのギャップ
Googleマップが万能だと思っていたあの頃が懐かしい。地番で調べてみてもピンが刺さるのは大雑把な中心点。番地とは違って、地番は本当に「そこにあるだけ」のもので、町名も含まれていなければ番地指定もない。そうなると地図はあまり意味をなさない。結局、手元にあるのは市役所からもらった白黒の図面と登記簿だけ。しかも図面は縮尺がバラバラで、「あれ?ここが○番?」と自問しながら歩くはめになる。こんなとき、紙の地図に戻りたくなるのは僕だけだろうか。
番地と地番の違いがもたらす混乱
「番地がわかれば行けるんじゃないの?」と聞かれることもあるが、司法書士にとっては番地と地番の違いが一番ややこしい。特に地番は登記用で、住所とは一致しないことが多い。地番○○番地と書かれても、その○○番地が表札に出ているわけじゃない。だから現地では「○○さんの家の裏」や「用水路の横の空き地」なんて、曖昧だけどありがたい表現を頼りにするしかない。地番で話が通じるのは、役所か法務局か、僕らくらいのもんだ。
「この辺だと思うんですけど…」と言いながら歩く
何度言ったか分からないこのセリフ。「この辺だと思うんですけど…」と呟きながら、手には地図、目はあちこちの風景を見回す。畑のあぜ道で、犬に吠えられながら、ポケットから取り出した登記簿のコピーを見つめ直す。「いや、この水路の向こうか?」と思って行ってみると、今度は用水路に阻まれて進めない。もう一度地図を見て、首をかしげながら「ぐるっと回るか」と独り言。この時間、誰にも見られたくないし、誰にも声をかけられたくもない。
司法書士になっても土地勘なんて育たない
よく「仕事してればそのうち土地勘つくでしょ」と言われるけど、それは幻想だ。司法書士の仕事は机の上の世界が多い。現地に行く回数なんて限られているし、一度行ってもそれっきり、ということも多い。同じ市内でも「え、こんなとこあるの?」という驚きばかりで、毎回が小さな冒険。地番は知っていても、その場所がどんな景色なのかは行ってみるまでわからない。それに、場所によっては車を止める場所すらなくて、ただウロウロして終わる日もある。
田舎の地名ほどクセが強い
地方に行くほど、地名や住所のクセが強くなる。たとえば「大字」「字」「○○村○○番地」みたいな表記が混在していて、ナビに入れても通じないことがある。古くからの土地の区切りが残っていて、隣の番地なのに全然違う地名だったりする。郵便配達員の方がよっぽど詳しいんじゃないかと思うほど。昔ながらの地番に頼ると、まるで迷路のような世界に放り込まれる。誰かが整理しない限り、永遠にこの混沌は続くんだろうな…と思いながら、僕はまた道に迷う。
登記簿に書いてある地番が現地にない理由
これもよくある話。登記簿にしっかり書かれている地番が、現地には何の表示もない。表札もなし、ポールもなし、ただの空き地。地番表示板というものがあるにはあるけど、壊れていたり、草に埋もれていたり、そもそも設置されていない場所も多い。新興住宅地ならまだしも、昔からある集落だと、完全に口伝えが頼りになる。こうなると、登記情報は“知識”でしかなく、“目に見える情報”とはほど遠い。それでも我々はそれを信じて現地に立つしかない。
自治体の人でも迷う場所は本当にある
実際、自治体の職員さんでも「ここどこ?」ってなる場所は存在する。僕が一度、役所に確認の電話をしたとき、担当者が「その地番…うーん、地図見てもピンと来ませんね」と苦笑していた。さすがにそれ聞いたときは少し安心した。地元のプロですらわからないんだから、僕が迷うのも無理はない。地番の世界は、誰もが不完全な情報の中で手探りしている。完璧なんて求めちゃいけない、そう思えるようになっただけでも、僕はちょっとだけ前進したのかもしれない。
現地で頼れるのは勘と経験と近所の人
いざとなったら、頼るのは近所の人。これが一番確実だったりする。年配の方が多い地域だと、「ああ、○○さんちの跡地かね」とすぐに答えてくれることが多い。感謝の気持ちを込めてお辞儀をしても、「がんばってね」と声をかけてくれる。こういう瞬間があると、やっぱり現場に来てよかったと思える。机上の登記だけじゃ得られない、土地の空気みたいなものがあるのだ。
犬に吠えられながら道を聞く
ただし、道を聞こうとするときに立ちはだかる壁、それが犬。田舎の家の多くには番犬がいて、近づくだけで大騒ぎになる。僕は過去に、道を聞こうとして門の前で仁王立ちされたことがある。あのときの冷や汗といったらない。結局、門の外から「すみませーん!」と叫び、出てきてくれたおばあちゃんに助けられた。人に道を聞くという行為も、時には勇気と声量が必要なのだ。
「ああ○○さんとこの裏ね」と言われる安心感
この一言を聞いた瞬間の安心感は計り知れない。「ああ、○○さんとこの裏ね」と地元の人に言われると、「あ、間違ってなかったんだ」と心からホッとする。それまでの不安や焦りが一気に溶けていく。しかも「ついでにあっちの道から回った方が近いよ」とルートまで教えてくれる親切さ。やっぱり人間ってありがたいなと、こんなときほど感じる。
道を聞けるというのも一つのスキルかもしれない
知らない場所で、誰かに話しかけて道を尋ねる。これって実はスキルなんじゃないかと最近思っている。相手に不信感を与えず、状況を説明し、答えてもらえる雰囲気を作る。それって仕事にも通じる要素だらけだ。司法書士の仕事って、書類だけじゃなく人とのやりとりも多い。だからこそ、こういう現場での経験も、自分を鍛えてくれているんじゃないか…と、ちょっとだけ前向きに考えてみた。
地番調査が終わった後の虚無感
すべて終わって車に戻った瞬間、なんとも言えない虚無感に包まれる。やり遂げたという感覚より、「これ、誰に伝わるんだろう」という空しさが勝る。クライアントには成果物を渡すだけ、誰にも褒められない。けれど、誰かがやらなければならない仕事。今日もまた、そんな一日が終わるのだ。
仕事は片付いたのに晴れない気持ち
書類に印を押して、メールを送って、業務は完了。それでも気持ちはどこかくすぶっている。達成感よりも疲労感の方が上回る日。そんなとき、ふとコンビニで買ったコーヒーが美味しく感じたりする。報酬なんて二の次で、誰かに「ごくろうさま」と言ってほしいだけ。だけど誰もいない。そんな日が積み重なっていく。
誰にも褒められない地味な業務
地番調査というのは、地味で泥臭くて、目立たない。でもこの作業がなければ登記は動かない。建物が建つ前、土地が売られる前、すべてのスタート地点。裏方中の裏方。それをやっているんだというプライドを持つようにはしているけど、たまには誰かに「よくやったね」って言われたくなる。誰にも届かない努力、そんなものを繰り返すのがこの仕事なのだ。
でもこれがないと登記はできないんだと自分に言い聞かせる
最後はやっぱりそこに帰ってくる。「これがないと、あの登記はできなかったんだ」と自分に言い聞かせて、また次の案件に向かう。誰も見ていなくても、自分だけは知っている。今日、自分がやったことが、少なくとも誰かの一歩目になっていると信じる。それだけで、また車に乗って、新しい地番を目指す勇気が湧いてくる。