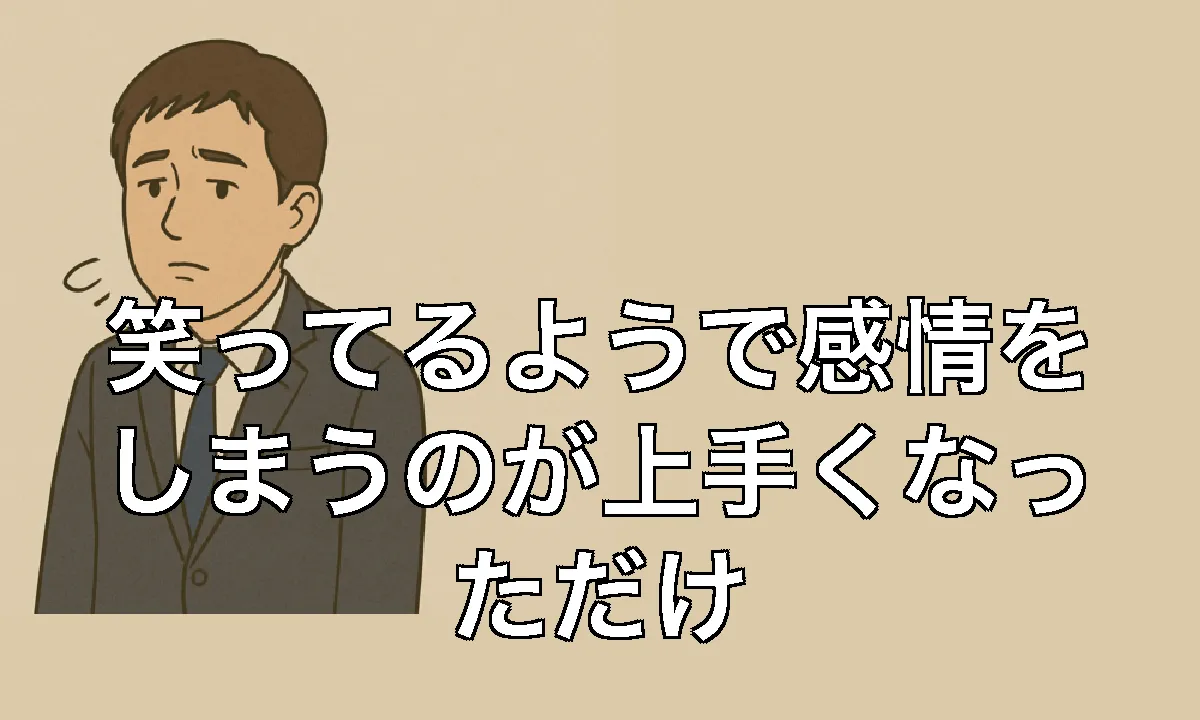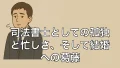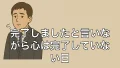感情の引き出しに鍵をかけた日
最近、自分の中で「うまく笑えるようになったな」と思うことがある。でも、それって別に幸せだからじゃない。感情をしまうのがうまくなっただけだ。誰かに本音を話すのが億劫になって、だったら表情を整えて「大丈夫です」と答える方が楽になった。そう気づいたのは、たぶん事務所で一人、冷めたコーヒーを啜っていたあの日の午後。あれから、感情の引き出しにはきっちり鍵をかけるクセがついてしまった。
何も感じなくなったわけじゃない
よく「無感情な人だね」と言われるけれど、別に感情がないわけじゃない。感じたくないと願っているわけでもない。ただ、表に出すタイミングがわからなくなっているだけだ。昔は、テレビドラマの感動シーンで泣くような普通の人間だった。けれど、忙しい日々のなかで、感情を出すことがトラブルや誤解につながると学んでしまった。だから、感じても見せない。見せないことが、身を守る手段になっただけなんだ。
人前で涙を流せなくなった理由
最後に涙を流したのは、たぶん父が亡くなったときだ。それも、通夜が終わったあとの一人きりの部屋で。誰かの前で泣くなんて、もう何年もしていない。事務所の中でも、自分のミスでクライアントに怒られたときも、グッと飲み込むことを覚えた。泣いても問題が解決するわけじゃない。そんなふうに自分に言い聞かせて、気づけば感情の出し方を忘れていた。ただ、泣きたくないわけじゃない。泣けなくなっただけだ。
自分で自分をなだめるクセ
一人でやっていると、自分を慰めるのも自分の役割になる。「まあまあ、こんな日もあるさ」って心の中で自分に声をかける。でもそれが癖になると、どんなに嫌なことがあっても、誰かに聞いてもらうより、自分で蓋をして終わりにしてしまう。話すことで楽になるって知ってはいるけど、その労力さえも面倒になる。だから最近じゃ、自分の心の奥にそっとしまって、鍵をかけて、笑ってやり過ごす。そんな日々だ。
一人事務所での感情処理は無音
事務所には事務員が一人いるが、僕の感情までは面倒見てくれない。パソコンのキーボードを叩く音と、コピー機の唸る音だけが響く静かな空間。そんな中でふと、自分がどれだけ心の声を押し殺しているかに気づく。怒りや焦り、悲しみもあるけど、それを音に出すことがないから、まるで感情が存在していないみたいに錯覚する。実際にはちゃんとあるのに。誰にも見せられないから、無音の中でひっそり漂っているだけなんだ。
愚痴を飲み込むのが日常になった
「なんでこんな依頼ばっかりくるんだよ」とか「もっと時間が欲しい」とか、言いたいことは山ほどある。でもそれを言うと、余計に疲れる気がしてしまって、結局心の中で終わる。愚痴を吐ける相手がいないわけじゃない。でも、そのあと気を遣ったり、聞いてくれた相手に申し訳なく思うのが嫌なんだ。だから、最初から飲み込む。それが日常になった今、たまに自分の気持ちを外に出す方法が思い出せなくなる。
机の上は片付いているのに心はごちゃごちゃ
外から見れば、僕のデスクはきれいに整っている。「几帳面ですね」と言われることもある。けれど、心の中はまるで片付いていない。気になる案件、先延ばしの手続き、ふとした孤独。全部が心の中で散らかっている。それを片付ける術がないから、せめて机の上だけでも整えておきたい。そんな気持ちで日々を過ごしている。見た目だけでも整っていれば、気持ちも整ってくる気がする。実際は逆なんだけど。
優しさは強さじゃない
「優しいですね」と言われることがある。たぶん、怒らないし、声を荒げないからそう思われるんだろう。でも実際は、怒る元気がないだけだ。優しいというより、無理して笑っているだけ。その優しさは強さとは違う。むしろ弱さの裏返しかもしれない。嫌われたくない、揉めたくない、面倒なことは避けたい。その感情が、優しさに見えているだけだ。自分でも、本当のところはよくわからなくなる。
「気にしない」が口グセになるまで
昔は何でも気にしていた。誰かの一言に落ち込んだり、仕事で失敗すると寝つけなかったり。だけど、それを繰り返しているうちに疲れてしまった。「気にしない」が口グセになったのは、その方が自分を守れると学んだからだ。気にしないことで、心をすり減らさないようにした。それはある意味の成長かもしれないけれど、同時に感情を閉じる扉も増えていった。今では、何を気にしていたかも思い出せなくなってきた。
期待されない方がラクになった
期待されることは嬉しいことのはず。でも最近では、それが重荷になるようになった。「先生ならきっとなんとかしてくれる」という言葉にプレッシャーを感じてしまう自分がいる。だから、むしろ期待されない方が気が楽だと思ってしまう。悲しいことだけど、それが現実だ。自分に過剰な期待をかけると、応えられなかったときの自分が一番辛い。そうならないように、最初から距離をとるようになってしまった。
我慢すれば丸く収まると信じていた
昔から「我慢すればそのうち落ち着く」と思ってきた。野球部時代も、先輩に怒鳴られても黙って耐えることで場が収まる経験をしてきた。その延長で、今でも多少の理不尽は我慢する方が早いと思ってしまう。でも、本当は我慢ばかりしていると、どこかで自分が壊れる。そう分かっていても、我慢のクセはなかなか抜けない。「言ったら余計にこじれる」と思って黙るけど、それで心がどれだけ削れているか、誰も知らない。
元野球部という肩書きに頼る自分
「元野球部」という言葉は、今でも自分の中で一つの看板になっている。体力も精神力もあるように見えるからか、それを言うと少し安心されることがある。でも実際は、その肩書きに自分を縛っている部分もある。「野球部だったなら、根性あるでしょ」「弱音なんて言わないでしょ」そんな周囲の勝手な期待に、自分でも応えようとしてしまう。気づけば、その肩書きにすがって、本当の自分を見失っている気がする。
根性論が支えだった頃の錯覚
高校時代は、「根性さえあれば何とかなる」と信じていた。真夏のグラウンドで何時間も練習する中で、根性だけが頼りだった。けれど社会に出て、それだけじゃ通用しないことを思い知った。理屈も、感情も、人間関係も、もっと複雑だった。それでも根性という言葉にすがっていたのは、他に頼れるものがなかったからだ。あの頃の錯覚を、今もどこかで引きずっているのかもしれない。
声を荒げたくないから声を飲む
本当は言いたいこともある。でも、怒りや苛立ちを表に出すと、相手との関係が悪くなる気がしてしまう。だから、いつも声を飲み込む。穏やかな対応をしているようで、心の中では何度も叫んでいる。でも、その声は誰にも届かないし、自分にもだんだん届かなくなってきた。怒りも悲しみも、出さなければ存在しないことになる。そうして、また一つ、感情の引き出しにそっと鍵をかけるのだ。