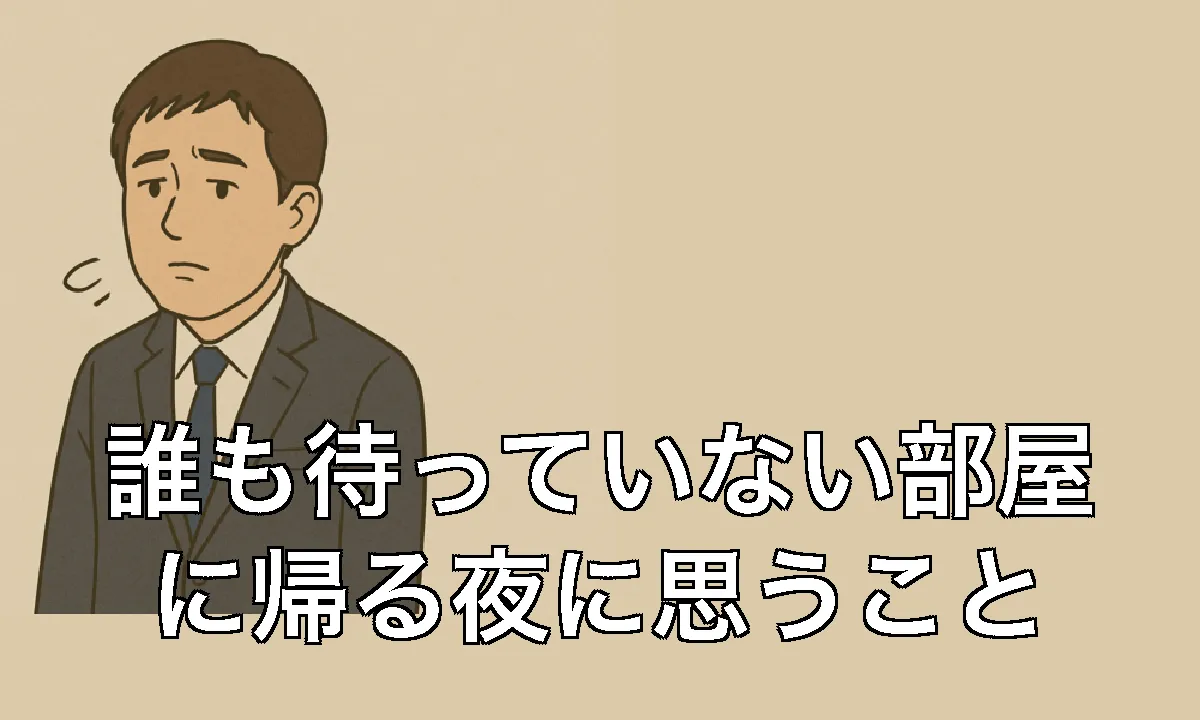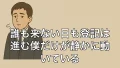仕事を終えて誰もいない部屋に帰るという現実
一日の業務を終えて、ようやく事務所を出る頃には外はすっかり暗くなっている。片手にコンビニ袋、もう片方にはカギ。エンジン音のない道を歩き、鍵を回してドアを開けると、そこには「誰もいない」現実が待っている。音も気配もない部屋。ただ、いつものように無機質な空気が、何も語らずそこにある。それが当たり前になってしまったことに、ふと気づく夜がある。
電気もテレビもついていない静寂の部屋
電気のスイッチを入れる音だけが、やけに響く。テレビもつけず、スマホも見ず、ただ椅子に腰を下ろしてため息をつくと、自分の吐息が妙に重く感じる。昔は帰宅したらまず誰かの声が聞こえた気がする。でも今は、その「誰か」もいないし、聞こえるのは冷蔵庫のブーンという音くらい。地方都市の片隅で司法書士として独立したけれど、この静寂は想定外だった。
音がないということは心を映す鏡でもある
無音の空間に身を置くと、自分の中のざわつきがむしろ大きく聞こえてくる。忙しさに追われているときには感じなかった「寂しさ」や「むなしさ」が、静けさの中でじわじわと顔を出してくる。音楽を流せばごまかせる。でも、あえて無音のままにしておくことで、心の中の本音と向き合う時間にもなる。実は、そういう時間も必要なんじゃないかと、最近は思い始めている。
沈黙に包まれた部屋と過去の自分の声
昔、野球部だった頃は、家に帰れば母の煮物の匂いがしていて、「どうだった?」と聞かれた。怒ったり笑ったりする声が、部屋の中にちゃんとあった。今は帰ってもその声はない。誰にも今日一日の話を聞いてもらうこともなく、自分の中だけで完結する。あのときの「当たり前」は、こんなに尊いものだったのかと、誰も待っていない部屋でひとり思い返す夜がある。
忙しさと孤独はなぜ同時にやってくるのか
「暇で寂しい」ならまだ納得もいく。でも司法書士という仕事は、ありがたいことに相談や案件が絶えず、日々忙しい。にもかかわらず、気持ちのどこかにぽっかり穴が開いているような感覚がある。誰かに必要とされているはずなのに、誰にも必要とされていないような気がする。そんな矛盾を抱えて生きている。
人の相談を受け続けた日の夜にふと感じること
今日も依頼者の不安や悩みに耳を傾け、少しでも安心してもらえるように動いた。それ自体はやりがいがある。けれど、一日中「人の話」を聞き続けたあとの夜、自分の話を誰にもしていないことに気づいて、少し胸が詰まる。仕事中は「先生」と呼ばれ、しっかり者として扱われる。でも夜にはただの独身男に戻る。ギャップにやられる日も、正直ある。
スケジュールは埋まっているのに心は満たされない
Googleカレンダーは予定で埋まり、日々のToDoもこなしている。でも、終業後に「今日は誰かとちゃんと笑ったか」と思い返すと、答えに詰まる。やらなければいけないことは山ほどあるのに、自分がやりたいこと、楽しみにしていたことって何だったっけ? そんな問いが浮かんでくる。埋まっているのはスケジュールであって、心ではない。
人の幸せに関わるほど、自分の空白が浮き彫りになる
不動産の相続登記、遺言の作成、会社設立の支援――人の人生の節目に関わる仕事は多い。感謝もされるし、信頼もいただく。それなのに、自分の生活には「節目」らしい節目がない。誰かの新しいスタートを手伝った直後、自分は何も変わらない部屋に戻る。そのコントラストが、時折こたえる。
誰かと話すという当たり前がない日々
「今日は誰かとごはんを食べたか?」と自分に問いかけると、ほとんど答えはNOだ。人と話すこと自体が特別なイベントになってしまっている。だからこそ、たまに雑談できる時間が、ありがたくて、そして少しだけ虚しい。
事務員との会話がその日のハイライトになる悲しみ
事務員さんとの何気ないやり取り、「コーヒーいれましょうか?」「今日も暑いですね」――それが一日の中で一番、人間らしい会話だったりする。もちろん感謝しているし、助けられてもいる。でも、それしかないという事実が、胸にくる。人間って、もっと会話で満たされる生き物だったんじゃなかったっけ、と思う。
雑談ひとつにも気を遣う独身男のつらみ
「話しかけすぎても迷惑かも」「これはセクハラと思われるかも」など、気遣いが先に立つ。仕事場での会話ひとつとっても、独身の中年男にはなかなか不自由が多い。その結果、余計に孤立感が深まっていく。でも気軽に話せる相手がほしいと思うのは、わがままなんだろうか。
帰宅後のルーティンに意味を求めない
コンビニで買ったおにぎりを食べ、風呂に入って寝る。誰かと過ごす夜とは無縁の生活が、もう何年も続いている。生活があるだけで感謝すべきなのかもしれないけれど、やっぱり人間ってどこかで「意味」を求めてしまう生き物なんだと思う。
弁当の容器を捨てて風呂に入って寝るだけ
そんな日々に慣れすぎて、逆に人と一緒に住むなんて想像できなくなってきた。自分のペースで暮らせる快適さと引き換えに、得られなかったものの大きさに目を背けている気もする。でも、容器を捨てながら「この繰り返しに意味はあるのか」と問いが湧いてくる夜も、たまにはある。
それでも生活を回すために続けていること
掃除をし、洗濯をし、書類を整理し、翌日の準備をする。それは誰のためでもなく、自分のため。でもその一つ一つの積み重ねが、自分という存在を保つための「小さな防波堤」になっているのかもしれない。そう思えば、孤独も多少は意味を持ってくれる。
「ただいま」と言う相手がいないことの重さ
玄関を開けるたび、つい口をついて出る「ただいま」という言葉。誰かに返事を求めているわけでもないのに、空間に向かって投げかけてしまう。返事がないと分かっていても、つぶやいてしまうのは、どこかで誰かに聞いてほしい気持ちがあるのかもしれない。
口に出さなくても胸の奥が知っている寂しさ
結局、「ただいま」と言わなくなった日が本当の孤独の始まりなのかもしれない。言葉にすることで、自分の存在を確かめていた。それができなくなるとき、人は心のどこかを閉ざすんじゃないか。そんなことを思いながら、今日もまた鍵を回す音が、静かな夜に響いていく。