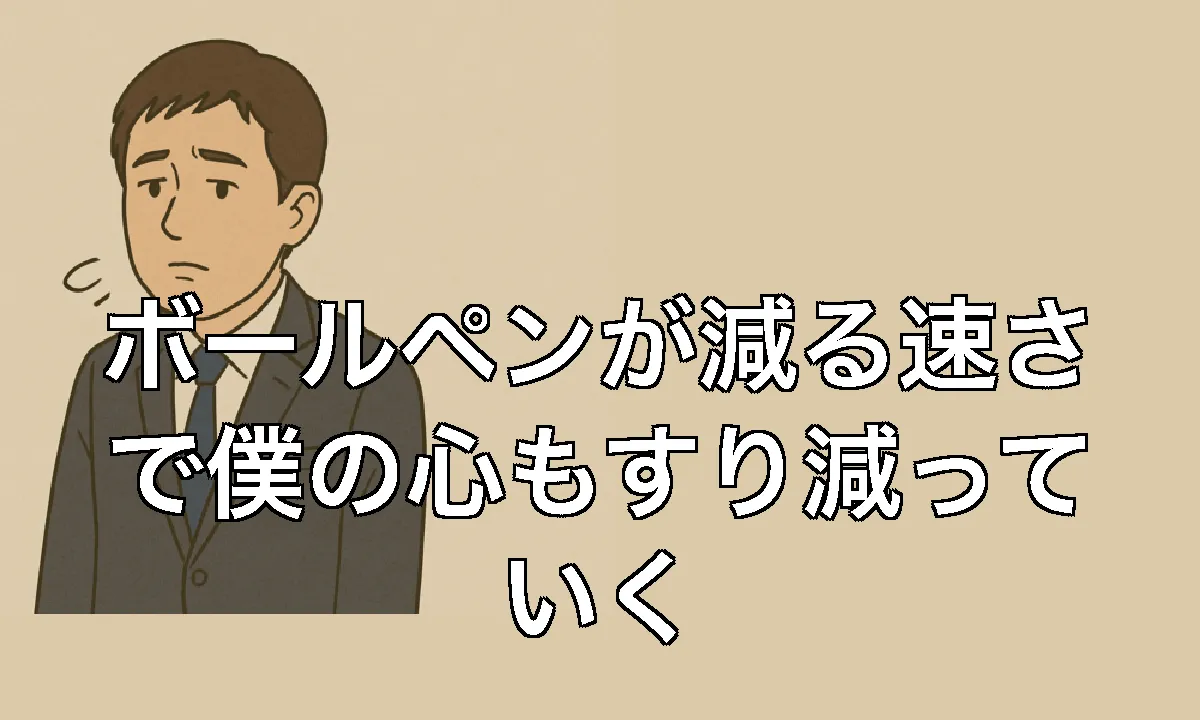減っていくボールペンのインクが教えてくれること
仕事用のボールペンが1本、また1本とインク切れになるたびに、ふと立ち止まってしまう。「あれ、今月もう3本目か?」なんて数える余裕もないほど、机の上は書類に埋もれている。司法書士という仕事は、実に多くの“書く”作業で構成されていて、まるで心を削って書き上げるようなものだ。いつの間にか、減っていくインクの量が、僕の気力の残量のように思えてきた。ペンの寿命が短いほど、自分の疲弊も進んでいる気がする。
どれだけ書類をこなしても終わらない日常
朝一番に届く依頼メールを開いた瞬間、今日のスケジュールはほぼ決まってしまう。登記申請、契約書のチェック、公証役場との調整……どれも“軽作業”ではなく、頭と心と手をフル稼働させる業務ばかりだ。ひとつ終わっても、次がやってくる。書類の山を登りきったと思ったら、また目の前に山脈が現れるような感覚だ。そんな日々が続くと、達成感よりも「終わらない疲れ」ばかりが残っていく。
「これで最後」の書類が最後だった試しがない
「よし、これで今日は終わり!」とファイルを閉じた瞬間に、FAXが届く。電話が鳴る。「急ぎでお願いします」の一言で、さっきの“終わり”はリセットされる。特に月末や連休前はこの連鎖が激しくなる。最初は「またか」とため息をついていたけれど、最近は何も思わなくなった。諦めなのか、慣れなのか、それさえもよく分からない。そうやって、心のバッテリーはじわじわと摩耗していく。
書いても書いても出口が見えない書類の山
登記簿の記載を見直して、申請書に書き写し、法務局の形式に合わせて整える。押印ミスがないか確認し、原本還付の処理も忘れずに……そういう作業の連続に追われる毎日。ひとつひとつはルールに従った作業だけれど、集中力を欠けば大きなミスにつながる。気が抜けない時間が長すぎて、いつしか自分の感情も“省エネモード”になっていた。書くこと自体が苦痛になる日は、正直ある。
静かに削れていく心の感覚
誰かに「疲れてる?」と聞かれても、「まぁぼちぼち」としか返せない。疲れというのは、派手に出るものじゃなくて、静かに削れていくものなんだと最近思う。元気がなくなるというより、“何も感じなくなる”に近い。日々のルーティンの中で、感情を殺さないと回らないような瞬間もある。でも、それが当たり前になってしまうと、自分が壊れていってることにも気づかない。
音もなく気力が失われていく実感
気づけば、休憩時間に好きだったコーヒーを飲んでも何も感じないし、昔は癒やしだった音楽もただのBGMになっている。これは「疲れている」ではなく、「擦り切れている」状態だと感じる。ボールペンのインクがじわじわ減っていくように、僕の気力も確実に減っている。それでも止まらないのは、やるべきことがあるから。いや、止まれないという方が正しいのかもしれない。
疲れに慣れてしまうことの怖さ
「忙しいですね」と言われると、なぜか安心する自分がいる。「ちゃんと働いてる証拠だ」と言い聞かせる癖がついてしまっている。でもそれは、ただ単に“疲れていることに気づかなくなっただけ”なのだ。かつての自分なら休んでいたであろう場面でも、今の僕はただ無表情で作業を続けている。疲れに慣れるというのは、麻痺と紙一重だ。
「まだいける」と思ってる時が一番危ない
身体は正直だ。ちょっとした風邪が長引いたり、肩こりがひどくなったり、眠っても疲れが取れなかったり……サインはあちこちに出ているのに、「まだ大丈夫」と思ってしまう。でも、本当に危ないのは、その「まだ大丈夫」が口癖になった時だ。限界は、ある日突然やってくるんじゃなくて、じわじわと忍び寄ってくる。ボールペンのインクがある日突然なくなるように。
事務員一人では回らない現実
うちの事務所は、僕と事務員さんの二人だけ。仕事のピークが重なると、どうしても手が足りない。「もう一人雇ったほうがいいんじゃないか」と思うこともあるけれど、経費のことや人材育成の負担を考えると、なかなか踏み切れない。結局、自分がやった方が早いという思考になってしまい、また心がすり減っていく。
人を増やせば楽になるのかという迷い
仮に人を増やしたとしても、ちゃんと育てる余裕がなければ意味がない。書類の処理ひとつとっても、専門的な判断が必要な場面が多い。教える側がバテてしまえば、ミスの連鎖が起きる。だから、「今はまだ耐える時期だ」と自分に言い聞かせてしまう。でも、それは言い訳であり、逃げでもあるのかもしれない。ボールペンと一緒に、自分の限界も静かに近づいているのに。
教える手間と抱えるストレスの板挟み
「人に任せるより自分でやった方が早い」――これは中小事務所あるあるだと思う。任せて失敗されてやり直すくらいなら、最初から自分でやる。その方がミスも少ないし、精神的にも楽だ。でも、その考えは長期的には自分の首を絞めている。ずっと走り続けるわけにはいかない。ボールペンだって、替え芯がなければ書けなくなる。
孤独と疲労とそれでも残るやりがい
疲れていても、やっぱり「ありがとう」と言われると心が少しだけ軽くなる。独立して良かったと思える瞬間もある。人の人生の節目に関われるこの仕事には、たしかに意味がある。だからこそ、心が削れながらも、僕はペンを走らせ続けている。
「ありがとう」が心に染みた日
相続登記を終えた高齢の依頼者が、手を合わせて深々と頭を下げてくれたことがあった。「これでようやく兄に顔向けできます」と笑ってくれた時、思わず涙が出そうになった。書類という“無機質な作業”が、人の心を救うことがあるんだと実感した。報酬よりも、こうした言葉が支えになっている。
役に立てた実感が救いになる
毎日がしんどい。それは間違いない。でも、誰かの役に立てた実感が、僕の中にかすかに灯をともしてくれる。その灯がある限り、僕はペンを持ち続けるだろう。どれだけインクが減っても、心が完全に擦り切れる前に、誰かの言葉が僕を立ち止まらせてくれる。
元野球部の僕が仕事で学んだ持久戦の意味
高校時代、炎天下で走り込みをしていた頃を思い出す。あの頃は、苦しくても声を出して乗り切っていた。でも今は声を出す相手もいない。ただ静かに、じっと、ひとりで耐える毎日。でも、踏ん張り続けることでしか見えない景色もある。きっとそれは、あの頃と同じだ。
声を出して乗り切れた学生時代との違い
部活では、声を出せば仲間が応えてくれた。今は、声を出しても誰も返してはくれない。そんな孤独に耐える力は、あの頃の僕にはなかったかもしれない。でも、今は少し違う。孤独を受け入れて、それでも進むことに慣れてきた。そういう意味では、司法書士という仕事も、持久走に近いのかもしれない。
無言で耐える社会人のしんどさ
誰にも頼れず、相談する余裕もなく、黙って耐えるしかない場面が多い。でも、無言で過ごす時間の中で、自分と向き合うこともできる。書類の文字に感情をのせないようにしているけれど、僕の心のどこかには、まだ熱が残っている。ペンを持ち続ける理由、それだけは忘れたくないと思っている。