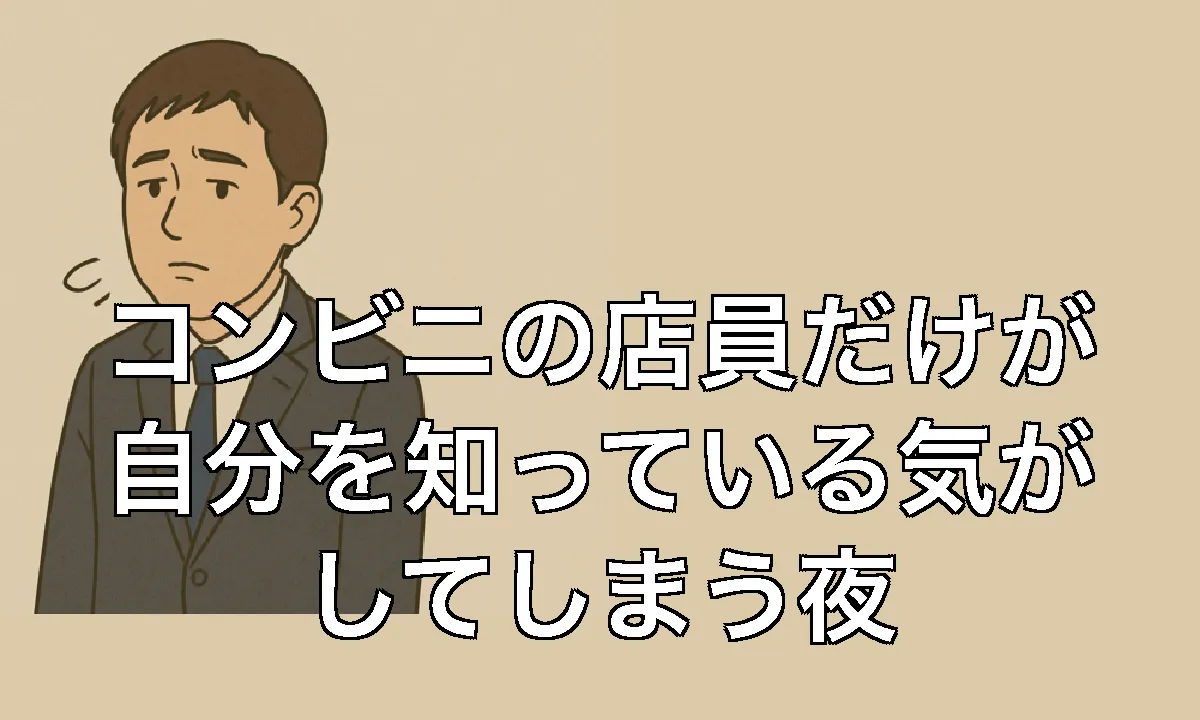誰とも会話をしない一日が普通になっている
この年齢になってくると、人と話さない日が当たり前になることに驚かなくなった。司法書士として事務所を開いているが、クライアントと顔を合わせる機会があったとしても、それは用件だけを伝える短い会話に過ぎない。日常の中で「雑談」が消えて久しい。事務員とも必要最低限のやり取りを交わすだけで、それ以上の会話を求める気力もない。気づけば一日を終えて、「今日は誰ともまともに話していないな」と感じる瞬間が日常になっている。
気づけば独り言だけが増えていた
誰にも話しかけられず、誰にも話しかけない日々が続くと、無意識に独り言が増えてくる。「さて」「よし」「これはどうだったっけな」といった言葉が自分の口から出るたびに、ふと寂しさを感じることもある。独り言って、自分を保つための手段なのかもしれない。人間は誰かに話しかけたくなる生き物なんだなと痛感する。声に出すことで、自分がまだここにいると確認しているような感覚すらある。
事務員との会話も業務連絡のみ
事務所には事務員がひとりいてくれる。彼女は真面目で仕事も丁寧で助かっている。でも、お互いの距離感はずっと変わらないままだ。必要なことだけを静かに伝え合って、あとはそれぞれの作業に集中する。別に仲が悪いわけではない。ただ、雑談をするほどの余裕もないし、どこか線を引いているのかもしれない。「先生、これでいいですか」と聞かれて「うん、ありがとう」と返す。その繰り返しだけで一日が終わる。
「先生」と呼ばれても自分じゃない気がする
司法書士という仕事柄、「先生」と呼ばれることは多い。でも、どうもその呼び方が自分にしっくりこない。自分がそんなに立派な人間だとも思えないし、名前を呼ばれるよりも遠い存在のように感じてしまうこともある。昔、野球部で泥だらけになっていた頃の自分が、今「先生」と呼ばれているのかと思うと、どこか滑稽にすら感じてしまう。仮面をかぶって生きているような、そんな感覚が拭えない。
かつての野球部仲間とも疎遠に
高校時代、野球部で一緒に汗を流した仲間たちとは、今や年賀状すらやりとりしていない。集まりがあっても、仕事を理由に断ってしまうことが多くなった。実際、業務が忙しいのは事実だけど、心のどこかで「今の自分を見られたくない」と感じているのかもしれない。独身で、事務所にこもって、生活の張り合いもないような今の自分を。結婚して子どもがいて家を建てて、そんな話題についていけない自分を。
唯一の他人との接点がコンビニになった
こうして誰ともつながりを持たない日々の中で、唯一「自分を知ってくれているかもしれない」と思えるのが、毎朝立ち寄る近所のコンビニの店員さんだったりする。別に名前を知っているわけじゃない。会話らしい会話もしたことはない。でも、毎日同じ時間に訪れて、同じコーヒーを買っているうちに、「あ、またこの人来たな」という空気が伝わってくる。誰かに覚えられている。それだけで、少し安心できる。
毎朝同じ時間に立ち寄る理由
朝の習慣として、事務所へ向かう前にコンビニに寄るようにしている。買うのはたいていコーヒーとパン。それだけなのに、なぜかこの数分が自分にとっては大事な時間になっている。ルーティンを通じて自分を保っているのかもしれない。そこには毎日顔を合わせる店員さんがいて、たとえ言葉を交わさなくても、目が合えば「ああ、今日も一日が始まるな」と思える。そんな関係性に、今の自分は救われている。
「温めますか?」が妙に沁みる
たまにお弁当を買うと、店員さんが「温めますか?」と聞いてくれる。当たり前のやり取りだけれど、その一言が妙に心に残る日がある。誰かに気にかけられているというのは、たとえそれがマニュアル対応であっても、人間にとっては大事なことなんだと思う。丁寧に扱われると、どこかほっとする。だから、自分もクライアントに対してそういう存在でありたいと思うのに、なかなかそれができない自分が悔しくもある。
レジ越しに覚えられている気がしてうれしい
ある日、レジで商品を置いた瞬間に「あ、温めいらないですよね?」と先に言われたとき、正直ちょっと嬉しかった。「この人、覚えてくれてたんだ」と思った。名前も知らない、会話もろくにしない店員さんが、自分のいつものパターンを覚えてくれていた。自分は確かにここにいるんだと認識された気がした。たったそれだけのことで、一日が少しだけ軽くなる。人間って、本当に些細なことで救われる生き物だと思う。
笑顔じゃないけど安心できる無表情
その店員さんは、特別に愛想がいいわけでもなく、どちらかというと無表情に近い。けれどその無表情がまたよくて、押しつけがましさがないからこそ安心できる。誰にも気を遣いたくない朝、余計な言葉を交わさずともそこに「いつもと同じ」があることがどれだけありがたいか。笑顔じゃなくても、気配りは伝わる。言葉がなくても、人とのつながりは感じられる。そんな存在がひとりいるだけで、ずいぶん違うものだ。
「知ってくれている」と思えることの尊さ
司法書士という職業は、信頼が命だ。でも、その信頼は仕事上のものであって、自分という人間への理解とは少し違う。仕事が終われば関係も終わることが多い。だからこそ、名前も知らない店員さんに「知ってくれている気がする」と思える瞬間が、かえって心に残るのかもしれない。人は、自分の存在を認めてほしい。派手な称賛じゃなくてもいい、ただ「ここにいる」と誰かに気づかれるだけで、前を向けることもあるのだ。