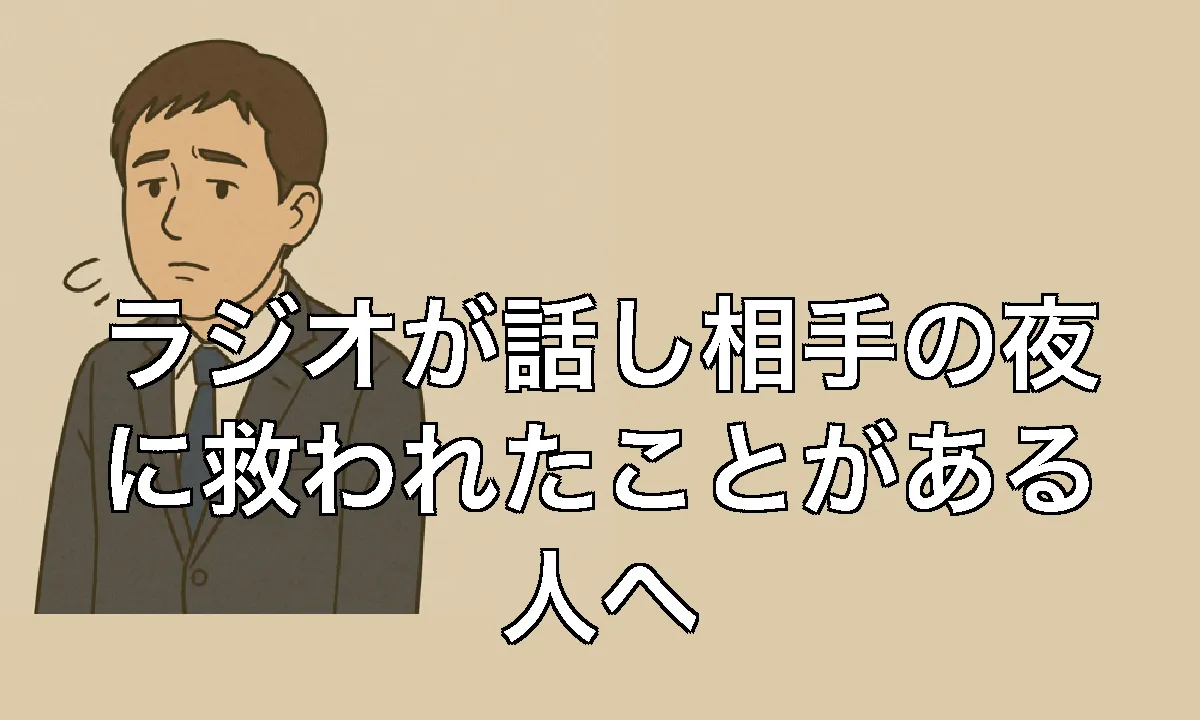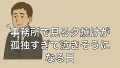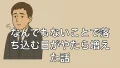誰とも話さない日々に声が届くという奇跡
地方で司法書士をしていると、想像以上に人と話さない日がある。相談の電話がない、来所予約もない、郵便とメールで業務が完結してしまう。朝から晩まで、まともな会話が一つもないまま一日が終わることもある。そんな日は、心の中で誰かに「今日も終わったよ」と呟いて、静かに帰宅する。ふとスイッチを入れたラジオから聞こえる何気ない声。それが胸に染みて、少しだけ涙がにじんだことがある。会話じゃないけれど、「声が届く」だけで、心が少しほぐれる夜があるのだ。
朝から晩まで無言のまま終わる一日
日報を書いていると、自分が何をしていたか整理できる。でも、誰とも言葉を交わしていないことに改めて気づく瞬間がある。黙々と書類と向き合い、登記のチェックをし、印鑑の位置を直す。気づけば、夕方。唯一交わした言葉が事務員さんへの「おつかれさま」だけという日もある。別に誰かと喧嘩したわけでもない。誰にも嫌われたわけでもない。ただ、ただ、言葉の往来がないだけで、人はこんなにも孤独になれるのかと驚く。
電話が鳴らないと少しホッとしてしまう
おかしな話だけど、電話が鳴らないとホッとする。急ぎの案件や面倒な依頼が増えるかもしれないから。でも一方で、誰にも必要とされていない気がして、しんとした事務所の空気がやけに冷たく感じる時もある。昔はクライアントとの会話に緊張もしていたが、今はその緊張すら恋しい。人と話す機会がないことに慣れてしまうと、それを取り戻すのは案外難しいのだ。
郵便受けの音すら誰かの気配に思えてしまう
夕方、ガサッと郵便物が届いた音がすると、思わず「誰か来た?」と身を乗り出してしまう。もちろん人じゃない。封筒が落ちただけ。でも、無意識に「誰か」と接点を持ちたがっている自分がいる。独身の司法書士にとって、仕事以外の接点は本当に少ない。そのせいか、わずかな物音にも過敏になる。たった一通の郵便すら、孤独な日々の証明になることがある。
そんな日にラジオの声が心にしみる
帰りの車で何気なくつけたラジオ。何を話していたかなんて覚えていない。でも、「こんばんは」という声に救われた。誰かが生きている、誰かが今、言葉を発している。その事実に安心する。司法書士の仕事は「無音の信頼」で成り立っているようなもの。だからこそ、無意味なようで意味のある「雑談」が、心に灯をともしてくれるのだ。
話しかけられている気がするだけで少し救われる
人間って不思議なもので、たとえこちらの名前を知らない相手でも、話しかけられているように感じるだけで孤独感が和らぐ。ラジオのパーソナリティが話す一言一言が、まるで旧友との会話のように聞こえることがある。それがたとえ録音であっても、深夜の静けさの中でふと耳に入る言葉は、思いがけず胸を打つのだ。
パーソナリティのどうでもいい話がちょうどいい
「きのうスーパーでレジ打ちのおばちゃんとケンカしちゃってさ」――そんな話がちょうどいい。相談でもなければ意見交換でもない。ただの独り言のような雑談。でも、その温度が心地よい。仕事で使う言葉は、どうしても目的ありきのものが多い。会話すら契約の一部になってしまう。だからこそ、なんの意味もないような話が、まるで心を撫でてくれるように感じられる。
こちらの名前は呼ばれないのになぜか嬉しい
当たり前だが、ラジオのパーソナリティはこちらの名前など知らない。それでも「あなたの一日、おつかれさま」という一言に、胸がいっぱいになる。名前なんていらない。言葉の輪郭が、心に届けばそれで十分なのだ。司法書士として、名前の正確性や肩書きに日々敏感になっているからこそ、匿名の癒しに、妙な安心感を覚えるのかもしれない。
ひとりごとのように返事をしてしまう夜
気づけば、「そうそう」とか「わかる〜」と声に出してしまっている夜がある。誰もいない部屋で、ラジオに返事をしている自分にハッとする。でも、それでいいのだと思う。声を出すこと自体が、心のバランスを保つ手段なのかもしれない。寂しさは、無言でいると増幅する。だからこそ、ひとりでも「声」を出すことが、立ち止まらずに生きる術になるのだ。
司法書士という職業の声のなさ
法律書類を扱う職業である司法書士は、正確さと慎重さが何よりも求められる。それゆえに、無駄な会話や軽口が許されない場面が多い。人と関わっているようで、心までは交わらない仕事。それがこの仕事の、やりがいであり、孤独さでもある。ラジオのような気軽な声とは、対極にある世界だと感じることもある。
ありがとうよりも無言の判子が多い仕事
仕事の成果が「ありがとうございました」ではなく、「印鑑を押されること」で完結することが多い。信頼を得た結果なのに、言葉ではほとんど返ってこない。契約書に印が押された瞬間、それはたしかに仕事の証だ。でも、やはり人間としては、言葉が欲しくなる。たとえそれが「大変でしたね」の一言でも、心は少し救われるのだから。
たまにある感謝の言葉が妙に響いてしまう
ごく稀に、依頼者が「本当に助かりました」と言ってくださることがある。その瞬間、自分の中の何かが崩れ落ちそうになる。無音に慣れすぎた体が、その言葉を全身で受け止めてしまうのだ。涙ぐみそうになるのをぐっと堪えて、「こちらこそ」と返す。言葉って、やっぱり偉大だ。
人と接しているはずなのに会話が少ない
司法書士は、対人の仕事だと思われがちだ。でも実際には、顔を合わせても形式的なやり取りで終わることが多い。世間話をしている暇もなく、淡々と進める方が信頼につながるからだろう。だからこそ、仕事が終わったあとにラジオを聴くと、そのゆるさが心の隙間をちょうどよく埋めてくれるのだ。
誰かと繋がっていたい気持ちは隠せない
一人の時間が長いと、自分自身と向き合うことが増える。けれど、人間はやっぱり、誰かと繋がっていたい生き物なのだと実感する。たとえその「誰か」が、声だけの存在でも。司法書士という仕事は孤独を伴う。だからこそ、その孤独を少しでも紛らわせる存在が必要なのだ。
仕事帰りの車で聴くラジオが唯一の癒し
夜の事務所を閉め、エンジンをかける。カーラジオのスイッチを入れると、見知らぬ誰かの声が流れてくる。仕事のミス、疲れ、人間関係の悩み――すべてを少しだけ横に置いて、「この声を聞いていればなんとかなる」と思える。そんな日がある。どれだけ忙しくても、この時間があるからまた明日を迎えられる。
話しかけられないまま終わる日を避けたいだけ
声をかけられないまま、誰とも話さずに一日を終えるのが怖い。だからラジオをつける。声があるだけで、自分が存在していることを確認できる。そんな自分に「弱いなあ」と思いつつも、そうでもしないと潰れてしまいそうな夜があるのだ。司法書士も、ただの人間だということを忘れてはいけない。
司法書士を目指す人へ伝えたいこと
もし、これから司法書士を目指そうとしている人がいるなら、この「声のない仕事」の側面も知っておいてほしい。華やかに見える部分の裏には、静かで孤独な時間がある。その時間をどう乗り越えるか、自分なりの支えを持つことが大切だ。ラジオでも、本でも、犬でも猫でもいい。自分を保つ手段を、あらかじめ用意しておくことが、長く続けるコツかもしれない。
孤独な時間とどう向き合うかが大事
孤独と向き合うには覚悟がいる。でも逃げずにちゃんと向き合えたら、案外悪いものでもない。自分の声を聴けるようになるし、人の声の温かさにも敏感になる。ラジオはその練習台だ。向こうの声に耳を傾けることで、自分の声も育っていく。孤独を悪者にせず、自分の味方に変える。司法書士に必要なのは、そんな強さと優しさかもしれない。
人と話せる場所を意識して作っておくこと
意外と盲点なのが「話せる場所の確保」だ。カフェでもジムでも、月に一度行くだけの習い事でもいい。司法書士という仕事は、自分で孤独にしてしまいやすいからこそ、意識的に外と繋がる場を作っておくことが必要だ。人の声を聴くことは、自分の心を整える行為でもある。放っておくと、どこかで限界が来る。
声は情報じゃなく存在の証明になる
声は、単なる情報伝達手段ではない。そこに誰かがいて、自分に向けて言葉を発している。それだけで人は救われる。司法書士は、日々文字や書類と格闘している。でも、ときには声を発すること、声を受け取ることが、自分の存在を肯定してくれる。ラジオの声がそれを教えてくれた。