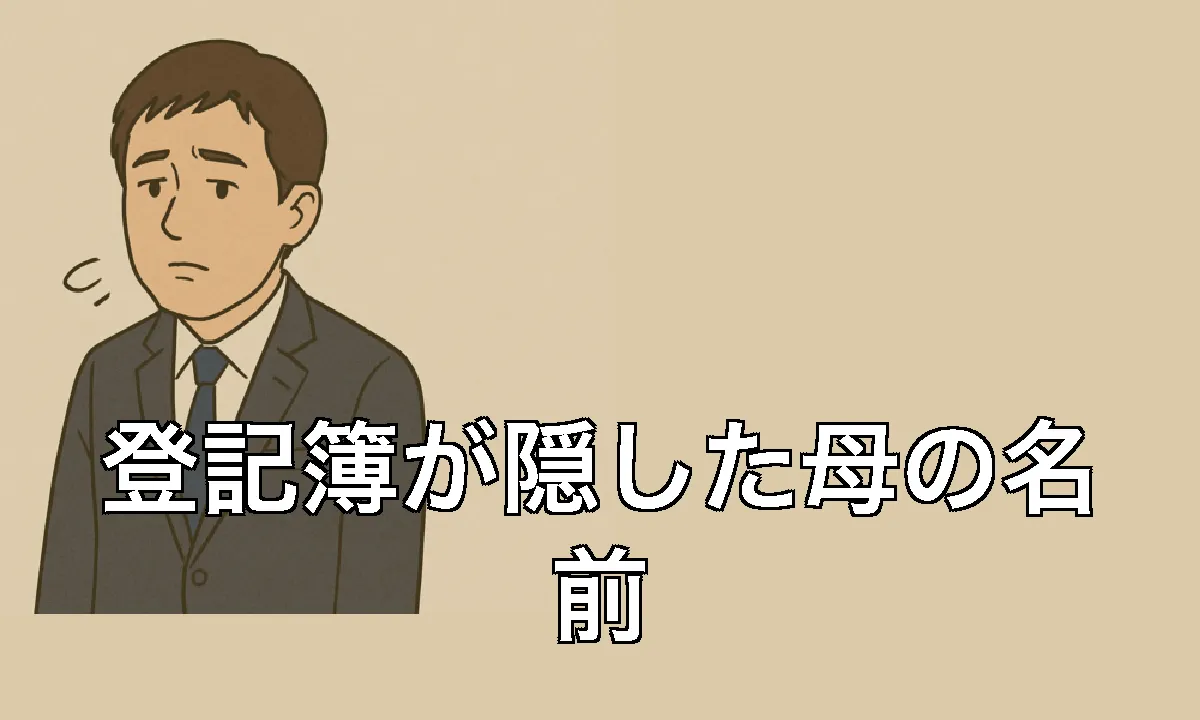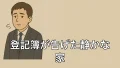はじまりは一本の電話だった
昼過ぎの事務所に、静かに電話のベルが鳴った。受話器を取ると、女性の震える声が聞こえた。「母の名義であるはずの家が、知らない名前で登記されているんです」。
よくある相続のトラブルかと思ったが、声の奥に含まれた一抹の不安が、なぜか耳に引っかかった。
電話の主は、若い女性だった。登記簿の内容を調べてほしいとの依頼だった。
依頼人は蒼ざめた様子でやってきた
翌朝、彼女は事務所に現れた。黒髪をひとつに結び、喪服のような黒いスーツに身を包んでいた。顔色は悪く、まるで何かに怯えているようだった。
「この住所の家、もともと母が住んでいたんです。でも登記簿を取ったら、まったく知らない男性の名義だったんです」
不動産の所有権が他人に移っているという話は珍しくない。しかし、彼女の目は、ただの名義ミスでは済まされない何かを訴えていた。
名義変更が語る不可解な点
登記簿を確認すると、確かにそこには数年前の売買による名義変更の記録が残っていた。しかし、売主とされているのは、依頼人の母とは別人の名義。
つまり、誰かが「所有者」として売却した形になっている。しかし依頼人によれば、母は認知症を患っており、そのような契約ができるはずがないという。
この時点で、登記簿上の記載と実情に明らかな乖離があった。
古い家の登記簿が示す違和感
私は法務局へ足を運び、家の過去の所有履歴をすべて洗い出した。最初の登記は昭和58年。売買の履歴も2回しかなく、一見すると不自然さはなかった。
だが、私が気になったのは、ある一件の「住所」だった。売主の住所が依頼人の母の旧住所と一致していたのだ。
つまり、登記上は他人の名義だが、住所だけは母のものと一致していたのだ。
明らかにおかしい売買履歴
もっと調べると、契約書の控えが出てきた。そこには署名と押印があるが、署名された名前と印影の筆跡が不自然だった。
私は思わず目を細めた。これ、もしかして……誰かが母の名を使って勝手に売買を行った可能性がある。
まるで、サザエさんに出てくるノリスケおじさんがまた余計なことをして波平に怒られるような、そんな無責任さが漂っていた。
住所が残していた奇妙な一致
さらに調査を進めると、かつてその家に住んでいた別の家族の名前が出てきた。売主とされる男は、その家の長男だった。
だが、依頼人の母とは無関係なはずである。なのに、いつの間にか彼が「家の名義人」として登録されていた。
いわば、他人の家を勝手に売ったのと同じである。
サトウさんが気づいた家系図の矛盾
事務所に戻ると、サトウさんがパソコンの前で眉をひそめていた。「この人、依頼人の母の戸籍には載ってませんが、父の方には…あ、やっぱりいました」
「え?」と聞き返すと、サトウさんは淡々と答えた。「依頼人のお母さん、実は一度結婚して養子を迎えてます。で、すぐに離婚してるみたいです」
つまり、依頼人の知らない“兄”が存在していたのだ。
法務局で見つけたもう一つの名義
調べ直すと、養子縁組がなされた後、家の登記名義がその養子へと移っていた。正式な登記移転だった。依頼人の母も署名していた。
ただし、その当時、母は既に軽度の認知症を患っていた可能性がある。
つまり、法的には問題なくとも、倫理的にはかなりグレーな移転だったのだ。
母親の名が消えていた理由
それからの数年で、母は老人ホームへ入所し、家は売却された。すべては“長男”である養子の判断だった。
依頼人は知らなかったが、法的には長男にも決定権があった。そのため、彼女が何も知らないまま家を失っていたのだ。
やれやれ、、、登記簿ってやつは、人の想いまで記してはくれない。
現れた元所有者の証言
私は養子となっていた男性に面会を申し込んだ。彼は意外にも快く応じてくれた。
「母さんとは疎遠でしたが、あの家は…俺が子どもの頃から住んでた家です。どうしても手放したくなかった」
それが彼の正直な気持ちだった。しかしその裏で、妹となる依頼人の存在が完全に無視されていた。
口を閉ざしていた老人の真実
ホームにいる母親にも会いに行ったが、もう言葉を発することはできなかった。
ただ、枕元に置かれた古びた写真立てには、幼い子どもがふたり映っていた。
その片方が依頼人で、もう一人が件の養子だった。
戦後の混乱期に交わされた契約
登記簿の奥には、昭和の終わりに取り交わされた古い公正証書の記録があった。養子縁組の詳細と、名義移転の覚書も含まれていた。
当時の価値観、家を守るという意識、それらが今の混乱を生み出していた。
結局のところ、全ては過去の“善意”が引き起こした悲劇だったのかもしれない。
相続の闇と隠された養子縁組
養子の存在を知らされなかった依頼人。だが、戸籍上はすべてが合法。彼女には所有権の主張はできなかった。
「せめて、ひとことあればよかったのに…」依頼人の言葉が重く響いた。
相続というものは、法と感情のはざまで揺れ続ける。
相続放棄が導いたもう一つの選択
依頼人は母の相続を放棄していた。それがさらに彼女を不利にした。だが、それも知らされていなかった。
すべては養子によって手続きが進められていたのだ。
私は「これは確信犯だな」と思ったが、証明はできなかった。
兄と名乗る男の正体
最終的に、その男は「母の看取りをしたのは自分だ」とだけ語った。
たとえ名義を得るための動機があったとしても、母と共にいたのは彼だった。
彼女の涙と、彼の沈黙が、すべてを語っていた。
登記ミスか故意か
私は最後に、登記内容の形式面を再チェックした。法的にはどれも整っていた。
おそらくこれは、法の網をくぐり抜けた“計画的な移転”だろう。
けれども、それを証明する手段は、すでに失われていた。
司法書士として見逃せない事実
登記簿に書かれていることが、常に真実とは限らない。
だが、我々はその“書かれていること”でしか仕事ができない。
それが、司法書士という職業のジレンマだ。
過去の登記簿が握る鍵
昭和の登記簿をめくると、ボロボロになった記録が現れる。そこに記された「家族」の痕跡。
それは確かにあったのだ。
けれども今、その記録は、未来を救う鍵にはならなかった。
一枚の古い手紙が語る真相
事務所に戻った私を、サトウさんが無言で封筒一通手渡した。
「家の物入れから見つけたそうです」とだけ言って、またPCに目を戻した。
手紙は、母が娘に宛てて書いた、未投函のものだった。
封筒に残された旧姓の印
封筒には、旧姓の判が押されていた。内容はこうだった。「あの子も、あなたの兄よ。怒らないであげて」
苦しい選択の末、彼女は二人の子を守ろうとしていたのだろう。
それが、皮肉にも争いの火種になったのだ。
母が守りたかった家族の形
母にとって、家とは血よりも深い想いの象徴だったのかもしれない。
けれども、法の世界では“想い”だけでは通用しない。
それが、この事件の根幹だった。
サトウさんの冷静な推理
私はため息をついた。「結局、何もできなかったな」
サトウさんはいつも通り、塩対応で言った。「でも、少なくとも本当のことはわかったじゃないですか」
やれやれ、、、ほんとに、この子には敵わない。
血縁よりも強い何か
依頼人は涙ながらに、手紙をそっと鞄にしまった。
「母がそう思ってたなら、それで十分です」
彼女の中では、もう答えが出ていたようだった。
やれやれ、、、まさかこんな結末とは
帰り道、私は空を見上げた。曇り空のすき間から、少しだけ光が差していた。
やれやれ、、、登記簿一つでここまで人生が揺れるとは、ほんと、皮肉なもんだ。
でもまあ、最後に救われた顔が見られただけ、よしとするか。
事件の終わりと始まり
今回の件は、事件ではない。ただの「家族の記録」だ。
だが、司法書士として、それを解きほぐすこともまた、ひとつの使命かもしれない。
次の電話が鳴るまで、少しだけ休ませてくれ。
依頼人が涙した一通の通知
数日後、彼女から礼状が届いた。「家のこと、全部わかってよかったです」
それは、司法書士として初めて“感謝された”気がする瞬間だった。
そして私は、また静かに次の登記簿を開いた。
司法書士としての静かな決意
登記簿には名前と数字しか書かれていない。
でもその裏には、数えきれない人生がある。
だから私は、今日もその“無味乾燥な帳面”に向かい続ける。