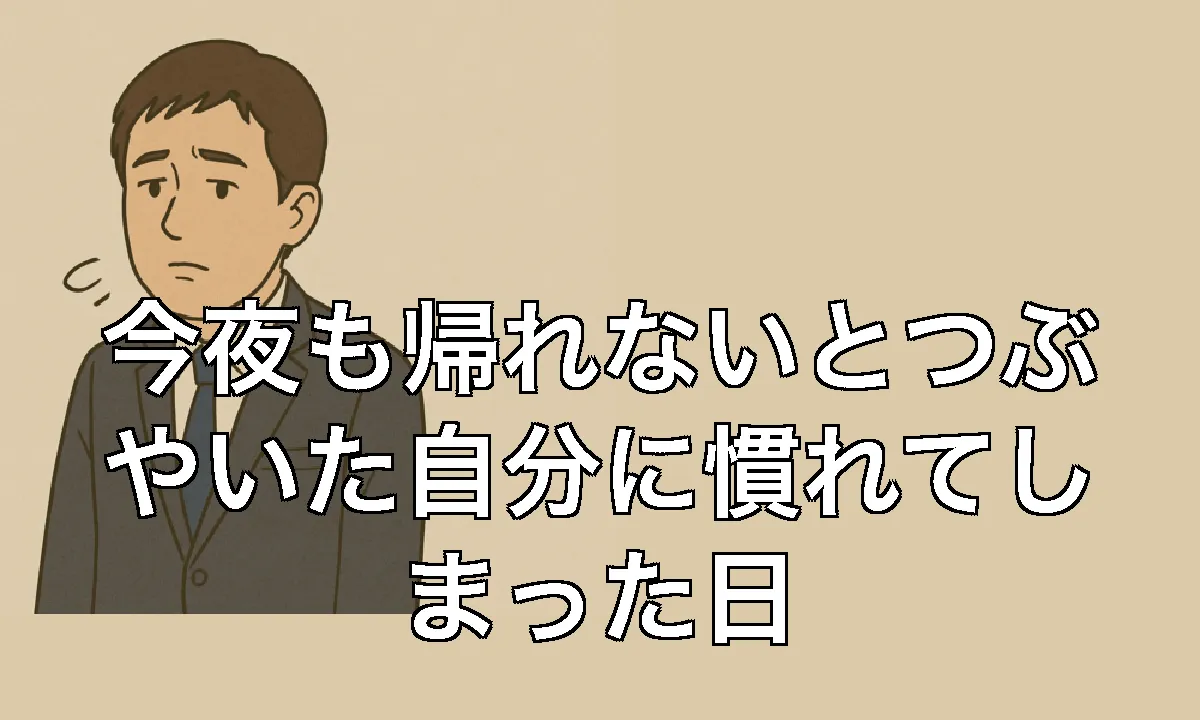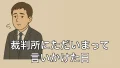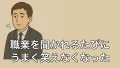帰れない夜が日常になったという現実
昔は「今日は遅くなったな」と思う日が月に何回かある程度だった。ところが今では「今日は早く帰れるかも」と思うことが年に数回レベルになった。気づけば、帰れないことが特別ではなくなり、残業に対する違和感も薄れてしまった。自分の中で“異常”が“日常”になってしまったことに、ふとした瞬間にゾッとする。けれど、それに慣れてしまった自分が、いちばん恐ろしいのかもしれない。
あの日までは帰ることが前提だった
最初に事務所を構えたとき、業務が終われば当然帰宅するものだと思っていた。あの頃はまだ、夜は自分の時間だった。食事をしたり、趣味の野球中継を観たり、家にいる意味がちゃんとあった。でも、登記の依頼が増えてくると、次第に「もう少しだけやってから帰ろう」が積み重なり、気がつけば終電後まで仕事をしていることが普通になった。帰る前提の生活は、いつの間にか消えていた。
「じゃあ今日はこのへんで」と言えた頃
事務員と一緒に「お疲れさまでした」と言い合って帰った日々が懐かしい。お互いに疲れていても、ちゃんと区切りをつけて帰っていた。今は事務員には先に帰ってもらって、自分はもう一踏ん張り、が定番になった。自分でそういう働き方を選んでるつもりはなかったのに、結果的にそうなっていた。「もう終わりにしよう」と自分に言うのが、だんだん難しくなっていった。
机の上に積まれた書類が増えたきっかけ
ある年の3月、相続の案件が集中して、事務所の机が書類の山になった。そのとき初めて「これは夜までやらないと終わらない」と本気で思った。あれ以降、繁忙期が過ぎても「夜に処理する」がクセになり、日中の面談や電話対応、行政とのやりとりをこなすだけでいっぱいいっぱい。書類と格闘するのは、もっぱら夜になってしまった。時間帯が逆転しても、誰も気づかないのが司法書士の仕事の孤独さだ。
終わらない業務に終電は関係ない
電車の時刻表が自分のスケジュールから外れたのはいつからだろう。今では「終電を気にして帰る」こと自体が贅沢に思える。車通勤であることも拍車をかけている。「終電がないから帰る」ではなく、「まだ車があるからもう少しやるか」となってしまう。時計を見ても、もう夜中の1時。それでも「あと一件だけ」などと自分に言い聞かせる夜は、いつも同じ匂いがする。
登記情報もPCも待ってくれない
登記情報提供サービスが24時間使えることは、便利でもあり、地獄でもある。「今のうちに確認しておこう」と思ったが最後、深夜に入力作業が始まる。作業が一つ片付けば、また一つタスクが湧いてくるような気がする。PCの光は優しいようで残酷で、照らされているうちは“帰れない理由”がずっと続く。昼と夜の境界線が、モニターの中では曖昧だ。
事務員に帰っていいよと言いながら自分は残る
うちの事務員は気が利く。忙しそうにしている自分を見て、無理に残ろうとする。でも「いいよ、もう帰って」と言うのが自分の役目だと思っている。問題はその後。誰もいない事務所で、静かに仕事を続ける。パチパチとキーボードを叩く音だけが響く。これがいつの間にか習慣になった。寂しいという感情よりも、麻痺の方が勝ってしまっている。
家という場所がただの寝床になった
昔は「帰る」という行為に意味があった。自宅は自分を休める場所であり、明日への活力をチャージする場所だった。でも、今の自宅は“寝るだけの場所”になってしまった。着替えとシャワーと仮眠だけが機能している空間。もはや「生活の場」とは呼べない。家賃を払っているのに、滞在時間はネットカフェ以下かもしれない。
誰もいない部屋に帰る意味を失う
独身であることを言い訳にしていた部分もある。「どうせ誰も待ってないし」と思えば、帰る必要も感じない。でも、それは逃げだったのかもしれない。誰もいない部屋は、最初は自由に感じた。でも今は、何の音もない空間が不安になることがある。家に帰ることが義務にならない代わりに、心の拠り所でもなくなってしまった。
消えていく「おかえり」という言葉の存在感
「おかえり」と言われなくなって久しい。実家にいた頃は、たとえ遅くなっても親がそう言ってくれた。今では誰もその言葉を口にしない。たまにテレビドラマで耳にすると、胸の奥がチクリと痛む。言葉一つがこれほどまでに人を支えていたのかと気づかされる。自分で自分に「おかえり」と言ってみたこともあるが、空しさだけが残った。
部屋着より先にスーツに袖を通す朝
朝起きて最初にするのがメールチェック、その次にスーツを着る。歯も磨かず、コーヒーも飲まず、まず“戦闘モード”に入る。家で過ごす時間が短いせいか、リラックスする感覚を忘れてしまった。部屋着でのんびりすることに、罪悪感すら覚える。休むことに慣れていない自分が、どこかで壊れないか不安になる。
食事も会話も独り言で済ます生活
誰かと一緒に食事をする機会がほとんどない。昼も夜もコンビニで買って、デスクで済ませる日々。時々「あ、これうまいな」とつぶやくけれど、返事は返ってこない。当たり前だ。誰もいないのだから。でも、そんな独り言すら、ちょっとした人間らしさの表れなのかもしれない。
コンビニのレンジ音だけが生活音
夜中にコンビニに立ち寄ると、「チン」というレンジの音が妙に心に響く。あれが今の自分の“食事の合図”なのだと思うと、何だか情けなくなる。食卓を囲む習慣はとっくに失われていて、電子音と照明の白さが、今の自分の生活の象徴になっている。温められた弁当は、便利だけど温かみは少ない。
「温めますか」と聞かれなくなった距離感
顔を覚えられるほど通っているコンビニなのに、店員との会話は必要最低限。「温めますか?」さえ省略されることがある。効率重視の社会に慣れてしまったのか、自分の方から目を合わせなくなったせいか。人との距離が遠くなったのは、仕事のせいばかりではなく、自分自身の心の余裕のなさが原因かもしれない。
誰かと食べるご飯がこんなに恋しくなるとは
誰かと一緒に食べた記憶を思い出すと、今の孤独さが際立つ。大学時代、友人とラーメン屋で深夜に食べた一杯がやけに美味しかった記憶がある。味ではなく、誰かと会話を交わす時間が、あの味を特別にしていたのだと今になって気づく。一人飯が当たり前になった今、その「共有」が何よりも贅沢に思える。