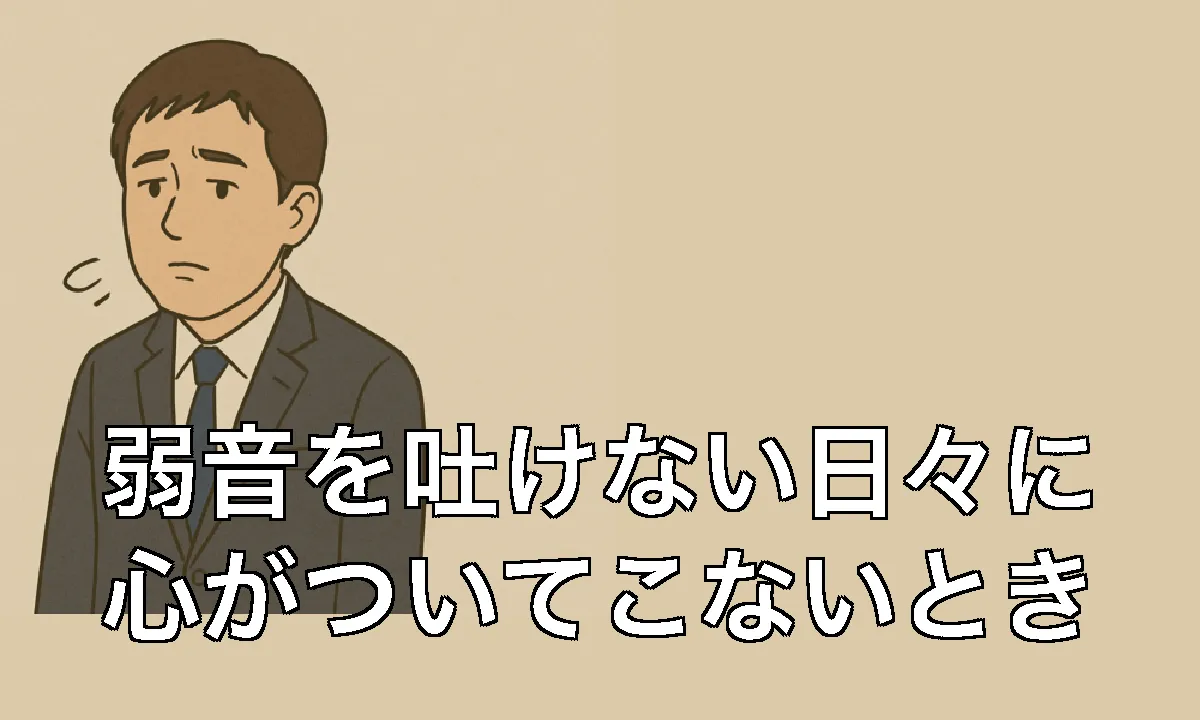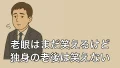一人で抱え込むことが癖になっている
「人に頼るのは甘えだ」と思い込んでしまったのは、いつからだっただろうか。若い頃、野球部でどれだけ体が痛くても「大丈夫です」と言って練習に出ていた癖が、今も抜けないのかもしれない。司法書士という仕事は、責任が重く、間違いが許されない。そんな中で、つい「自分がやらなきゃ」と背負い込みすぎてしまう。助けてと言えないまま、今日も疲れだけが溜まっていく。
誰にも頼れないのではなく頼らないだけ
事務所にいるのは自分と事務員一人。彼女に全部を任せるわけにもいかないし、こちらが不安や愚痴をこぼせば、かえって気を使わせてしまう。そんな思いから、「頼らない」ことを選んでしまう。でも実際には、周りが冷たいのではなく、こちらが勝手に壁を作っているのだと気づく。頼れないのではなく、頼らないようにしている自分に気づいた瞬間、少しだけ肩の力が抜けた気がした。
迷惑をかけたくないという優しさが裏目に出る
「迷惑をかけたくない」という気持ちは、一見すると思いやりのように見えるが、実は自分を苦しめる枷になることもある。たとえば、風邪気味の日でも無理に出勤し、誰にも言わずに仕事をこなす。そういう自分を「プロ意識がある」と思っていたけれど、本当はただの意地っ張りだったのかもしれない。少しだけ勇気を出して「今日は体調が悪い」と言ってみたら、案外すんなりと受け入れてもらえたこともある。
元野球部のクセでとにかく我慢が染みついている
「気合と根性」が正義だった昭和の野球部出身としては、とにかく我慢が美徳だった。水も飲まずに練習していたあの頃の習慣が、未だに心に残っているのだろう。痛みも疲れも、他人に見せるものではない。だから今でも、誰にも言わずに書類の山に向かう日々。でも、我慢が限界を超えると、突然動けなくなる。我慢は時に美しいが、放っておくと壊れる。そんなことに40代になってようやく気づいた。
平気なふりを続けていたら疲れてしまった
「平気そうですね」と言われることがある。それは嬉しいような、悲しいような。本当は全然平気じゃない。だけど、そう言われると「やっぱり弱音は見せない方がいいのか」と、さらに自分を抑えてしまう。弱音を吐かない自分は、一見すると強く見えるが、内側では静かに崩れている。平気なふりは、見た目だけの鎧だ。その鎧の下で、自分の心は今日も冷えている。
「大丈夫ですよ」と言いながら心がすり減る
「大丈夫ですよ」が口癖になってしまっている。電話の応対、役所とのやり取り、顧客への説明…どんなに予定が詰まっていても、「大丈夫です」と無理して笑う。でも夜、自宅に戻って一人になると、どっと疲れが押し寄せる。自分の心は大丈夫じゃなかったのに、無理をした代償だ。笑顔の裏で削れていくのは、心の余白だった。
事務所を守る責任感がプレッシャーになる
この事務所を畳んだら、もう次はない。そう思うと、どんな状況でも守りたくなる。赤字になった月も、すべて自分の責任だと感じていた。責任感があるのは悪くない。でも、それが過剰になるとプレッシャーに変わる。誰にも相談できず、数字を一人で睨みながら夜遅くまで残業する。守りたいはずの事務所に、逆に押し潰されそうになる瞬間がある。
事務員に心配をかけまいとさらに無理を重ねる
事務員は一生懸命頑張ってくれている。だからこそ、自分の弱さを見せることができない。「先生が元気でいないと、この事務所回りませんからね」なんて冗談っぽく言われたとき、本当は胸がぎゅっと締め付けられた。心配をかけたくない、そんな気持ちがまた新たな無理を呼ぶ。何気ないやさしさが、時には重荷になることもある。でもそれを責めることはできないから、また一人で抱え込んでしまうのだ。
言葉にできない疲れがたまる瞬間
「疲れた」の一言が言えたらどんなに楽だろう。けれど、その一言さえも口に出せない日が続く。いつのまにか、疲労は心の底に沈殿していく。誰にもぶつけられない感情が溜まっていき、ある日突然涙が出る。理由なんて分からない。ただ、限界だったのだ。
電話を切ったあとにどっとくる虚しさ
一件の登記を終えて、お客様と電話を切った直後、「ふぅ」と深いため息が出る。無事に終わってよかったはずなのに、どこか満たされない感覚が残る。「誰かに褒められたい」「労ってほしい」そんな感情が、ふと顔を出す。でも、それを言葉にする場所がない。電話が鳴り続ける限り、こなすしかない日々の中で、自分の存在が薄くなっていく感覚に襲われる。
登記の書類を眺めながらため息だけが増える
机に山積みになった書類を前に、「またか」と思う。同じような手続き、同じような書類、変わらないルーティン。効率よくやろうとしても、書き損じやミスを防ぐには神経をすり減らす必要がある。疲れていても、一文字一文字に気を配らなければならない。そんな中で、ふと「この仕事、いつまで続けられるんだろう」と不安がよぎる。ため息が、答えを濁していく。
心の中で誰かに助けてくれと言っている自分がいる
誰にも言わず、何も見せず、それでも心の中では「助けてくれ」と叫んでいる自分がいる。だけど、それを声に出せない。声に出した瞬間、崩れてしまいそうで怖いのだ。助けを求めることは、恥ではない。でもその一歩が踏み出せない。だから、ただ机に向かって黙々と仕事をする。その姿を見て、誰もが「頼れる先生ですね」と言ってくれる。でも、その言葉が少しだけ切ない。
弱音を吐くことは甘えじゃないと気づけるまで
「弱音を吐いたら負け」そんな思い込みが、ずっと自分を縛ってきた。でも今思えば、それは間違いだったかもしれない。誰かに話すことで、心が少し軽くなることもある。それを知ったのは、ほんのささいなきっかけだった。
愚痴を言える相手がいないことの孤独
飲みに行く友人も減り、休日は一人で過ごすことが多くなった。「話し相手がいない」ことの寂しさは、想像以上にこたえる。たわいもない愚痴を言えるだけで、こんなにも楽になるのかと、久しぶりに高校の同級生と再会したときに思い知らされた。話すことで、自分が人間らしく戻っていく感覚があった。
一言「しんどい」と言える場を持つ大切さ
「しんどい」と言ってもいい場所。「それは大変だったね」と返ってくる安心感。そんな場が一つでもあるだけで、人はずいぶん救われる。司法書士という立場上、常に冷静でいなければならない気がしていたけれど、誰かに甘えることができる瞬間もまた、人として大事なのだと思う。これからは、弱音を吐く練習を少しずつしていきたい。完璧じゃない自分を、少しずつ認めていきたい。