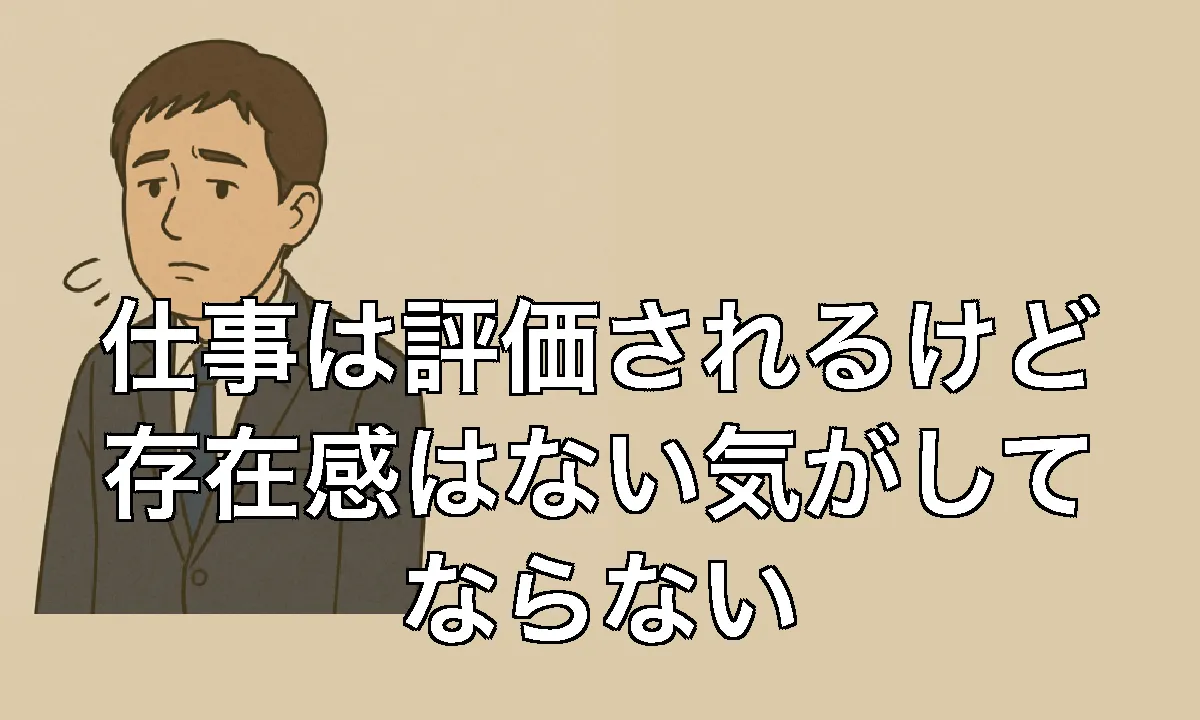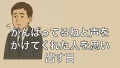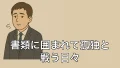忙しくしていれば孤独は紛れると思っていた
司法書士という職業柄、日々やることは山積みです。登記、相続、契約書の作成……集中すればするほど仕事は進み、周囲からの評価も悪くない。けれど、ある日ふと気づいてしまいました。「自分がここにいる意味って何なんだろう」と。忙しさでごまかしてきた孤独や存在の薄さに、あるとき不意にぶち当たることがあります。誰かに必要とされているという実感がないと、仕事の達成感も空虚に感じてしまうんです。
評価はされているはずなのに誰にも話しかけられない
書類の完成度は高いと褒められるし、顧客対応も丁寧だと感謝される。だけど、事務員さんとの会話は業務連絡のみ。電話が鳴らない昼休みは無音。そんな日常が続くと、自分が職場の空気の一部と化しているような感覚に陥ります。評価されているのは「成果物」であって、「自分」という人間ではない気がしてくる。人としての存在感が、どんどん希薄になっていくんです。
存在感が薄いのは自分のせいなのか
そもそも、自分から積極的に話しかけたり、飲みに誘ったりするタイプではありません。だからといって誰とも話さず黙々と仕事をしていると、「あの人は一人が好きなんだろう」と思われる。無意識に壁を作っているのは自分かもしれない。でも、それを崩すのがこんなに難しいとは思いませんでした。孤独に慣れたころには、もう誰とも深く関われなくなっていたんです。
仕事の能力と人間関係は別物だと気づいた
「仕事ができる」と「好かれる」は、まったく別物なんだと痛感しています。たとえどれだけ速く正確に処理できても、人との雑談が苦手なら、親しみやすい存在にはなれない。そう思うと、自分が評価にすがっていたのは、寂しさを紛らわせるためだったのかもしれません。人間関係のない評価は、賞状だけもらって帰る孤独な運動会のようなものでした。
ひとり事務所の静けさが染み込んでくる
今の事務所は静かで快適だけれど、耳鳴りがするほどの無音がときに胸を締めつけます。とくに事務員さんが休みの日。椅子の軋む音すら気になるほどの沈黙。人と関わることが少ない分、ひとつひとつの声に重みを感じるようになります。その重みが、時には「寂しさ」に変わることもあるんです。
誰にも相談できない時間の重さ
過去に一度、顧客対応で判断に迷ったとき、隣に相談できる誰かがいればどれだけ救われたかと思いました。でも、そんなときに限って誰もいない。法律書を引っ張り出して正解を探し、それで終わり。でも心のモヤモヤは消えない。相談というのは、正解を聞くためだけじゃなくて、「一緒に悩んでくれる存在」が欲しいということなんだと実感しました。
「ありがとう」より「一緒にいる」ことの大切さ
顧客から「ありがとう」と言われても、それが心にしみ込まないときがあります。言葉はあっても、関係性は浅い。その場限りのやりとりでは、人とのつながりを実感するのは難しい。だからこそ、「ありがとう」よりも、「一緒に働いている」「一緒に過ごしている」という感覚がほしかった。そういう時間を自分はずっと避けてきたのかもしれません。
昼休みに誰とも話さない日々
昼の時間。外に出るのも億劫で、事務所でお弁当を広げる日が続いています。テレビもつけず、スマホも見ずに、ただ黙々と食べる。そんな時間が当たり前になると、昼休みのはずなのに、全然休まっていないことに気づきます。心が休まるには、「誰かと笑うこと」が必要なのかもしれません。
机に向かって食べる弁当の味気なさ
事務机で食べる弁当は、どんなに豪華でも味が薄く感じます。昔は同僚とコンビニに行って、たわいのない話をしながら食べたものです。でも今は違う。味噌汁の湯気すら寂しく見える日がある。心が乾いていると、食事は「作業」になる。お腹は満たされても、心は空っぽのままです。
声を出すのが億劫になる感覚
話す相手がいない日が続くと、声を出すこと自体が面倒に思えてきます。久しぶりに来た電話に、思ったように言葉が出てこない。そんなとき、自分がどれだけ孤独と隣り合わせで生活していたかを痛感します。会話というのは、筋肉のように使わなければ衰えるものなのかもしれません。
気を遣わせたくない気持ちが余計に壁を作る
事務員さんに話しかけようと思っても、「忙しそうだから」「変に思われたら嫌だな」と躊躇してしまう。その遠慮が積もると、ますます距離ができてしまいます。自分が作った壁の中で、自分だけが寂しがっている。なんとも不器用で、滑稽な話です。でも、そう簡単には変われない。これが現実です。
自分がいなくても回るのではという不安
事務所にいる意味、自分がこの仕事をしている意味。それが分からなくなる瞬間があります。顧客とのやりとりもスムーズ、トラブルもなし。でも、逆に「じゃあ自分がいなくても誰かがやるだけなのでは?」と考えてしまう。存在意義が見えなくなると、どんな評価も心に響かなくなります。
ミスがないことは逆に存在を消す
完璧な仕事ぶりは、時に目立たない。何も問題が起きないということは、誰も自分の存在に気づかないということでもある。たまに「今日はすごく忙しいですか?」と聞かれると、うれしくなる自分がいます。ミスではなく、存在で気づいてもらいたい。そんな欲が出てくると、ますます心が重くなります。
頼られないのは信頼かそれとも無関心か
「あの人に頼めば大丈夫」という信頼と、「あの人は勝手にやってくれるから」という無関心は紙一重です。どちらに見られているかは、態度でなんとなく伝わってくるもの。本当に頼られているのか、それともただ使われているだけなのか。そんな疑念が、静かな事務所でじわじわと広がっていきます。
それでも誰かに必要とされたい
愚痴ばかりの文章になってしまいましたが、根っこにあるのは「誰かに必要とされたい」という想いです。仕事ができるとか、正確とか、そんなことよりも、「あなたがいてくれてよかった」と言われる瞬間がほしい。それが、この職業を続ける意味になるんじゃないかと、最近やっと思うようになりました。
お客様との短い会話が救いになることもある
登記の相談に来たお客様が、帰り際に「先生にお願いしてよかった」と言ってくれたことがあります。ほんの一言。でもその言葉が、その日一日を救ってくれることがあるんです。事務員さんとの会話がなくても、その一言で「今日、自分は人間だったな」と思える。それくらい、人の言葉は大きい。
書類の説明のあとにこぼれる一言の温かさ
形式的な説明が終わった後、ふと漏れる「最近暑いですね」とか「大変ですね」といった一言。そういう何気ないやりとりに、逆に救われます。「自分と話してくれている」という実感が、評価や報酬よりもずっと心を満たす。誰かと心が交わる瞬間は、やっぱり人間にとって必要なんです。
「またお願いします」の重み
リピーターのお客様からの「またお願いします」。その一言は、単なる営業成績以上の意味を持ちます。「この人は、自分という人間を信頼してくれた」。そう思えた瞬間、存在感の薄さも、孤独も、一瞬だけ消える気がする。だから、また明日も机に向かって仕事を続けられるんです。