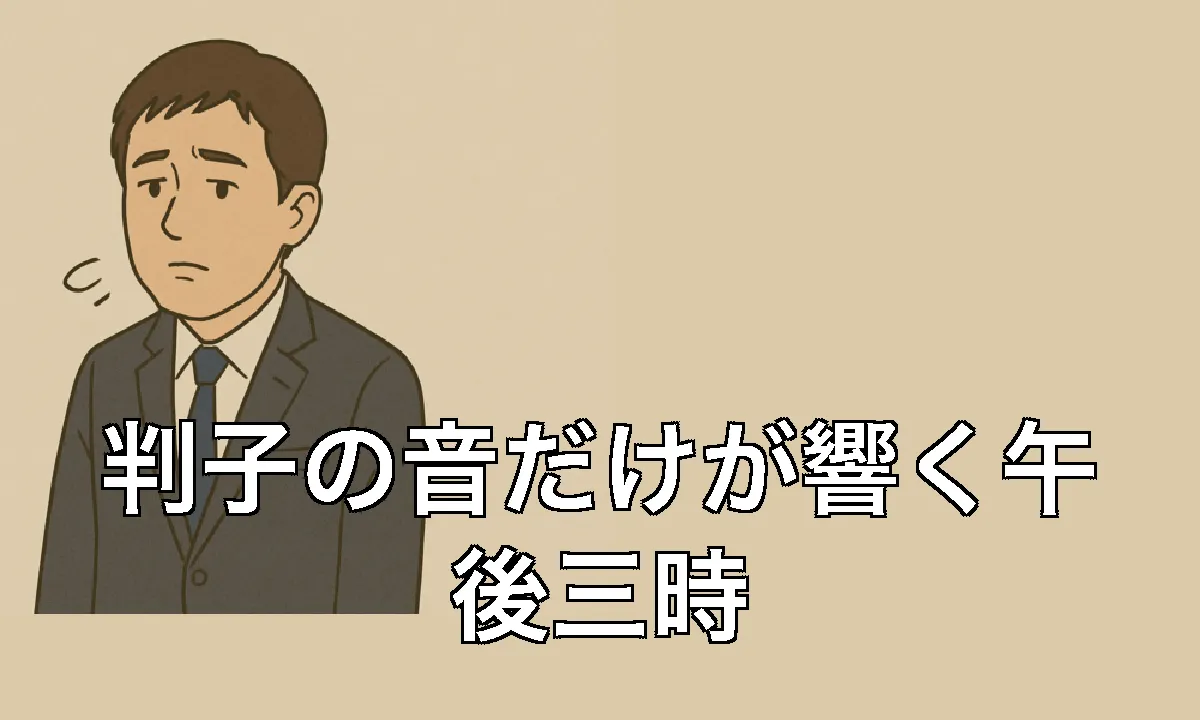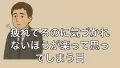午後三時の静けさが教えてくれること
午後三時というのは、なぜか特別に孤独を感じやすい時間だと思う。昼食後の眠気も抜け、仕事が一段落する頃。事務所の時計の針の音がやけに大きく聞こえて、ふと気がつけば、部屋の中にいるのは自分と書類だけ。判子を押すたびに、その音が静かな部屋に響いてくる。まるで自分の存在だけが際立っているような気さえしてくる時間帯だ。あの「ポン」という音が、今日もまた誰にも知られずに過ぎていく時間を刻んでいる。
印鑑の音だけが響く部屋
その音は、小さな印鑑が朱肉に沈み、紙に押しつけられるときに出る。たいした音ではないが、シーンとした事務所の中では、妙に存在感がある。まるで誰かが「ここにいるよ」と言ってくれているようでもあり、逆に「誰もいないね」と突きつけられているようでもある。昔、野球部のグラウンドで聞こえていた掛け声や金属バットの音とは正反対だ。仲間と声を張っていたあの頃の音はもうここにはない。今はただ、一人の男が、静かに責任を押し固める音だけがある。
書類は溜まり人は来ず
登記関係の書類、遺産分割協議書、定款変更…どれも重要で、間違いは許されない。なのに、この静けさ。依頼者は電話の向こうか、たまにやって来る郵便物の中にいるだけ。直接顔を合わせることも少なくなり、仕事はまるで孤独との戦いになってきた。気がつけば、誰かと笑ったのはいつだっただろう。人が来ないと仕事が減るかといえば逆で、どんどんデジタル経由で仕事は届く。だが、その中に人間味を感じる瞬間は少ない。
電話も鳴らず朱肉が減る
一日を振り返ったとき、電話が鳴ったのは1回だけ。その電話も営業の電話だった。結局今日も一人で、黙々と書類を確認し、判子を押し、また次のファイルに目を通す。朱肉は知らぬ間に減っているのに、感情はすり減らないどころか、鈍っていく。日常が単調になるというのはこういうことかもしれない。判子を押す手だけがルーチンで動き、頭の中では「こんなこと、あと何年続けるんだろう」と思考がぐるぐる回っている。
事務所に漂う孤独と業務の重み
業務量は決して軽くない。むしろ年々重くなっている。それでも事務所にいるのは、僕と事務員のふたり。彼女は真面目でよくやってくれるが、業務連絡以外の会話はほとんどない。話しかけても、うなずく程度で終わる日が多い。たぶん僕の愚痴が多すぎるんだろう。孤独感はさらに強まるばかりで、「誰のために働いてるんだろう」と考えることが多くなった。
笑い声のない午後
以前はもっと明るかった気がする。いや、事務所に笑い声なんて最初からなかったのかもしれない。誰かのミスに笑ったり、テレビの話題で盛り上がったり、そういうのとは無縁の世界。午後三時に笑っていたのは、グラウンドで泥だらけになっていた頃の話だ。今は笑うどころか、独り言すら減ってきた。話しかけても相手がいないからだ。
事務員との会話も業務連絡ばかり
「この書類、法務局に出しておいてください」「はい」これが大半の会話。天気の話や最近のニュースに触れても、「そうですね」と短く返されて終わる。もちろん事務員が悪いわけじゃない。むしろ気を遣ってくれてるのかもしれない。でも、なんだかすべてが淡々としすぎていて、気持ちがついていかない。人と接しているようで、接していない。そんな感覚が日に日に強くなっている。
「お疲れ様です」すら機械的に聞こえる
夕方、「お疲れ様です」と事務員が帰っていく。その一言すら、最近はルーティンにしか聞こえない。僕も「おつかれ」と返すけれど、その言葉に感情がこもっているとは言い難い。まるで押印と同じ、形式のようなやりとり。そんな事務所で、僕は今日も仕事を続ける。感情が空回りする午後三時から、何も変わらずに夜が来る。
元野球部の自分と今の自分
あの頃の自分と比べてはいけないと思いつつ、つい比べてしまう。野球部時代の午後三時は、グラウンドの真ん中で汗をかいていた。仲間と笑い合い、怒られながらも前に進んでいた。今の僕はどうだろう。仲間もいない。汗もかかない。ただ、朱肉の匂いと紙の手触りに囲まれて、一人で判子を押しているだけだ。
声を張っていた青春の記憶
「ナイスボール!」「声出していこう!」そんな掛け声が飛び交っていた頃、僕は元気だった。自分の居場所がちゃんとあったし、必要とされている実感もあった。それが今では、声を出すことさえ億劫になる。電話でさえ、どこか億劫だ。青春と呼べる時間は終わったのだと、午後三時の静寂が教えてくれる。
今は判子を押す手が重い
あの頃はグローブをはめてボールを投げていたのに、今は印鑑を握って静かに紙を押している。それも、何十枚、何百枚と。手が疲れるというより、心が疲れる。結果は出しているはずなのに、誰にも褒められることはない。正確にやって当たり前、失敗したら責められる。そんな毎日だ。判子の音が、自分の存在を無言で確認しているだけのような気さえしてくる。
それでも続ける理由を探す日々
愚痴ばかり言っていても、結局はまた朝が来て、また午後三時が来る。辞めたいと本気で思った日もあった。でも、それでも続けている理由は、どこかにまだ「誰かのために」と思っている自分がいるからだ。小さな「ありがとう」が、まだ心に残っているからだ。
小さな「ありがとう」に救われる瞬間
ある日、登記を終えたお客さんが、「本当に助かりました」と頭を下げてくれた。その言葉が、どれほど重かったか。何日も眠れないくらい悩んだ案件だったからこそ、その「ありがとう」が心に沁みた。午後三時に押した判子も、誰かの人生の一部を支えていたんだと、やっと実感できた瞬間だった。
誰にも見えない努力を積み重ねて
派手さはない。人に褒められることも少ない。けれども、この仕事は確かに誰かの生活を支えている。誰にも見られていない判子の音にも、意味はある。今日もまた、午後三時がやって来る。そして僕はまた、一人で朱肉を押して、次の書類に向き合う。それでも、それが僕の仕事であり、生き方なのだ。