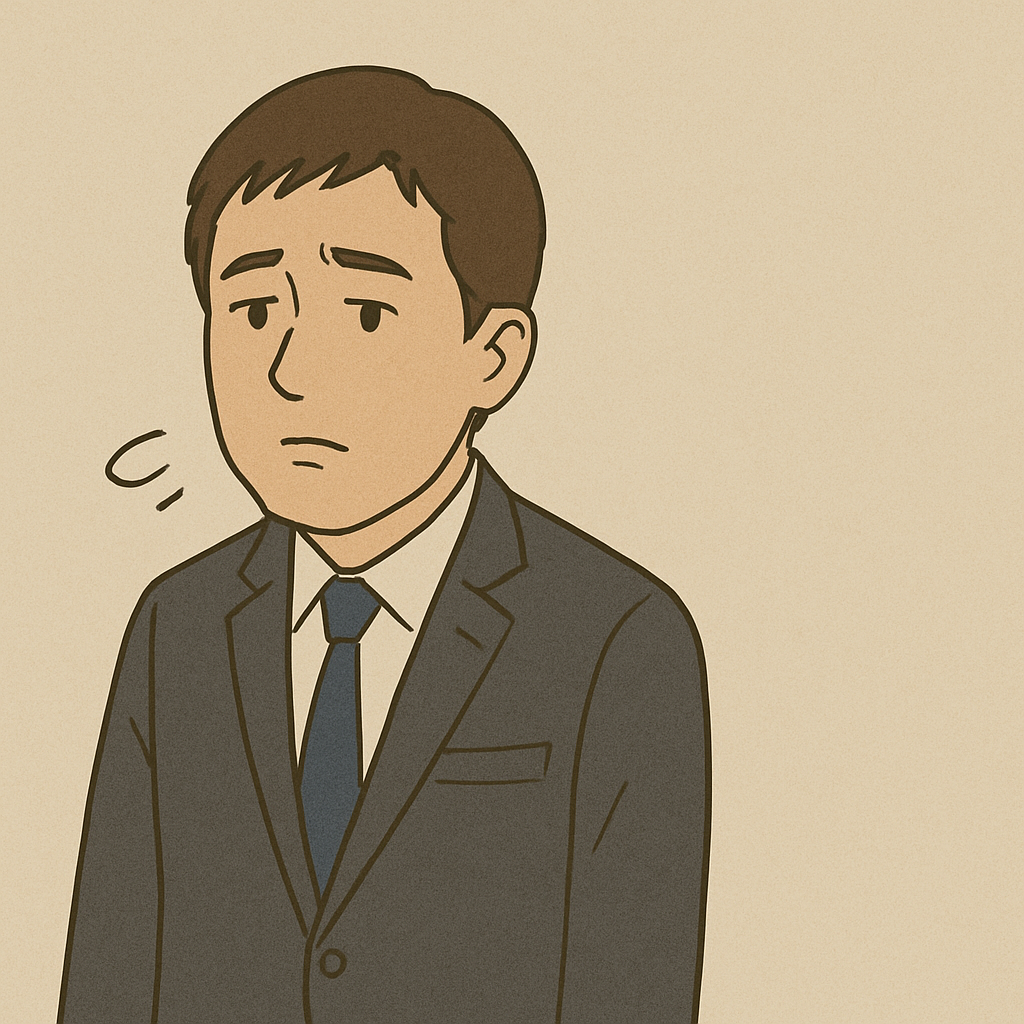登記簿が語らない夜
夜の来訪者と一通の謄本
ある秋の夕暮れ、シャッターを半分閉めかけていた事務所に、スーツの男が滑り込んできた。 顔色は悪く、右手にはくしゃくしゃになった登記事項証明書を握っている。 「この登記、何かおかしいんです」と、男はかすれた声で言った。
境界未定地に潜む違和感
ざっと証明書に目を通すと、確かに違和感があった。 あるはずの筆界が地図に記されておらず、申請された地番も歯抜けになっている。 土地家屋調査士の図面と見比べても、どうにも辻褄が合わなかった。
サトウさんの冷静な視点
「これ、昭和の航空写真と重ねて確認すれば出てきますね」 サトウさんが冷たく、しかし頼もしい口調で言い放つ。 無表情の奥で、なにか鋭く計算しているようだった。
昭和の名義と令和の矛盾
古い名義人は戦後すぐに死亡しており、相続登記は一度もされていなかった。 にもかかわらず、数年前に売買登記がなされている。 「死んだ人と契約したってわけか…ゾンビ登記か?」とつぶやくと、サトウさんは小さく鼻で笑った。
実地調査はまるで宝探し
次の日、現地に足を運んだ。道なき道を分け入ったその先に、割れた境界標が転がっていた。 その近くには、風化した石碑のようなものも半ば土に埋もれていた。 昭和32年の日付がかすかに読み取れた。
閉鎖登記簿が開く口
市内の倉庫に保管されていた閉鎖登記簿を引っ張り出す。 ページを繰るごとに、埃とともに時間が舞い上がる。 そこには現在の地番とは異なる、失われた土地の記録が残っていた。
売買契約の裏に潜む影
売買契約書は一見、正規の書式を満たしていた。 しかし決済に使われた印鑑証明が、期限切れのまま放置されていたのだ。 名義変更だけが通っていたのは、誰かの“助け”があった証だ。
騙されたふりをした依頼人
「本当に困ってるんです…」と依頼人は言うが、どこかセリフ臭い。 会話の端々に矛盾が混じり、私の眉はじわじわと寄っていく。 「最初から知ってたんじゃないですか、その土地の正体を」とサトウさんがズバリ言った。
やれやれ、、、とつぶやく午後
お茶をすすりながら、机に広げた地図とにらめっこ。 午後の日差しが書類を照らし出し、ふとした拍子に地番の間違いに気づいた。 「やれやれ、、、。また一文字違いでここまで振り回されるとはな」と独り言を漏らす。
地番に隠されたもう一つの土地
原因は、わずかな地番の記載ミスによる隣接地の混同だった。 本来の売買対象地は別に存在し、それは数年前から空き家となっていた古民家。 不動産業者も気づかないほどの盲点だった。
不法占拠か正当な継承か
問題の土地には、すでに第三者が長年住んでいた。 登記と実態が食い違うこの状況を、どちらの権利と見るか。 私は法務局と家庭裁判所に意見照会を送ることにした。
サトウさんの決断
「もう、私が行ってきます」 突如サトウさんが立ち上がり、かばんを肩に掛けた。 役所に着くと、若手の登記官に無表情で詰め寄り、15分後には訂正を勝ち取っていた。
謄本一枚が招いた罪と罰
依頼人は、別の土地と偽って売却した容疑で警察に連行された。 詐欺未遂の立件は難しかったが、虚偽登記の共同正犯として扱われた。 謄本一枚の裏に隠された計画は、あまりに稚拙で、しかし周到だった。
最後に笑うのは誰か
依頼人は泣きながら「知らなかった」と叫んだが、誰も信じなかった。 損害は限定的で、幸い被害者はすぐに救済された。 ただその背後にいた不動産ブローカーの姿は、最後まで浮かばなかった。
書類の裏に残った鉛筆の跡
調査を終えて書類を整理していた時、裏面にかすかな鉛筆の跡を見つけた。 「本当はここに書かれるべきじゃなかったんだな…」 私はその跡をそっと指でなぞり、机の引き出しにそっと仕舞った。
登記簿は語らなかったが
あの土地も、名義も、もう静かに眠るだけだった。 語らなかったのは登記簿であり、語らせたのはわずかな違和感だった。 夜の帳が降りる中、私はそっと窓を閉めた。