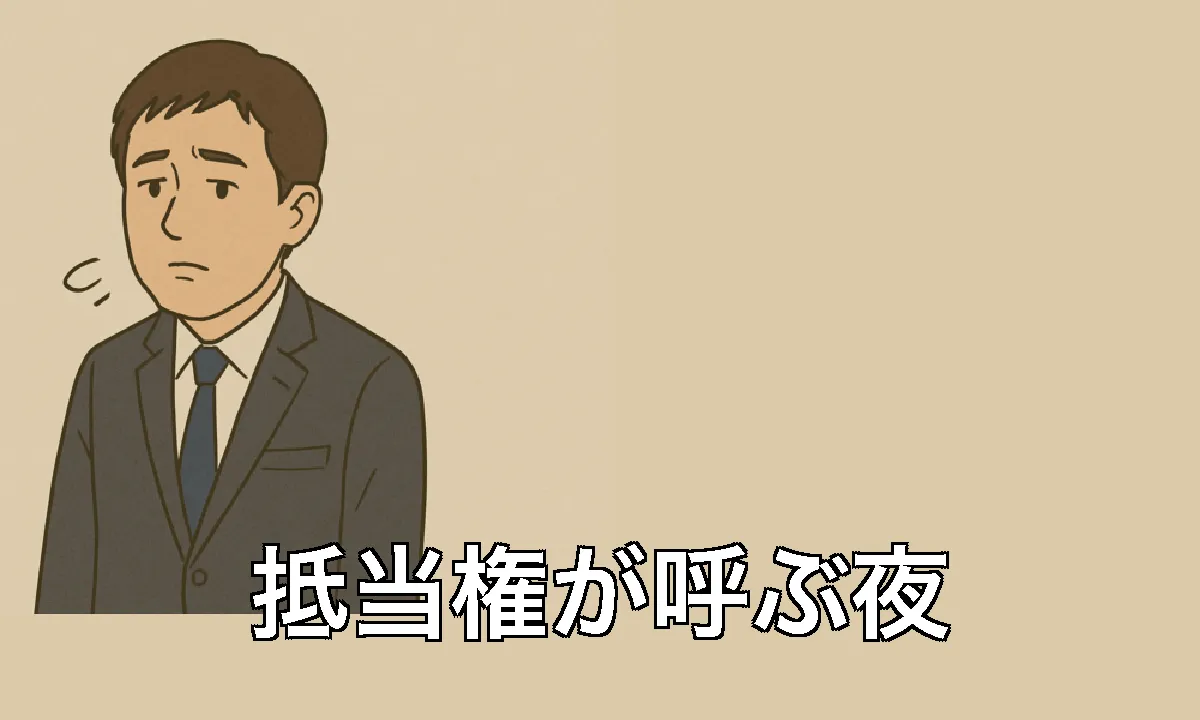開かれた扉と呼び鈴の音
その夜、事務所に鳴り響いたのは、営業時間をとうに過ぎた頃の無遠慮なインターホンだった。誰もが帰宅の準備を始める中、私はまだ机の上の登記簿と格闘していた。仕方なく扉を開けると、スーツ姿の若い女性が立っていた。
「急ぎでお願いしたい登記がありまして……」と彼女は小さく頭を下げた。まるで深夜のスナックに飛び込みで現れた酔っ払い客みたいな態度だったが、その声には妙な切迫感があった。
夜の来訪者
彼女の名は西村アカネ。亡き父の名義だった実家に抵当権を設定したいという。「期限があるんです。どうしても明日中に」と彼女は繰り返した。理由を尋ねても、「それ以上は……」と歯切れが悪い。サトウさんが眉をひそめた。
この時点で、すでに事件の臭いがしていた。とはいえ、司法書士の仕事は基本的に、事件を起こすことではなく、粛々と処理することだ。
書類の束に隠された違和感
彼女が差し出した書類一式は形式的には問題なかった。だが、抵当権設定契約書の日付がやけに古い。「これ、1ヶ月前のですね。公証人の印影もあるけど……」と私はつぶやいた。
「父が亡くなる前に交わしていた契約です」とアカネは答えた。けれども、その口ぶりにどこか他人事のような温度があった。
依頼人の顔に浮かぶ影
アカネは何かを隠している。それは明らかだった。司法書士の仕事は、依頼を断ることもまた選択肢にある。だが私は昔から断れないタイプで、そういう性格が今も尾を引いている。
机の端で腕を組んでいたサトウさんが、ふと私の方にだけ聞こえるような声で言った。「あの人、抵当権の意味、本当に理解してますかね?」
住宅ローンと過去の因縁
西村家の不動産を過去に調べた記録を引っ張り出すと、5年前に一度差し押さえられた形跡があった。「あれ?この家、一度競売寸前までいったのか……」と私はつぶやいた。
つまり、今回の設定は二度目の抵当。しかも担保にする理由が不明だ。いや、彼女はそれを明かそうとしない。ここに何かある。
法務局にない記録
管轄の法務局に照会したが、直近1ヶ月にこの不動産に関する登記申請はなかった。だとすれば、彼女が持ち込んだ契約書は、単に温存されていたものか、あるいは別目的か。
その瞬間、頭の中で何かがつながった。これは、遺産隠しのカモフラージュではないのか。いや、もっと悪質な何かだ。
サトウさんの違和感センサー
「先生、これ、債権者の印鑑が偽物じゃないですか?」とサトウさんが一枚の契約書を指さした。目の前が一瞬白くなった。確かに、印影が微妙に違う。私は震える指で印鑑証明書を取り出した。
一致しない。つまり、これは偽造文書だ。
メモの走り書きに隠されたサイン
書類の中に、アカネのメモが一枚混ざっていた。「A銀行にはまだバレていない」と走り書きがあった。これで確信した。彼女は相続登記をすっ飛ばして、自分のものとして担保設定しようとしていた。
要するに、不正登記の片棒を担がせようとしていたのだ。
日付のズレと登記のミス
さらに調べると、契約書の日付が父親の死亡日よりも後になっていた。やれやれ、、、これはもう完全にアウトだ。私は深くため息をつきながら、顔を上げた。
「この書類、使えません。登記の依頼はお引き受けできません」と冷静に言い切った。
失踪と抵当の接点
アカネはそのまま事務所を飛び出していった。それから一週間後、警察から電話があった。西村アカネが詐欺未遂容疑で事情聴取を受けたという。
やっぱり、そういうことだったか。だが、なぜ彼女はそんな危ない橋を渡ったのか。
消えた債権者の正体
債権者名義になっていた男が、実はすでに5年前に死亡していたことが判明した。つまり、実在しない人物の名前で契約が作られていたのだ。しかも、公証人役場の印影も偽物。
どこからこんな知識を仕入れたのか。今どきの若者は、ググれば何でも分かるらしい。
保証人の意外な告白
保証人にされていたのはアカネの元恋人だった。彼は警察の取り調べに対して「頼まれて判子を押しただけ」と証言した。彼女の父親の死後、すべてが狂い始めたと彼は語った。
まるで昼ドラのような展開に、私は呆れるやら悲しいやら複雑な気分だった。
シンドウ動く
「一応、司法書士会にも報告しておきましょう」と私は重い腰を上げた。やれやれ、、、こういうことに時間を取られると、本業が進まない。
だが、こういう裏仕事もまた、司法書士の重要な役目ではある。正義感というより、単なる職業病だ。
戸籍と登記の交差点
今回の件は、相続登記と抵当権設定の順序の重要性、そして書類の真正性について改めて考えさせられる出来事だった。戸籍、印鑑、登記簿、どれも1つでも崩れれば、全部が虚構になる。
登記は嘘をつかない?いや、人が嘘をつけば、登記だって汚れる。
真実を示す登記事項証明書
私は改めて本来の正しい手続きを記した登記事項証明書を見つめた。そこには、亡き父の名前が静かに残されていた。
それを見て、アカネの気持ちが少しだけ分かった気がした。守りたかったのだ、父の名前を。あるいは、父の残したものを。
サインされた契約書の裏
問題の契約書の裏には、アカネの手書きのメモがあった。「ごめんなさい、お父さん」とだけ書かれていた。
その言葉が胸に刺さった。悪いことをしたのは間違いない。でも、誰かを騙すためだけではなかったのかもしれない。
証拠が語る死の理由
警察の調べでは、アカネの父親の死も不審な点が多いという。つまり、ここにはまだ続きがあるかもしれない。
事件は一件落着とはいかないのだ。
深夜の再訪と告白
数日後、アカネがもう一度事務所を訪れた。目には涙をため、封筒を差し出した。「迷惑をかけたお詫びです」
「いや、受け取れませんよ。私はあなたを裁く立場じゃない」と私は返した。
灯りの消えた依頼人宅
その夜、アカネの家を訪ねると、もう明かりは灯っていなかった。引っ越したのか、どこかへ消えたのか。それはわからない。
ただ、あの夜の契約書と涙の意味は、きっと本人にしか分からないのだろう。
遺されたノートと最後の言葉
ポストには一冊のノートが入っていた。表紙にはこう記されていた。「抵当権が呼ぶ夜 これは私の物語」
私はそっとノートを閉じ、サトウさんに渡した。「記録として、保管しておいてくれ」
真相と小さな救い
どれだけ嘘に塗れた書類であっても、そこに人の感情がある限り、全てが無意味とは言えない。少なくとも、私はそう信じたい。
「やれやれ、、、もう少し静かな日常に戻りたいもんだ」とつぶやきながら、私は事務所の蛍光灯を消した。
抵当権の抹消と静かな涙
後日、問題の不動産は正式に相続登記がなされ、抵当権の話も自然消滅した。だが、私の中ではこの事件は終わっていなかった。
感情と法律、その間にある微妙なグレーゾーンに、私はまた一歩踏み込んでしまったような気がした。
サトウさんの淡々たる報告
「先生、次の登記依頼が来てます。今回は農地法の許可が必要です」
「はあ……」と私は書類を受け取る。事件が終わっても、仕事は終わらない。司法書士の宿命かもしれない。
翌朝の事務所にて
いつものように朝のコーヒーを片手に、私は椅子に沈み込む。サトウさんは相変わらず塩対応だが、それが逆に安心する。
今日もまた、誰かの人生の断片が、この狭い事務所に持ち込まれるのだろう。
請求書とあのときの笑顔
未払いの請求書の束の中に、あのときアカネが差し出した封筒が一通だけ混じっていた。開けると、手紙とともに小さな写真が入っていた。笑顔のアカネと父の姿だった。
私はそれをそっと机の引き出しにしまった。
今日もまた依頼者がやってくる
「こんにちはー、登記のことでちょっと……」とまた新たな声が響く。私はため息をつきながら立ち上がった。
やれやれ、、、今日もまた、事件が始まりそうだ。