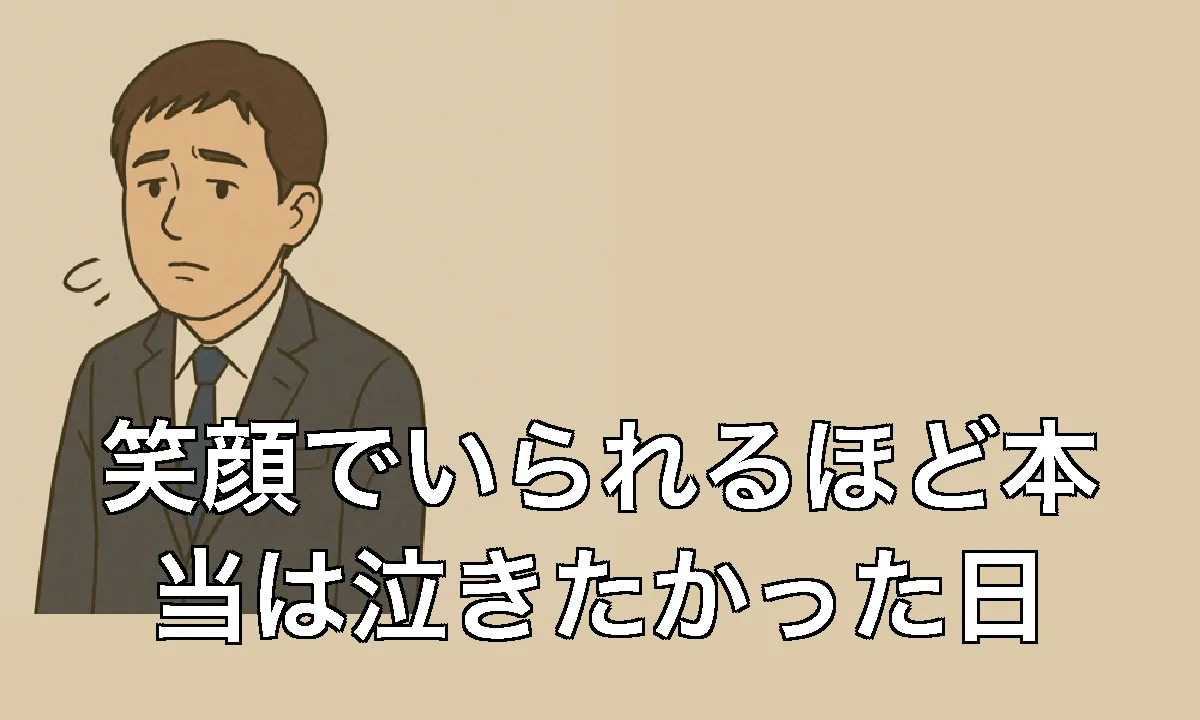笑ってる自分に違和感がある日もある
「よく笑う先生ですね」と言われることがある。でも、その言葉に返す笑顔の奥で、どうしようもない疲れと孤独を隠している日がある。笑うのが好きというより、泣く場所がないから笑っているだけ。朝、鏡を見て「今日もやれるかな」と呟く自分にすら、どこか他人事のような感覚を覚える。司法書士という肩書に、日々の生活に、そして何より“期待される自分”に、気づけば息苦しさを感じるようになった。
事務所ではいつも「明るい先生」で通している
小さな町の司法書士として、それなりに名前も知られてきた。だからこそ、弱みは見せづらい。事務員の前では依頼者の前でも、いつも笑顔で接してしまう。たとえ昨日の夜に眠れなくても、朝ごはんを抜いても、「どうぞおかけください」とにこやかに迎え入れる。役者のようにセリフと表情を使い分けているような感覚になることすらある。でもそれは演技ではなく、“そうするしかない”からなのだ。
本音を言える相手がいない日常
ふと気づくと、本音を吐ける相手が一人もいないことに気づく。高校時代の野球部仲間とは連絡が減り、家族とも話す時間は少なくなった。仕事の話をしても理解されにくいし、結局「まあ、大変だよね」の一言で片づけられることが多い。本音を話すのは、どこか怖い。理解されないのが怖いし、弱い自分を見せたときの沈黙が怖い。
愚痴すらこぼせない静かな孤独
事務員に気を使わせたくないから、愚痴も控える。でも一人になると、心の中は愚痴だらけだ。書類の山にため息をつきながら、「なんで俺が…」とこぼしたくなることもある。だけど口に出せない。誰にも届かない言葉が、心の奥に積もっていく。静かな孤独とは、音がしないぶん、じわじわと蝕んでくるものなのだ。
依頼者の前では泣けないから笑う
人の人生に関わる仕事だからこそ、依頼者の前で取り乱すわけにはいかない。相続や離婚、借金問題。相談に来る方々は、皆どこか不安そうだ。そんな人たちに、こちらが涙ぐんでしまったら安心してもらえない。だから笑う。笑って「大丈夫ですよ」と伝える。でも、内心では「俺は誰に大丈夫と言ってもらえるんだろう」と思っている。
相続の話をしながらこっちが泣きそうになる
先日、あるご婦人が亡きご主人の相続で訪れた。思い出話をぽつりぽつりと語るその声に、こちらの胸が締めつけられた。自分にはそんな風に誰かに惜しまれる人生があるだろうかと、不意に考えてしまった。依頼者の話に共感しすぎて、こっちが泣きそうになることがある。それでもプロとして、笑顔で手続きを説明する。まるで心と表情が別の生き物になったような瞬間だ。
家族の温かさが逆に胸に刺さる瞬間
「主人は几帳面な人でね」と話すその言葉に、ふっと胸が痛くなる。誰かに大切にされた思い出が語られるたび、自分の空白が際立つ。帰り際に「先生もお体に気をつけて」と言われると、なぜだか涙がこぼれそうになる。あたたかい言葉が、かえって今の自分の冷え切った心を炙り出してしまうのだ。
他人の幸せ話を受け止めるプロの顔
司法書士は聞き役だ。だから、他人の人生の幸せや後悔を、ずっと聞き続ける。それが仕事。でも、受け止めるばかりで、自分の感情はどこへやればいいのか分からなくなる。他人の幸せ話に心から「よかったですね」と言える日もある。でも時々、自分の中に「それに比べて自分は…」という黒い声がささやく。そんなとき、笑顔の仮面が少しひび割れる。
元野球部のクセでつい我慢してしまう
高校時代、野球部のキャプテンをしていた。根性と我慢の精神は今も体に染みついている。「痛くても走れ」「苦しくても声を出せ」。そんな教えが、今でもふと顔を出す。疲れていても仕事を受ける。辛くても「大丈夫です」と言ってしまう。それが習慣になってしまっている。でも、本当はもう限界かもしれないのに。
泣くのは甘えと思っていた時代の名残
男が泣くのはかっこ悪い、という空気の中で育ってきた。悔しくても涙をぐっとこらえてバットを握っていたあの頃。泣かないことが強さだと思っていた。だから今でも、涙が出そうになると無理に笑ってしまう。感情の逃がし方が分からないまま、大人になってしまったのかもしれない。
本当は逃げたいと思う瞬間もある
仕事中にふと、「もう何もかも投げ出して、どこか遠くへ行きたい」と思うことがある。でもそれを実行する勇気もないし、そんな時間もお金もない。だからまた机に戻って、淡々と書類に向かう。逃げたいのに逃げられない現実が、肩にどっしりとのしかかってくる。
でも逃げ道の作り方すら忘れてしまった
たまには誰かに「休んでもいいよ」と言ってほしい。でも、自分が休んだら誰がこの事務所を回すのか…そう思うと、結局また今日も仕事に向かってしまう。逃げるという選択肢が、頭の中から消えてしまったようだ。走り続けてきたぶん、立ち止まり方も忘れてしまったのかもしれない。
ひとり事務所に残る夜の寂しさ
事務員が帰った後、事務所に一人で残ることが多い。静まり返った部屋の中で、パソコンの音だけが響いている。その時間が一番、自分の“本音”に出会ってしまう時間だ。誰かに「今日もお疲れさま」と言ってもらいたくて、でも言ってくれる人もいない。ただ静かに、夜が過ぎていく。
明かりを消せば押し寄せる不安
電気を消して玄関を閉めると、暗闇と静けさに包まれる。その瞬間、得体の知れない不安が襲ってくる。「この先、俺はどうなるんだろう」「誰かと一緒に生きていけるのか」。そんな思いが、どっと押し寄せてきて、帰り道はため息ばかり。笑顔で過ごした昼の自分が、嘘みたいに遠く感じる。
電話も鳴らず ただ時間だけが過ぎる
夜の事務所は静かすぎて、時計の秒針の音だけがやけに大きく響く。誰からの連絡もない、鳴らないスマホを見て、またため息をつく。自分の存在なんて、誰かにとって必要なのか。そんな思いが頭をかすめる。こんな時、誰かとたわいもない話ができたらどれだけ楽だろう。
「誰かとご飯が食べたい」と思う夜
一人暮らしの部屋に帰っても、冷蔵庫は空っぽ。結局コンビニで済ませてしまう夜。温かい味噌汁の香りすら恋しくなる。「誰かとご飯が食べたい」。それだけの願いが、こんなにも大きな孤独に繋がっているとは、若い頃は思いもしなかった。
事務員の前では気丈にふるまっている
彼女はまだ若いし、気も使ってくれる良い子だ。だからこそ、自分が弱っている姿は見せたくない。余計な心配はかけたくない。でも時々、ふとした拍子に「先生、大丈夫ですか?」と聞かれる。その一言が、ありがたくて、同時に切なくもなる。
心配かけたくないという意地
年上の自分が情けない姿を見せたら、彼女も困るだろう。そう思って意地になって笑っている部分もある。「大丈夫だよ」と言いながら、自分の心の声には耳を塞いでいる。でもその“意地”が、逆に自分を苦しめている気もする。
本当は少しだけ甘えてみたい
誰かに「よく頑張ってるね」と言われたら、きっと泣いてしまうと思う。甘えるのは恥ずかしい。でも、人間って、本当は誰かに受け止めてほしい生き物なんだと思う。少しだけ甘えてみたい。たった一言「今日は疲れた」で、全部が楽になるような気がする。
でもうまく笑えなくなるのが怖い
弱音を吐いたら、もう元の笑顔に戻れない気がする。それが怖い。今まで築いてきた「明るい先生」という看板が、崩れてしまいそうで。だから今日も、誰にもバレないように、笑っている。笑顔でいることでしか、自分を保てない日もあるのだ。