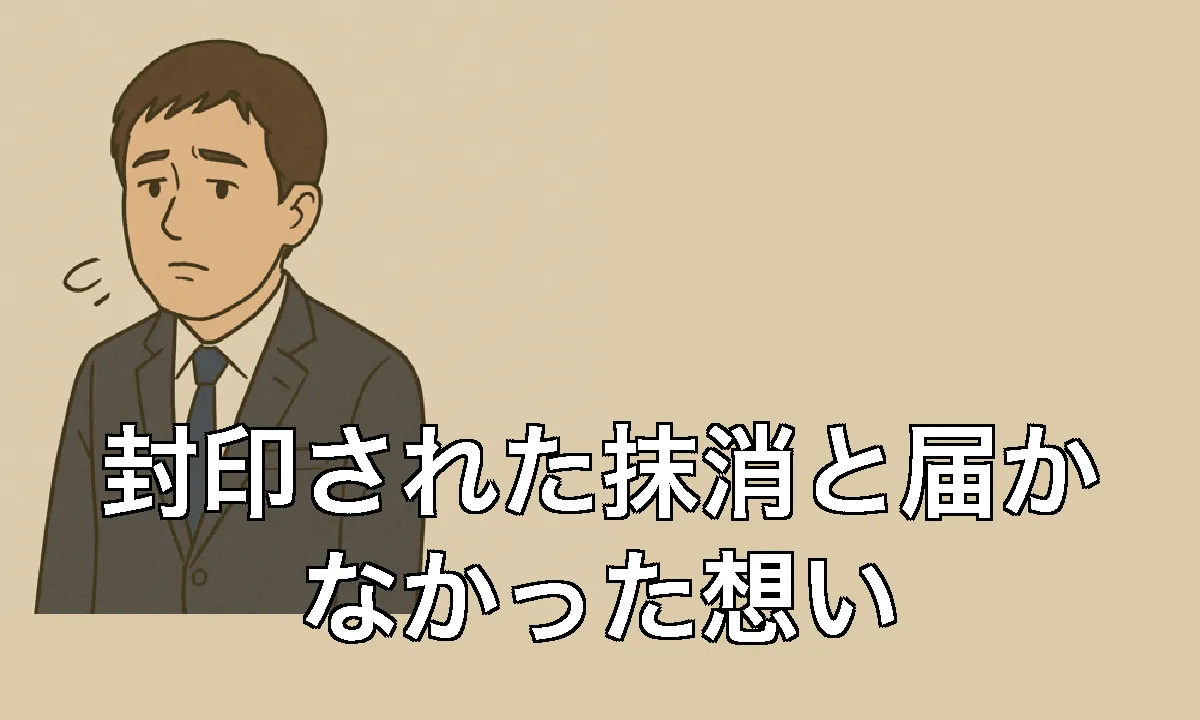封印された抹消と届かなかった想い
その日、机の上に積まれた封筒の山の中に、やけに古びた一通が混じっていた。茶封筒には、かすれたボールペンで「抵当権抹消の件」とだけ書かれていた。差出人は不明、消印は三ヶ月も前のものだった。
「シンドウさん、これ、戻ってきた封筒の中に紛れてました」 サトウさんが手袋をしたまま、封筒を差し出した。
司法書士に届いた一通の茶封筒
封を開けると、中には一枚の委任状と、メモ用紙に走り書きされたような短い文が入っていた。「夫が亡くなりました。抵当権を外してください。できれば静かに…お願いします」。筆跡は震えていて、何かを隠そうとしているように見えた。
どこか懐かしい、でも見覚えのない住所が記載されていた。依頼人の名前は「青木澄子」。記憶にはないが、どこかで見た気もする。
「抵当権抹消登記をお願いしたいのですが」
不動産登記簿を見ると、確かに青木という名前の所有者がいた。その横にしっかりと根抵当権が設定されている。だが、債権者欄に記された銀行の支店は既に閉鎖されていた。
閉鎖された支店に問い合わせることはできない。だが、抹消にはその銀行の承諾書が必要だった。話がややこしくなるな、と思いながら、古い資料をあさる。
亡き夫の名義と消えた債権者の謎
ふと、以前別件で受けた相談の記録に、似たような名前を見つけた。「青木信夫 借入金の相談」。一年前、病床で手続きの話をしていた男性だった。やはりこの案件には、単なる登記以上のものが絡んでいる。
「どうせまた誰かの“秘密”が登記簿に滲んでるってわけですね」 サトウさんが呆れたように言った。まるでキャッツアイが盗みに入る前の顔だ。
旧住所に送られた封書と戻された記録
送付記録を確認すると、この封筒は一度旧住所宛てに発送され、不在で戻ってきたものだった。だがその時、封筒は開封されていた形跡がある。つまり、誰かが一度は中を見て、また戻したということだ。
封筒の端に、見慣れない黒インクで印が押されていた。「受取拒否」。受取人の意志ではない。誰かがこの手紙を封じようとした。
登記原因証明情報のズレに潜む違和感
登記原因証明情報を作成しようとすると、時系列に矛盾があった。借入契約が切れていた時期と、信夫さんが亡くなった時期がどうしても一致しない。さらに、借用証書の日付と登記簿の契約日は微妙にズレていた。
普通なら気づかない。だが、こういうズレは「誰かが過去を書き換えようとした痕跡」だ。ルパン三世の偽造パスポートを見抜く銭形警部のように、登記簿の行間を読むのも司法書士の仕事だ。
サトウさんの冷静すぎる観察力
「この“契約書”、フォントが新しすぎますね。平成初期の書類でMSゴシックは使わないはず」 サトウさんの鋭さは相変わらずだ。あたしには見えないものが見えている。
彼女の指摘で、偽造の可能性が濃厚となった。だとすれば、この抹消登記は“故人の名を使った詐欺”である可能性すら出てきた。
遺族年金と抵当権の微妙なバランス
さらに気になるのは、抹消を急いでいる理由だった。遺族年金の申請書類を閲覧すると、不動産の無担保状態が条件となっていた。つまり、抵当権を抹消すれば、満額支給される。
それを狙った誰かがいた? それとも本人が望んでいた? いや、それならこんな裏工作は不要だ。誰かが、澄子さんの代筆をしたのだ。
地方銀行支店長が語った一年前の出来事
旧銀行の元支店長を訪ねると、思いがけない言葉が返ってきた。「青木信夫さん? ああ、あの人は“口約束”で抹消の話をしてたが、正式な書類は出なかったよ」。
それは登記的には何の効力もない。しかし、人の思いとしては残っている。そしてそれが、誰かの復讐の導火線になったのかもしれない。
地元郵便局で交わされたもう一通の会話
「実は、その封筒、一度開けた人がいましたよ」 郵便局員がぽつりと教えてくれた。「青木家の息子さんが“手違い”と言って、持ち帰ってから再び返しに来たんです」。
やれやれ、、、家族間の確執まで掘り起こす羽目になるとは。 こんなことなら、サザエさん一家にでも中立調停してもらいたい。
登記簿と手紙に刻まれた別々の「日付」
改めて登記簿と手紙の日付を照合すると、封筒の日付は登記原因より“未来”の日付になっていた。つまり、この手紙は「未来の誰か」が書いた可能性がある。
いや、もしくは、誰かが偽装してこの抹消を“演出”した。復讐の対象は、家族か、それとも司法そのものか。
二重登記の影と復讐の筆跡
古い別の地番で、同一人物名義の不動産が登記されていた。しかも、同じような抵当権設定。筆跡鑑定の結果、それらはすべて“青木信夫”の名前を誰かが模写したものだった。
真犯人は、彼の死後に財産を整理するはずの身内だった。そしてその人物は、抹消を通して“澄子”の受け取りを封じようとした。
手紙が宛てたのは司法書士ではなかった
あの手紙は、実はわたし宛てではなかった。本文の隅に「義父へ」と書かれていた。それは、息子の妻からの“警告”だったのだ。
司法書士は、たまたまその封印を解いてしまっただけだった。
登記完了後に届いた最後の返信封筒
結局、登記の抹消は行われた。正当な証明を経て、権利関係は整理された。手紙は澄子さんのものと判明したが、本人はすでに行方をくらませていた。
その後、封筒だけが届いた。中には「ありがとう、これで義父を越えられます」とだけ書かれていた。何を越えたのか、わたしには分からない。
サトウさんの一言が事件を締めくくる
「人の想いと登記の整合性って、本当に交わりませんね」 彼女はそう言ってコーヒーを一口飲んだ。
私はため息をついた。「やれやれ、、、今日もまた、登記じゃないものを処理した気がするよ」。