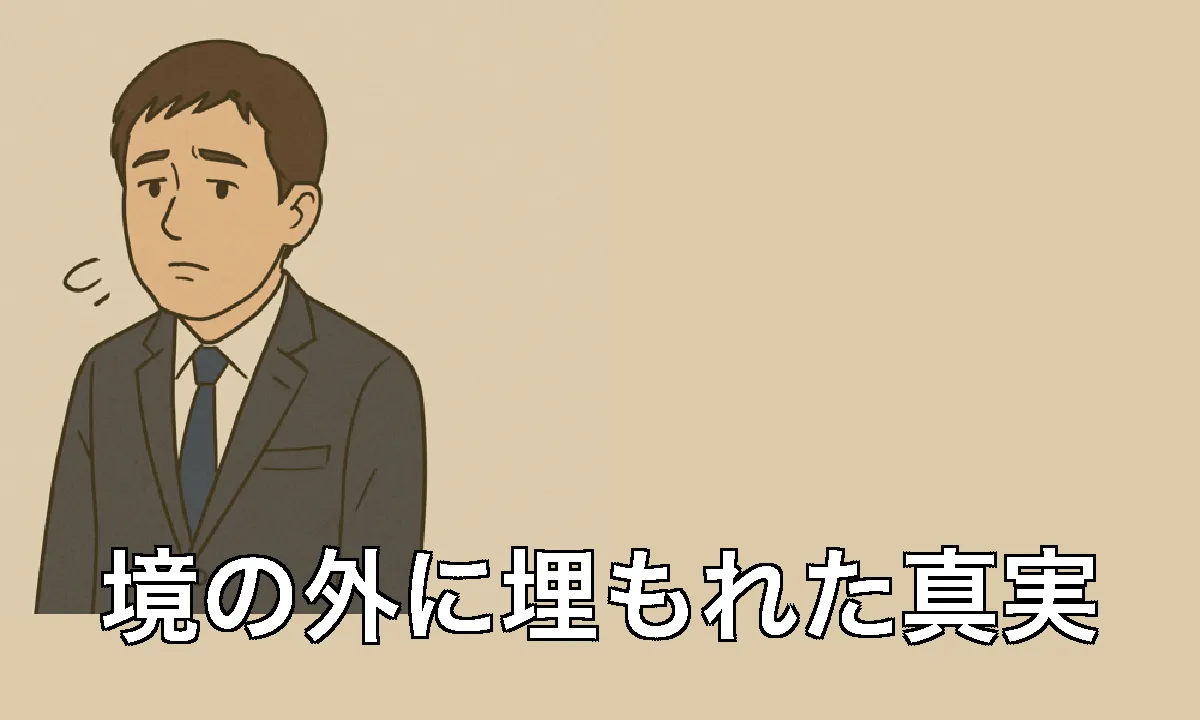朝一番の電話
朝のコーヒーを一口飲んだ瞬間、事務所の電話が鳴った。受話器の向こうから聞こえたのは、年配の男性の焦った声だった。土地の境界がわからなくなったという。
「杭がないんです。うちの土地の端が、どこなのかわからなくなったんです」と男は繰り返した。登記簿も謄本も手元にあるらしいが、現場と一致しないのだという。
まだ寝ぼけた頭をコーヒーで叩き起こしながら、私はその案件を引き受けることにした。
不穏な声の依頼人
依頼人は地元の旧家の次男坊。実家の土地を分けてもらって家を建てたが、最近になって隣地所有者と境界をめぐって揉めているとのことだった。
「昔からこの辺の土地は曖昧なんです」と彼は言った。私はその言葉に、なにか面倒な匂いを感じた。
不動産の話が曖昧で済んでいた時代は終わっている。紙の上で整然としていても、現場は混沌としていることがある。
土地の境界が消えた
問題の土地は、分筆後に新築が建てられた一画だった。だが境界杭の一つがなくなっており、残りの位置も微妙にズレていた。
依頼人は「以前は確かに杭があった」と主張するが、現地の写真などは残っていない。しかも隣地の住人は別の主張をしていた。
筆界をめぐる争いは、時に人間関係まで壊してしまう。私の胃もまた、朝から微妙に痛み出していた。
現場は山間の分筆地
杉林を背にした斜面の一角にその土地はあった。古い里道がかすかに痕跡を残しており、地元の人の記憶の中でかろうじて存在を保っていた。
「ここは昔、道だったんだよ」と語る老婦人の言葉に、私は少しだけ耳を傾けた。その道がいつ消え、いつ土地が区画されたのかはわからない。
でも、その“あいまいな過去”こそが、今回の事件の鍵になる気がしていた。
杭が一本足りない
現地の測量図では四隅に杭が設置されているはずだったが、そのうちの一つがどうしても見つからない。風雨に流されたか、故意に抜かれたか。
私は金属探知機を借りて現場を調査した。が、見つかるのはサビた釘や古い缶ばかり。測量士に頼んだ立会でも、特に有力な情報は出てこなかった。
「やれやれ、、、探偵ごっこじゃないんだから」と私はつぶやいた。だが、その言葉はどこか懐かしい響きを持っていた。
謄本と地積測量図の矛盾
サトウさんが事務所で調べていた謄本と測量図を突き合わせていると、奇妙な点が見つかった。地積測量図の縮尺が、途中で不自然に変わっている。
「この図、どう見ても後から書き直されてますよ」と彼女は言った。なるほど、筆跡の違いまで気づくとは、さすがだ。
改ざんされたか、あるいは意図的な修正か。いずれにせよ、ただの「杭の消失」では終わらなさそうだ。
サトウさんの冷静な一言
私は興奮して調査の報告を始めたが、サトウさんは冷静だった。「依頼人の話、ちょっと変じゃないですか?」と彼女が言ったとき、私は思考の流れが変わるのを感じた。
「杭があったって断言してるわりに、証拠を何も出してこないですよね」とサトウさんは続けた。その通りだった。
確かに、彼の主張には“信じたい”感情が混じっているように思えた。現実を見ていないのではなく、見たくないのかもしれない。
封筒に残された旧測量図
彼の自宅で書類を預かる際、封筒の奥から出てきたのは古い旧測量図だった。昭和の時代に作られたもので、今とは微妙に線が違っていた。
「この図面、捨てたと思ってました」と彼は言った。だが、その図面には今と違う筆界線が記されていた。
境界線の謎は、過去の図面と現在の記録とのズレに潜んでいたのだ。
境界立会に現れた隣地人
境界立会の日、隣地の所有者である若い夫婦もやってきた。彼らは険しい表情で、こちらの主張に一歩も引かない姿勢を見せた。
「うちは、あのラインまでが自分の土地だと父に聞いてます」と言うが、証拠は曖昧。感情だけがぶつかり合っていた。
そのとき、思いもよらぬ人物が現れた。依頼人の父親の古い友人であり、元測量士の男だった。
目撃証言と謎のスコップ
その男は言った。「あの杭は、お父さんが引っこ抜いたんだよ。理由は知らんけどな」と。周囲が静まりかえる。
さらに彼は、以前スコップで何かを埋める姿を見たという。筆界線を動かすなど、本来あってはならない行為だ。
だがそれは、息子に不利な登記を避けたいという、親の“思いやり”だったのかもしれない。
昔ここは私道だった
もう一つの証言で、ここがかつて共有私道だったことが明らかになった。土地の所有者たちが、口約束だけで道を譲り合っていた時代。
その後、正式に分筆される前に、その線引きが曖昧になってしまったらしい。まるでサザエさんの町内会のような、ゆるやかな合意。
だがその“やさしさ”が、今になって争いを生んでしまったのだった。
古い筆界確認書の落とし穴
最終的な決め手となったのは、役所で発見された一通の筆界確認書だった。それは亡くなった地主が生前に残したもので、署名も押印も確かだった。
ところが、その書類には一つだけ問題があった。添付された図面が現地と一致しなかったのだ。
私は地元の測量士に連絡を取り、過去の測量履歴を調べてもらった。そこで出てきた真実に、私は驚いた。
ゴルフ仲間が証人に
かつての地権者のゴルフ仲間が、その日現場に居合わせていたことが判明した。彼の証言によって、当時の杭の位置が裏付けられた。
測量に立ち会っていたのは、彼と亡くなった地主、そしてその息子。三者の合意で杭を打った記録が手帳に残っていた。
それは正式な図面よりも、何倍も重い“記憶の証拠”だった。
亡くなった地主の遺志
結局、依頼人の父親は、息子に少しでも広い土地を残そうとして境界を動かしていたのだった。それが後になって仇になった。
だが、手帳に書かれた「将来困ったら、元の線に戻せ」という一文に、私は胸が締めつけられた。
愛情の形は、ときに法を超えてしまう。私はそれを、ただ静かに見届けるしかなかった。
シンドウのうっかりと逆転
一度は測量図のミスだと断じていた私だが、実は登記識別情報の番号がずれていたことに後で気づいた。依頼人が最初に渡した情報が間違っていたのだ。
「なんだよこれ、、、」と自分に呆れた。だが、ここから一気にパズルのピースがはまっていった。
あの杭は筆界のものではなく、ただの目印杭だった。真の境界線は、少し内側にあったのだ。
筆界ではなく所有権の問題
つまり、争っていたのは筆界ではなく、実は“所有権”の範囲だった。それが測量図のズレと相まって、話がこじれていたのだった。
私は法務局で補正申請の準備をしながら、しみじみと肩をすくめた。「やれやれ、、、司法書士って探偵みたいなもんだな」
ただ、今回は探偵漫画より少し泥臭かった。だけど、心にはどこか温かいものが残った。
決着と静かな謝罪
依頼人は静かに隣地の夫婦に頭を下げた。「父が勝手をしてすみませんでした」と。それに夫婦も無言で頷いた。
土地は数平方メートル、されど人の感情は計れない。最後は人と人の信頼でしか、境界を越えることはできないのだ。
私は黙ってその場を離れた。あとは、図面と登記がすべてを語ってくれる。
境界の外にあった友情
その後、依頼人は亡き父のゴルフ仲間と久しぶりに会い、昔話に花を咲かせたという。私はその話を聞いて、少しだけうれしくなった。
土地の線引きの外側に、こんな人間関係があるなんて、誰が思っただろうか。
事件は終わったが、それは一つの始まりでもあった。
事務所に戻る二人
夕方、事務所に戻ると、サトウさんが無言でアイスコーヒーを差し出した。私は黙って受け取り、椅子に沈んだ。
「今回、最後にちゃんと気づいたのは良かったですね」と彼女。これは彼女なりの褒め言葉だと信じたい。
私は一口飲んで、天井を仰いだ。
サトウさんのアイスコーヒー
冷たいアイスコーヒーが、喉を通って胃の痛みを和らげる。今日という一日は、思ったより長かった。
事件が解決しても、誰かの心にはわだかまりが残る。それでも前に進むのが仕事だと、自分に言い聞かせた。
それにしても、このコーヒーはうまい。今日いちばんの癒やしだった。
やれやれ、、、暑いのは苦手で
「やれやれ、、、暑いのは苦手でね」とつぶやくと、サトウさんが珍しくクスッと笑った。
それだけで、少し救われた気がした。たぶん私は、まだこの仕事を続けていける。
また新しい依頼が、明日も届くのだろう。