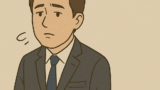朝の依頼人
突然訪れた中年女性の相談
朝のコーヒーをすすっていると、事務所のドアが控えめに開いた。入ってきたのは、髪をきちんと束ねた中年の女性だった。肩にトートバッグをかけ、どこか気の張った面持ちだ。
「父の土地のことで、ちょっと見てもらいたいことがありまして……」 そう言って彼女は一枚の地積測量図を広げた。古い紙に描かれた線は、まるで迷路のように複雑だった。
境界線に揺れる古い家
話を聞けば、彼女の実家の隣人と、境界線を巡ってトラブルになっているという。 「このフェンスが元々うちの敷地にあったはずなんです。でも、隣のおじさんが勝手に直して…」 言葉の端々に苛立ちと不安がにじむ。
私はひとまず登記簿を取り寄せ、土地の沿革を調べることにした。何かが、この話には引っかかっていた。
書類の中の違和感
古い公図と今の現地
法務局から届いた公図には、妙な点があった。現況の敷地と、登記上の線がわずかにズレている。だが、そのズレが生じた原因までは書類からは読み取れない。
「おかしいですね…フェンスの位置、昔からですか?」 私は依頼人に聞いたが、「父がそう言ってました」としか答えが返ってこなかった。
固定資産評価証明の矛盾
念のため役所で固定資産評価証明も確認すると、土地の面積が登記簿とわずかに異なっていた。これは珍しいことではないが、今回の件では無視できない。
「やれやれ、、、こういう微妙な違いが、一番面倒なんだよな」 つぶやくと、背後から塩のように冷たい視線を感じた。
サトウさんの冷静な指摘
筆界未確定の記載に着目
「あの、シンドウ先生」 サトウさんが差し出してきたのは、別の登記簿だった。 「これ、筆界未確定って書いてあります。多分、そのせいで隣地と揉めてるんじゃないですか?」
彼女の指摘に私はハッとした。確かに、筆界未確定の土地では現況と登記の不一致が起きやすい。それが、今回のズレの正体かもしれなかった。
実測図に隠された真実
さらに彼女は、以前の測量業者が提出した実測図も引っ張り出してきた。 「このメモ、父親が書いたんじゃないですか?」 裏面には鉛筆書きの走り書きで、「境界はこの石垣の外側」と記されていた。
それは、長年家族内でも共有されてこなかった小さな真実だった。そこから、話の全体像が見え始めた。
隣人とのトラブルの記憶
境界フェンスを巡る口論
依頼人の話によれば、フェンスは数年前に隣人が「壊れてる」と言って勝手に作り直したという。「あの人、何でも自分の都合で動くんです」 表情を歪めてそう語った。
だが、話をよく聞くと、父親が生前に隣人と口頭で合意していた節もある。つまり、書面には残されなかった約束があった可能性だ。
亡くなった父の言い残し
「そういえば、父が亡くなる前にこんなこと言ってました。『フェンスのことは心配するな、ちゃんと話してある』って」 それが事実なら、境界の位置変更は合意の上だったかもしれない。
この手の口約束は、証拠になりづらい。だが、そこにこそ人間ドラマがある。まるで昔のアニメで、おばあちゃんの知恵袋が最後に活躍するように。
登記簿の裏にある歴史
一度抹消された名義の謎
さらに登記簿を遡ると、過去に一度だけ第三者名義に移転され、すぐに抹消されていた記録を見つけた。仮登記だったのだろう。
その時期と、フェンスの工事時期がほぼ一致していた。これは偶然ではない気がした。
相続登記を怠った影響
依頼人の父は相続登記を長年していなかった。名義人が祖父のままだったため、法的な境界確定には常に時間がかかった。
「サザエさんちみたいに家族全員で話し合えばいいのに、どこも結局はバラバラですよ」 苦笑しながら私は資料を閉じた。
真実を明かす一通の書類
法務局に眠る地積測量図
決め手になったのは、法務局の閉架資料だった。測量士が提出していた図面に、隣地所有者の署名と押印があった。境界変更に関する立会確認書だ。
つまり、両者の間で合意は成立していた。そして、それは記録としてちゃんと残っていた。
サトウさんのファインプレー
「最初から見てれば良かったですね」 サトウさんはそう言いながらも、ほんの少しだけ口元が緩んでいた。 「まぁ、シンドウ先生にしては上出来じゃないですか」
皮肉交じりの褒め言葉に、私は反論できず、ただ天井を見上げるしかなかった。
予想外の犯人
意外な人物の故意の境界変更
後日、隣人に話を聞くと、実は彼が一方的にフェンスを移動していたことが判明した。立会確認書は、測量当時の話であり、今回の移動には無関係だったのだ。
「どうせみんな忘れてると思ったんだよ」 そんな言葉に、怒りというより、虚しさを感じた。
手書きメモが指し示した真相
結局、依頼人の父が残したメモが、真の境界を示す証拠になった。そのメモは、登記簿よりも説得力を持っていた。 人の記憶と紙の記録、どちらが重いのか、難しい問題だ。
依頼人の涙と決断
父への贖罪と家族の再生
「もっと早くちゃんと話しておけばよかった……」 依頼人はそう言って涙を流した。父親の苦労と、残してくれた家を守ることの意味に、今さら気づいたのだ。
人は失ってからしか気づかないことが多い。そう、司法書士という仕事をしていると、毎日そんな場面に出くわす。
争いの終わりと新たなスタート
調停を経て、隣人との間に改めて境界確認書が交わされ、問題は解決した。 無数の書類の山の中から、本当に必要な一枚を見つけ出す。それがこの仕事の本質だ。
私は、依頼人が笑顔で帰っていく背中を、ただ静かに見送った。
やれやれ司法書士はつらいよ
疲労困憊の帰り道での独り言
「あー…腰が痛い。やれやれ、、、またサトウさんに怒られるな」 夕暮れの中、コンビニでおでんを買いながら私はため息をついた。 世間の名探偵と違って、こちとら地味で地道な仕事だ。
塩対応でも頼りになる相棒
帰ると、机の上に一言メモが貼られていた。 『書類未提出 忘れてたら許さない』 たぶん、これが彼女なりの励ましなのだろう。 「……はいはい、ちゃんと出しますよ」
静かに閉じる登記簿のページ
正義と現実の間で揺れる日々
今日も誰かの過去を紐解き、誰かの未来に繋ぐ。それが司法書士の仕事であり、業なのだろう。
正義という言葉が遠く感じるこの時代に、小さな納得を積み重ねていくしかない。
次なる相談者の影
ドアがまた控えめに開いた。「あの…すみません、ちょっと相談が…」 私は背筋を伸ばし、笑顔を作った。 「はい、なんでしょうか。どうぞお入りください」