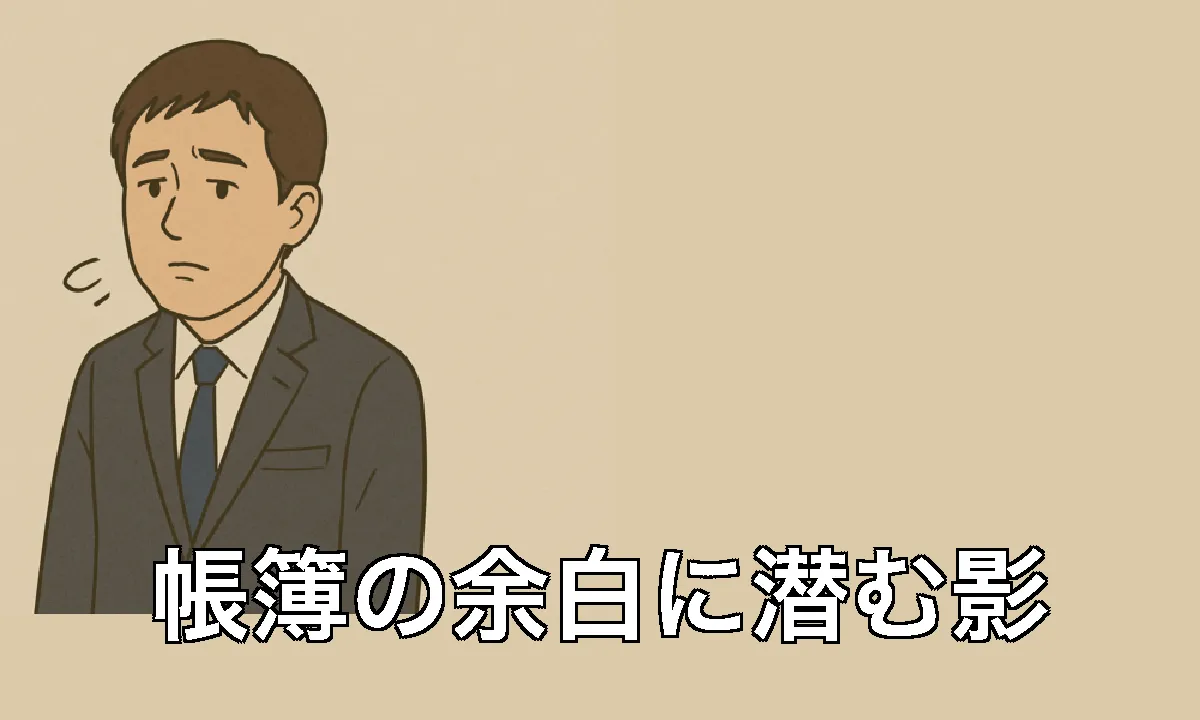帳簿の余白に潜む影
その朝、事務所の空気はいつもより少し重かった。僕の手元には、黄ばんだ封筒に入った旧土地台帳の写しがある。依頼人は70代の男性で、祖父名義の土地を相続したいという話だった。
「でも、登記簿には名前がないんです」と彼は困ったように言った。地元では“幽霊地番”とも呼ばれる、古い地番のまま放置された土地だ。僕の頭の中に、サザエさんのエンディングのように、ご近所の人たちが手をつないでくるくる回る光景が浮かんだ。みんなの記憶も曖昧だ。
僕は封筒を開き、資料に目を通し始めた。これは、ちょっとやっかいな案件かもしれない。
朝のコーヒーと封筒一枚
コーヒーの香りと共に、サトウさんのため息が聞こえてきた。「また地番ネタですか。流行ってるんですかね」とぼそり。無理もない。ここ最近、古い地番絡みの案件が増えてきていた。
旧土地台帳に残る情報は断片的で、しかも誤記も多い。資料を手に取った時点で、僕の胃はうっすらと痛み出していた。「また胃薬の出番ですか?」サトウさんが皮肉っぽく笑った。
やれやれ、、、朝から前途多難だ。
謎の古家登記相談
依頼人によれば、問題の土地には今も古家が建っているという。しかし登記簿にはその建物の記載が一切ない。建物図面もなければ、保存登記の記録もない。まるでその家は最初から存在していないかのようだ。
「登記漏れ…というより、最初から登記されてなかったのかもな」と僕はつぶやいた。サトウさんが冷ややかに一言、「つまり、また泥沼ですね」。まさにその通りだった。
だが、この案件にはなにかひっかかる感触があった。ただのうっかりとは違う。計画的な何かの匂いがした。
サトウさんの冷たい視線とするどい指摘
「この“余白”、気になりません?」サトウさんが台帳のコピーを指差した。確かに、所有者欄の下に妙な空白がある。書き損じにしては不自然な余白だった。
「もしかして…誰かが消した?」僕が言うと、サトウさんが無言でうなずいた。古い台帳に修正液なんてない。つまり誰かが意図的に記録を消した可能性がある。
そして、その誰かは、台帳の中に“記されなかったこと”を知っている者だ。僕たちは、そこに仕掛けられた罠に気づき始めていた。
消えた所有者の手がかり
古い村落では、土地の記憶は人の記憶に残されている。僕は資料室へ向かい、戦前の旧地番台帳をひもといた。手書きの記録の中に、依頼人の祖父と同姓の人物の名があった。
しかし、今の台帳にはその名前がない。不動産の登記簿の“断絶”は、まるで失われた血縁のように、冷たく、悲しい。
「これは、ただの記載漏れじゃないな」僕はぽつりとつぶやいた。
明治時代の地番が語ること
登記官の手による記録は、時にその時代の事情を反映する。明治後期の地番台帳には、村の再編による整理が記されていた。所有者が変わっていないのに、地番だけが変わっている。
つまり、誰かが登記上の“痕跡”を隠すために、再編という名のマジックを使った可能性がある。名探偵コナンで言えば、暗号のような地番移動だ。
しかし、僕らは決して諦めない。そこに法と記録がある限り。
古い資料室に眠るもう一つの台帳
資料室の棚の奥に、埃をかぶった一冊の分厚い冊子があった。通常の土地台帳とは別に保管されていたその書類に、問題の土地が旧名義で記載されていた。
所有者は、依頼人の祖父。そしてその横に小さく、鉛筆書きで「名義変更未申請」と記されていた。「これだ…!」僕は声を上げた。
一見、空白に見えた“余白”には、こうして消されかけた真実が眠っていたのだ。
旧土地台帳の罠
記録はある、でも登記はない。これは、行政の“見なかったことリスト”に載っていた物件なのかもしれない。行政が気づかなければ、登記簿にも反映されない。幽霊地番とは、まさにそのことだ。
僕は地番調査票と、法務局保管の登記済書類を照合しながら、もう一度現地を確認することにした。
そこには、想像以上の闇が広がっていた。
所有者欄に記された違和感
発見した旧台帳の中で、一つだけ記載の筆跡が違うものがあった。所有者の名前が一部だけ濃い。筆跡鑑定をするまでもない。これは後から誰かが書き加えた跡だ。
「つまり、これは贈与に見せかけた乗っ取り…?」サトウさんの目が鋭くなる。彼女のその瞬間の顔は、ルパン三世の峰不二子にも似ていた。美しさと冷酷さを兼ね備えた表情だった。
「やれやれ、、、峰不二子に睨まれたら、僕も動くしかないな」と僕は苦笑いした。
二重登記か名義貸しか
法務局に照会した結果、驚くべきことがわかった。戦後の混乱期に、一時的に別の人物の名義で仮登記されていた記録が残っていたのだ。その人物はすでに故人、だが孫が今も土地に住んでいる。
依頼人の祖父の登記は形式上抹消されておらず、つまり二重登記状態に近いものだった。僕の頭の中に、探偵漫画の「この二人は同一人物…いや違う!」という場面が浮かんだ。
あのトーンの線が見えそうなぐらいの衝撃だった。
小さな村と大きな嘘
村の古老に話を聞くと、件の土地については「ああ、あそこはな…」と妙に歯切れが悪かった。どうやら地元でも触れてはいけない“土地”だったらしい。
「戦後に誰かが勝手に住み着いたらしいですよ」そんな噂も聞こえた。昭和の香りが残る集落では、登記よりも人付き合いが優先されていた時代が確かにあった。
でも今は令和。証明できないものは、法的に存在しないのと同じ。サトウさんが静かに言った。
サザエさん一家のごとく隣人事情が複雑
現地確認でさらに驚いたのは、土地を取り囲むように複数の家がひしめいていたことだった。まるでサザエさんの家の周囲にワカメちゃんや波平が独立して暮らしているような状態だった。
「あそこはもともと一つの土地だったんだよ」と古老が言う。つまり、筆界未確定のまま、代々分割利用されてきた土地だったのだ。
だから誰もが“自分の土地”だと信じていた。事実と登記のズレが生んだ、もう一つの闇だった。
噂と証言の交差点
聞き込みの中で、「あの人は土地を譲ると言ってた」「いや、そんな話はなかった」という矛盾する証言がいくつも集まった。
登記は記憶に勝つ。だが、その記録すらあいまいだった時代には、記憶と記録がどちらも曖昧なままだった。
僕は、そこに“誰かの意図”を感じた。台帳の余白は、真実を記す場所でもあり、消す場所でもある。
地番の向こう側にあったもの
祖父が残したという手紙を依頼人が持ってきた。その中には、「将来、土地はお前のものになるが、まだ時期ではない」とあった。時期とは? なぜ今まで隠していたのか?
その答えは、登記簿ではなく、人の心にあった。
祖父は戦後の混乱で、土地の登記どころか生活すらままならなかった。そして“住まわせていた人”に対する罪悪感が、手続きを遅らせたのだった。
遺言書に記された一筆
最終的に見つかったのは、昭和44年に書かれた遺言書だった。そこには「この土地は長年住んでくれた○○に譲る」とあった。正式な方式ではなかったが、証人もいて日付も明記されていた。
「これは、相続登記と贈与登記の間に挟まった“思い”ですね」とサトウさんが言った。僕はうなずきながら、静かに台帳を閉じた。
記録には残らない感情。でも、確かにそこにあった。
登記簿から消された最後の名前
最終的に、登記簿には依頼人の名前ではなく、その祖父が譲ると記した○○さんの孫が所有者として記されることになった。
依頼人は静かに笑って、「じいちゃんらしいや」とつぶやいた。彼にとっては、所有よりも真実が大事だったのかもしれない。
やれやれ、、、たまには、こんな終わり方も悪くない。
サトウさんの推理と僕のうっかり
サトウさんが言った。「最初の余白に気づかなかったら、ぜんぶ見逃してましたよね」。僕は恥ずかしさを隠すように笑った。
彼女の観察眼がなければ、単なる“未登記問題”として処理していたかもしれない。
そして僕の“うっかり”が逆に、正義にたどり着くきっかけにもなったのだった。
意外な人物が持っていた鍵
最後のピースは、現地の郵便配達員だった。「あそこ、ずっと○○さんとこの孫が住んでたよ」と彼は言った。その証言が、すべてを確かにした。
土地は、ずっと“正しい人”の手にあった。ただ、記録がそれを知らなかっただけだった。
登記ってのは、本当に奥が深い。いや、深すぎる。
やれやれ、、、最後に走るのはいつも俺だ
結局、登記申請書をまとめるのは僕の仕事だった。サトウさんは「しっかりお願いしますよ」とだけ言って、さっさと帰ってしまった。
やれやれ、、、本当に、最後に走るのはいつも俺だ。
でもまあ、それが僕の仕事なのだ。司法書士ってやつは。
解決とその代償
事件の真相は明らかになった。土地は正式に移転され、関係者も納得した形で終わった。でも、心の奥にはぽっかりと“余白”が残ったような気がしてならない。
それは、登記簿の中にも、人生の中にも存在する“語られない空白”だ。
そして僕は、今日もまた、新たな“余白”に向き合う準備をしていた。