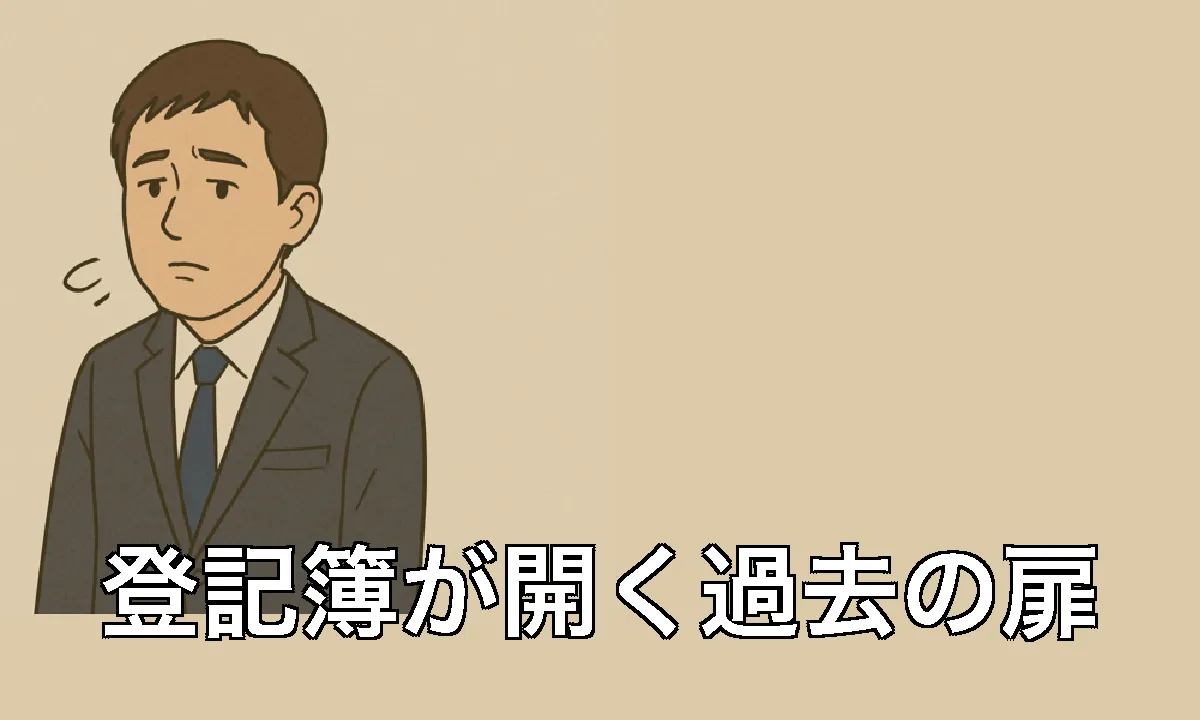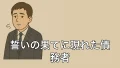現れた依頼人と不自然な遺言
雨がしとしとと降る火曜日の午後。私の事務所に突然現れたのは、濡れた髪を無造作に拭きながら大きな封筒を握る中年の女性だった。「亡き父の遺言について、ちょっと気になることがありまして…」その声には、不安と警戒が入り混じっていた。
封筒の中には三枚綴りの自筆証書遺言が入っていた。日付も署名も一応は揃っている。しかし、どうも気にかかる。何より彼女が「父はこんな漢字を使わなかった」と呟いた言葉が、妙に胸に引っかかった。
髪を振り乱した女性の訪問
あの「カツオ〜!」と叫ぶサザエさんのように、感情のままに飛び込んできた彼女だったが、話しぶりから察するに冷静さを欠いているわけではなかった。むしろ、何かを確信してここに来たような気配があった。
封筒の角は擦り切れ、中の紙は湿気を吸ってよれていた。これが数日前に出てきたとは思えない。長い年月、どこかで眠っていたものを、誰かが急に持ち出したのではないか。直感がそう囁いた。
三枚複写の遺言書と古びた封筒
珍しく三枚も同じ内容の遺言があることが気になった。通常、自筆証書は一通で済ませる。しかも、それぞれ微妙に筆跡が違う。これが生前に書かれたものであることを証明するには、少々根拠が薄い。
私はコピーをとって、原本は返却した。「念のため、戸籍と不動産の資料も集めておきます」と伝えると、彼女は静かに頷いて帰っていった。その背中に、何か重たいものを背負っているように見えた。
登記簿に記された矛盾
数日後、法務局から取り寄せた登記事項証明書を見て私は眉をひそめた。遺言で名指しされていた物件が、数年前に別人に所有権移転されていたのだ。しかも、その人物の名義は現在も残っている。
これはおかしい。遺言に記された物件を相続する権利がそもそも存在していない可能性がある。私は、例のサトウさんに確認を頼んだ。すると彼女はたった一言だけ言った。「この人、相続人じゃないかもしれませんね」
相続人が名乗らない理由
確かに彼女の戸籍を確認すると、亡き父とのつながりが不自然だった。養女縁組の痕跡があるのだが、それが遺言作成の半年後に届出されている。つまり、遺言当時はまだ法的な親子関係は成立していなかった。
「やれやれ、、、」私は思わずため息を漏らした。遺言が無効である可能性は高い。が、それだけでは終わらない。誰が、何のためにこの偽装を?登記と遺言、2つの世界が交わるところに何かある。
サトウさんの違和感の一言
「この遺言、三枚あるけど、最後のだけ筆圧が強すぎますね」彼女はコピーを指差しながら言った。筆跡鑑定士でもないのに、よくそんなところに気づくなと感心している場合ではなかった。
最後の一枚だけ、文字が明らかに濃く、他よりも「押し込む」ように書かれていた。まるで誰かが、それだけを目立たせようとしたかのように。となれば、偽造の可能性が急浮上してくる。
消えた兄と空白の十年
戸籍をさらに掘り下げると、依頼人には「兄」がいたことが判明した。しかし、その兄の戸籍は十年前に除籍されていた。死亡の記載がなく、どこかへ転籍したわけでもない。完全に行方不明扱いである。
これはよくある「家族が連絡を絶った」ケースか、それとも、、、?私は旧住所の附票をあたり、転出先を追いかけることにした。まるで怪盗ルパンの後を追う銭形警部になった気分だ。
戸籍の附票に現れた新住所
ようやく辿り着いたのは、某県の山奥の村だった。しかも、そこには「村外れの廃屋に一人住む男がいる」との話があった。登記上、兄の名前がその不動産の所有者として残っていたのだ。
私は現地を訪れ、住人の確認を依頼した。返ってきたのは「すでに数年前に亡くなったらしい」という曖昧な返答と、火事で焼けた家の写真。これでは生存確認も死亡確認もままならない。
住民票コードが語る奇妙な足跡
それでもなお食い下がったサトウさんが、住民票コードで照合した情報を持ち帰ってきた。そこには別人として登録された記録があり、明らかに兄は別の名前で生き延びていた可能性があった。
「この人、自分の死を偽装したかもしれませんよ」と、彼女は淡々とした声で言った。やれやれ、、、推理漫画じゃあるまいし、まさか現実でそんなことがあるとは思わなかった。
土地の売買契約に潜む罠
件の不動産について、旧地主が登記簿に現れた日付と、依頼人が提出した遺言の日付にズレがあった。もしも遺言の日付があとならば、すでに遺贈の対象ではなくなっていたことになる。
つまり、相続させる意思があっても、実体のない権利では登記は通らない。私は、所有権移転登記の経緯を洗い出すことにした。そこには、不可解な契約書が隠されていた。
売主と買主の署名が一致しない
契約書の筆跡を確認すると、売主の署名と、過去の別書類にある署名が一致していないことが判明した。専門家に見せるまでもなく、素人目でも違いが明らかだった。
誰かが売主の名前を騙って契約を交わし、登記を進めた可能性が高い。だが、それが誰なのか。この先に登場する人物が真犯人であるとは、この時点ではまだ想像できなかった。
過去の登記に残る見落とし
私は法務局に出向き、登記申請書副本を確認した。そこには、手続代理人として見慣れた名前が記載されていた。なんと、昔の知り合いの司法書士だった。
まさかとは思ったが、彼も「名前だけ貸した」と渋々話してくれた。これでようやく、事件の輪郭が見えてきた。目的は登記ではない。遺産の争奪だったのだ。
真実に至る最後の鍵
サトウさんが目を輝かせながら持ち込んできたのは、電子申請システムのログ情報だった。アクセス記録を照らし合わせると、ある特定の時間帯に申請されたことが分かった。
そして、その時間、依頼人は海外に滞在中だったというアリバイが証明された。つまり、遺言の提出も、登記の申請も、第三者によるなりすましである可能性が濃厚になった。
すべてを繋ぐ一通の手紙
すべての証拠をまとめていると、一通の封筒が再び私のもとに届いた。中には古い手紙と、戸籍の写し。そして一言だけ「許してください」とだけ書かれた便箋が入っていた。
それは、依頼人が実の娘ではなく、兄の婚外子だったことを示していた。すべてを知った上で、彼女は嘘をついていた。いや、守ろうとしていたのだ。死んだ父の「秘密」と「名誉」を。
逆転する遺産分割協議書
私は関係者を集め、事実を説明した。法的には相続の権利はないが、感情としては複雑だった。だが、ここでひとつの提案が出された。「じゃあ、法定相続人で話し合って分けましょう」
争いではなく、合意による協議が始まった。最後には、兄の失踪も、依頼人の出生も、すべてが明るみに出た形となり、誰もが納得する形で終わった。
誤認に気づいた相続人たち
「あの子はウチの子じゃないと思ってたけど、父さんが隠してたのね」と泣く女性もいれば、「それならそれで、早く言ってくれれば」とうなだれる男もいた。
血と戸籍のあいだで揺れ動いた家族の姿は、実に人間的だった。そして、それを整理しながら、司法書士という立場で向き合うのも、また奇妙な宿命のように思えた。
修正登記に至るまでの説得劇
最終的には、土地の所有権を法定相続人で登記し直す形でまとまった。私は登記原因証明情報と、相続関係説明図を作成し、法務局に提出した。
登記が完了したその瞬間、やっと終わったかという安堵とともに、ひとつの時代が閉じたような気がした。
サトウさんの冷静な総括
「だから最初から怪しいって言ったじゃないですか」
サトウさんは、机の上のファイルをトントンと揃えながら言った。その口調はいつも通り淡々としていて、手柄を誇る様子はまるでない。だが、その目はどこか満足げだった。
やれやれ司法書士は便利屋じゃないんだけどなあ
事件が終わっても、私のデスクにはまた別の依頼書類が積まれていた。隣の部屋からは、電話応対をするサトウさんの声が聞こえる。「やれやれ、、、」私は呟いて、また一枚書類を手に取った。
まるでエンドレスな探偵アニメのように、事件は繰り返される。でも、それが私の仕事だ。きっと今日も、司法書士という役割を演じる舞台の幕が上がる。
そしてまた普通の一日に戻る
外は快晴。雨に濡れた日々の記憶も、登記簿の中に静かに閉じられていく。私とサトウさんは、何事もなかったようにコーヒーを淹れ、いつもの一日を始めた。
事件の余韻が残る中、事務所の電話がまた鳴る。今度はどんな相談が来るのか。私は書類の山に目をやりながら、肩をひとつすくめた。
次の依頼のベルが鳴る
サトウさんが電話を取り、「はい、○○司法書士事務所です」といつもの低めの声で応じる。どこかでまた、新しい扉が開こうとしている。
登記簿が語るのは、不動産の履歴だけじゃない。そこには人間の過去と、秘密と、たまに少しの優しさが詰まっている。