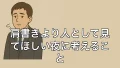肩書きよりも心を渡したい夜に
「この名刺、何枚目だろうな……」
名刺入れのフタを閉じながら、俺はひとりごちた。肩書きは司法書士。名前は進藤。年齢は45歳。独身、元野球部、女性運ゼロ。どうでもいいプロフィールばかりが頭に浮かぶ。
今夜は市の創業者交流会。地方らしい、肩書きがズラリと並ぶ名刺バトル。中には「わたくし社長やってます」なんて、“サザエさん”に出てくる波野ノリスケばりに威張ってるのもいる。
俺はというと、壁際でチビチビとウーロン茶をすする哀しき司法書士。周囲は意識高い名刺交換マシーンたち。マイクロ法人のCEO、デザイン起業家、地元インフルエンサー。どれもピンと来ない。
名刺交換に込められた期待とむなしさ
ふと隣に現れたのは、控えめな笑顔を浮かべた女性。年の頃は30代前半、ナチュラルなスーツ姿。名刺を差し出すその手が少し震えていた。
「…あの、初めまして。中井と申します。司法書士さんって、どんなお仕事なんですか?」
珍しい。名刺を渡す前に質問してくるなんて。
「ああ、まぁ…書類を作って、登記して、書類をまた作って……」
自分でもつまらない説明だとわかっていた。
「でも、相談してくれる人の話を、ちゃんと聞くのが仕事、かな」
彼女は少し笑った。
心の交換ができたときの記憶
「今日、名刺たくさんもらいましたけど、進藤さんみたいにちゃんと話してくれたの、初めてです」
不意にそう言われて、心臓がトクンと鳴った。
「でも、まだ名刺、いただいてないですよ?」
彼女が笑いながら言う。
俺は慌てて名刺を渡した。
たったそれだけのやりとりなのに、今夜の交流会で一番、心が動いた。
司法書士としての名刺の重み
次の日、事務所でサトウさんに昨晩のことを話すと、彼女は肩をすくめた。
「えっ、何それ、珍しく進藤さんのターンだったんですね。『名刺じゃなくて心で勝負』とかって探偵マンガの名ゼリフですか」
「そういうつもりじゃ…」
「…まあ、やれやれ、、、たまには良いこと言いますね」
サトウさんは皮肉を言いながらも、ちゃんとコーヒーを出してくれた。
形式よりも感情が動いた瞬間
その週末、中井さんからメールが来た。「あのときの会話、思い出してます。何かあったら相談してもいいですか?」
俺はそっと返信ボタンを押した。
「もちろん。名刺じゃなくて、話ができるなら、いつでもどうぞ」
名刺は紙だけど、つながりはそれ以上であってほしい。そんな夜も、あっていい。