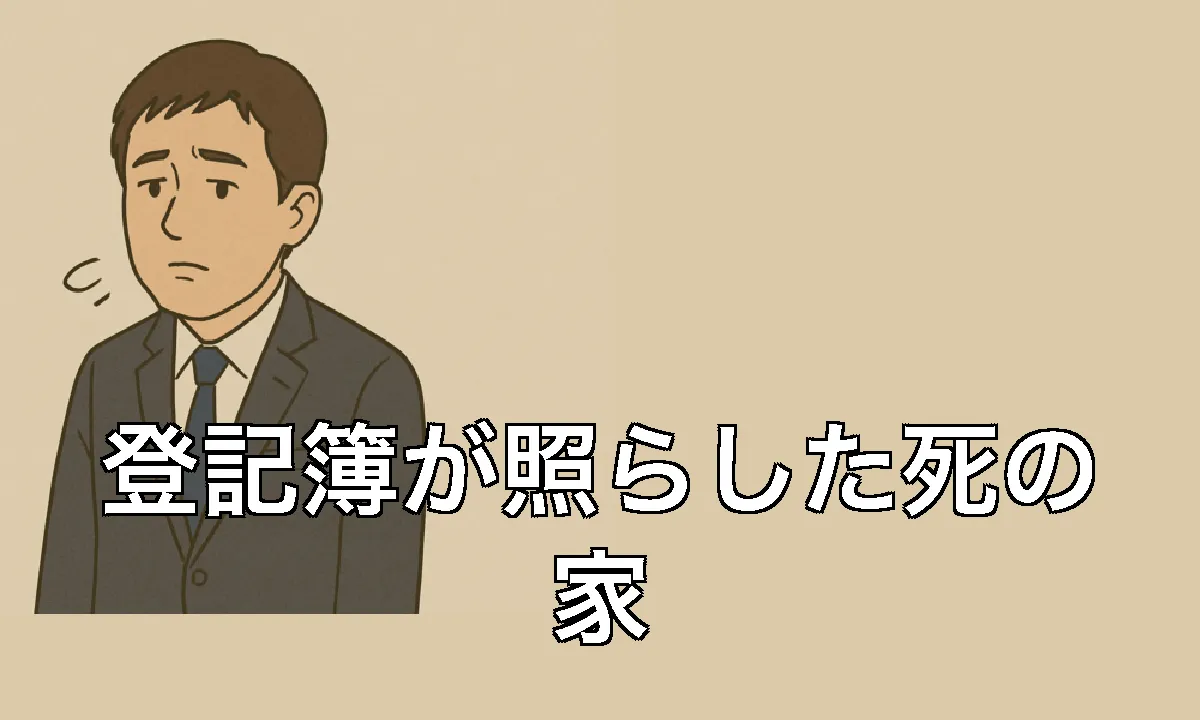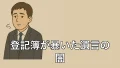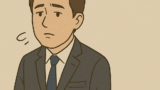登記簿が照らした死の家
その日、朝から妙な予感がしていた。電話も来客もないはずの時間に、ドアがノックされた。
開けると、古びた封筒を握った中年女性が立っていた。「亡くなった兄の土地について調べてほしいんです」
それだけ言うと、封筒を机の上に置いて去っていった。名乗りもせず、まるで幽霊のように。
朝一番の訪問者
中には、簡素な手紙と登記事項証明書のコピーが入っていた。住所はこの町内、だが、記録は何年も前のままだ。
更新されていない謄本は、過去をそのまま封じ込めているように見えた。
「あの建物、今誰が住んでるのかしら?」と背後からサトウさん。すでに調査に取り掛かっているらしい。
無言の依頼書
その家に関する情報は、どこかちぐはぐだった。登記は存命中の兄の名義、しかし固定資産税は支払われていない。
町役場の台帳でも空き家扱いになっていた。だが、近所の噂では「誰か住んでいる」という。
不気味な静けさと、かすかな生活の匂い。それがこの事件の第一印象だった。
その住所には誰もいない
私がその家を訪ねたのは午後三時。玄関には郵便物が溜まり、インターホンは反応しない。
だが、室外機は微かに唸っていた。誰かがいる、確かに暮らしている。
サザエさんのオープニングのように、誰もいない家の中に勝手に入る勇気は、さすがになかった。
忘れられた登記と二重の所有者
登記情報を詳しく調べてみると、奇妙な点が浮かび上がってきた。
昭和時代の名義変更がなされておらず、しかも一度、名義が別人に移されていた形跡があった。
その後、再び兄の名義に戻されている。いったい何があったのか。
サトウさんの不機嫌な調査開始
「これ、仮登記が途中で止まってますね。名義戻しの登記も、どう考えても何かおかしいです」
サトウさんはモニターを睨みつけながら、私に冷たく報告してきた。
私は思わず口をついた。「やれやれ、、、また登記簿が何かを隠してるってわけか」
地元民の噂と昭和の事件
地元の駄菓子屋のおばあさんに話を聞くと、あの家は昔「火事を起こして死人が出た」と教えてくれた。
火災後、その家に兄が移り住んだという。「でもね、あれは養子だったんじゃないかって噂もあったよ」とおばあさん。
養子?となると、相続関係もややこしくなる。ややこしい話には、ややこしい過去がつきものだ。
遺産分割の裏にあった秘密
その兄には実の子がいなかった。だが、旧戸籍には「長女」と記された名前が一つだけ残っていた。
登記の時点では未成年だった彼女は、どうやら相続放棄をしたことになっていた。
それが本当に本人の意思だったのかどうかは、今となっては確かめようがない。
元夫婦の隠された関係
調査を進めるうち、亡くなった兄には籍を入れていない内縁の妻がいたことが判明した。
彼女は、登記の不備を理由に遺産分割に関与してこなかった。
そしてその内縁の妻の連れ子が、今もあの家に住んでいるらしい。だがその名は、登記簿にはない。
消えた養子の行方
その連れ子こそが、謄本上に一度だけ現れた名義人である可能性があった。
しかし、登記は抹消され、本人の足取りも掴めない。家に人が住んでいても、表には出てこない。
一体その人間は、法的には存在しているのか、それとも過去の亡霊なのか。
調査報告書に浮かんだ名前
サトウさんが提出した報告書には、旧住民票、謄本、戸籍謄本、すべてに一致する人物の名前があった。
そして、その人物が「偽名」を使って不動産を取得していたことも判明した。
つまり、事件の本質は「所有権を巡る身元の偽装」だった。
昔の登記簿に残る別人の署名
古い登記申請書を法務局で閲覧すると、そこにあった署名は、今も住む人物の筆跡と完全に一致していた。
登記官のミス、あるいは故意の見逃し。それを逆手に取って所有権を操作したのだ。
登記という制度の穴を突いた、まさに現代の怪盗キッドとでも言うべきトリックだった。
不動産屋が語った真実
「あの人ね、何度も名前変えて取引してるんですよ」と不動産屋の店主が証言した。
宅建業者の内部記録により、複数名義を使った取引の証拠が出てきた。
だが、どれも法的には微妙にグレーゾーン。捕まえるには一歩足りない。
やれやれまた厄介な展開だな
誰も罪を認めず、誰も被害を訴えない。こんな事件が一番面倒だ。
だが、私は淡々と法的な整理を始める。登記の不備を正し、相続関係を再構成することが、私の役目だ。
それにしても、やれやれ、、、と何度つぶやいたことか。
鍵を握るのは近所の駄菓子屋
最終的に決定的な証言をしたのは、例のおばあさんだった。
「その子、昔ここでラムネ買ってたもん。あの名字で呼ばれてたよ」
それが本件の決め手となり、名義の連続性と存在証明に繋がった。
遺言書の存在と再登記の罠
兄が書き残したとされる遺言書が、最後に出てきた。それは公正証書ではなく、封のある自筆証書だった。
中にはすべてを養子に譲ると書かれていた。だが、家庭裁判所の検認を受けていなかった。
つまりそれは、法的効力を持たない。遺産は再分割となった。
法務局が沈黙を破る
今回の件をまとめた報告を法務局に提出した。
一週間後、訂正登記が完了し、法的な整合性がようやく保たれた。
そのとき初めて、無言だった法務局担当官から「よくやりましたね」と言われた。
記録された一筆のメモ
訂正後の登記には、小さく「調整済」と朱書きがあった。
それは、現実と制度のはざまで、何かが折り合いをつけた証だった。
「これでやっと、家が家らしくなるんでしょうね」とサトウさんが言った。
サトウさんの推理と私の勘
サトウさんの推理力がなければ、今回の事件は闇に消えていたかもしれない。
私はといえば、昔取った杵柄で、現場の雰囲気を嗅ぎ取っただけ。
元野球部の勘も、まんざらじゃないと思いたい。
犯人は誰でもなかったという結末
結局のところ、誰も罪には問われず、すべては制度の隙間に起きた不幸だった。
人の思惑と法の制度が噛み合わないと、こんなことが起きる。
それでも私は、今日も登記簿と向き合いながら、淡々と仕事を続けていく。