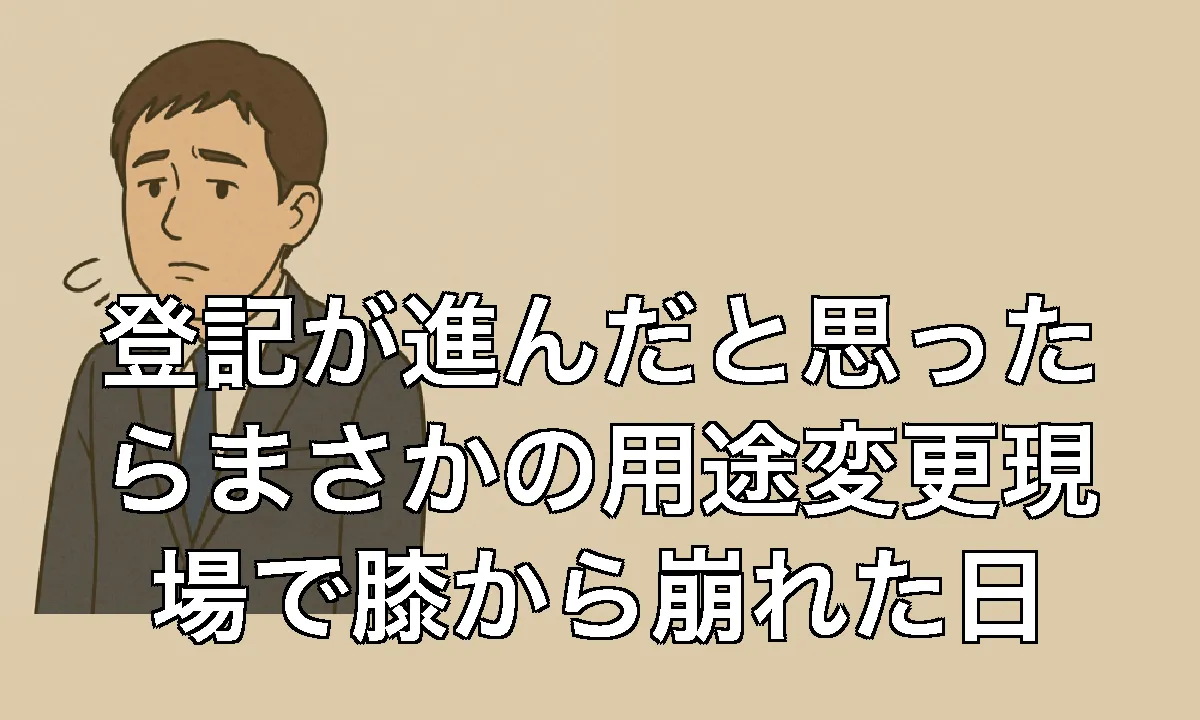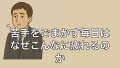なぜ今なのかという話から始まる
登記手続きというのは、基本的には段取りを組んで進めていくものだと思っている。だからこそ、すべてが順調に進んでいた案件で「用途変更がありました」と言われた瞬間、思わず「は?」と口にしてしまった。決して珍しいケースではないのかもしれない。でもその日は朝から疲れていて、たまたま睡眠も浅く、そんなときに限って電話が鳴る。嫌な予感はだいたい当たる。
登記手続きは予定通りだった
正直、今回の案件は「楽なほう」だとさえ思っていた。地目も宅地で問題ない、売主買主ともに協力的。司法書士としては書類を整えて提出すれば、あとは淡々と処理が進む──そう思っていた。
必要書類も整っていたし油断していた
いつもなら何度もチェックする地目も、今回は「まあ大丈夫だろう」と高を括っていた。登記識別情報もスムーズに届き、代理権限も問題なし。事務員も「今回は楽ですね」と笑っていた。そんな余裕が完全に裏目に出た。
依頼者も安心していたはずだった
買主さんも「これで安心です」とにこやかに言っていたし、売主さんも「じゃああとはお任せします」と穏やかな笑顔。このまま滞りなく終わると思っていた。あの日の午前中までは。
突如届いた変更の知らせ
予想外のことって、たいてい一報が軽いノリでやってくる。今回もそうだった。「あ、先生、あの土地、ちょっと用途変更あったみたいですよ〜」って。
法務局からの一本の電話で空気が変わる
「変更届出、出てたらしいです」「え、いつ?」と聞き返したら、先週の話だった。依頼者からも何の連絡もないまま、事が進んでいた。「こちらとしては情報提供の義務はありませんので」と淡々とした口調で言われ、軽くめまいがした。
用途変更という言葉の重み
たかが用途変更、されど用途変更。地目が変わると登記も当然見直さなければならないし、書類も追加になる。しかも変更された用途がまさかの「雑種地」。一気にややこしくなった。
用途変更がなぜ登記に響くのか
用途が変わるということは、すなわちその土地の性質が変わったということ。それは登記簿にとっては無視できない情報だ。現況と登記内容が一致していなければ、申請は通らない。これは基本中の基本だ。
所有権移転に絡む問題点
今回は売買による所有権移転だった。つまり、買主は「宅地」としてその土地を購入したわけだ。にもかかわらず、用途が「雑種地」になっていたとなると、そもそも売買契約自体が問題になる恐れすらある。
地目変更登記の必要性が浮上
「現況と違うので、まず地目変更登記をお願いします」と言われた瞬間、頭の中でスケジュール表が崩れ落ちた。そんな余裕はないし、依頼者にとっても想定外の追加費用と手間だ。説明にかかる時間も想像がついた。
予定していたスケジュールが一瞬で崩壊
決済日も決まっていたし、買主はローン審査も通していた。そこに「用途変更なので少し待ってください」と言うことの重さ。依頼者は納得してくれたけれど、その後の調整に追われることになった。
依頼者への説明の難しさ
一番疲れるのはここだと思う。法的に正しく、事実を淡々と説明しても「何でそれ今言うの?」と言われる。言いたいのはこっちだ。
「何で今?」と詰め寄られる日々
何度も言い訳めいた説明をした。「実は用途変更の情報が…」「そういうの、事前にわからないんですか?」──言われて当然だと思う。でも、じゃあ誰が悪いのかって話になると、誰も明確には責任を負わない。板挟みだ。
感情の受け止め役になるつらさ
「そちらのせいではないとわかってます」と言われても、そのあとに続く「でもモヤモヤするんですよね」がずっしりくる。司法書士って、何かあったときに感情を受け止める役割もセットなのだとつくづく思う。
独り事務所の現実
大手事務所なら、担当が分かれていて分担もできるだろう。でも、うちは事務員一人と自分だけ。忙しさは日によって波があるけれど、こういう「突発対応」が来ると一気に限界を超える。
事務員さんに言えない本音
「またこういうの来ましたよ」と笑いながら言える日もある。でも本音を言えば「もう勘弁してくれ…」という気持ちでいっぱいだ。
「またですか」と言われたくなくて
事務員さんは本当に優秀だ。でも、あまり無理をさせたくなくて、「この対応はこちらでやっておきます」と自分で抱える。結局、自分の首を絞めているのは自分だったりする。
愚痴はいつも自分の中でこもる
誰にでも言える愚痴ならまだいい。でも「用途変更で登記やり直しになってさ…」なんて話、なかなか共感されない。専門的すぎるし、言えば言うほど自分がみじめになる。だから、夜中に缶チューハイ開けながら黙っている。
モテない司法書士の疲れ方
誰かに話を聞いてほしい夜もある。でも、もうそんな年齢でもないし、かといって彼女がいるわけでもない。誰にLINEするわけでもなく、ただ布団に潜り込む。
家に帰っても何も変わらない夜
外で「先生!」と呼ばれても、家ではただの中年男。テレビをつけても気休めにならず、スマホを見るのも面倒になる。疲れすぎて何もできない夜って、ほんと虚しい。
自分に問いかける意味とは
「なんでこの仕事選んだんだろうな…」と自問する。誰かを助けたかったはずだ。でも今は、自分が助けを求めたい気分だったりする。
それでも前に進む理由
じゃあ、やめるのか?って話になると、やめない自分がいる。それは多分、どこかで誰かの「ありがとう」に救われているから。
誰かの安心のためにやっている
「先生がいてくれてよかったです」──この一言のために、何日も苦労してる気がする。誰にも評価されない仕事だけど、誰かの人生に関わっている実感は、確かにある。
依頼者の「ありがとう」に救われることもある
「大変だったんですね。無理言ってすみません」──そう言われたとき、思わず涙が出そうになることがある。人に寄り添うって、たぶんこういうことなんだと思う。
失敗ではないと信じたい自分
ミスじゃない。トラブルじゃない。ただの現場の現実。それをどう受け止めて、どう乗り越えるか。それがこの仕事の本質なのかもしれない。
同業者へ伝えたいこと
こんな日もあります。いや、むしろこんな日ばかりかもしれない。でも、それでも仕事をしている人がいる。それだけで、少し救われる気がします。
誰もが一度は膝から崩れている
失敗してない人なんていない。完璧な司法書士なんて幻想だ。皆、何かしらで膝から崩れた経験を持ってる。そのあと立ち上がれるかどうか、だけなんです。
それでもやっている人がいるから
一人じゃない。どこかで同じように頑張ってる人がいる。その存在を思い出せば、なんとか今日もやれる。だから、今日も机に向かっているんです。